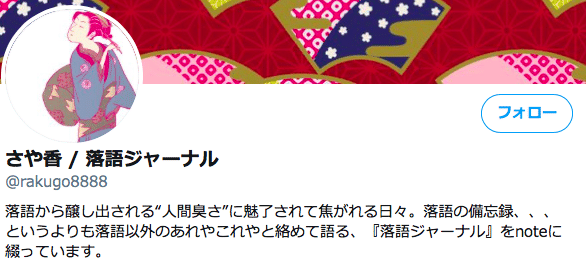落語とお香と、遊女。
『嗅覚』
それは、人間の五感のうちで唯一脳にダイレクトに響く感覚だという。
感情や記憶に関する部分が、匂いを処理する脳の嗅覚野と密接につながっているのだそう。
たとえば、街中で見知らぬ誰かとのすれ違いざまに、ふと昔の恋人の香りが漂って思わず振り返ってしまったという経験はないだろうか。
あの頃の思い出が一瞬で甦って、痛いような甘いようななんとも言えない気持ちを呼び起こすことがある。
「・・・あぁ、大好きだったよね。ウルトラマリン」
これを“プルースト効果”という。
『失われた時を求めて』という小説の主人公が、マドレーヌを紅茶に浸したときに、その香りから過去を想起するという描写があるのだそう。
この小説の作者が、マルセル・プルーストというので“プルースト効果”と名付けられている。
わたしのちょっとした趣味に
『お香を焚く』
というものがある。
落語に夢中になるより先に出会った趣味のひとつである。
といっても、香炉を用いた香道のそれのように大仰なものではなく、お香立てに、香り高い線香状のものを気まぐれにスッと立てる程度のことだ。
わたしは、“和の香り”が好きだ。
白檀や沈香のような。
そう、よく寺社などを訪れるとどこからともなく漂う、まろやかでスパイシーなあの香りだ。
もちろん、香水を身に付けることもあるのだが、この和の香りを焚き、仄かなそれを纏うことにちょっとした優越感を感じているような気がする。
マリリン・モンローのナイトウェアが“CHANEL N°5”ならば、わたしのそれは“伽羅香”である。
・・・ウソ。ごめん。ホントはジャージ。←
そして、
『わざわざ香りを買い求める自分』
『わざわざお香を焚く自分』
『香りに重きを置いている自分』
そんな自分自身にどこか気を良くしている部分があることも自覚している。
“できる限り見えないものにペイしたい”という考え方が強いのである。
その昔、遊女は客と過ごす時間を線香で計っていたそうだ。
線香が燃焼している間、サービスを提供し、燃えた線香の本数で会計が決まった。
時計が一般に普及していない時代に、線香で時間を把握したなんて洒落ているし、非常に合理的であると思う。
しかも、それを提案したのが、幼い舞妓だというのも驚きである。
未だにその名残で、“そういう大人の遊びの花代”を“線香代”と呼ぶことがあるそうだ。
そこにどんな男女関係が花咲いていたかは知る由もないけれど、“ごっこ”だろうが“本気”だろうが、“愛の語らいの最中”に線香が焚かれていたと思うと、なんだかうっとりとする。
そしてやはり、線香には時間管理の目的だけでなく、その香りに『プルースト効果』や『媚薬』として狙いがあったのだと思う。
なんてロマンチックなのだろう。
鳴り響くデジタル音で
「終了でーす!」
と現実に戻されるなんて不粋な昨今である。
古典落語に『たちぎれ線香』という演目がある。やはり、遊女が灯す線香に関する噺である。
これは演るには腕が必要な難しい噺だそうで、どうやら大師匠向けのネタらしい。
わたしは一度も拝聴したことがないのだが、いつかぜひぜひ聴いてみたいものだ。
だから、それまで具体的なあらすじはなぞらずに、大切に胸にしまっておこうと思う。
そういえば、学生の頃、気になる男の子のベッドに自分の香水をばらまいて帰ったことがある。
まぁ、そんな原始的で古典的なことは、平安の昔から皆がやっていることなのだが。
好きな女が自分の香りを抱いて眠ることを想定して、敢えて香りを焚き込めた自分の上着を置いて帰る。
本能に訴えかけるものの効果は、アミニズム時代から、科学技術が発達した現代においても普遍なのである。
きっと遊女もそんな効果を狙って香を焚いていたのだと思うと、その計算高く見える策略に、切ない“人間臭さ”に繋がる悲哀が滲み出ていて、とても心理的に放っておけないような愛しさを感じてしまうわたしなのである。
・・・きっと次回も香りネタ。
文章が長くなってしまうので分けてみました。
今回は序章、次回は本論・・・という感じでお付き合いいただけたら嬉しい限り☆
↑ 気に入ってもらえたら、フォローしてくれると嬉しいです。
いいなと思ったら応援しよう!