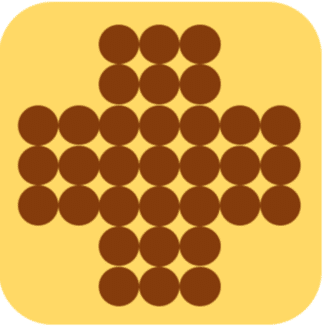「シレソ」の和音?!「真の和音」は数学的に美しい(1)
ドミソの和音、って有名です。日本では全員が音楽の授業で教えられますから。
今回は、この「和音」にまつわる、とっても悲しい話をします。
知っている人は当然知っている/知らない人は全く知らない話ですけど、オーケストラとかで基準音とされている「ラ」は440Hzの音です。そして1オクターブ上の「ラ」は、ぴったり2倍の880Hzの音になっています。
*慣例的に劇場(現場)では442Hzを愛用しがちという話は今回は無視。
*その次の「ラ」は3倍の1320Hzではなくて4倍に相当する1760Hz。「2倍・2倍・2倍」の関係になっています。
そして2つの「ラ」と「ラ」の間にはさまっている「シドレミファソ」は、この1オクターブの間隔を12等分して作られています。
「12等分」と言っても「等間隔」切り分けではなく、それら12個は「等比率」で切り分けてあります。
「等比率」の12分割は、周波数を見た目で表すとこんな感じになります。

「12個に等分割」という割り算しやすい数字(約数が多い数字)を使ったので、ドミソの和音とか、ソシレの和音、ファラドの和音とかは、3つの「音波」がお互いに「数多くの共振点」を持ちます。

すなわち3つの音が足し算された結果は「お互いが強め合い、大きく音が響くタイミング」が、一定のリズムを持ちながら繰り返し現れる状況になります。
このゆらぎ/ふるえ?/うねり?/が、「なんとなく聞こえてくる音が心地良い」と感じるシカケなのだと思われます。
*カラオケでも「ビブラート」は採点の対象になっていますよね?そういうのが、みんなが好きみたいな感じです。

***
さて、いよいよ悲しいお話に入りましょう。ラジくまるの小学校の音楽の時間、和音の勉強は 超・ザツな授業内容 でした。
後日、大人になってから音の理論を独学したラジくまるが激怒しちゃうほど、ひどい授業内容。
今でもちょっとイライラ気分を感じつつ思い出すのです。
当時、こんな授業を受けました。
まずはとにかく、和音を聞いてみよう!ということで
和音をピアノ音として聞かされたわけです。
ドミソの和音 ♪ポーン
ドファラの和音 ♪ペーン
シレソの和音 ♪ボーン
ほら、それぞれ、音同士が共鳴して、きれいに響くでしょう?
・・・・
とまあ、そんな授業を受けたわけです。
ラジくまるは小学生のくせに、こんなことを感じました。
(ほんとに、憎ったらしいマセガキだったんです)
「ドミソの3つの音の「間隔(はなれてる距離)」と、ドファラの3つの音のはなれ具合と・・・・全然、音の距離がバラバラで共通性がない?
どうして ドミソ も ドファラ も、どっちも和音だと言えるの?
理論的におかしくないか?これ?・・・・
まじ全然理解できない。
音楽っていうのは、理論なしで感性だけで突っ走らないといけないのか?
だとすれば、ボクには音楽はむりだ。
音楽って、理解不能なバケモノに思える。
小学生時代のラジくまるは可哀そうな子供でした。
この記事をごらんの皆様、皆様の身近にいるお子さんたちにはこういう可哀そうな思いを絶対にさせないであげてください。
そのためにぜひ、この記事の続きをお読みください。
和音理論の美しさをぜひ、お近くの、あるいは知り合いのお子様達に伝えてほしいです。
和音には理論がちゃんとあります。
数学的な説明が可能なのです。
・・・・ということで来週に続きます。
いいなと思ったら応援しよう!