
「鉄路の行間」No.7/司馬遼太郎を仰天させたJR木造駅
歴史小説家・司馬遼太郎には、もちろん明治維新以降をテーマとした作品もあるのだが、鉄道の影は薄い。ただ、『街道をゆく』シリーズには、”道”の一つとして鉄道が登場する。
時代が平成に入り、1994年から翌年にかけて連載された『北のまほろば』には、わざわざ「木造駅の怪」と題した一章がある。話は青森県木造町(現在のつがる市)出身の横綱旭富士から亀ヶ岡遺跡出土の遮光器土偶へと移り、JR五能線木造駅へとたどり着く。そして、「駅舎をみて、仰天する思いがした」と、この稀代の作家に記させた。

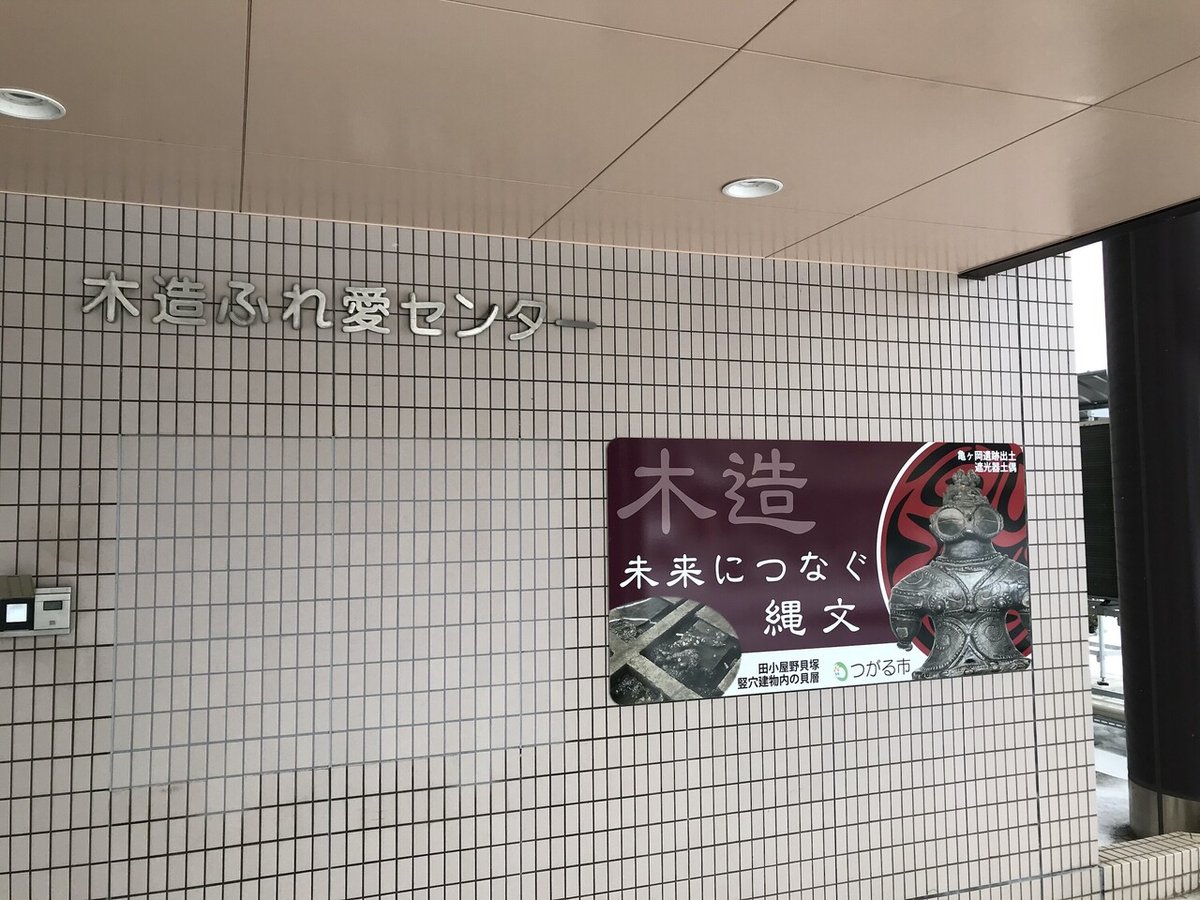
ふるさと創生事業の一環として1992年、木造駅舎はプラスティック製の巨大な遮光器土偶を外壁に張り付け、賛否両論、話題をさらった。その直後に、『北のまほろば』の取材旅行があったのだ。
司馬の感想は、同行者をふりかえり「やるものですなあ」と。そして、津軽人一般の気質として、気弱とされるものの、「ときに床を蹴やぶって起ちあがるときもある」と分析している。その表れが、この巨像だと言う。そこまで深い考察をさせただけでも、奇抜な駅を作った価値がある。

土偶は、今も同じ姿で立っている。一時期、取りやめられていた目の発光も、最近、復活したそうだ。「巨像に耐えている」と言われた町の人も、もう慣れたと判断されたらしい。訪問は冬の昼間だったが、もし夜の姿を見たら、彼はどういう思索をめぐらせただろうか。

