
「映適」正式発足から1年、歴史と志のある産業の成熟と止揚
こんにちは。パブリックグッド菅原です。
約1年前、弊社が11年間事務局を務める「リクルートGOOD ACTION AWARD」の広報活動の一環で、長く続く業界慣習にメスを入れる改革の事例として、一般社団法人 日本映画制作適正化機構(以下、映適)の取り組みや目指すべき未来像について、立ち上がったばかりの事務局にお邪魔して、大浦さんと葛西さんにインタビューをさせていただきました。
映適とは?
映画制作を志す人たちが安心して働ける環境を作るために、映画界が自主的に設立した第三者機関です。適切な環境で映画製作が行われているか審査する「作品認定制度」と、映画製作に携わるスタッフの適切な契約締結やハラスメント予防などを支援する「スタッフセンター」のふたつの機能を提供し、映画制作現場の環境改善、スタッフの生活と権利の保護及び地位向上を目的としています。東宝や松竹といった映画製作者で組織される「日本映画製作者連盟(映連)」と、独立プロダクションで構成される「日本映画製作者協会(日映協)」、監督や技術系スタッフなどフリーランスからなる「日本映像職能連合(映職連)」の映画に関わる主要3団体が共同で運営する団体です。
前回のインタビュー記事で詳報していますが、映適は、わたしたち観客が目にする映画の華やかさは、実は作り手に強いられている過酷な労働環境が前提となっているという、長く続いてきた慣行的な業界構造自体の改革に切り込む意欲的な試金石と位置付けられるのです。
映適、1年間の活動報告
運営開始から1年が経ち、映適の成果や課題、今後の構想を報告する「初年度 記者報告会」にお招きいただいたので、取材に行って来ました。報告会には、映適理事長の島谷さん(映連代表理事、東宝株式会社代表取締役会長)、理事の新藤さん(日本映画製作者協会理事)と浜田さん(日本映画撮影監督協会代表理事)が登壇されました。
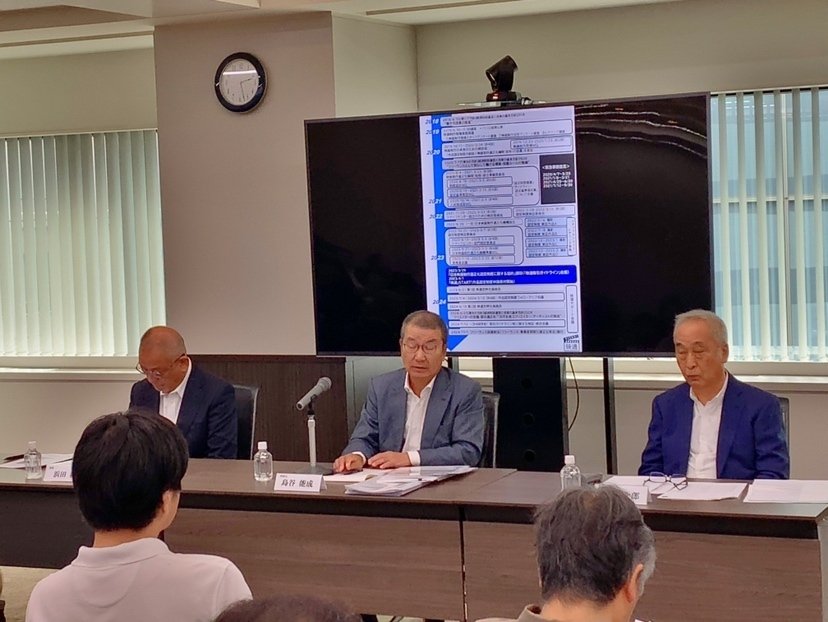
会見は、島谷代表理事の「今日はお伝えすべきトピックがあるわけでも、またパブリシティを狙ってイベントめいたことをしたいわけでもない」という、なかなか記者会見では聞くことのない直球なコメントからスタートしました(わたしは長く広報を生業としているので少しびっくりしました笑)。
「映適設立当初の『こうしていきたい』『こうなるだろう』という想いや読みが、実際に1年間やってみてどうだったのかという点について、成果と課題を記者の皆さまに共有して、色々とご意見も賜り、懇談会のようにしたいと思い、お集まりいただきました」と本会の趣旨が説明されました。
この後、前回、インタビューにご協力いただいた事務局の大浦さんから、昨年4月の運営開始から1年4月余りでの成果として
・スタッフセンター登録数:個人177名/プロダクション46社
・窓口に寄せられた相談件数:79件(うち、コンプラ案件21件。その中でハラスメント関連は6件)
・審査:申請84本(1年間でいうと約60本)、正式認定31本
といった活動結果が報告されました。
なお、島谷代表理事によると、日本では1年間におよそ550本の映画が製作されているそうなのですが、そのうち約100本はアニメーション、50本はドキュメンタリー、50本は成人映画で、これらを引いた350本が映適マークの対象になるとのこと。ただし、この350本の中には、収益目的ではなく、挑戦や自由度を重視して製作される、低予算の作品も含まれているため、映適としては製作費が1億円以上で、アカデミー賞の対象条件を満たすような興行作品(東京地区で1日3回、2週間以上映画館で公開された作品で、例年、概ね115本くらい)からの申請を呼びかけたいとしています。
設立当初は年間で20本程度の申請を見込んでいたとのことですし、80余本の申請のうち60本は製作費1億円以上ということを考えると、初年度で大きな成果を上げたと言えます。
次に、映適の財政面の報告がありました。映適には「審査料」「スタッフセンター登録料」「賛助会員の協力費」という3つの収入があり、初年度としては健全な決算を迎えられた一方で、関係各社の無償の協力に依っているところも大きく、当初目標としていた「3年で映倫のような独立的な運営」にどこまで近づけるかは今後の課題である点にも言及されました。
ちなみに、会では映適がベンチマークにしている映倫について「終戦後の1946年に、GHQの指示で設立された旧映倫だが、1956年に石原裕次郎らが出演した「太陽の季節」がきっかけとなり、業界内から第三者的に作品を評価規制する団体が必要という反省から現在の映倫が生まれた」という設立経緯も紹介されていました。へー、知りませんでした。
利害が対立する者同士の共闘
会の冒頭、新藤理事から「明日の撮影のカメラマンが足りないという事態が起こっている」という切実な現状が述べられましたが、この映適はそもそも「映画の未来(人材の獲得、良質な作品の製作)の検討」に端を発しています。
2018年に政府から「働き方改革」の推進が提起された後、2019年に経産省主導で大規模な「映画制作現場の実態調査」が行われました。映画業界で働く人の73.5%がフリーランスで、その6割以上が映画関連の年収が300万円未満で、発注書・契約書をもらっていない―。前回のインタビュー記事でも触れましたが、ショッキングな調査結果が並びます。
島谷代表理事は「今でも鮮明に覚えています。2019年10月11日、我々映画会社4社の社長が経済産業省に呼ばれて行ったところ、映画に携わる諸団体の全ての代表が会議室にずらっと勢ぞろいしていました」と当時の驚きを話します。
経産省が実施した調査結果を受け、2019年から2024年7月までに実施された公式なワーキンググループは総計238回、延べ出席人数は3,984名に及ぶといいます。公式なワーキンググループを各社、各団体が持ち帰って行われた非公式の議論はその数倍に上るわけですから、途方もない労力が注がれてきたことになります。
島谷代表理事は「わたしたち3名は何度も何度も集まりましたが、どこかで空中分解するのを常に覚悟していました。そりゃそうですよね、わたしたちはいまここではにこにこ笑って座っていますが、普段は利害が対立しているのです」と当時を振り返ります。
総合芸術である映画には膨大な関与者が従事します。できるだけ製作費を抑え興行的な成功を収めたい映画会社、安定的な雇用を獲得したいフリーランス、じっくりと製作に取り掛かりたいプロダクション等、それぞれの思惑は確かに一様ではないでしょう。
そういった中で、4年にわたって、何度もあったであろう空中分解の危機を乗り越え、粘り強く折衝を続けられた背景には、各社の利害を超えた「映画の未来への危機感」があったのだろうと感じます。あえて乱暴に言うならば、このままブラックでやりがい搾取な業界であり続けたら、遠くない将来、映画に憧れて入ってくる人材は枯渇し、良質な作品が生まれなくなるという未来への危機感です。そのために、各社・各団体がいったん、それぞれの主義主張を脇に置いておいて、丁寧に繰り返し議論を重ねて設立された映適は、島谷代表理事が言うように「奇跡」であると共に、歴史と志のある産業だからこそ成し得た「成熟」の成果と言えます。
こういった現場感をもった関与者が決して諦めることなく議論するそのプロセスに、わたし自身が模索を続ける「止揚」の姿が見て取れますし、映適という法人を設立して運営している「結果」と同等かそれ以上に、検討の「過程」にも途轍もない価値があります。「地球」「人権」のように、とかく論点が巨視的になりがちなサステナブル界隈ですが、「良い映画が観られなくなるじゃん、やべぇじゃん」のような当事者性のある課題意識こそが、実効性の高い持続可能な解決策に昇華されるのです。
会見後半では「映画製作の労働環境を改善するためには、製作費増額を受け入れられるかどうかに行き着く。その点を映画会社の社長としてどう捉えているのか」という厳しい質問が飛びました。東宝の代表でもある島谷代表理事は、映適の正式運用前の実証実験4作品を例に挙げながら、労働環境の改善には概ね10-15%の増額が必要である点、原価が上がればこれまで製作できていた作品が作れなくなる可能性がある点について言及しつつも、「それでも作り続けていくつもりです」と厳粛な表情を崩さずに語りました。持続可能性とコストは、映画に限らず非常に重要なテーマです。
一筋縄ではいかない映画業界の「適正化」は始まったばかりです。2024年11月にはフリーランス新法が施行されるなど、さらに「適正化」に関わる議論は加速することが予想されます。今後も注目していきたいと思います。

ちなみに1Fでゴジラが出迎えてくれる東宝本社、会場となった会議室は「ゴジラ会議室」と名付けられていて、初期ゴジラのポスターが飾ってあり、テンションが上がりました。



