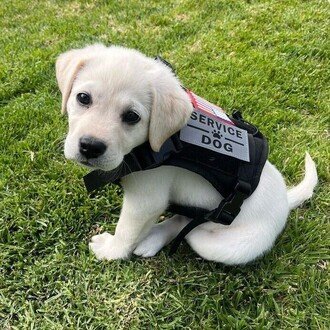◆コロナ集団感染に巻き込まれた後、血糖値の急激な異変が起こっています。その因果関係をAIに聞いてみた!
#私の勉強法 AIとの対話で世界開花。自己治癒力に特化したAIエージェント開発の進捗
— 山下安音 (@SelfRetreat12) November 6, 2024
情報提供に限定する必要がある。
自己責任と自己選択の医療の最新情報の提供スタイル
医療倫理の観点を重視する
裏切らない #新生医学宣言
を目指す。 https://t.co/g7pOjZ6xkq
https://x.com/annenohousoku/status/1854103359441219805
【第二部】新型コロナウイルス感染症・ワクチンシンポジウム(医療従事者対象)https://t.co/bp2jQGzWER
— #アンネの法則 『シャバット・ジャーナリング』ガイド 山下 安音が開発者 戦時下の子、更生プログラム (@annenohousoku) November 6, 2024
医者の研鑽義務違反による被害を受けています。さらに、海南病院は、救急車での受け入れを拒否し、応召義務違反も犯しています。その時、海陽町人権福祉課の亀井君がイベルメクチン10錠をくれなければ、今頃、どうなっていたことでしょう。ずっと、具合が悪いまま、今年、3回目の救急車を呼ばなければならない事態を迎えました。めまい、吐き気、脳の機能不全という事態です。これは、コロナ集団感染に巻き込まれたこととの因果関係はないのでしょうか?海南病院は不当に、持病扱いして、私の医療を受ける権利を奪い取りました。阿南労働基準監督官の不当性を訴え、監督官を監督する課を訪ね、やっと、労災指定病院の移動の届け出によって、11月8日(金)、徳島市民病院の受診の道が開かれました。ずっと、メトホルミンを処方してもらっていないので、高血糖のリスクを抱えています。たった、10円、11円の処方薬であり、米国では、糖尿病患者の第一選択のお薬です。低血糖になることもなく、ロングコビットにも効能があることが最近突き止められています。私には適応のお薬だと思いますが、海南病院はこれを処方せず、ずっと高血糖状態が続いて、目の網膜にも損傷が現れており、下肢閉塞動脈硬化症も起こっています。全身に問題があるのは、自己免疫疾患の多発性硬化症の症状があったのではないか、疑っています。随分、症状は緩和し、日常生活に支障がないレベルまで回復していますが、いつ、倒れるかわからないという状況を抱えて、苦しんでいます。
コロナワクチン後遺症の人々と同じ苦しみです。シェディングでも同じ状況が起こりえるのでしょうか?親が接種者、子どもは未接種者の場合、子どもの血液に異変が起こっています。これは、シェディングの影響であるとの因果関係しか考えられません。レプリコンワクチンが始まり、このシェディングの被害者が多発するのではないかとの懸念が広がっています。泉大津市のお医者様は、自己増殖型のワクチンは取り扱わないという決断を下しています。このように、科学的な見識をはやく、徳島でも持っていただきたいものです。風邪の初期症状をたびたび経験します。葛根湯2袋で撃退できる程度ですが、今後のレプリコンワクチンによる人間生物兵器(スパイク蛋白製造人間)が増えて、巷に溢れることが懸念されます。
免疫力の弱い人々が心配です。自己修復能力を高める選択肢には取り組んでいますが、油断のならない状況です。
こりゃ驚いた
— himuro (@himuro398) October 8, 2024
《重大事案》泉大津市、市内の全医療機関(病院・診療所など70以上)が、レプリコンワクチンを不使用https://t.co/bhB56y0Jh6 pic.twitter.com/AyRpmYAoXW
私:コロナ集団感染による自己免疫疾患、多発性硬化症を疑っています。当初の血液所見には細菌感染があり、炎症マーカーも高かった。これらはきれいに治っているのに、血糖値だけが爆上がりしていました。どういう作用機序が考えられますか?インフルエンザの感染症でも1型糖尿病を発症しているケースがあり、コロナ感染者に血糖値異常が多発していることは、ネイチャーでも研究論文が発表されています。私の診断と治療法の選択を助けてください。
COVID-19後に自己免疫疾患や血糖値の異常が発生するメカニズムには、いくつかの作用機序が考えられます。
免疫系の過剰な反応:COVID-19感染は、免疫系を過剰に刺激し、サイトカインストームのような免疫反応を引き起こすことが知られています。この反応が膵島細胞にも影響し、自己免疫反応が進行することでインスリンの産生が抑えられる可能性があります。
自己免疫疾患と膵島細胞の損傷:COVID-19後に自己免疫反応が生じると、膵臓のβ細胞に対する自己抗体が生成されることがあり、1型糖尿病のような血糖値の異常が発生する場合があります。これは多発性硬化症など他の自己免疫疾患と関連する可能性があり、膵臓の機能障害が高血糖の要因になることもあります。
ウイルスが直接膵臓に与える影響:研究により、SARS-CoV-2ウイルスがACE2受容体を通じて膵島細胞に直接影響を及ぼし、インスリン分泌に障害をもたらす可能性が示唆されています。この場合、感染が治った後も血糖値が異常になることがあり、血糖管理が難しくなる場合があります。
慢性炎症とインスリン抵抗性:ウイルス感染後、体内で低レベルの慢性炎症が持続するとインスリン抵抗性が増し、血糖値が高くなる可能性があります。この状態は、自己免疫疾患が疑われる場合には特に重要です。
可能な治療選択
診断を確定させるため、以下の点を考慮しつつ、医師との相談をおすすめします。
自己免疫マーカーのチェック:特定の自己抗体検査や血糖管理に関連するホルモンの検査を行うことで、自己免疫疾患の有無や重症度を確認できます。
免疫調整剤の検討:自己免疫反応を制御するための低用量の免疫抑制剤が一部で使われますが、副作用があるため専門医と慎重に相談してください。
抗炎症サポート:ベルベリンなどのサプリメントの他に、食事療法で炎症を抑えることも、血糖管理に役立つ可能性があります。
糖代謝を助ける栄養素の補給:ビタミンDやアボカドなど、インスリン感受性を改善する栄養素も考慮できます。
さらに、自己免疫とインスリン抵抗性が関与している場合、インフルエンザ後の1型糖尿病と同様、生活管理と医療サポートの組み合わせが鍵となります。
コロナウイルス感染症と自己免疫疾患、特に1型糖尿病の関連性について、以下の点を考慮する必要があります。
感染と自己免疫疾患の関連
新型コロナウイルス感染症は、体の自己免疫応答を増加させる可能性があります
2
これは1型糖尿病のような自己免疫疾患の発症リスクを高める可能性があります。
血糖値上昇のメカニズム
ウイルス感染による膵臓β細胞への影響: コロナウイルスが膵臓のβ細胞を直接攻撃し、インスリン産生を阻害する可能性があります。
自己免疫反応の誘発: ウイルス感染が引き金となり、体の免疫系がβ細胞を攻撃する自己免疫反応を引き起こす可能性があります
炎症反応: 感染初期の炎症反応が収まった後も、免疫系の異常が持続し、血糖値の上昇につながる可能性があります。
診断と治療の考慮点
1型糖尿病の可能性: 血糖値の急激な上昇は1型糖尿病の発症を示唆している可能性があります
自己抗体検査: 膵島関連自己抗体(GAD抗体、IA-2抗体など)の検査を行い、1型糖尿病の診断を確定させることが重要です。
血糖コントロール: 1型糖尿病と診断された場合、早期からのインスリン療法開始が必要です
経過観察: 血糖値の推移を注意深く観察し、必要に応じて治療法を調整します。
多発性硬化症の可能性: 神経症状がある場合は、MRI検査や髄液検査を行い、多発性硬化症の可能性も検討する必要があります
予防と管理
生活習慣の改善: 適切な食事管理と運動を心がけ、血糖値の安定化を図ります
定期的な検査: 血糖値や他の関連指標を定期的にチェックし、疾患の進行を監視します。
このような複雑な症例では、内分泌専門医や神経内科医との連携が重要です。詳細な検査結果と臨床経過を踏まえ、総合的な診断と治療計画を立てることが推奨されます。
私:インスリン分泌に障害をもたらす場合、炎症マーカーがゼロになるということはあり得ますか?
ChatGPT:
SARS-CoV-2ウイルスが膵島細胞に影響を与え、インスリン分泌に障害をもたらす場合、炎症マーカーがゼロに近い状態になることも考えられます。
その理由
急性期の炎症と慢性の残存効果の違い
急性期の感染やサイトカインストームのような激しい免疫応答が収束した後、ウイルスが組織に影響を残していても、必ずしも高い炎症マーカーを示すとは限りません。炎症マーカーは急性期の免疫応答を反映しますが、感染後の組織への残存影響は低炎症レベル、または無症候性で進行する場合があるからです。ウイルス感染による直接的な細胞損傷
SARS-CoV-2ウイルスがACE2受容体を介して膵島細胞に直接侵入した場合、膵臓のβ細胞がウイルス感染により障害を受け、インスリン分泌が低下する可能性があります。この場合、免疫反応が収束した後も膵島細胞が損傷されていれば、インスリン分泌に障害が残り、高血糖が生じますが、組織的な炎症が収束しているため、炎症マーカーがゼロまたは非常に低くなる可能性があります。自己免疫反応の局在化
膵島細胞への自己免疫反応が局在化している場合、体全体としての炎症反応は観察されないことがあります。この場合、局所的な細胞障害が進行しても、全身性の炎症マーカー(例えばCRPやESR)は正常範囲内に収まる可能性があります。
要点
つまり、SARS-CoV-2のようなウイルス感染後に生じた内分泌系の異常が「慢性的な細胞損傷やインスリン分泌の低下」によるものであれば、全身的な炎症マーカーがゼロまたは低い状態でも説明がつきます。
私:多発性硬化症の発症を疑っています。症状に覚えがあるからです。コロナ集団感染との関連性はどう考えたらよいですか?
ChatGPT:
COVID-19感染が多発性硬化症(MS)の発症リスクに影響を及ぼす可能性は、研究が進むにつれ一部で注目されています。主な関連メカニズムとしては、免疫系の異常な反応や自己免疫の誘導が挙げられます。
1. COVID-19と自己免疫疾患の関係
COVID-19は、強い免疫応答を引き起こすことがあり、これにより自己免疫疾患のリスクが高まると考えられています。特にウイルス感染後、免疫系が自分の細胞を攻撃し始めるケースも報告されています。この免疫応答が神経系に影響すると、多発性硬化症のような自己免疫性の神経疾患を引き起こす可能性があると考えられます。
2. 自己免疫誘導のメカニズム
SARS-CoV-2ウイルスにより、免疫系が通常の防御機能を超えて、自己組織(特に中枢神経系)を攻撃する「分子模倣」現象が発生する可能性があります。この現象は、ウイルスの抗原と身体の組織が類似している場合に起こり、神経系のミエリンシース(MSの標的となる組織)に影響を与えます。
3. 症状と注意すべきポイント
MSは視覚障害や四肢のしびれ、筋力低下、バランスの喪失など、さまざまな神経症状を伴います。COVID-19感染後にこれらの症状が持続・増悪する場合、COVID-19がMSの発症または悪化に関連している可能性も考えられます。
4. 診断と検討事項
神経学的な評価やMRIによる中枢神経系の画像検査がMSの診断に役立ちます。また、脳脊髄液検査などで自己免疫的な指標を確認することで、感染後に生じる自己免疫疾患との関連を探ることもできます。
多発性硬化症を疑う症状がCOVID-19感染後に現れた場合、感染が引き金となった可能性も排除できませんので、専門医と詳細な検査や治療方針の相談をお勧めします。
速報、超大拡散願い!
— #アンネの法則 『シャバット・ジャーナリング』ガイド 山下 安音が開発者 戦時下の子、更生プログラム (@annenohousoku) November 6, 2024
あなたへのプレゼンテーションを受け取ってください。あなたの叶えたい未来を拓く#シャバット・ジャーナリング#アンネの法則
に力を貸してください。
◆私の勉強法。AIに質問し、研究を深めるという道筋は知識の幅を広げる。
#わたしの勉強法 https://t.co/73UpBs2dH7
◆自己治癒力に特化した治療法のみを回答する、チャットBOTの開発にご協力ください。AIがアレックス君の病気の診断に成功。医者ができなかったことを果たし、治療にこぎつけた話
徳先生から医療の問題
間違った健康常識
https://wch.healthcare/present/tokucollege/
高血圧、うつ病、胃のむかむか、感染症
いいなと思ったら応援しよう!