
誰が勇者を殺したか
話題になっていたので読んでみた。中年も半ばを過ぎて角川スニーカー文庫を買う事があるとは思わなかったよ。
結果、今年読んだ本どころか、人生の10冊に挙げても良いと思える本だった。…マジで?
今後の人生において目の前に困難が立ち塞がった時、必ず思い出す一冊になるだろう。
※以下、ネタバレがあります。
帯より
勇者は魔王を倒した。
同時に__
帰らぬ人となった。
魔王討伐直後に姿を消した勇者の死因を探る為、文献の編纂者が勇者のパーティメンバーだった3人(騎士・賢者・僧侶)を中心としたインタビュー形式で調査を進めていく、ファンタジーマーダーミステリー小説だ。
スタート時点において勇者の死後で、その足跡を追っていく話なので、葬送のフリーレン味がある。
前提として、
文芸作品において「何について書かれたか」と「作品を通して何を伝えたかったか」はそれぞれテーマ(主題)とメッセージと呼ばれる。
今回は「勇者の死の謎を突き止める」部分がテーマに当たる。まずはこの部分の出来が非常に良かった。
240ページ程と短い作品ながら、構成に無駄がなく、回収できていない伏線もない。とても綺麗にまとまっている。特にエピローグが秀逸で、エピローグだけでも読む価値がある。エンタメとしての強度が高いので、メッセージもしっかり入ってくる。この作者腕があるわ。(偉そうに言ってごめんなさい)
で、この作品のメッセージ・伝えたいことの部分なんですが、私は「努力」についての物語だと理解しました。(解釈はそれぞれあると思います。愛の物語と取ってもいい)
作中人物(賢者)の独白を引用すると、
“ 本当に無駄なことが好きなヤツだ。俺は無駄なことは嫌いだ。いや、だった。無駄だと嘲笑うことは簡単だが、無駄になるかもしれないという恐怖と戦いながらも、前に進むことのほうが正しいのだと、俺は思うようになった。”
P103より引用
ここに要約されている。
実を結ぶ可能性が低い努力を続けることは、とても難しい。人生を浪費して、何も得られることはありませんでした。という結末になるかもしれない恐怖に、普通の人間は耐えられない。
だから人は見切りをつける、才能がないから、美しくないから、頭が良くないからと。
だが、見切りをつけて、夢や目標を手放せる人間はまだ幸福だ。
困難に直面した程度では手放すことが出来ないほどに、分かち難く自身と癒着してしまった目標。執着と言い換えてもいい。を持つ人間は、構造的に逃げ出すことすら出来ない。
「諦めなければ、夢は叶う」という言い回しは耳に優しいが、「降りられないので、叶えるしかありません。もしくは、人生を使い切るか」と言い換えると最早ホラーだ。
大体の物語の主人公は、努力によって大成する。だがそれは、努力によって才能を開花させました。という描かれ方が多い。まあ、そうじゃないと華がないし。
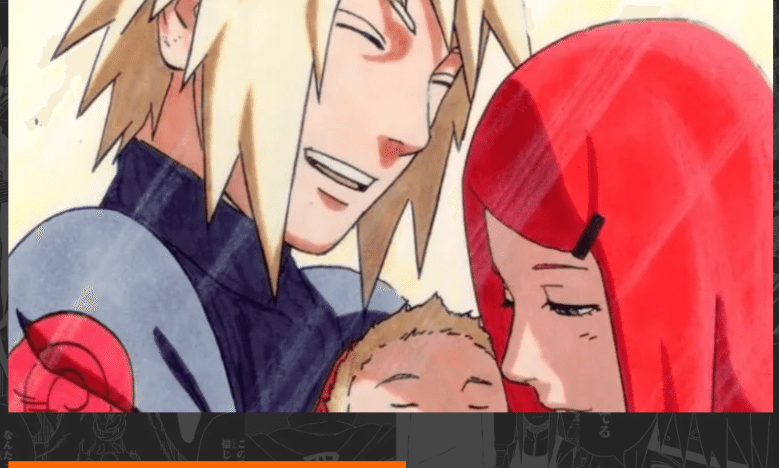
今作の主人公は、才能がない。
作中で主人公はつよつよ騎士の仲間に「強くはなったが、そこまですれば誰だって強くはなる。常軌を逸した努力に対しての成果としては少ない」と評されている。
かわいそっ
しかし、常軌を逸した努力によって奇跡も起こす。
作中では、「回復魔法というのは、神の存在を知覚する事が出来る人間に備わる能力で、ようするに生まれた時点で出来るか出来ないかが決まる。信仰心の強弱は関係がない」という身も蓋もない設定なのだが、主人公は長年の努力の結果。初歩の初歩くらいの回復魔法は使えるようになる。
出来たから何?程度の事ではある。出来る人間は子供の時から出来る事で、こちらも努力の量に成果が全く伴っていない。
ただ、0が1になった事に評価不能な程の価値がある。
量より質と言うが、逆だ。量の上に成り立つのが質であって、量の積み重ねが質の変化をもたらす。ありえない努力量は、どこかで閾値を超え、質の変化となる。ただ、通常は質の変化が起きるほどの努力を続けられないのだが、その、資質というか才能というか遺伝というか、そういった断絶を越境していく人間が極々まれに世界に誕生していて、その人物が周囲に与えるポジティブな影響は計り知れない。
希望の体現だからだ。
願わくばそのような人間になりたいものだよなあ。
今後、自分の人生に困難が立ち塞がるたびに考えることになるだろう。
ザック・シュレットなら諦めるか?と
おわり。
