
撮影者は歌う|竹久直樹
共有不可能な経験を共有するための拡張子。
竹久直樹は「撮影」のプロセスからこぼれ落ちたものをすくいあげる。シャッターを押すことで捉えられなかったフレーム外の膨大な出来事を伝えようとする。それは写された出来事を豊かに物語ると同時に口をつぐみ秘密を抱えてしまう写真の相反する性質を重ね合わせようとする行為だ。そのプロセスを竹久はあえて「撮影」と名付け、あたかも普遍的で当たり前の行為かのように示している。
写真はいま、インターネットで繋がったSNSやメッセージの内部に溶け込み、何かを伝えるための手段となった。撮影は、他人に見せることを前提とした行為や経験へとその重心を移しつつある。しかし、写らないものがあり、伝わらないものがあるという決定的な断絶は消えてはいない。どうしたら伝わるのだろうか。この極めて個人的でありながら、誰もが抱える普遍的なディスコミュニケーションの問題に竹久は取り組もうとしている。われわれの間にある絶対的な距離を縮めるためには、あらゆるところに存在する複数の「撮影」が衝突し、もつれ、重なり合う新たな“拡張子”が必要だ。
text|酒井瑛作
image|竹久直樹 “Car Music 4K” 2023 IG



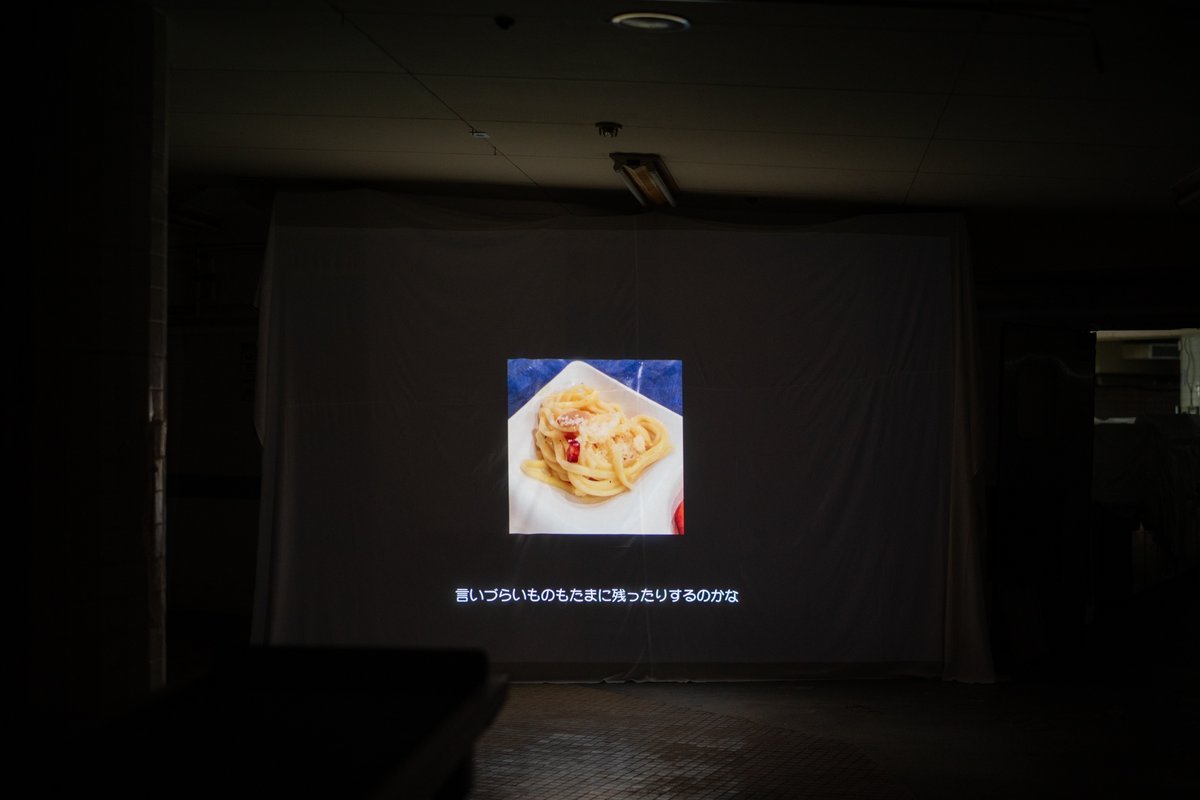

「写真とは何か?」なのか?
――以前、竹久さんと話したとき、2010年代あたりから生まれた写真の流れにたいして、ちゃんと写っている/写っていないという観点から話してましたよね。それが面白くてもう少し聞いてみたいな、と。
酒井さんがおっしゃっているのは、例えば 港千尋さんと後藤繁雄さんの共同キュレーションの展覧会で扱われていたような流れですよね。自分はもろにそういうものを見て育ってきた世代です。大学入学くらいのタイミングでCharlotte Cottonの『Photography Is Magic』(2015年)という本が出たこともあり、これから写真の時代だ!と言われていたりして。それで写真を使ったインスタレーションがものすごく流行ったように感じるのですが、 流行っているものを見ていると「なんだかぼんやりしてるな」と思ったんです。
――それは言説的な部分が?
そうです。批評において「そもそも何を写した写真なのか」「なぜ撮りたかったのか」が抜け落ちてるなと思いました。「写真の写真」を撮ればいいのかよ、と。
――写真表現は、自己言及的な方向へと進んでいって「写真とは何か?」がメインのテーマになって、その結果、写真で写真をあらわすというメタな感じになった。
そうなると、作家の体験から鑑賞者の体験へ脱出できない気がするんです。つねに作家の体験の焼き回しになるから、暗室的な外からは見えないものを展示することになっている。表現のフォームとしては「写真とは一体何なのか?」をあらわしているわけですが、それだとやっぱり自己言及の外に出られない。
――その問い自体、普遍的に見えて、実は属人的で個人的なものなんじゃないか、みたいな?
というか、カメラがないと撮れないとか、シャッターを押さないと撮れないとか、そういう不思議さがまだ解決されてないと思うんです。なのに、撮れるということが前提の問いになってしまっている。目の前に光があって、それを写す、何かが出てきしまう。それは一体何なのか。そして人間はなぜそんなものを使うのか。自分としては、そこに撮影者がいるということを考えたくて。そのとき作家と撮影者が混同されていると思うんです。それで、撮影者のユニークさで作品を担保するのは甘いんじゃないか、とも思ったんですよね。
――甘い……。
甘いというか、それはわかんないよ、と思っちゃうんですよね。
――作家の体験と鑑賞者の体験が断絶するから。
そう、あなたの撮影体験を見せられても、こちらはどうしたらいいかわからない。話は飛ぶかもしれませんが、これはまるごと荒木経惟さんなどが評価されてきた「個人的なことを作品にしてしまう」という文脈に繋がる話です。
――私写真ですかね。
それを写真という土壌でやる場合、自分が写真を撮るときに一番大事にしてはいるけど、同時に不満に思っていることが解決されていないとも感じる。日本だけなのかどうかはわからないのですが、人は他人の秘密を知りたいのだなとも思ったんですけど。

――不満に思っていることがある?
ここでシャッターを切ったら、自分と酒井さんは写るけれど、この場の細部って共有できないじゃないですか。そもそもこの出来事を人に見せるために写真はあるのに、一方で表現になると見せ方自体に終始している感じがするんです。人に見せようとしているものを毀損して見えない状態にして、写真の写真ですよ、というふうに言うのは、そもそもの役割が潰されている。自分にとっての写真は、まずものが写っていること。それがどういう状態かというと、知らない人に見せたときに何が写っているか識別できる状態。ぼんやりしているね、でもいいと思うんですけど、写ってないね、では意味がないというか。
――写したものを人に共有するものとして写真があるはずなのに、同時に秘密も生まれてしまう二面性があるということですね。なおかつ表現では、秘密をさらに重ねるような方向になっている。竹久さんは写真の存在理由を解き明かすというよりは、撮影者としての私の普遍性とか、写真にまつわる行為の普遍性について考えてますね。
カメラやメディアについては普遍化されてはいるけど、写真が持っている社会の中のロールは普遍化されないなと思ったんですよ。写真が一般的にどういうものなのか定義はされないけど、カメラの不思議さは定義される。だけど、それはカメラであって写真ではない、みたいなことは常々思います。
撮影できないフレームの外側。
――新宿眼科画廊での個展「セルフポートレイツ」(2018 年)は、2つのカメラで同時に撮影する作品でした。これは撮影している様子を撮影するという試みでもあって、以降の作品にも連なるテーマですよね。
展示の核になっていたのが《fpsss》という作品で、iPhone2台をシンクさせて、片方のシャッターが切られるともう片方のシャッターも切られるという。撮影する度に2枚の写真があらわれる作品です。重要なのはiPhoneを使っていることで、誰でも撮れるからいい、と当時は考えてました。大きなカメラになると上手い下手が出てくるけど、iPhoneの手軽さはそこから脱出できるな、と。それまでネガフィルムで写真を撮りためてはいたんですが、ぼんやりと作品にならないという手触りがあって。そこで感じたのが「撮影を共有できない」ということだったんですよ。例えばどこか車に乗って遊びに行って写真を撮る経験って誰にでもある一方で、フィルムで撮って現像するという経験が、誰にでもあるとは到底思えなかった。もっと言えば、フィルムカメラを構えて撮りたくなる被写物とか、その経験が一般的なものかと言われれば、全然そんなことはない。


――カメラ自体から行動が喚起されることはありますよね。
でも、遊びに行ったときにカメラをぶら下げている人よりも、そうではない人の方が多いわけで。すごく当たり前のことなんですけどね。ただ振り返ると、「iPhoneは誰でも持っている」 というのは先進国の考え方だな、と今は思います。
――そこまでいきますか。
自分的にはそのレベル感で考えたいです。あと撮れば撮るほど写っていないもの、写らないものが増えていくなと思うんです。
――時間的なものが抜け落ちるということ?
カメラの後ろは写らないじゃないですか。
――フレーミングか。ある枠組みで切り取ってしまう。
自分がそういった抜け落ちたものに強く惹かれるのは、撮影中より撮影前や後の方が楽しいからなんですよ。車に乗って撮影場所まで行く過程は楽しいし、何より時間がすごく長い。1時間の撮影のために、8時間移動するみたいなことはザラにある。その総体をやっぱり撮れない。というか、人に見せるには長すぎるんですよね(笑)。
――(笑)。誰もが経験する撮影の体験や、その総体を撮影したり見せたりするスタンスをミニマムな形であらわしたのが《fpsss》 だった。
そうですね。当時はそれをどうやって撮ろうかと考えながら、頑張って達成しようとした作品が《fpsss》でした。せめてカメラがどうなっていたかくらいは撮れるようにしておこう、と。学部3年生の終わりの頃の作品で、はじめて作品と呼べるものをつくったという実感があったものです。すごく粗いんですけど、何にキレていたのかがよくわかる(笑)。こんなに綺麗に写ってるのに、全然撮れてないじゃないか!という。
ニュータウンは透明な街ではない。
――竹久さんはインスタレーションを主軸にしていますが、デカメロンでの「スーサイドシート」(2022年)からディスプレイとプリント以外のものも入ってきて、より複雑な構成になった気がして。それは撮影にまつわる総体を見せようとした結果、そうなったのだと話を聞いていてよくわかりました。ただ、これまで「決定的瞬間」的なものが、あるひとつの出来事の全体を1枚であらわそうとした試みだったとして、インスタレーションという形式も一応はひとつの空間に収めないといけないわけじゃないですか。そのあたりはどう考えていたんですか?
エスティマに詰め込めるボリュームでインスタレーションをやるということだけは、最初に決めていました。ちょうど展覧会の話が来たくらいのタイミングで、エスティマが廃車になって、スクラップされてしまったんです。エスティマは学生のときに友人が持っていたトヨタのミニバンで、大学時代の撮影や設営のみならず、本当に毎日乗っていました。「車に乗る」といえばエスティマに乗ることだ、というくらいの……自分の車でもないのに、強い思い入れがあって。だから廃車は本当に悲しかった。それであの乗っていた体験を残すにはどうすればよいのか、というところから展覧会を組み立てることにしたんです。

――エスティマというフレームから考えはじめた。
最初は過去の写真で構成しようと思ったんですが、ちょっと骨を拾いすぎてるなとも思って。なので、新しく撮り下ろしたんです。展示がまとまったのは、人が展示に来て帰るまでのことと、わわれわれが会場に搬入搬出することが重なるところだけで構成すると、普遍的なプロセスが作品化できるんじゃないか、と思いついたとき。やっぱり自分の体験だけだと、個人的すぎて話が通じない。あ、そういうことがあったんだね、と他人事になってしまう。なのでカメラを持っていなくても、撮影がどういう体験かがわかるものにしたくて。なので、鑑賞者の経験と自分の経験がベン図のように重なるもので、展示を構成したんです。
――竹久さんのいう「撮影」の幅はやっぱり広いですね。自分的には、モチーフとして郊外的なものを感じたんです。建売の一軒家を写したものだったり、マックの袋だったり、ホンマタカシの『東京郊外 : TOKYO SUBURBIA』にも重なるモチーフがありますよね。ただ、竹久さんは外部に立つ観察者に徹するというよりは、プロセスの一部となって自らも参加しているような感じで。ここにも個人的でありながら、普遍的でもあるような質感があると思います。
もちろん郊外のことも考えてました。展示を構成するモチーフを選ぶうえで、郊外だったら自分が許せるレベルで普遍性があるな、と。ホンマさんの写真集で港北ニュータウンが出てくるんですが、そのなかに自分の通っていた学校の裏あたりの、北山田の写真があって。それを見たときになぜかすごく怒っちゃったんですよね。そうやって冷たい目線で撮って !って(笑)。なんだかバカにされているような気分になったのかもしれない。

――自分もニュータウンではないですが、郊外(相模原市)育ちなのでわかります。付属の冊子に宮台真司のコラムが掲載されていて「郊外の子どもたちは生気のない目をしている」的なことが書いてあって、読んだ当時はそんなことないけどなーと素朴に思いました。
鷲田清一さんが著書の中で「ニュータウンには大木と、宗教施設と、いかがわしい場所がない」 と書いていて。そんなことはないだろ、と(笑)。たしかに郊外では、 農村地区だったところの土俗的な信仰は棄却されている。だから、ないのではなく、消されたのだというのがひとまずの自分の理解で。郊外を扱うとなったとき、ひとつの返し方として別に冷たい場所ではない、と言いたいのはあります。かつての時代の熱さはもちろんないのだが、しかし何かを信じるような個人的なものは残っているし、ある。
――チェーン店が並ぶ国道16号線のような人工的で均質的な風景と言われるなかにも、個人の存在はありますからね。別の作品ですが、東京都と神奈川県の間を流れる境川も撮影してますよね。
面白いところですよね。もともと境川は地元住民の運動で整備されなかったんですよね。橋本から相原あたりは、いまでも蛇行したまま。だから雨のときはレーダーが真っ赤になって、めっちゃ氾濫するんですけど(笑)。このあたりは工場地帯と新興住宅地の緩衝地点に法政大学とか多摩美とかがあるような場所です。そういえば、卒業制作展のビジュアルを担当したときに、ぼんやりとしたニュータウンを撮ったんですよ。テーマは「透明」でした。タイトルは「#00000000」と8桁の数字で。いわゆるメディア芸術の展示の問題は、メディアが前傾化することであり、作家の意図が透明になることで、それを逆にするにはどうしたらいいのかというステートメントでした。そういうことを話していたときに、さっきの鷲田清一のテキストを思い出して。透明でも面白いし、神社がなくても全然面白い、ということに気がつきました。

――そもそも透明な街ではないし。
透明に見えてるだけ。というかたぶん、あんたが持ってるカメラがボロいんじゃないかって、卒展のときは本気で思ってました(笑)。自分の作品には、ニュータウンとまだニュータウンになっていない端境がずっと登場してるんです。それは自分が好きだからというのもあるけど、ある程度狙って撮ってもいます。

――きりとりめでるさんが書かれたレビューでは竹久さんの作品について「プンクトゥムとストゥディウムの往還」という表現をしていて、その通りだと思いました。それは写真家と撮影者、個別的な経験と普遍的な経験、ニュータウンの透明さと不透明さといったものの揺らぎですよね。
写真を撮るということは、そもそもそういうことなのかも。最初の話に繋がると思うんですけど、写っていて何かが判別できるという状態は、もう個別のものではないと思うんです。自分の撮ったものを見せるのは、すでに他人の経験でもある。その時点で見る人に引き渡されているんですよね。
鼻歌はインターネットを超えて。
――共有、伝達というテーマが繰り返し出てきていると感じます。SNOW Contemporaryでの倉知朋之介との二人展「逆襲」では、SNS以降の感覚や表現を形にしようとしています。たぶん共有や伝達って要するにインターネットの話でもありますよね。竹久さんはTumblrに触れてきたということですが、どんなものを見てきたんでしょうか。
前置きとしてTumblrは、ポートフォリオとして使いはじめたんです。高校生のとき、写真を貯めておく場所としてサイトをつくって、とにかくアップしてました。なので面白い画像が転がっていると気がついた頃には、Tumblrの流行が終わっていた(笑)。自分は「インターネットの残り香世代」と思っていて。一番おいしいところを逃したな、と。
――Tumblrが一番面白かったのは、2010年代前半から中盤くらいまでと言われてますね。
その後に Tumblr上で、ポストインターネット・アートと呼ばれるもの……なぜかほとんどがインスタレーションビューだったんですけど、そういうものを本当にいっぱい見ましたね。あとは、上妻世海さんが「世界制作のプロトタイプ」(*1)という展示を日暮里でしていたのですが、見に行ったら全員年上だと思って。年代も年齢も違うけど、鷲田清一やホンマタカシと、お絵描き掲示板やポスト・インターネットの人たちと自分とのギャップは重なるところがありますね。羨ましいなっていうまなざしがある。
――そのあたりの感覚を踏まえて今回の展示がある?今回の作品は、縦位置の画角で雨がしとしとと降っているなか、車の助手席に座っている竹久さんを固定で写している映像です。あれを見て自分はGIFを思い出しました。あの、川とか滝とか水だけが動いているやつ。Tumblrの叙情、ムードの残り香っぽいと思いました。
ありましたね。雨はたまたまです(笑)。あれは「歌ってみた」動画なんですよ。だから一人で、定点の映像になっていて。変なものができちゃったなーという感じで、まだ自分でもよくわかってないんです。完成までの経緯を話すと、もともとは字幕が入ってました。映像では歌っているだけなんですが、その前に長い一人語りもありました。ただ、「長い一人語り」とか、「意味不明な映像に字幕がついている」とか、そういったものが作品のためのエクスキューズに思えちゃったんですよね。それで最終的に取ったんです。声撮りを頼んだ友人に字幕なしの映像を送ったのですが、こっちの方が見てはいいけないものを見た感じがすると言われて、じゃあこれで、と。

――人に聞かれることを前提として歌っていない感じはします。
普段の自分だったら絶対字幕はつけて出すと思うんですが、二人展で倉知くんもいるし、なしでいってみるか、とはじめてそういう気持ちになって出してみました。
――それで、歌っているのみの映像になった。自分は原曲を知っていたので歌われているのがSOPHIEの“BIPP”だとわかったのですが、彼女はポスト・インターネットのアーティストであり、Hyperpopと言われる前のBubblegum Bassと呼ばれていたジャンルの音楽でしたよね。
そうですね、SOPHIEはすごく聴いていて好きだったんですが、作品とは接続されていなかった。亡くなったとき、自分なりに骨を拾いたいなと思っていて、でも拾い方をどうしたらいいんだろうかと思っていたところで、この作品でいきなり結実したという。
――そもそもなぜ「歌ってみた」なんですか?
学生のとき、車の中で音量をゼロにしたEDMに乗るという遊びをしてたんですよ。SkrillexとかPorter Robinsonとか、どのタイミングでドロップが来るのかを覚えて。このことを思い出したのが、今回展示している写真作品の撮影に向かう道中だったんです。重要だったのは、歌詞のない電子音楽だったことで、ボイスサンプリングをベースにした音楽がコミュニケーションで使うはずの声を楽器にして口で身体を制御している、その状態を扱えたらいいなと思いました。

――結果的に歌詞のあるSOPHIEの曲になって、ふんふん歌ってるんですけど、コーラスのフレーズ“I can make you feel better”は、はっきりと歌っていて、そういうところがミームのように伝播していく感じだなと思いました。
それもたまたまなんですよね。自分としては、SOPHIEの曲を知らない人が覚えて帰ったらいいと思ってます。そうすると、少しインターネットから自由になるんじゃないかな。今回はすごく自分勝手で、深く考えずにつくった作品なんですよ。
*1|2015年4月18日(土)~4月29日(水)、日暮里「higure17-15cas」にて開催されたグループ展。宇川直宏、梅ラボ、GraphersRock、50civl、千房けん輔田中良治など14名が参加。キュレーターの上妻世海は、前年の2014年に展覧会「≋wave≋ internet image browsing」(TAV GALLERY)を企画している。
経験はもつれて重なり合う。
――覚えて帰ったらいいっていうのは、これまで竹久さんが話していた共有の別の方法かなと思うんですよね。感覚的にやっているかもですが、リアルとインターネットが複雑に絡み合った共有の方法だなー、と。
歌詞やデータじゃない共有、を考えていたときに、ふと前にネットで読んだ「鼻歌が一番優れた保存・再生の拡張子なんじゃないか」というテキストを思い出して。自分が考える「撮影」というものは、基本的に完璧な記録ができない。過去のことだし、個人的すぎるから。でも個人的なことは全員が持っていて、それぞれの一番身近なものと言ったら鼻歌なんじゃないかなって。
――拡張子って形式じゃないですか。竹久さんは保存・再生の形式そのものをつくりたい?
そうしないと人に引き渡せないなと思うんです。自分が何かを表現したいとかではなくて、人への引き渡し方をずっと考えちゃうんですよね。どう見せるか、ですらなくて、見た人がどうなるか。だから、次の日に食べたご飯の味がどうなるかとかをずっと考えてしまう。例えば「スーサイドシート」であれば、展示を見て次の週にマックへ行ったときに、突然展示が発動するみたいな感じだといいなと思う。それが体験として保存と再生ができていることなのかなって。
――それが「撮影」の経験の引き渡しである、と。
そうですね。自分の身体でも記憶でもないけど、そういう複合的な何かのなかに発動条件があって、自分がうまいことやると、世界の見え方が突然変わるような。

――それは見え方に変化があればいい?
気持ちよくなってほしくはないかもですね。普通のものが不気味に見えたらいい。例えば、目の前のなんでもない車がいまここで突然爆発したらヤバいな、みたいな。でもそうなるのって、すごく長い時間がかかるじゃないですか。「スーサイドシート」は、事故で一番死ぬ確率が高い席という意味なのですが、結局自分の経験では事故は起きていない。そもそもロケに行くということと、事故に遭うかもしれないということは、共存できるけど別の出来事なんですよね。でもその別々になっているものが一緒くたになっている状態を、自分のことを知らない人に引き渡せたら作品になっているし、展覧会になっていると思うんです。そういうプロセスを「撮影」と呼びたいですね。
竹久直樹/Naoki Takehisa
美術家。1995年生まれ。多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース卒、2019年よりセミトランスペアレント・デザイン所属。「撮影」という概念を通じて、インターネット普及以降のイメージやそれらをめぐる人間の意識とコミュニケーションの体系を主題に制作と研究を行う。また様々な美術館やギャラリーにおいて展覧会の記録撮影を継続的に担うほか、他分野のアーティストとの共同制作も行っている。
IG|takehisanaoki
Web|https://pointlessimages.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
