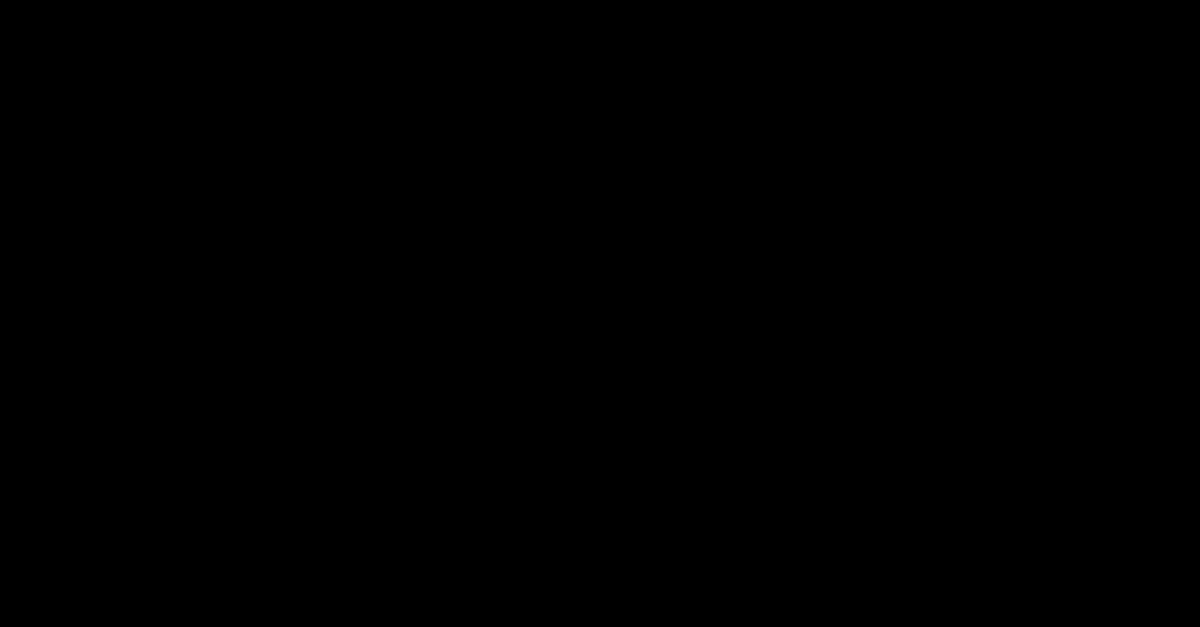
【短編小説シリーズ】 僕等の間抜けたインタビュー 『徒然坂』
柿谷 はじめは25歳の社会人の男。百代 栄香は18歳の大学生の女。二人は共に歩く。
彼等は友人、とは違う、「ありがとう」を言い合う仲。様々な場所に行き、のんびりとした時間を過ごす。話す。話す言葉はお互いに踏み込まず、傷付けない。妙に哲学じみてて馬鹿げてる。そんな日々を切り取って、彼等は笑っている。
柿谷はカキタニ、カキヤ、どっちの呼び方かは本人もあまり分かっていない。呼び方など、どうでも良いのだ。百代は柿谷を認知しているのだから。
百代は柿谷と共に出掛けている事を周りに秘密にしている。理由はない。ただ、刺激が欲しい彼女は自分を騙しているのだ。
二人共、小説に浸っていたからなのか、耽美に陶酔している。愚かにも、この関係を楽しんでいる。
発端
二人の出会いはカフェだった。隣同士席に座り携帯端末をいじっていた。二人がふと隣の端末を横目で悪気なく見ると同じ携帯小説を読んでいた。お互いにその状況に驚き、その驚く相手を見て相手も同様だと理解した。
二人は意気投合し、携帯小説について語り合っていたが、話題が尽きた頃にはお互いの素性が気になっていた。お互いに連絡先を交換し、その後も会うようになった。
二人は会う事をお互いの素性を知る『インタビュー』と呼んだ。今となっては、それもない。ただ『インタビュー』に行こうとお互いに行きたい場所を指定して会っていた。
関係は曖昧を極めていた。彼等は寄り添ってはいるが繋がろうとはせず、お互いにお互いの距離を保っているが、立場を尊重しお互いへの理解を深めている。
二人共、適当に生きていた。余計な気力はなく、ただ二人はお互いの行きたい所に行き、漂流していった。
徒然坂
ビルの隙間から覗く藍色につられて街は電灯を点け始める。百代と柿谷の二人は駅に併設されたショッピングモールを歩いている。
「ねぇ柿谷君どこ目指してるの?」
「あー、決めてなかった」
「そっか」
「足疲れるよね。ごめん。どっかで座る?」
「ううん。大丈夫。今日はハイヒールじゃないし」
「どうしよっか。とりあえず、どこかには行こうか」
「そうだね。あれは?ご飯は?」
「え、晩御飯用意されてるんじゃない?お家で」
「いや、今日親いないんだ。なんか旅行に行くとかなんとか」
「え?子供置いて旅行?そんなラノベみたいな事実際あるんだ」
「そう、なんか周りの人は驚くんだけど、私にとっちゃそれが普通だからさ」
「また、どうして旅行に?」
「毎年結婚記念日に一泊するの。本当に仲良しでさ、びっくりだよね」
「へぇ……いいなぁ」
「で、どうすんの?私はご飯食べるでもいいけど」
「ああ、うん。じゃあ、そうしようか」
二人はフロア案内が表示されているパネルの前で立ち止まる。
「レストランは8階だって」
「じゃあ昇ろう」
「エレベーターの方が早いかな」
「エスカレーターでも良いでしょ。せっかく近くにあるんだし」
「あーそうだね」
百代がエスカレーターに乗る。一段空けて柿谷が乗る。百代が振り返り柿谷を見る。
「なに」
「いや?」
「危ないから前向いとけ」
「はい」
エスカレーターを降り、また乗る。レストランフロアまではあとこれを二、三回は繰り返す必要がある。百代は再び振り返り柿谷を見る。
「なんだよ」
「いや、なんかエスカレーター乗るだけで全然違う景色見れるの面白いなぁって」
「え、そんな事?」
「そんな事って酷いなぁ」
「きちんと前見なさい」
「横向いてるから良いの」
「まぁ確かにそれなら良いか」
エスカレーターを降り、百代はそのままフロアへ歩き出す。慌てて柿谷も降りる。
「えーちゃんここじゃないよ」
「それは分かってるよ。ちょっとここも面白いかなって」
「メンズファッションの階だけど」
「柿谷君って会社行く時はスーツだもんね」
「そりゃな?」
「良いネクタイ私が見つけてあげる」
「良いよそんな。それより飯だろ?」
「いや、まだだって6時とかでしょ?早いかなって」
柿谷が袖をつまみ腕時計を見て、すぐに袖を戻す。
「まぁ確かにちょっと早いかもね」
「それにさ、エレベーターと違って一階一階景色が見れるでしょ?そこが面白くて」
「エスカレーターに乗らなきゃこのフロアに来る事もなかったかもしれないね」
「そう。良い機会だから、だから柿谷君に似合う良いネクタイを探します」
「えーちゃんが楽しそうなら僕はそれで良いけどさ」
百代が多彩なネクタイが畳まれた棚に行き、いくつか取ってから柿谷の鎖骨の間にそれを当てる。百代は片目を閉じ、柿谷の体や顔とネクタイの調和を見定めている。
「んー……これは?柄が少なめで主張もそんなにないけど」
柿谷に渡されたネクタイは濃紺に細い線のストライプ柄が入った艶やかなものだ。
「おー、結構良いなこれ」
柿谷がさりげなく値札を見てその値段の高さに思わず声が出る。
「うぁ」
「もー値段とか良いから」
「で、でもさ」
「柿谷君の誕生祝い」
「え、全然違うけど」
「知らないからもう今祝っちゃう」
「そんな適当な」
「適当でしょ?私」
百代は笑いながら持っていたネクタイを綺麗に畳み元に戻していく。その様子を見て柿谷は百代の言う適当さが見合っていない事に笑った。
「うん、良いねこれ。これにしようかな」
「じゃあ買って来る」
「あ、ありがとう」
ネクタイを渡すと百代は小走りでカウンターに向かう。柿谷は会計が済むまで何をすれば良いのか分からずに店の陳列を眺めて歩く。
「お待たせ!これ、どうぞ」
「うん、ありがとう」
差し出された小さな紙袋を手に取る。黒い紐の確かな質感に百代が込めた想いを感じる。
「なんか、いや、ちょっと突然の展開に困ってる」
「困れ困れ」
「うおー困ったなぁ困ったなぁ」
「いつも貰ってばっかりじゃないんだぞこっちも」
「じゃあご飯は僕が奢ろう」
「えー!それじゃ意味ないでしょ」
「えーちゃんも困らせる」
「困るよそれは」
「困れ困れ」
二人は再びエスカレーターに乗り、レストランフロアを目指す。百代が振り返り柿谷の持つ紙袋を突く。
「大事にしてよね」
「勿論」
「これから食べるご飯で汚さないでよ」
「じゃあしまっとくよ」
「ダメ」
「なんで?」
「私がそれつっつけないから」
「つつくなよ」
「揺れる紙袋って面白いでしょ?」
「相変わらず分からないなえーちゃんは」
「分からないもんだよ。人の事は」
笑う百代に柿谷は敬意を払い、優しく小突いた。
いいなと思ったら応援しよう!

