
【5e】オークが載ってない…?じゃぁ作ればいいだろう!Monster Overhaulで色々モンスターを作ってみよう【世界で最初に作られたTRPG】2025/02/11 配信台本
Discord のサーバも用意しています。雑談とかしてます。ご参加いただけると幸いです。
また、ご支援していただける方のために欲しいものリストを公開しています。
正直な告白をします。この記事が面白かったと思ったり役立ったと思ったりした方は、「ハート」のマークをクリックしていただけると嬉しいです。承認欲求を満たしたい。
注意:本記事は全編無料です。応援いただけると軽率に買ったサプリメントの翻訳や利用、感想とか捗るので、ちょっと試験的に販売ボタンをつけてみます。
注意2:このページのアマゾンへのリンクは確かアフィリエイトが設定されてると思います。思いますってのは、若い頃に設定したっきり忘れてるからです。10年かけて最近500円ほど帰って来ました。素人でも時間をかけるとお金が返ってくることあるんですね、アマゾンのアフィリエイト。
注意3:最近DriveTHRU RPGのアフィリエイトプログラムにも参加しました。そのため、リンクをクリックして購入すると私に幾ばくかの謝礼が入るシステムになります。RPGのソースブックを紹介した結果手に入れた金でRPGのソースブックを買う、という永久機関を発明してノーベル賞取りたいのです。
この記事ではDungeons&Dragonsなどの書籍や記事から引用していますが、これらはファンコンテンツポリシーに従って引用しております。
----
このnoteはファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。©Wizards of the Coast LLC.
----
2025版モンスターマニュアルのプレリリースが始まりましたね…
やっぱ最大のトピックは「プレイアブル種族をモンスターのカテゴリから撤廃した」という動きですかね…というかこの動き自体は前の2014版MMでも同じで、「エルフ」や「ドワーフ」「ハーフリング」のモンスターとしてのデータは載っていない。
ただ、2014DMGに「特定種族に仕上げたいならNPCにこのテンプレートを使って調整してくれ」ってチャートが282ページに載っている。
だけどこれは「種族が異なると能力値が変わる」っていう扱いになるので、2024のPHBにて採用したポリシーと噛み合わなくなる問題もあるので結構難しい。
なぜオークがモンスターマニュアルから消えたのか
これに関しては詳細はわからない。営利企業がやることなので、ビジネス的な要素が絡んでいるのは想定出来る。
ハーフオークが初手からPC種族になったのはWorld of Warcraftの影響がでかく、オークを「誇り高いヒューマノイド」にまで引き上げたのが大きい…と評価されてる。
日本ではあんまりメジャーではなく(ボクもよく知らない)日本語対応されてるかどうかも把握出来てないのでここは伝聞でしかわからんのだが…実際「オークが善、ヒューマンが悪」と受け取ることが可能な世界の構築になっているらしいのも大きいのだろう。
で、その上で「ハーフ」の概念もあまり当世向けではない(こういう結論に至るのも、ハーフになると能力に大きく変化があると言うことにしたら「生物学的本質主義」という問題のある思想に引っかかってしまう…というややこしい話も出てきてですね)ということで、PHB2024では旧来ハーフオークとしてビルド出来るキャラクターを「ヒューマン達の中で育ったオーク」みたいな表現で再構築した、というかそういう感じです。あるいは人類と相容れない宗派に属してないオークとか。そう言うのですね。
つまり「オーク」はもうモンスターではない、「オークのタフガイ」「オークのチンピラ」は居るが「オーク」だけでモンスター扱いは出来ないと言うことだ。まぁこれはこれでいいのだけども…とはいえこれは味気ない処理だなぁという気持ちはある。ゴブリンやコボルドも遠くないうちにそっちに入るかも知れない。
これに関しては、DMG2024にも種族別の簡単な変換テンプレートとかあれば良いんですがね…(たぶんにPHBにある生得特徴を加えてほしいという扱いなんだと思うけど)
この辺のことは、様々な人種的な問題やら差別解消に至るまでの過程とかで起こってる様々な余波の1つで、これはまぁ行きつ戻りつをしながら適切なところに落ち着くと思うし、落ち着けるようみんなで考えて進めていかなきゃいけないことなんだろうね。たとえ空想の世界で遊ぶゲームとはいえ、現実の問題から完全には逃れられないんだろうなぁという想いが最近は強くなってきましたね。うん。
とはいえ、最後に決めるのは君の卓での合意だ
正直なところ、中世期の欧州をモチーフにすることが多いD&DなどのファンタジーTRPGでは、現代においては時代錯誤だったり眉をひそめるようなインモラルなことだったりがプレイ中に織り込まれることは避けられない。
避けられないのだが、だからってそれに我慢しなければいけないってのも違うわけで。そのためのセッションゼロだったりセーフティツールだったりゴールデンルールだったりを用意しているのが21世紀のTRPGの進化でもあったわけでしてね…つまり「オークという存在をどう扱うか」は君の卓で決めることだ、ってなる。
自分の場合は、「オークやゴブリンは混沌神の手先として人類に牙を剥いてきた」ということで、現時点では未だ和解の道も見えないという扱いにしている。これに関してはプレイ前にプレイヤー達に提示して一応合意は取っている。
オークやゴブリンとはそもそも話し合いも不可能なほどの断絶があるのだ、って設定にしてもいいし、話し合いの余地があるが「それ故に」拗れてるのだってこともある(これは現実でも起こりえる話だ)。どう扱いたいのか、どういうゲームにしたいのかを卓に集まるみんなと考えてみるのが良いはず。
とはいえ、モンスターとしてのオーク、敵対勢力としてのオークに魅力があるのも確か
とはいえですね、グルームシュを崇め、戦の神イルネヴォールの名を叫びながら戦場に飛び込み、ルシックに庇護を受けながら敵対勢力への憎しみを染みつかせた古典的なオークだってだしたいわけですし、そういう存在と敵対したり呉越同舟したり出来るのもTRPGの魅力であるわけで…
敵対勢力としてのオークを事細かく書いた本に「ヴォーロのモンスター見聞録」という名著があるわけですが、こいつがまた本国でも絶版となっていて非常に惜しいことになっておりまして…
ならば、どうするか。色々方法はある。
サードパーティーのゴブリノイド本を持ち出す
例えば、僕が時折持ち出している「Ultimate Bestiary: Revenge of the Horde」を使って「ちょっと毛色の違うオーク」の伝承を取り入れてみると言う手はあります。
この本は人間と敵対しがちなヒューマノイドの伝承とデータを沢山載せていて、オークももちろん一章分割いて細かく説明しています。
重いブーツの落下により巻き上げられた埃と灰が空中で渦巻き、残りの建物に燃え移った炎に照らされる。 深々とした笑い声と雄叫びが悲鳴をかき消す。 ほとんど。 立ち上る煙の雲から、うねる影から身を分離し、彼は全力で現れ、血まみれの荒削りな斧の柄で硬くなった手を調整する。分厚い毛皮、皮、革は、怒れる海のように、踏みしめる足音に合わせて波打つ。彼は獣のような血に飢えた叫び声を上げ、割れた黄色い牙を剥き出しにし、顔を覆う傷跡、隆起した肉のこぶ、こびりついた戦化粧、飛び散った血の模様を歪める。汗と加工されていない皮、血と死と恐怖の悪臭が立ち込める。咆哮は次第に高まり、彼は斧を恐ろしいほどの力で振り下ろす。これがオークだ。
序文からこんな感じで紹介される、戦闘民族オーク達の登場だ。この本では遊牧民族として再定義され、信心深いオークは特に困難な敵を選んで攻撃してくる傾向がある(軽装備のエルフと重装備のヒューマンがいたらヒューマンの方を優先して攻撃する)などのロールプレイや戦術の指針がまとめられている。
また、以下のようなサイトの記述も使える。自分で思いつかないなら、英語圏ではあるがこういうサイトから情報を収集して混ぜ合わせて自分なりのオーク像を組み立てていくといいだろう。
このサイトはインディーズのTRPGパブリッシャーのサイトなのだが、D&D 5e用のモンスターデータブロックをリファインし、自分でD&Dの過去版から連なる伝承を付け加えてまとめ上げており、戦略提案なんかもあって使い処が沢山だ。
ヴォーロ本に掲載されてた、伝統的な混沌神を奉じるオークのデータブロックも用意されていて、フォーゴトンレルムをもう一歩踏み込んで遊びたい人には使い勝手がよさそう。
いっそオークの伝承やスタットブロックを自分で作り込むというのはどうだ…?
こういう発想もある。TRPGはこういう想像力をかき立てるゲームだ。そして想像力をサポートしてくれる本も沢山出ている。自分がオススメする本はこの本「The Lazy DM's Forge of Foes」だ。
この本はTRPGにおいてモンスターを運営するとは、遭遇を構築するとは、即席のモンスターを作る、モンスターをフルスクラッチする、戦闘以外でモンスターを登場させる、など様々な示唆に富んだ内容がつまっている。コアの部分は下のリンクから全文無料で読めるので参考にしてみてほしい。
上記リンク先のドキュメントは、自分が現在機械翻訳の力を借りて日本語にまとめているのでチマチマ公開して行きます。
この本を使ったモンスターの運用ですが、特に役立っているのは「脅威度別モンスター・データ・ブロック」の欄ですかね。これ、バランスをの取れた遭遇を作る際に非常に有効でして。即席モンスターを作るときばかりでなくて、出版済みアドベンチャーの冒険を遊ぶ際にその強さのバランスが取れてなかったら他のモンスターに変えたり、パラメータを調整したり。そういうことをしてますね。
あと、4版時代のモンスターロールを5版にも導入するのは楽しいと思いますよ。だいたい2~3種の役割モンスターを出していくといい。
様々なモンスターの「味変」を付け加えるのに使える本 The Monster Overhaul
作者さんのBlogがこちら
そして、もう1冊。モンスター達のディティールを詰めるために使えるチャートやコラムが満載の本「The Monster Overhaul」だ。この本自体は5eのための本ではなく、OSRと総称される赤箱以前のD&Dとそのクローンゲーム向けなのだけども、モンスターを汲み上げる際、イメージソースとして使える非常に優れた資料だ。
以前から様々なTRPG系のYoutuberが紹介していて興味があったのだけど、Sly Flourishのポッドキャストでオススメされていてグンと興味が伸びて、最近ちょっとした臨時収入とPontaポイントが貯まってきたのでようやく購入出来たのでした。いや、PDFで買うにはちょっとお高めの本でしたからね…
で、オークのページですが、2ページにチャートとコラムがぎっしり載っていて見応えありますね…「オーク」を同キャラ盾するか、なぜ世界と対立しているか、なぜ彼らは殺されるべきものとしてそこに居るのか…そういった伝承を作るインスピレーションを導いてくれる記述が沢山含まれてますね。
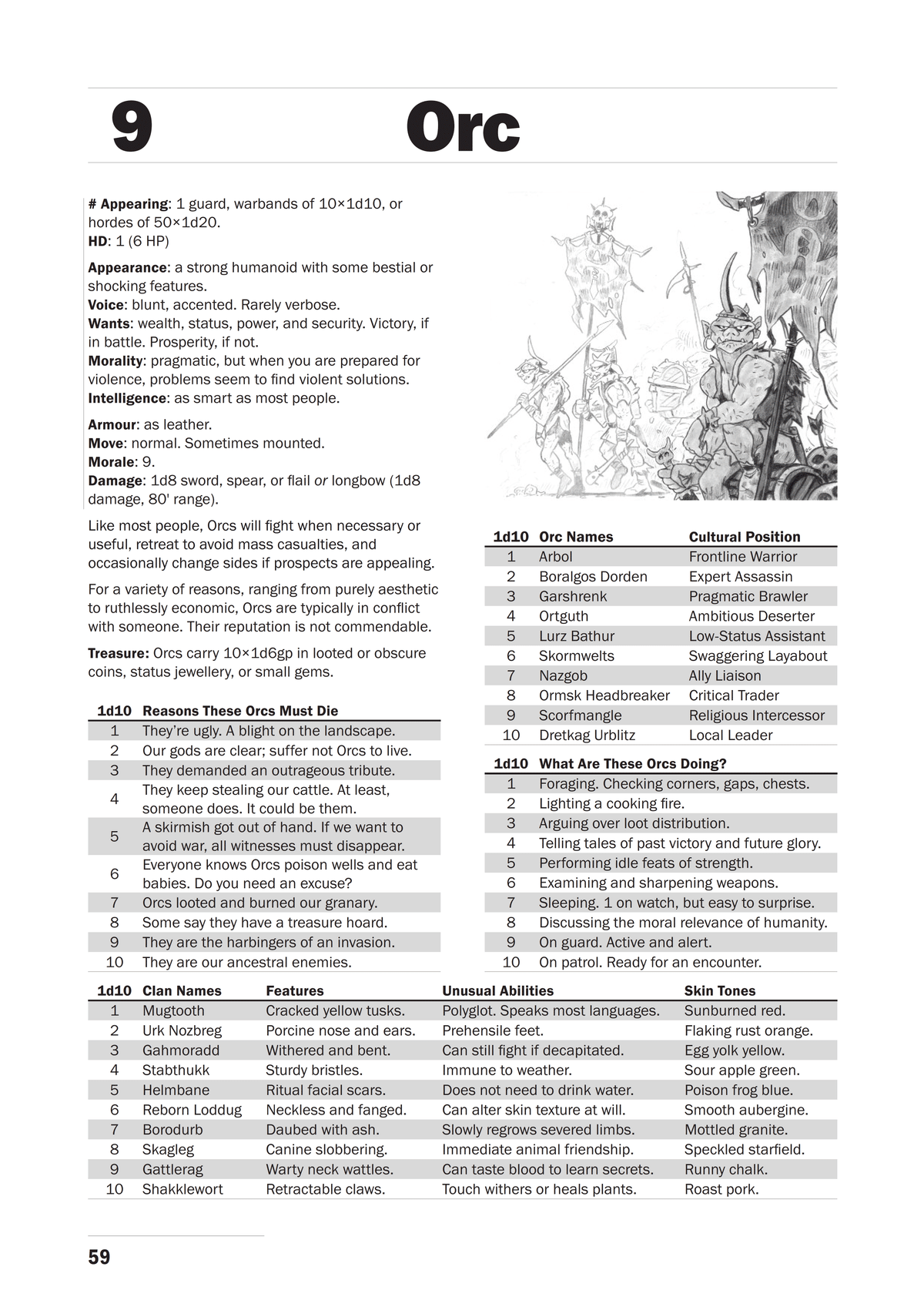
この本のコラムには「オークは典型的な『よそ者』である」という指摘もあり、『もう少し踏み込んでオークを取り扱いたい』という人に向けた示唆なんかも盛り込まれている。

ダイスを振って作ってみるのも良いし、ここから導き出されたインスピレーションを元に『俺の考えた俺の世界のオークの部族』を考えるも良し。色々考え盛り込んでみよう。
というわけで、配信でオークの部族作ってみましょうかね…。
The Monster Overhaulの凄いところ
この本、何がいいって、構成が凄く面白いんです。
まず、本の目次がそのままD20+D10のランダムチャートになっているんですね。ボンヤリと『なんか新しいモンスター考えてーなー』って時にこの目次を使えばきっかけがつかめたりします。

で、スタンダードなモンスターはだいたい用意されているんですが、よりスタンダードなものはページ数多め、そうでないものは半ページくらいでちょっといじる程度のチャートだけというのもある。でも、半ページ程度のものにも様々なインスピレーションをかき立てるものが用意されていて楽しい。「Hateful Goose(憎しみの雁)」なんてのは敵と言うより『現象』のような気もしますが。"見たこともない雁が空を渡っている、何かの兆しか…?"って感じの。
あと、Appendixも面白い。『用途別のモンスターリスト』という、シチュエーション別モンスター逆引きリストはシナリオにつまったときにだいぶ役立ちそう。『こういう役割はどんなモンスターに任せるといいかな…?』みたいな悩みに。
そして、これをPDFで買うと、収録されている挿絵だけを収録したアートブックも含まれててこれも見応えあり。クラシカルな白黒のアートだが、精緻なものからワイルドなものまで様々なアーティストが関わっているから見応えが沢山。
モンスターについてもう一歩踏み込んで作りたいというヒトには、かなりいいツールキットとして使えるんじゃないでしょうか。何にせよ気になる人はこのページのリンクからご購入いただけると幸いです。よろしくお願いします。
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
