
5分で覚える麻雀入門
「麻雀って聞いたことがあるけど、どんなゲームかわからない」という方に麻雀を5分で説明します。
麻雀はカードゲームの一種です
プレイ人数は4人が一般的で、3人や2人のルールもあります。
カードを組み合わせて和了形(ルールで定められた完成形)にするスピードを競います。この和了形を整えて手牌を公開することを和了と呼びます。一番最初に和了したプレイヤーが勝ちで、ひとり和了が出たら次のゲームに移ります。
また和了にはそれぞれルールによって定められた点数があり、ルールに定められた回数のプレイで点数をやりとりして、最終的にもっとも点数を持ったプレイヤーが勝者となります。
①使う道具
牌(カード)
卓(テーブルorマット)
これだけです。
ルールによってはサイコロや(点数を表すための)点棒などを使うこともあります。
卓の上にある牌(カード)には「置き場所」が三種類あります。
山「牌が裏(close)になっている場所」
手牌「自分の手持ち、つまり牌の表が自分にのみ見える場所」
河「牌が表(open)になっている場所」

②牌(カード)の種類
数牌(1~9までの数字が割り振られた牌)
萬子(ワンズ/マンズ)
![]()
筒子(ピンズ)
![]()
索子(ソーズ)
![]()
字牌(数字と関係のない牌)
![]()
各種4枚ずつ合計136枚使用が一般的。花牌と呼ばれるカードをこれに加えるルールもあります。
③ゲームの手順
①まず配牌(最初に牌を配る)し、13枚の手牌を構成する(手牌は13枚が一般的だが、16枚や4枚のルールもある)
②山から牌を1枚ドローし、手牌に1枚加える
③手牌の牌を1枚選び、河に置く
④以後、②と③を繰り返す
⑤誰かの手牌が和了形(ルールで定められた完成形)の14枚になった時点で手牌を公開し、和了宣言をすることで1ゲーム終了。和了形の組み合わせに応じて点数が加算される
⑥ルールによって①から⑤を決められた回数繰り返し、最終的にもっとも点数を持ったプレイヤーが勝利する
ネット麻雀やゲームアプリなら牌を1枚ドロー(抽選)し、いらない牌を1枚捨てるの繰り返しです。それ以外の操作は後述する「副露」だけです。この単純な操作を繰り返して「和了形」を目指します。
④和了形(ルールで定められた完成形)
13枚麻雀の場合
面子(牌3枚の組み合わせ)が4つ、雀頭(同種牌2枚の組み合わせ)が1つ完成した形を和了形といいます。
![]()
面子(3枚の牌の組み合わせ)×4+雀頭(同じ牌が2枚の組み合わせ。この場合は中)=14枚、で完成です。
これを4面子1雀頭と呼びます。例外として4面子1雀頭にならない形がありますが、最初は覚えなくても良いです。
面子には「刻子(コーツ)」と「順子(シュンツ)」の2種類があります。
刻子「同種の牌3枚の組み合わせ」
![]()
![]()
![]()
順子「連続した同系統の牌3枚の組み合わせ」(9から1には循環しない)
![]()
![]()
![]()
⑤副露
河に捨てられた牌1枚を自分の手牌にある牌2枚と組み合わせ「面子」を構成することが出来ます。ただし加えることが出来るのは直前に捨てられた牌のみで、それ以前の牌は取得できません。
これを副露と呼び、基本としてポンとチーの2種類があります。
(カンという副露もあるが、これは最初は覚えなくて良い)
副露は「晒す」という意味。他のプレイヤーが河に捨てた牌を取得できる代わりに、面子に必要な残り2枚の牌を手牌から選び、すべてのプレイヤーに見える形で「面子を晒す」義務があります。また「晒した面子」は手牌に戻すことが出来ません。

ポン
刻子を構成する副露。どのプレイヤーが捨てた牌でも取得することが出来る。「ポン」と発声が必要。
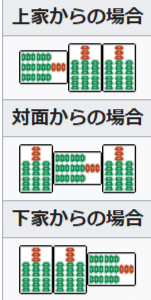
チー
順子を構成する副露。自分のひとつ前の順番のプレイヤーが捨てた牌のみ取得できる。「チー」と発声が必要。
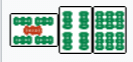
ポンとチーの発声がふたりのプレイヤーに同時にされた場合、一般的にはポンが優先します。ただし発声の早さが優先するルールもあるので注意。
⑥和了
4面子1雀頭を揃え、かつルールで定められた他の条件(これはまだ覚えなくてよいが、役など)を満たしたときに、和了を宣言し、手牌を公開することで得点することが出来ます。4面子1雀頭の形以外にも和了出来る形はありますが、最初は覚えなくていいです。
和了には「ツモ」と「ロン」の2種類があります。
ツモ
山から牌をドローし、和了形が完成すること。「ツモ」と発声する。

ロン
他のプレイヤーが捨てた牌で和了形が完成すること。「ロン」と発声する。

まとめ
以上が麻雀の基礎となります。後はルール次第で「役」が必要となったり、他にも様々な和了条件や禁止事項がありますが、とりあえずネットやアプリでプレイする分には問題ありません。細かいルールはプレイしながら覚えましょう。
「役」がいらない麻雀には
アルシーアル麻雀
台湾麻雀
などがあります。これらは今回のnoteで学んだルールで十分に遊べます。
もっと普通の麻雀がプレイしたいという方は次回のnoteで「役」を覚えてください!
