
"ポポポ"から"カービィ"になったことで得られたもの、失われたものを考える
君を見ていると、ずっと昔からおともだちだった気がするよ。
1992年04月27日に発売した『星のカービィ』。ここから紆余曲折を経て今に至る訳ですが、カービィという名前のキャラクターが、最初は「ポポポ」で、『星のカービィ』というタイトルは『ティンクル★ポポ』だった…という話はファンの間ではよく知られた話です。
この、ポポポからカービィに変わったことで、何を得て、逆に何を失ったんだろうなという疑問が浮かんできたため、記事としました。
カービィという名前の由来については定かではありません。こういった、真偽も曖昧で、恐らく未来永劫定まることのないであろう話に首を突っ込むより
何故、「ポポポ」から「カービィ」に変えようと思ったのか。任天堂(正確には宮本さん)は何を狙って変えたのか。
もっと言えば、それは生みの親である桜井さんにどう影響したのか。
考えてみてもいいのではないでしょうか。
当然ですがこれは筆者個人の見解のため、皆様も"ポポポ"から"カービィ"になって何が変わったのか。コメントでもなんでもいいので話してくれると嬉しいです。
※本当は1月20日に出したかったのですが、忘れてて21日となりました。
ポポポからカービィという逸話
ポポポからカービィに変わった話については、任天堂の元社長であった岩田聡氏と糸井重里氏の対談である程度語られています。
元々1992年1月発売予定だった『ティンクル★ポポ』は任天堂、正確には宮本茂氏の進言から色々な面で作り直しとなりました。
既に1991年11月の時点で雑誌広告が出ており、2万6千本の注文数も入っていたのにも関わらず。
「『ティンクルポポ』っていうのが
あるんですけどね……
ちょっといじるだけで、ものすごく
おもしろくなるやつがあるんです。
あれ発売を中止して
作りなおしていいですか?」
元々「ティンクル★ポポ」で1月下旬に発売予定だったゲームは、任天堂販売となり、結果は500万本という記録に。『星のカービィ ディスカバリー』が出るまでこの記録は破られませんでした。
この逸話は売上やハル研究所の歴史では話題に上がりますが、ポポポの設定がカービィに引き継がれたことから、ポポポとカービィの違いについてあまり考えられていなかった領域と思っております。
カービィで得られたもの
カービィという名前でこのピンク玉は世界に羽ばたき、AIにも「カービィ」という架空のキャラクターで連想されるイメージで「星のカービィ」の表現が出てくるレベルには既に爪痕を残しております。
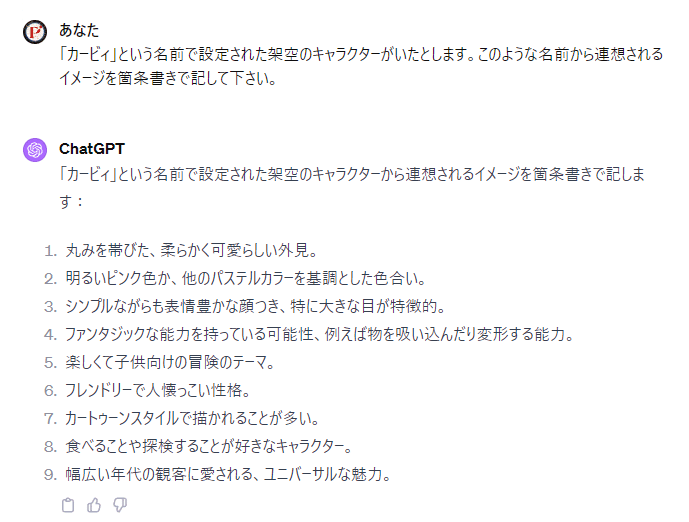
さて、宮本さんは「サンリオっぽい」という感覚から「ポポポ」から「カービィ」に変えたと言います。ここでサンリオのキャラクター表とにらめっこしてもいいですが、まずは「カービィ」という名前にしたことで得られたことを考えましょう。
(やや男性に寄った)中性的イメージ
"カービィ"というのはどちらかと言えば姓の方が用例が多いです。そのため男性・女性どちらでも利用が想定できます。
後のカービィの公式設定で「性別が不明」となりましたが、それを補強するという点ではとても似合った名前です。


ただ、どちらかと言えば姓と言ったように名前でも用例はあります。英語版Wikipediaの「カービィの名を与えられた人」を見れば分かります。名前では男性の方が多いです(というより女性は皆無?)
姓では男女(当然ですが)、名では男性という点で、例えば男性名詞の「マリオ」と比べると中性に傾いていることが分かります。
プププランドではないどこかからやってきた"たびびと"
そもそもデデデやロロロと同じような法則を持つ名前が出てきたら、それは同じ世界の住人と解釈しやすいです。「カービィ」といった、特異な名前がピンク玉に与えられました。
結果、彼はデデデやロロロとは違った世界にいるというイメージを持つようになりました。他の連中も妙に洒落た名前(ワドルディ、ブルームハッター、ウィスピーウッズ)ですから、「カービィ」と付くキャラクターは極論を言えば異星人であると考えやすいです。
ポポポがどこから来たかは不明ですが、カービィについては出自は不明です。カービィは旅人という設定ですがそのイメージと名前が合っていと言えます。
(どこからともなくやってくる、アニメ版星のカービィのカービィは設定に忠実な訳です。原作者監修なのですから当然ですが)

主に英語圏に通用する名前
「カービィ」の名を与えた任天堂は既にドンキーコングやユニバーサルとの裁判など、1980年代から世界に打って出て活躍されていました。最初から日本だけでなく他にも進出しようという心意義があり、その実績もある中彼らが出した「カービィ」という名。
彼らの中で自然と出てくる名前をモチーフにしたのは、主に米国を視野に入れていた任天堂の考えが見て取れます。
実際、初代星のカービィは500万本売れ、同作品のシリーズでは、2022年に『星のカービィ ディスカバリー』が発売されるまでその本数は破られませんでした。
得られたもののまとめ
ここまでをまとめると、以下の3点がカービィから得られたと考えております。
やや男性に寄った、中性的イメージ
プププランドの住人とは一線を画す名前
世界(英語圏)に通用するイメージ
カービィで失われたもの
では、逆に「カービィ」と名付けられたことで失われたものは何でしょうか。
ポジティブ、ユーモラスに偏る
ChatGPTで「ポポポ」という名前で設定された架空のキャラクターから連想されるイメージを尋ねた所、以下の回答が出てきました。
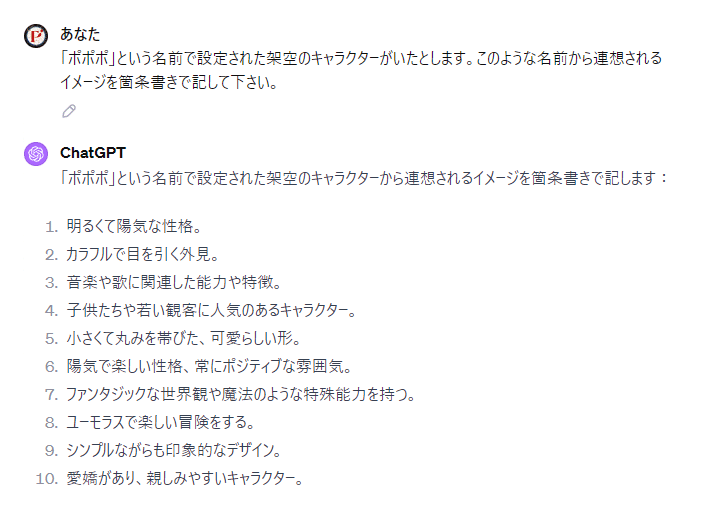
ChatGPTのようなAIは確率が高い回答を出しているだけなので同じ文面でも何度も繰り返すと微妙に回答が異なってきますが、基本はそんなに変わりません。
カービィに類似した回答も多いですが、なんと言いますか最初から「子供たちや若い観客に人気」「ユーモラスで楽しい冒険」「常にポジティブ」など楽しい方向に振り切っている回答が出てきます。
これは個人的な想像ですが、「アニメ星のカービィ」の最初に登場したワープスター型の宇宙船を「ポポポ」で出せたかと言えば…別に出せたでしょうが、「カービィ」と比べるとだいぶミスマッチ感があるなと思っています。
誤解を恐れずに言いますと
良く言えば可愛らしい、悪く言えば幼稚。
そんなイメージが「ポポポ」から感じられます。
"サンリオっぽさ"と表現された、日本風の可愛さ
先程の点は、サンリオっぽいから改名したという逸話とも関わってくるのではないかと踏んでいます。
サンリオのキャラクターを見ても、「ポポポ」のように同じ文字を連続して構成する名前のキャラクターが出てこないのです。例えば1980年代後半デビューのキャラクターを見ても、該当しません。

しかし名前で類似するキャラクターはいませんが、例えば1988年デビューの「ホプティコプティ」、1989年デビューの「あひるのペックル」、「ウィンキーピンキー」、「カッパルンバ」、「ミリーピクシー」など半濁音を持つキャラクターはいます。
こういった、半濁音を名前に持つキャラクターが集うサンリオが形成してきたのは「日本産のマスコットキャラクター」感ではないか。そんな意見も出ました。
日本風のマスコットキャラクターのイメージを持つポポポから、英語圏では珍しくない名前のカービィに変わる。
ゲームの内容はほとんど変わらない訳ですが、まん丸で可愛らしいピンク玉が不思議一杯の冒険(未来の話を言えばコピー能力も駆使して)を繰り広げるのなら、キュートに振った名前より比較的カッコいい名前の方が合っています。
少なくとも、私は「ポポポ」のキャラクターが「メタナイトの逆襲」みたいなモードに登場して、小学生がそのゲームを遊ぶ姿が一般的になったかと言うと…私には確信できませんでした。
失われたもののまとめ
ここまでをまとめると、以下の2点がポポポにあったものです。
良く言えば可愛らしい、悪く言えば幼稚のイメージ
サンリオと表現された、「日本産のマスコットキャラクター」感
桜井氏が考えていたものと合致するのはどちらか
ということで、「ポポポ」から「カービィ」に変わったことで
以下のイメージが得られ
やや男性に寄った、中性的イメージ
プププランドの住人とは一線を画す名前
世界(英語圏)に通用するイメージ
一方、以下のイメージが失われたと考えました。
良く言えば可愛らしい、悪く言えば幼稚のイメージ
サンリオと表現された、「日本産のマスコットキャラクター」感
こう考えてみますと「ポポポ」は、生みの親である桜井氏が考えていた主人公のイメージとはどうも違うのではないかと思います。
すでにROMも出来上がって、ゲームの展開も殆ど同じである以上桜井氏が考えていた"ピンク玉"像が激変するというのは考えにくい話です。
いや、むしろ「カービィ」という名前の方がより適切だった…そうも言えそうです。
「君を見ていると、ずっと昔からおともだちだった気がするよ。」のヘンなところ
この台詞はティンクル★ポポの広告にあった台詞です。カービィの時代には長らく出てきませんでしたが、2018年発売の『星のカービィ スターアライズ』以降、さりげない形で類似の台詞が出てきております。
ずっと、君を見ていると。
ただ、ここまで見ると分かるように、ポポポという名前の生物が一般的でないこの地球で、"おともだち"だったと考えるのはなんというか変な気がします。
それよりかはカービィという想像しやすい名前で出したほうが、まだそれっぽいでしょう。
"初心者向け”を謳うならば
「ポポポ」という名前の持つかわいさは強すぎます。ただでさえ、容姿が小さなピンク玉ですからキュート(宮本さんはパックマンのイメージから黄色と考えていたようですが)です。
そこで初心者という漠然とした、多くの人々をターゲットにするならば「可愛さ」に振りすぎるより、先程も言いましたように中性のイメージを付け加えたほうが良いです。
1990年代という、今と比べてもまだまだ「男らしさ」「女らしさ」が強かった時代に、容姿も名前もかわいいキャラクターを女の子はともかく、男の子が積極的に手を取ったのか、あるいは親御さんが買ってくれたのかという点も大きな問題です。
…ここまで考えて最善手だったと思いますが、それが感情的に受け入れられるかどうかは別です。
それを「受け入れられた」のか?
すでにROMも出来上がって発売を予定していた作品のキャラクターをわざわざ変えて、他細かな調整まで加えるというのは前代未聞です。
任天堂の宮本氏が「ちゃぶ台返し」をしたという逸話は例えば『スターフォックス』や『メトロイドプライム』で言われていますが、カービィの件についてははっきり言えば「乱暴」です。糸井重里氏もそう評しており、当時21歳の桜井氏はどう受け止めたのでしょうか。
500万本という結果が出せなかったらどうなっていたのかは分かりません。
…ともかく、これが、「ポポポ」から「カービィ」になったことについて振り返った私の感想です。
最後に、1月20日に本当は出そうとしていたことを話します。「ポポポ」は1992年1月下旬に出ることが予定されていました。1992年1月のカレンダーを見てみますと、20日は「先負」の月曜日です。

一方、「カービィ」が世に出た1992年4月のカレンダーで、4月27日を見てみますと27日は、先負の月曜日です。

下旬で先負の月曜日に注目すると、1月にあるのは20日、26日のどちらかのため20日に合わせたかったという理由です。
カレンダーの六曜に合わせることなどどうでもいいですし、結局何日かも分からないのですから何日に記事を出そうが関係ないのですが、仮に「ポポポ」を振り返るなら1月下旬はいい時期だと思っています。
追記
「パ行がかわいい」。
音が持つイメージについて研究する学者が、こんな研究成果を発表している。
後にパ行の可愛さについて研究された方の記事も出てきました。ChatGPTの見解より有力な根拠が得られたと思っています。
