
起始停止の位置が教科書と違うと、臨床はどう変わる?
こんにちは!パパPTです!
私は今現在、実際に御献体の解剖をしながら肉眼解剖学を学んでいます。
実際の解剖をしてみると、教科書とは違うことも多々あり、そのたびにテンションが上がります!
なんでいちいちテンションあがるのか不思議な方もいらっしゃると思いますし、
起始停止の位置が違うとどうなるの?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
そのことについて、noteを書いていこうと思います!!!
起始・停止が変わるってどういうこと??
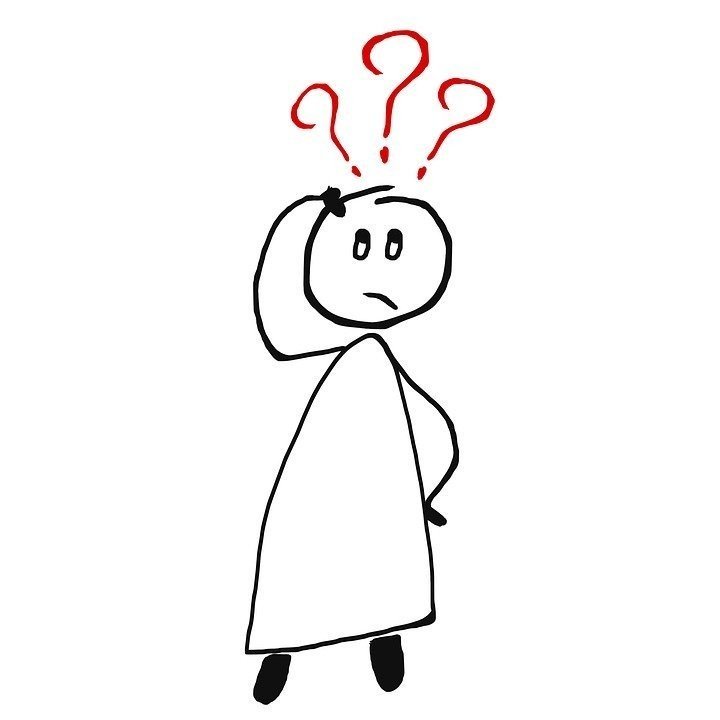
まず、起始・停止が変わる=作用が変わります。
例えば、今まで『屈曲』だけの作用だったものが起始・停止が変わるだけで『回旋』や『内外転』という作用がプラスされるということです。
これ、すごくないですか?!
現在note作成中の『横隔膜』で説明していきますね。
↑↑↑我ながらいい記事だと思うので、公開したら是非ご購入ください!(笑)
教科書などで得られる情報には限度がある?
横隔膜の起始はご存じでしょうか?
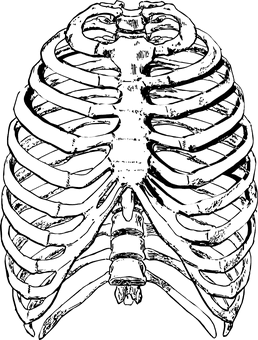
教科書的には、
☆起始
肋骨部:肋骨弓の下縁第7-12肋軟骨の内面
腰椎部の内側部は第1-3腰椎体、第2-3椎間板、前十靭帯
外側部は第1腰椎椎体全面から起こる腹大動脈の第1の腱様弓(正中弓状靭帯)
第2腰椎体から肋骨突起にわたる腰筋弓の第2の腱様弓(内側弓状靭帯)
第2腰椎の肋骨突起から第12肋骨の先端に至る方形筋弓の第3腱様弓(外側弓状靭帯)
胸骨部:剣状突起の後面
☆停止は中心腱
☆作用
横隔膜・胸郭呼吸運動の最も重要な筋であり、腹腔内臓への加圧を助ける。上下移動でありおよそ3~6㎝である。
☆支配神経
頸神経叢の横隔神経(C3-C5)
と、ずらずらーっと書かれています。
解剖学の教科書ではこれまでしか分かりませんよね?
そう、ただこれだけなんです。
国試対策のためにしかたなく覚えたという方も多いかもしれません。
だからなんとなく、
起始停止って臨床に役に立つというイメージがなかなか出来ない・・・
起始停止を参考にしようとしても、
呼吸に重要なんだ。
とか
上下に3~6㎝動くんだ。
とか・・・
本当にそれだけで、よくわかりませんよね。
話を戻して、ある報告では、
大腰筋との筋連結(表現はいろいろありますが、とりあえず連結としておきます。)がある。
腹横筋膜に一部付着している。
という報告があるのです!!!
これはすごいことですよ~!!
それで結局何が変わるのか?
結局、なにがすごいんですか?という話になるかもしれませんが、
起始停止が変わるのはすごいのは分かった、でも具体的にはどうなんだ?ということになってきますね。
起始停止が変わるって具体的にはどういうこと?
横隔膜の起始停止が変わるということは・・・
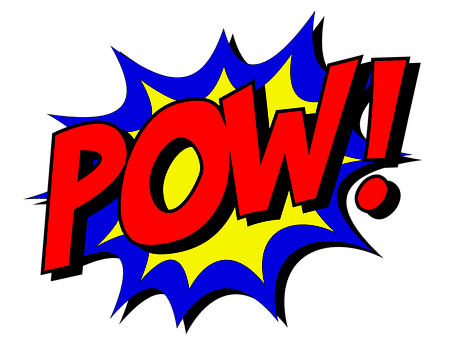
横隔膜の機能低下は体幹機能や股関節機能に影響を及ぼしている可能性があるということです。
ここから分かることは、
『体幹機能悪いから腹筋運動』
『股関節悪いから外転運動』
ではないということです。
それはつまり、
『体幹機能・股関節機能が悪いのは、横隔膜の機能低下かもしれませんよ?』
といえるので、かなり評価や治療の幅が広がると私は思います。
このnoteでみなさんに伝えたいこと
ここまでこのnoteを読んでいただいたみなさんには、
起始停止を臨床にどう活かすか
ヒントが見えてきたと思います。
起始停止の横隔膜をつかった例え話についてはいったん終わりますが、(気になった方は横隔膜のnoteをチェックしてください(笑))
このnoteで、みなさんに伝えたいことは、
解剖学(起始・停止)を学ぶことは、評価治療の可能性を広げることができるということです。
学生や若手のセラピストの頃、
『解剖って覚えるだけだからきつい~』
と言ってないがしろにしてませんでしたか?
個人的な意見ですが、これはかなり勿体ないと思いますので今からでも復習してください。
解剖って最高に楽しいし、使い方を学ぶと臨床でのパフォーマンスが圧倒的違ってきます!

なので、気になる筋(骨でも神経でも可)があれば私に御一報ください!
パパPTのnoteでは、解剖から臨床への活かし方などを中心に書いていこうと思います。
私は解剖が好きなので、これからのnoteでは
☆肉眼解剖から得た学び、気付き
☆解剖をどう活かしていくのか
☆起始・停止・作用を臨床に活かせるようなnote
などをこれから書いて、お手伝いさせていただきます!
これからパパPT・パパPT水道局。をよろしくお願いします!
パパPT水道局。メンバーには、全てのパパPT有料noteは無料で開放中です。
