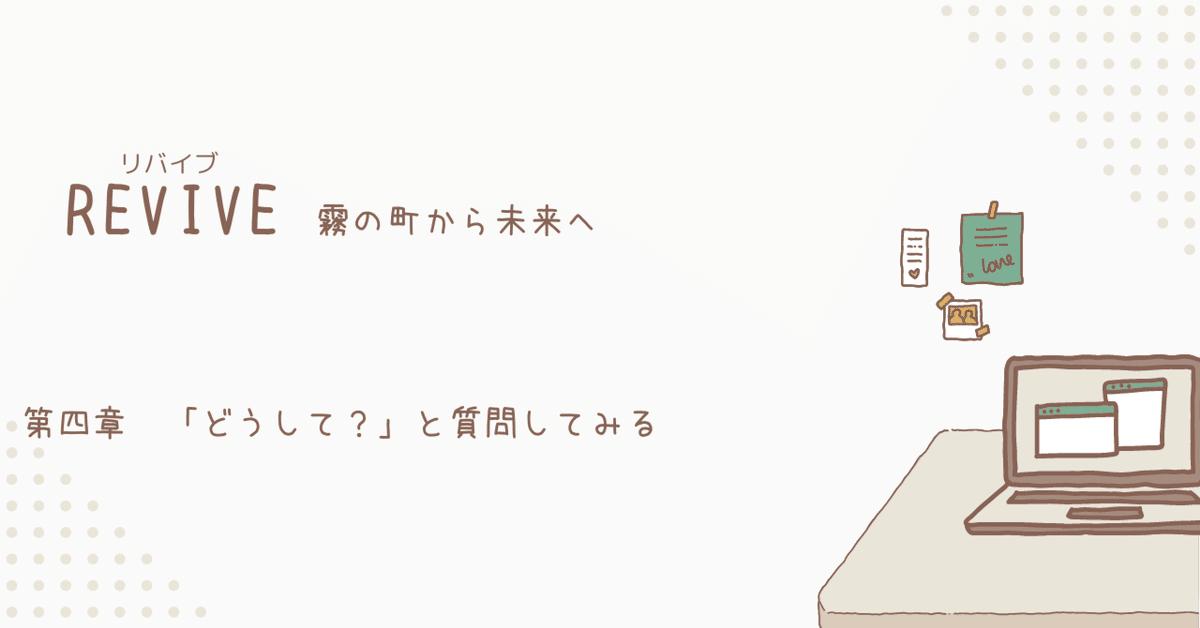
REVIVE 第四章
第四章 「どうして?」と質問してみる
亀岡市での生活が少しずつ落ち着いてきた頃、拓真は地域の魅力や課題についてさらに深く理解しようとしていた。地元の食材を毎日取り入れるようになり、地元の人々との距離も縮まってきたが、まだまだ知らないことが多いと感じていた。
そんな時、東京に残してきた彼女、由香(ゆか)から連絡が入った。由香とは三年間付き合っており、彼女は三十一歳、東京の丸の内でアパレル関係の仕事をしているキャリアウーマンだ。拓真は、亀岡市に戻ってからはほとんど連絡を取っていなかったが、彼女が「亀岡に行ってみたい」と言い出した時、彼は嬉しく思った。
「亀岡に来るなら、その時に思い切ってプロポーズしようか…」
拓真はそう考えた。亀岡市での生活が落ち着いてきたこともあり、彼女との将来を真剣に考えるようになっていた。そして、由香が亀岡に来ることを楽しみに待つようになった。
数日後、由香が亀岡市に到着した。久しぶりに再会した二人は、最初はぎこちない笑顔を交わしていたが、由香の様子が次第に変わり始めた。彼女は亀岡市の静けさや暗さ、遊ぶ場所がないことに苛立ちを感じていた。
「ねえ、拓真。ここで何してるの?こんなところ、何もないじゃない!真っ暗で、何か生きてる感じがしないよ。それに、虫だらけで…気持ち悪い。」
彼女の言葉が、まるでナイフのように拓真の心に突き刺さった。彼が大切にしているこの街を、由香が価値がないかのように感じていることが、耐え難かった。彼は、彼女のために特別な時間を過ごそうと計画していたが、彼女の態度がそれをすべて打ち砕いたように感じた。
「ここには本当に何もないの?どうしてあなたがこんな場所を選んだのか、私には理解できない。」
その言葉に、拓真は胸が痛んだ。プロポーズを考えていた彼の心が、一瞬で冷たくなったように感じた。
「由香、いい加減にしてくれ!ここは東京じゃないんだよ!亀岡には亀岡の良さがある。それを理解しようともしないで、ただ文句ばかり言うのはやめてくれ!」
彼の言葉に、由香は驚いた表情を浮かべたが、すぐに苛立ちが顔に現れた。
「私が悪いって言うの?私はあなたのことを心配してるだけなのに…どうしてそんな風に言われなきゃいけないの?」
彼女の声が震え、涙がこぼれ落ちた。由香は感情を抑えきれずに泣き出し、言葉を詰まらせながら続けた。
「あなた、最近全然連絡もくれなくて…私たちの関係はどうなるの?ここで一緒に暮らせるわけでもないのに、私はどうすればいいの?」
その問いかけに、拓真は答えることができなかった。彼女の気持ちを考えることなく、自分の怒りをぶつけてしまったことを後悔したが、もう遅かった。
「もう、いい!こんなところ、私には合わない。東京に帰る!」
由香は涙を流しながらその場を去ろうとした。拓真は何とか彼女を引き止めようとしたが、彼女の背中は既に遠ざかっていた。
「由香、待ってくれ…」
必死に呼び止めようとする拓真の声も、由香には届かなかった。その夜、彼女は東京へ戻るために亀岡を離れてしまった。拓真は深い後悔と孤独に苛まれ、自分が何を失ったのかを痛感した。
彼女が東京に帰ったその日、拓真は無意識のうちに町の居酒屋に足を運んでいた。静かな亀岡の夜、居酒屋の暖簾をくぐると、薄暗い店内には数人の常連客がいるだけで、活気はない。彼はカウンターに座り、静かに酒を注文した。
失ったものの大きさを感じながら、酒を口にするたびに思考が巡る。彼女との口論が頭から離れず、心にぽっかりと空いた穴が広がっていくようだった。何かがうまくいかなかったのだろうか、どこで間違えたのだろうかと、自問自答を繰り返していた。
そんな時、ふと隣に座る気配がした。顔を上げると、そこには鶴見さんがいつの間にか座っていた。彼は無言で酒を注ぎ、静かに拓真にグラスを差し出す。鶴見さんは、まるで風のように現れる謎めいた存在。いつも、誰も気づかないうちに拓真の前に現れ、何も言わずに見守ってくれる。
「お前さん、今感じているその疑問は実に大切なんだよ。」
鶴見さんが語りかける。
「昔あるところに、旅人が旅をしていて、ある村にたどり着いたんだ。村人に『この村はどんなところか?』と聞くと、村人は逆にこう聞いた。『あんたが来た町はどんなところだったかね?』旅人は言ったよ。『賑やかで、楽しい場所だった。だけど、人々は冷たく、気にしないような感じだったね。』すると村人はこう言った。
『じゃあ、この村も同じようなところだろうよ。』」
鶴見さんは少し間を置いて、拓真の反応を見ながら続けた。
「数日後、また別の旅人が村に来て、同じように『この村はどんなところか?』と聞いた。村人は同じ質問を返した。『あんたが来た町はどんなところだったかね?』その旅人は言った。『平和で、美しい場所だった。人々は温かく、助け合っていたね。』村人はこう答えた。
『じゃあ、この村もきっとそうだろう。』」
鶴見さんは静かに笑い、拓真に目を向けた。「この話、わかるかね?結局のところ、場所の良し悪しってのは、そこにいる人がどう感じ、どう受け取るかで決まる。お前さんの彼女が亀岡を受け入れられなかったのは、彼女が都会での生活を基準にしてこの街を見ていたからなんだ。亀岡は彼女にとって、暗くて、静かすぎた。だが、地元の人たちは、そんな亀岡を自分たちの居場所として、愛着を持って受け入れている。彼らの基準で見れば、静けさも、虫の多さも、大した問題じゃないんだよ。」
彼は続けて、少し声を落として言った。「歴史上の人物を見ても、同じことが言えるさ。例えば、偉大な発明家エジソンも、周囲からは多くの疑問を持たれたり、無駄だと言われたりした。それでも彼は諦めずに『どうして?』と問い続けた。その結果、世界を変える発明を次々と成し遂げたんだ。もし彼が最初の批判で心を折っていたら、今の世の中はまったく違ったものになっていただろう。」
鶴見さんはさらに深く話を掘り下げた。「質問をすることで、本当に大切なものが見えてくる。彼女が感じた違和感や不満は、ただの表面的なものだ。そこに隠された本当の理由を見つけるために、もっと深く『どうして?』と問い続けることが必要なんだよ。表面的な反応だけで判断するのではなく、その裏にある人々の価値観や背景、歴史を理解することで、初めてその場所や人々の本質が見えてくる。」
この鶴見さんの言葉を聞いて、拓真は大きく頷きながら、再びメモ帳に鶴見さんの言葉を記録した。そして、彼は地域の課題や歴史、価値観を掘り下げるために、より多くの「どうして?」を持ち続けることが大切だと強く感じた。
