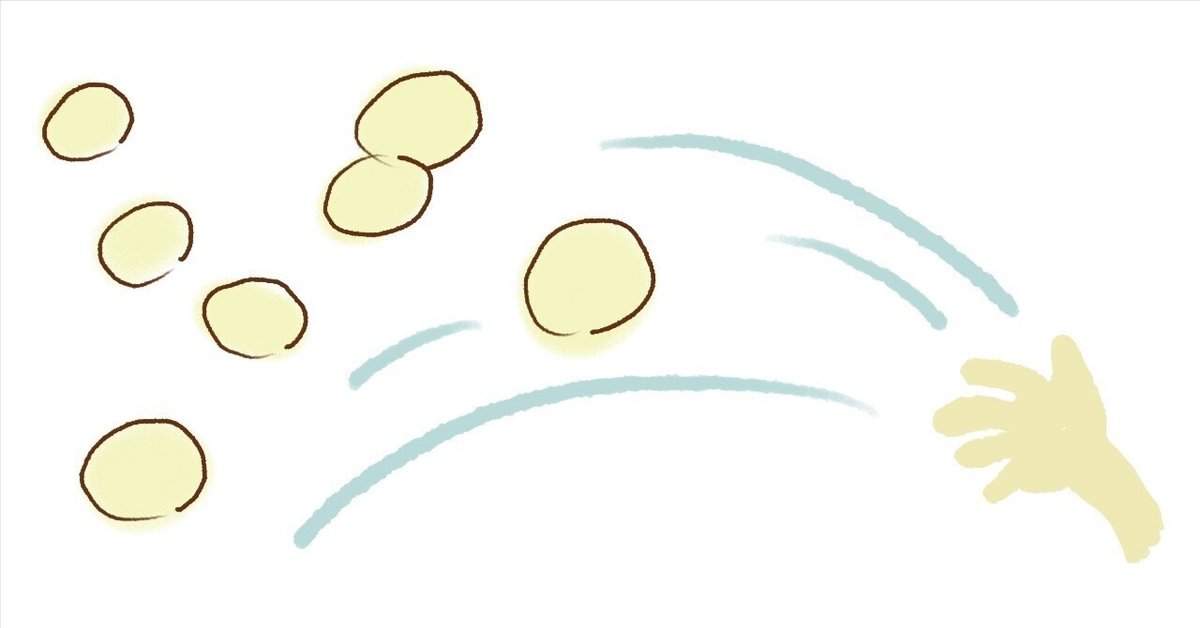
餅まき|パラスパレスの ヒト モノ コト #3
パラスパレスの店頭にてお渡ししている、季節の小冊子<シーズンブック>。そこで「ヒトモノコト」という連載をしています。
スタッフの暮らしや出来事を綴るちいさなエッセイ。
今回は、関西出身のニットデザイナーにバトンがわたりました。
彼女の故郷の秋祭りのお話です。
私が生まれ育った関西の地方では「餅撒き」の行事があります。
餅撒きが開催されるのは、おおきな神輿が練り歩き、町中が活気に包まれる秋のお祭りのとき。
もともと祭事が盛んな地域、お神輿も刺繍や飾りで贅を尽くした豪華なもの。上京してから関東のお神輿をみて、こんなにも風情がちがうものかと驚きました。
神社の境内では巫女さんや神職の方が、丸い餅を節分のように勢いよくばら撒きます。
餅がほうぼうに宙を舞い、拾おうとする人たちの熱気は最高潮。硬い餅なので、ぶつかると痛いくらいです。
私の母は目の上に餅が飛んできて青あざができていました。
餅拾いの人々は直撃しないよううまくよけながら、下に落ちたお餅は踏まないようサッと拾います。人と人、餅と人のぶつかり合いです。
そんな話をスタッフの間でしていたら、
「餅は丸くない」
「そもそも餅を撒かない」
と衝撃の意見が。私は餅撒きがスタンダードだと思っていたのです。
聞けば、餅を撒くのはお嫁入りのときや上棟式など、場面に地域差があり同じ県でも地区により微妙に違うのです。さらにはお雑煮の餅のかたちにも話はひろがり、西と東の違いの新しい発見も。
スタッフは出身地もバラバラ。それぞれの郷土のお話がきけて楽しいひとときでした。
「播州の秋まつり」として祭り事が盛んな地域ならではのお話でしたね。
兵庫を旅したときに、お神輿の展示をみて立派さに目を奪われました。その時の写真です。

刺繍や金銀の飾りがみごとです。

ここにお餅を入れて、もち投げに使っていたそう。
参考:お神輿動画
