
ブンゲイファイトクラブへようこそ。第1回のメインページです
ブンゲイファイトクラブってなに?
BFC2メインページ
BFCオープンマイク
—————————————————————————
ブンゲイファイトクラブ第1回の勝者は以下のファイターに決定いたしました。
北野勇作
—————————————————————————
決勝ジャッジ樋口恭介による評
散文、その複数性について
-ブンゲイファイトクラブ決勝戦・総評-
完璧であるためには、存在するだけでよい。
――フェルナンド・ペソア「断章 76」
文、最初にその定義を確認する。
文には大きく二つの分類が存在する――韻文と散文。韻律と形式を伴う文と、そうではない文。和歌や俳句は韻文に属し、小説や批評は散文に属す。ただし、小説や批評は〈文学的表現〉として独自の発展を遂げたがために、散文をめぐる事態はもう少々込み入っている。たとえば、小学館『日本大百科全書』は、散文について次のように説明する。少し長くなるが引用しよう。
「(散文は)普通には、詩趣のない、趣味のない、とか、退屈な、平凡な、俗悪な、無味乾燥な、とかという意味で使われる。つまり、散文的ということばは、詩的な美しさや人間的な感情の高揚や奔放なイマジネーションなどとは、まったく対立的なものということになっている。「散文的な生活」という場合には、生活が前記のような意味で散文的だということである。
けれども、散文的ということばはそういうふうに使われようと、散文そのものは、つねにそういうふうに散文的だとは決まっていない。もちろん、散文のもっとも普通の形としては、非文学的な説明や記述による文書的表記一般としてのそれがあり、このほうが多いのだが、これに対して文学的表現(韻律の制約を受けぬ)としての散文が一方にあって、文学作品に限らず、諸種の文章表現のなかにそれはみいだされる。とくに小説のなかにそれは独特な形を示しており、『散文芸術の位置』(1924)での広津和郎(かずお)の散文精神論が示すように、散文による芸術を高く評価して、「結局、一口でいえば、沢山(たくさん)の芸術の種類の中で、散文芸術は、すぐ人生の隣りに居るものである。右隣りには、詩、美術、音楽というやうに、いろいろの芸術が並んでゐるが、左隣りはすぐ人生である。」とする」
要するに「散文」という言葉は、歴史の流れの中で分岐して、「非文学的な文」という意味と「文学的な文」という相反する意味を同時に持つに至った、引き裂かれた語彙なのである。
こうした経緯を踏まえ、本稿では、韻律を持たず、文学と非文学のあいだで揺れ続ける、不確定的な文の集合を、散文と呼んでいる。
そして私は今ここで、二つの散文を読んでいる。
きわめて優れた小説であろうとし、実際にきわめて優れた小説として書かれた散文。そして、優れた小説であるどころか、小説ですらなくなってしまう可能性を恐れず書かれ、そうしてなお、結果的に優れた小説となった散文。
両者はともに、愛について語っている。前者は離れようとして離れられぬ恋人同士の、後者は多感な時期の親と子の。両者はそれぞれの仕方でそれぞれの人間愛について語りつつ、それでいて全く対照的な作品となっている。前者は饒舌で、動的で、誰が読んでも面白く思えるような、〈完璧な小説〉たらんとし、後者は言葉足らずで、静的で、一見すると面白みのない、〈素朴な散文〉たらんとしている――ここで呼ばれる〈散文〉とは、小説以前の小説、あるいは小説以後の小説、小説と呼ばれる領土から漏れ出た、脱小説的小説とでも言える、小説に似た何か、既知であるかのような未知、無限に両義的であり原理的に決定不可能な、宙吊りの――宙吊りという言葉すらも足りていない――決して名指し得ぬ、〈不確定性そのもの〉を指している。
人は、自分が知っているものしか読むことができない。人は未知のまま未知を見ることができない。未知との遭遇の際に、人は未知に似た既知を探し、既知を用いて未知を既知のものにしようとする。私たちが本を読むのは、知らないことを知るためではない。私たちは、私たちが知っていることを知っていると知るために、知らない本から知っているものを読み取るのだ。それが未知であるか既知であるかを問わず、何かを評価し論じようとするとき、多くの人は、既存の言葉に準拠する。そして大抵の場合、既存の批評理論を適用することで、それらしき批評文をこしらえることができる。小説らしく書かれた小説のかたちは、小説らしく書かれた小説に対する批評らしく書かれる批評のためのものさしによって測ることができる。私はそのことをよく知っている。私はかつて、そうしたものさしを肌身離さず持ち歩いていた。
私の人生、その10代の終わり。夜行バスに8時間揺られ、生まれ育った人口6.6万の田舎を離れ、人口33.8万の都市へと移り住み、そこにある大学で文学を学び、小説の理論的な読み方を学び始めた頃。その頃、私は自分が無敵だと思っていた。当時の私は全能感に満ちていた。当時の私は、自分に論じることのできないものは何もないと思っていた。私は覚えたばかりの小難しい言葉を振り回し、世界の全てにそれらの言葉を当てはめた。どんな本を読んでも、漫画を読んでも、テレビを観ても、恋人と散歩をしても、友人と飲みに行っても、ライブに行っても、私は批評の言葉を使って何かを論じ続けていた。
むろん、それがある種の思考の放棄の方法であることを、今の私は知っている。昔の私は、いつも何ごとかを論じ続けていたが、それらの論は、論じることを避けるために論じ続けられているものだった。10年以上の歳月が流れた今、私にはそれがわかる。あるいは当時の私も気づいていた。気づいていながら、気づかないふりをしていたのだ。私は便利なものさしを手に入れ、その便利さに依存するあまり、ものさしなしでは世界を見ることができなくなっていた。私はそれを知っていた。私はそれを知りながら、考えることをあきらめていた。私は多くの本を読んだが、当時の私は、考えるためではなく、考えることをやめるために本を読んでいた。そう、私は本を読んだ。たくさんの、既存のものさしを手に入れるために。さまざまな形の、さまざまな大きさをしたものさしで、強い自分を手に入れるために。たとえそれが皮相的なものであったとしても――もちろん、今でも私はそれを悪癖と知りながら、ときどき世界をあるがままに見ることをやめ、どこからか持ってきたものさしを使って世界を測ろうとすることがある。私はそれを自覚している――というか、私がやっているのはそんなことばかりだ。私は引き出しの鍵を開け、奥から古びたものさしを取り出し、世界を測り、世界を測れず、そのことに気づいてため息をつき、ものさしを引き出しの奥底にしまい、ふたたび鍵をかける。気を抜いて、反省して、襟を正して、また気を抜いて、反省する。今書かれているこの文章も、どこまでがものさしを使わず書かれたもので、どこからがものさしを使って書かれてしまったものなのか、書いている私にはよくわからない。あるいは、こうして日本語によって書かれた〈論〉そのものが、一つのものさしであるとは言えるだろう。それとも〈日本語〉そのものが、〈言葉〉そのものが、〈思考〉そのものが、〈人間〉であるということが、〈生命〉であるということが、そもそもある種のものさしであるとも言えるかもしれない――いや、これ以上はやめておこう。私は混乱している。私は自分が混乱していることをわかっている。私は混乱しながら、この文章を書いている。
それでも、とにかく、話を前に進めよう。
ごくまれにではあるものの、手持ちのものさしが全く使えない〈散文〉、ものさしを捨てざるを得ない〈散文〉に出くわすことがある。どんなに多く、どんなに多様なものさしを持っていたとしても、そうしたものさしなどでは測ることができず、既存の言葉では語ることができず、私たちに考えることを強いる〈散文〉が、私たちの前に立ち現れることがあるのだ。そうした文は、既知の小説らしく書かれていないために、一見小説ではない何かのように見える。私たちは、そうした全く未知の〈散文〉に出くわしたときには、全く新たな言葉を創造しようとあがくか、あるいは素直に沈黙するほかない。既知の言葉をどれほど費やしたとしても、未知の言葉の前では、それらの言葉はどこにも辿り着くことなく、無限に上滑りを続けるだけだろう。たとえば今ここにある、固有のタイトルの存在しない、ただ存在しているだけの、名もなき〈素朴な散文〉の前では。
そこに書かれたものは一枚の紙片に満たない。そこにはほとんど何もない。壮大な物語があるわけでもなければ魅力的な人物の造型があるわけでもない。謎解きがあるわけでもなければ驚きに満ちた奇想があるわけでもない。そこには絵画のような、写真のような、たった一つの断片的な風景が切り取られているだけだ。しかし私は、その、何でもないような、未だ名付けられていない、単なる〈散文〉の姿に、新たな小説の可能性を見ずにはいられなかったのだ。
「自転車でスーパーに行った帰り道、中学校帰りの娘の背中に声をかけてそのまま追い抜こうとすると意外にも、いっしょに帰ろう、と。友達といっしょのときには無視するくせに。お言葉に甘えて、自転車を押して歩いた」
たった100字のその〈散文〉には、小説の巧緻や面白さといった既知の次元を超え、むきだしの言葉を用いて、ラディカルに〈小説〉という概念を再-創造しようとする運動が蠢いている。私はそれを感じ取り、それから私は自分の手持ちのものさしが、そこでは何の役にも立たないことを直観した。そこでの私は、まるで、『百年の孤独』のマコンドの人々のように、目にしたものの全てを逐一指さして確認し、触れ、氷をダイヤモンドだと思い込み、冷たいものを熱いものだと思い込んだ。そうすることで、私は宇宙を自らの認知の中に閉じ込め、飼いならそうとし、当然ながら失敗したのだった。
親と子の何気ない日常の風景。自転車をゆったりと漕ぐ父親(あるいは母親)、制服の少女、一つの会話、自転車を降り、娘と二人で歩き始める父/母。この作品に書かれたものはそれだけだ。ここにあるのはたった一つの風景だ。しかしそうした風景は、その内側に、外へとつながる無数の〈孔〉を持っており、それらの孔の一つひとつもまた、無限の広さと時間を持った、巨大な宇宙へとつながっている。そんなことを書くのが気恥ずかしくなるほどに、この小さな作品は、あまりにも当たり前に巨大である。
「自転車でスーパーに行った帰り道」という一般性の高い描写、そしてそれに続く「中学校帰りの娘の背中に声をかけてそのまま追い抜こうとする意外にも」という、語り手固有の認知体験――「中学校帰りの娘の背中」という視覚情報に対して「声をかけ」「追い抜こうとする」という語り手の習慣的な認知反応と、「意外にも」という、習慣が裏切られたことへの相反する認知が、読点を挟むことなく同時に去来したという体験――、それについての端的な表現。読点を挟まず、圧縮率の高い情報が一挙に押し寄せたのち、やっと読点が置かれた瞬間、強く、高らかに、一切の雑音を排してはっきりと響く「いっしょに帰ろう」という娘の声。そのときの「いっしょ」という言葉は、あまりに強く語り手の認知に作用したために、語り手はその言葉を引きずり、次に続く文でも「いっしょ」を反復してしまう――「いっしょに帰ろう」「友達といっしょのときには無視するくせに」と。語り手の中で浮かび上がる娘の声と父=母の声、それらの声は、「いっしょ」の響きで接続されている――そして最後にはふたたび、「お言葉に甘えて」と、思春期の子を持つ親ならば誰しも感じるであろう心理描写と、「自転車を押して歩いた」という、夕刻の商店街の日常の、一般性の高い風景へと帰っていくのである。
交互に繰り返される一般性と固有性。読むという運動の中で、それらは相互に入れ替わり、反転し、繰り返し、明滅する。そうして私たちは一般性の中に固有の私を目撃し、固有の私の中に一般性を目撃する。
当然ながら、以上の読みは私の勝手な読みでしかない。ここにある、私の批評と呼びうる文には、「私はそう思った」ということ以上に頼りにできるものはない。壮大な物語があるわけでもなければ魅力的な人物の造型があるわけでもなく、謎解きがあるわけでもなければ驚きに満ちた奇想があるわけでもないその〈散文〉には、論じるための根拠としうる手がかりがあまりにも少ない。そこにはたしかに何かがあるのだが、その何かを取り出すための手がかりがわからない。そうして私たちはその〈散文〉の前に立ち尽くし、わけもわからぬまま、ああでもないこうでもないと、多くの言葉を費やすことになる。何度も読み、吟味し、語り、書くことになる。不可能性に向けた、無限の挑戦を試みることになる。
ロラン・バルトは、「作品からテクストへ」の中で次のように言っている。「メタ言語を破壊すること、あるいは、少なくともメタ言語を疑うこと(というのも、一時的にはメタ言語に頼る必要がありうるからである)が、理論そのものの一部をなすのだ。「テクスト」についてのディスクールは、それ自体が、ほかならぬテクストとなり、テクストの探求となり、テクストの労働とならねばならないであろう」
本稿で私が〈散文〉と呼んできたものは、ここでバルトが「テクスト」と呼んでいるものと置き換えていただいても相違ない。バルトが主張するように、作品ではなく、純粋に〈散文=テクスト〉であるものは、メタ言語=批評の言葉を疑い、拒絶し、破壊し、そのことをもって自らの領域を形成し、新たな理論を成立させるのだ。〈散文=テクスト〉という時空においては、作品内に書かれたものだけが全てなのではない。〈散文〉は新たな〈散文〉を呼び寄せる。〈散文〉は〈作品〉とは異なり、無限に――読解が続く限りにおいて、そこに人間がいる限りにおいて――拡大を続ける。読まれたこと、想起されたこと、語られたことの全てを〈散文〉は飲み込み、そしてまた新たな言葉を生み出してゆく――そして、残念ながら、ここにあるもう一つの散文は、〈作品〉としての完成度が高いがゆえに、この100文字の〈散文=テクスト〉と比して、生成可能な時空の〈無限性〉という点において、足かせになっているように思われたのだ。
蜂本みさ「竜宮」は優れた小説である。それは誰が読んでも明らかなことだ。語り口は軽妙で、登場人物の造形にはリアリティがあり、日常と非日常の融け合う描写は魅力的だ。『かめくん』という代表作を持つ北野勇作との戦いを意識し、「亀」を直接的なモチーフに据えるのも面白い。物語、そしてそれが孕むテーマも普遍的と言えるだろう。
「竜宮」は、すれ違いながらともに生きる、恋人たちの物語だ。恋人たち、二人の男女――むろん、女・女の組み合わせの可能性も考えられたが、本稿では作中用いられた「ウェイター」という語彙の一般的な運用を汲み、二人は男・女の組み合わせを指すものとして読んだ――、そして二人のあいだにやってきた「亀」と「竜宮」を巡る物語。
そこでは、今まさに別れようとする恋人同士が亀を助け、亀を通して各々の「竜宮」の幻影を見る。男が見ている幻と、女が見ている幻は異なるものの、二人は亀が見せる「竜宮」の幻影を通して、二人の日常に帰ってゆく。二人のあいだに「決着」はつかない。二人は宙吊りになった日常の中で、これからも各々異なる世界を見続け、そしてその世界は決して一致することはない。二人はおそらく子供を持たない。二人は未来を確定させることはない。二人は子供を育てることなく、代わりに亀を育て続ける。二人は子供に夢を見ることなく、亀を通して夢を見る。亀が二人をつなぎ、竜宮が二人をつないでゆく。そうして二人の日常は続いてゆく――私はそう読んだ。私にはその小説が何を言おうとしているのかがよくわかった。少なくともよくわかるような気がした。そこには私がよく知る小説の――優れた小説の――姿があった。私は「竜宮」について考えながら、自分の身体によくなじんだ、記憶というものさしのことを考えていた。
思い出された私の記憶。
その記憶とは、次のようなものだ。
私は名古屋の亀島という町に住んでいる。私は亀島にある家から歩いて栄に向かう途中、納屋橋の歩道で亀を見つけたことがある。甲羅をつまんで持ち上げて、橋から河原に向かう階段を降りて、それから堀川の中へと放してやった。亀は甲羅で風を受け、くるくる回転しながら流されていった。
「亀、助けたね」と妻は言った。「亀を助けるとね、絶対いいことがあるよ」と妻は言った。妻は子供の頃に亀を助けたことがあり、それからかれこれ20余年、いいことばかりが続いているらしい。
亀を助けたことを起点にすることで、妻は生活の中から「いいこと」をつないで見ることができるようになった。亀は助けた人を龍宮城に連れていってくれる。亀はそうして、助けた人に「いいこと」をもたらしてくれる。竜宮城はどこにもないが、竜宮城はどこにでもある。私たちはなんでもない日常の中に、竜宮城の影を見ることができる。私の妻は、竜宮城のありかを知っている。
竜宮城とは何か。
答えはもはや、自明のことだろう。
先日、娘が二歳になった。私は娘に絵本を買ってやる。娘と一緒に絵本を読む。娘と一緒に歌をうたう。娘はどんどん言葉を覚える。娘はどんどん大きくなる。娘はどんどん変わっていく。娘とともに、私や妻もまた変わっていく。私は小さな娘と浦島太郎を読む。娘もいつか、竜宮城を探すだろう。やがて亀を助け、竜宮城の場所を知るだろう。そうではないかもしれないが、少なくとも私は、そう願っている。
何もかもが変わっていく。変わっていく先で、やがて私たちはいなくなる。それでも娘は残り、助けた亀は残るだろう。何しろ亀は長生きだ。変わっていくことは、失われることではない。竜宮城は消えることはない。たとえ私たちがいなくなったとしても、竜宮城は私たちの娘に「いいこと」をもたらし続けてくれるだろう。竜宮城は全ての時間に、全ての空間に偏在している。助けた亀は、私たちにそのことを教えてくれる。
ところで、「竜宮」の二人は決着をつけないことを選んだ。
二人は未来を宙吊りにし、未来を確定させないことを選んだ。
二人はそれぞれの見たい「竜宮」の幻影を、亀を育てることで見続けることを選んだ。
けれどもそれは、本当に決着をつけないことになるのだろうか?
北野勇作はかつて、『かめくん』の中で次のような文を書いた。
「未来を観測するという行為が、結局は未来を確定することになる」
量子力学。その法則が正しければ、私たちは私たちである限り、決して未来から逃れることはできない。宙吊りにするという仕方で宙吊りを明示化することはできない。決着をつけないと書くことは、決着をつけないという仕方で決着をつけることにほかならない。
私は蜂本みさの小説を読みながら、気づけば北野勇作の小説のことを考えていた。
私は自分が今まで読んだ小説のことを考えていた。その結果、私は私の記憶を通して、その「決着をつけない小説」を、私の身体になじんだ、私のための、私自身の物語として読むことができた。それは私にとっては特別な読書体験となった。しかしながら、そうした意味で、私にとってその小説は、逆説的に、ある種の有限性を帯びているような気がした。私にとって「竜宮」は、無限性を担った〈散文〉ではなく、有限で、閉じた〈作品〉であるように思われたのだ。
もちろんそれは私の主観であり、何の根拠もありはしない。異論や反論はあるだろう。これが正しい読みであるとは言えるはずもない。一体私は何を書いているのか? もはやこれはただの信仰告白に過ぎないのかもしれない。それでも私は――私の全ての思考は――2400字の〈作品〉の有限性よりも、100字の〈散文〉の無限性に賭けてみたい、と、確信にも似た直観に貫かれてしまったのだ。
脱線ばかりで申し訳ないが、唐突ながら、ここで私は一つのできごとを思い出す。
たった100字のその〈散文〉は、発表される際に、ジョン・ケージ「4分33秒」にたとえられた。
しかし私は、たとえとしては「4分33秒」というよりも、どちらかと言えば「4分33秒」への「解答」として構想された灰野敬二による楽曲、「奇跡」と題されたその一瞬の音楽の方が適切だろう、と思った。
灰野敬二「奇跡」は、ピアノの88鍵を、88人の人差し指をもって同時に鳴らすという楽曲であり、作曲と即興、能動と受動、演奏と聴取の境界を無効化する、純粋な〈音〉そのものを志向する音楽である。88鍵と、そこから広がる倍音が可能にする、全ての可能な音が込められた、たった一つの音色。有限性の中に閉じ込められた無限性。汲み尽くすことのできない響き。奇跡。
たとえそれが一音に過ぎずとも、数秒で消え失せる、何気ない、単なる――恣意的に、人工的に構成された――ピアノの音色に過ぎずとも、そこには、全てのリズム、全てのメロディ、全てのハーモニーの可能性が、折り重なって存在する。88人の身体が、その指先が、一台のピアノを中心にして、上に、下に、縦に、横に、内に向かって、外に向かって、折り重なって存在するように。
「奇跡」と呼ばれるその音は、折り重なるイメージを引き連れて、響きの中で響き続ける。たとえその響きがやんだとしても、響きが響いたというその事実は、やがてまた、響きの外へ、新たな響きをもたらすだろう。何気ない、親と子が並んで歩くその一瞬の光景が、それを目撃した者の内で、それが思い出されるつど、語り直されるつど、書き直されるつど、永遠に、際限なく、無数の異なる光景として蘇るように。
話を戻そう。
「未来を観測するという行為が、結局は未来を確定することになる」
北野勇作の〈散文〉はそこから始まっている。
たしかに未来は確定される。
しかしながら、未来は一つではない。
〈散文〉の複数性によって、未来を複数化させること。
〈散文〉の無限性によって、未来に無限性をもたらすこと。
〈散文〉の不確定性によって、観測そのものを不確定性の中に投げ込むこと。
北野勇作は、100字の〈散文〉を、分岐する、分岐し続ける、分岐し続けることを分岐し続ける、複数的で、ゆえに不確定的な、分岐そのものとしての未来に向けて、書き続けている。
既知への意志と未知への意志のあいだで生まれる、終わりのない闘争――絶えざるその生成の運動。〈散文〉の中で、秩序と混沌が衝突し、自壊する寸前において、ぎりぎりその姿を保っていること。小説として書かれた言葉が自ら、小説=秩序の領域を超え出ようとする意志を持つこと。混沌への意志を持ちつつ、それでもなお秩序の重力に引かれていること。その捻れ。その歪さ。その美しさ。そこでは言葉が自らを欲し、自らを書いている。
〈散文〉は、ただ単に存在する。単に存在するものは単に存在する。それは、自己を自己によってのみ生成し続ける運動体として。語り得ぬもの、何ものにも還元し得ぬものとして。作者にも読者にも、固定的な何ものにも依存せず、ただそれのみの言葉によって生きながらえるものとして。私たちが既に知っている〈小説〉であろうとする言葉ではなく、ただ単に言葉であろうとする言葉――誰もが初めて目にする〈存在そのもの〉としての〈素朴な散文〉のその姿に、私は新たな〈ブンゲイ〉のありかたを見た。私は、〈散文〉の中で引き裂き合う、その闘争の場としてのこの〈素朴な散文〉こそが、まさに、〈ブンゲイファイト〉という言葉を冠するこのイベントの優勝作品にふさわしいと考えた。
全てである、この〈存在そのもの〉としての〈散文〉。
それは存在している。ただ単に、存在し続けている。そして、ただ単に存在するがゆえに、それは完璧な小説たり得ている。
そう、「完璧であるためには、存在するだけでよい」のだ。
前置きが長くなった。私はたった一つの文を書くために、それ以外の――私が私の手持ちのものさしから逃れるための――文に多くを費やしすぎた。一方で、費やされた思考は少なすぎるとも言える――結局のところ、私は私のものさしから逃れることはできなかった――のだが、ものさしから逃れるための私の、思考のための思考の続きは、また別の機会にゆだねることにしよう。幸か不幸か、その〈散文〉に貫かれてしまった私は、これからもずっと、その〈散文〉に試され続けるのだから。
今日は2019年の11月30日。本稿が発表されるのは2019年の12月1日。つまり明日だ。時間は限られている。約束の時間はとうに過ぎている。未来は既に確定されているのにもかかわらず、私は未来を先延ばしにしようとしている。それでもやはり、決着はつけられるほかない。私は未来を知っている。次に続く言葉を知っている。未来はたしかにそこにある。確定されることを運命づけられた未来が、観測され、確定されることを待っている。
いずれにせよ、もはやこれ以上の言葉は不要だろう。
第一回ブンゲイファイトクラブ優勝作品を、北野勇作「【ほぼ百字小説】(1783)」とする。
これが、私の最後のジャッジだ。
—————————————————————————
決勝

ジャッジ 樋口恭介
決勝作品
【ほぼ百字小説】(1783)

♦
竜宮






♦
準決勝

金子 玲介
小説教室







北野 勇作
中州の恐竜






蜂本 みさ
ブンダバランド




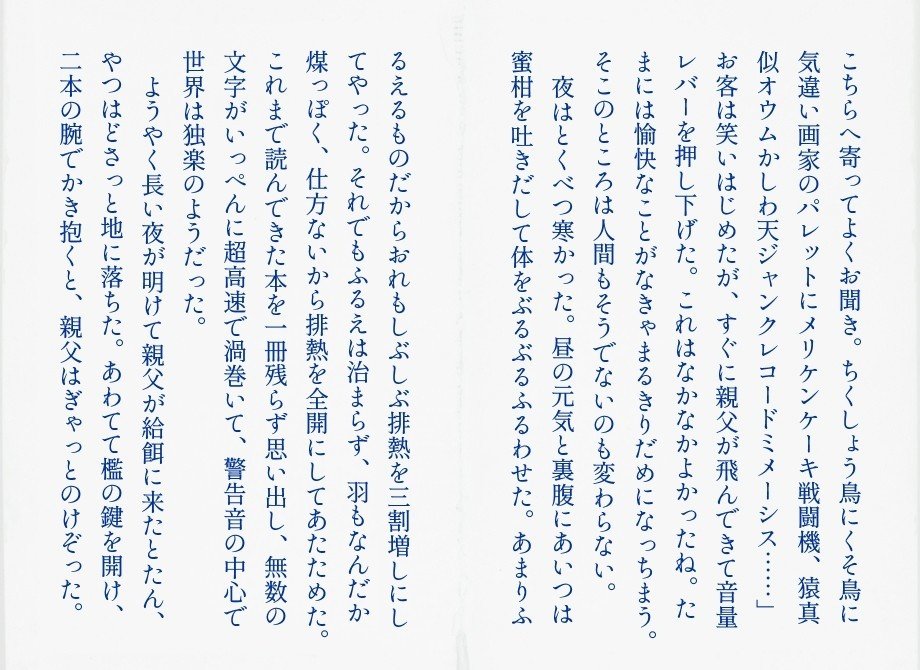

齋藤 友果
いまもいる

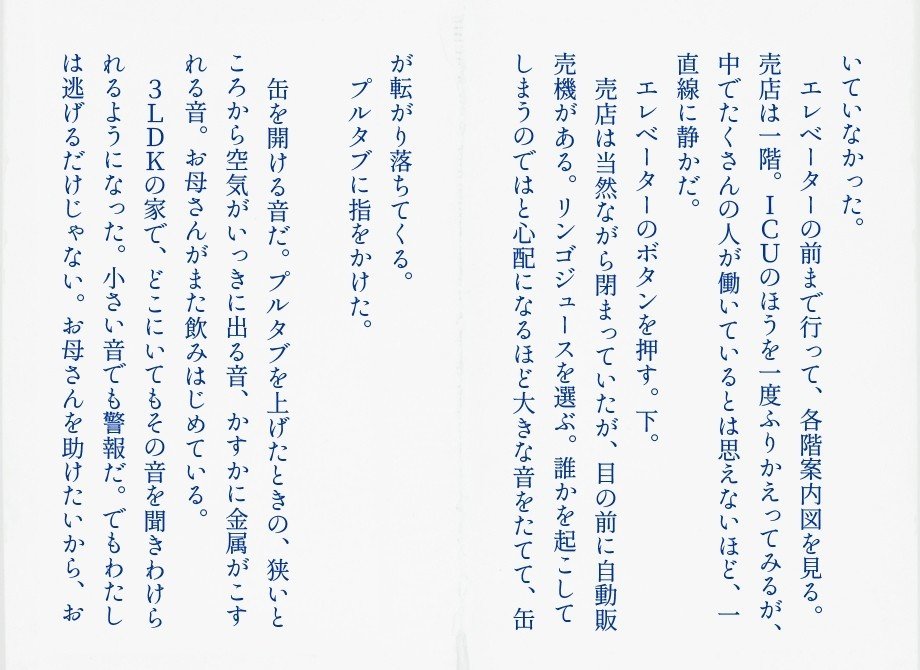





———————————————
準決勝ジャッジ
笠井康平
樋口恭介
元文芸誌編集長 ブルー
———————————————
ジャッジによる準決勝作品評
♦
ファイターと運営によるジャッジ評
2回戦

対戦 A
「あなたと犬と」金子 玲介
「森」雛倉 さりえ
対戦 B
「砂のある風景」北野 勇作
「グリーン テキスト」齋藤 優
対戦 C
「抜ける日々からむいていく」大前 粟生
「いっぷう変わったおとむらい」蜂本 みさ
対戦 D
「天狗の質的研究」吉美 駿一郎
「ミドリノオバサンとヒト、およびウマ」齋藤 友果
作品
採点・評・コメント
2回戦結果とジャッジによる選評
2回戦ファイターによるジャッジの採点およびコメント
準決勝に際して——ファイターのコメント・感想あるいは三つの質問
———————————————
2回戦ジャッジ
笠井康平
仲俣暁生
橋本輝幸
樋口恭介
元文芸誌編集長 ブルー
1回戦

ー作品ー
Aグループ
「読書と人生の微分法」大滝瓶太
「愛あるかぎり」冬乃くじ
「あの大会を目指して」鵜川 龍史
「アボカド」金子 玲介(2回戦進出)
Bグループ
「飼育」雛倉さりえ(2回戦進出)
「インフラストレーション」大田 陵史
「宇宙が終わっても待っている」後谷戸 隆
「伝染るんです。」竹花 一乃
Cグループ
「天の肉、地の骨」北野勇作(2回戦進出)
「期待はやがて飲み込まれる草」伊藤 左知子
「来たコダック!」蕪木 Q平
「愚図で無能な間抜け」植川
Dグループ
「その愛の卵の」齋藤優(2回戦進出)
「甲府日記 その一」飯野 文彦
「逆さの女」正井
「殺人野球小説」矢部 嵩
Eグループ
「私の弟」大前粟生(2回戦進出)
「抱けぬ身体」原 英
「立ち止まってさよならを言う」 栗山 心
「月と眼球」式さん
Fグループ
「手袋」珠緒
「天空分離について」伊予 夏樹
「遠吠え教室」蜂本 みさ(2回戦進出)
読書感想文「残穢」 一色 胴元
Gグループ
「跳ぶ死」伊藤なむあひ
「夏の目」吉美 駿一郎(2回戦進出)
「ニルヴァーナ 川柳一〇八句」川合 大祐
「パゴダの羽虫」中島 晴
Hグループ
「鳩の肉」齋藤 友果(2回戦進出)
「ハハコグサ」磯城 草介
「くされえにし」林 四斜
「ハワイ」貝原
ージャッジー
笠井康平(2回戦進出)
QTV
帆釣木 深雪
道券はな
仲俣暁生(2回戦進出)
橋本輝幸(2回戦進出)
樋口恭介(2回戦進出)
元文芸誌編集長 ブルー(2回戦進出)
ー評・採点ー
1回戦作品 ジャッジ採点表
1回戦作品へのジャッジの評などの詳細はこちらです。
♦
1回戦:ファイターによるジャッジ採点表
1回戦:ファイターによるジャッジ採点の補足・説明
参加者プロフィール
■ファイター部門
【公募】
飯野 文彦 (いいの・ふみひこ)
愛車の日産ノートを運転していて、左折したら、コンクリート片にぶつけて、修理代20万かかるわ、駐車場で扉を開けたら、となりに停まっていた黒塗りのレクサスに、ぶつけるわ。なんてこったーーと思いながらも、まだ何かぶつかるかな……とおびえていたら「ここ!」で、ぶつかった。ふうぅ。この頃の晩酌はホワイトホースのハイボールですが、なんか味がよくなった。すぐ、苦くなるのかな? よろしくお願いします!
一色 胴元(いっしき・どうもと)
意識やばい読書会及び、ハードボイルド読書探偵局の胴元。
伊藤 左知子(いとう・さちこ)
フリーライター。俳句、詩、小説を作っています。たまたま永平寺に居たときに予選通過を知り、とりあえず手を合わせておきました。
伊藤 なむあひ(いとう・なむあい)
プロフィール:仮想出版社、隙間社から主に電子書籍で作品を発表している他、文学フリマ等のイベントでも活動中。好きな食べ物はパン。得意なプレイスタイルは改行。
抱負:自分にしか書けないものを書き続ける。
伊予 夏樹(いよ・なつき)
1992年生まれ。現在は某博物館の学芸員を務める傍ら、趣味で小説を書いています。学術関係の専門は日本近代史、創作の専門は幻想小説・怪奇小説・怪談です。
繊細な心の持ち主ゆえ、殺伐とした雰囲気は苦手です。けれども、今までに読んだり書いたりする事でそれなりに磨いて来た幻想を紡ぐ力と、歴史学という学問を中心として構築し続けている知識の迷宮の力を信じ、力を抜いて参加したいと思います。
植川
後谷戸 隆(うしろやと・たかし)
趣味で小説を書いています。本戦に出場する機会を頂いたので、できる限り頑張ります。よろしくお願いします。
長時間小説を書いても疲れない頭が欲しいです。
Twitter:@ushiroyato
鵜川 龍史(うかわ りゅうじ)
ゲンロンSF創作講座2期受講生にして、3期生応援ラジオGGRのメンバー。野良犬として牙を研いでいたら、驚きの白さに(歯が)。コント集団〈文芸部〉やお笑いコンビ〈クラクションズ〉(ボケ・脚本担当)で舞台に立つ傍ら、流しの落語家としても活動。まれに、プログレメタルシンガーとして、ライブやセッションに出没。
原稿用紙六枚という制限は遅読を促す装置になる。奇想を駆使して、読者の想像力を極限まで刺激したい。
大田 陵史(おおた・りょうじ)
一九八三年群馬県生まれ。東京都在住。
たべるのがおそい vol.5 寄稿。
映画「ロッキー」のテーマが頭の中でずっと流れているんです。
ここまできたら、なんかもう誰もがロッキー・バルボアでアポロ・クリードみたいで。
最後のストップモーションがどんなに汚くても美しい瞬間になるように、虎視眈々とブンブン肩を回していく所存です。
貝原(かいはら)
『てのひら怪談』シリーズ(ポプラ社、KADOKAWA)に短いものを何度か載せていただきました。蕎麦田名義で第10回『幽』文学賞短篇部門佳作。椎名寅生名義の『花園』(星海社)が発売中。
金子 玲介(かねこ・れいすけ)
お招きいただきありがとうございます。金子玲介です。僭越ですが、私ほど、この宴にふさわしい作家はいないと思っています。なぜなら私は、これまで、「小説ではない」という評で幾度も涙をのんできたからです。君の小説は、小説ではなく演劇だよねコントだよね詩だよね云々。しかしこの宴の応募規定は、“日本語による作品”です。ここでは誰も「小説ではない」という理由で、私の小説を非難することはできないのです。どうぞよろしくお願いいたします。
蕪木 Q平(かぶらぎ・きゅーへい)
趣味はけん玉です。よろしくおねがいします。
川合 大祐(かわい ・だいすけ)
一九七四年長野県生まれ。今も信濃の山奥に生息中。川柳書き。というかほぼ川柳しか書けません。Twitterで発表しているので見てくださーい。「川柳スパイラル」同人。そちらの原稿を落とす危険を犯しつつ参戦。それでも、川柳でブンゲイと闘いたいのです。著書に「川柳句集 スロー・リバー」。あと、カレーライスが好きです。“Stand and fight.”
栗山 心(くりやま・こころ)
「世界小説化計画」講座受講生。小説を書くために、一番短い詩形である俳句を16年勉強しました。アイドリングは完了。ここから飛ばします。
齋藤 友果(さいとう・ゆか)
本まわりのいろいろ、デザイン、装丁、手製本、プライベートプレスと
手を出してきましたが、今はおもに小説を書いています。
いままでの制作物はこちら( https://saitoyuka.com/ )です。
特技はコオロギの飼育。
誰を殴るつもりもありませんが、おのずと皆をひれ伏させる所存です。
式さん(しきさん)
式さんです。第3回54字の文学賞にて大賞を受賞しました。現在はゲンロン大森望SF創作講座第4期受講生です。
BFC予選には文芸という「贅沢《ラグジュアリー》」を掲げる「贅沢者《セレブ》」が多数集まりました。
そして激戦を勝ち抜き本戦に出場した「上《ハイクラス》」な者達――もはや「神学論争不要《つべこべいうな》」、「ファイター《セレベスト》 」達の 「決戦《おもてなし》」 を見逃す手はないだろォ~~~ッ!!(ホッコリ)
磯城 草介(しき・そうすけ)
10月より山村教室に入会。文学を語れるほどの知識も実力もありませんが、ブンゲイファイトクラブを通じて、なにかを見つけられるのではないかと期待しています。
竹花 一乃(たけはな・いちの)
小説を書いてます。あとは運に任せます!
珠緒(たまお)
このたび初めて小説を書きました。
ふだんは会社員で、福岡で食べ物の仕事をしています。時折、文章も書きます。ぴったりの言葉をさがしてさまようのは、本当に楽しいです。
今回書きたかったのは、幼少の頃より漠然と抱いていた不安や恐れ。ずっと闇が怖かったし、何より人が怖かった。そんなとき小説を読むと、なぜだか心が安らぎました。小説をつうじて負の感情にも向き合い、それを言葉に昇華してゆく人たちの勇気に、力をもらっていたのだと思います。それは今でも。
私もそんな風に書き続けていきたいです。
中島 晴(なかじま・はる)
図書館も本屋も駅もない小さな町で生まれ育ちました。父がたまに買ってきてくれる本が何よりのお土産で、新しい本を買ってもらえるまで何度も何度も同じ本を読みました。本を読み始めると他のことをしなくなるので、しまいには母に読書を禁じられてしまいました。本を読むのはどうしてこんなに楽しいのでしょうか。私の書いたものもどうか皆様に面白いと思っていただけますように。
蜂本みさ(はちもと・みさ)
大阪生まれ大阪育ち京都在住。サンカクカンケイ所属。普段の拠点はTwitterとはてなブログ。次点から繰り上げでファイターになりました。高校も大学もぎりぎりで受かったので、もうそういう人生なのだと思います。戦いたい相手は大前粟生さん。蜂と本とグミが好き。
林 四斜(はやし・ししゃ)
川端で健康な未成熟が水をかけ合ってはしゃぐ姿を眺めている。自分も慌てて靴下を脱ぎそっと踏み入れてみたものの、足首の裏が痛むだけなので、岸に腰を下ろして靴下を履き、右に頬杖をついてきらめきを目尻で暈している今日この頃です。
原 英(はら・えい)
俳句結社「ひまわり」、俳句同人誌「奎」、徳島文学協会、俳人協会所属
自己紹介抱負肩書鵙の贄
冬乃 くじ(ふゆの・くじ)
すでにお読みくださった選考員の皆様、これよりお読みくださるジャッジ、そして読者の皆様、厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございます。冬乃くじです。たくさんの言葉に救われて生きてきました。この世界のどこかで、わたしと同じように孤独を感じている人の、傷を少しでも癒せるような言葉を紡げるようになれたなら、これ程の幸せはありません。二度三度、読んでいただける文章をめざしてがんばります。どうぞよろしくお願いいたします。
正井(まさい)
正井と申します。普段は野山でドーナツなどをかじりつつ暮らしておりますが、この度参戦のため都会に出て参りました。なるべくたくさんの文芸者を薙ぎ倒せるように頑張ります。以後お見知り置きを。
矢部 嵩(やべ・たかし)
漢検二級
吉美 駿一郎(よしみ・しゅんいちろう)
ただのアマチュア、ずぶの素人です。大会参加にあたって考えたのは、「短歌に勝ちたい」でした。だってどう考えても強いでしょ短歌。短歌に勝てる小説なら、きっとほかのジャンルとも渡り合えそうな気がします。そんな気がしませんか。あとは、大会に参加しなかったプロを死ぬほど後悔させたいなとも思いました。観客すべてが「あのリングに上がりたかった」と思ってしまうような熱い戦いを望みます。
【招待】
大滝瓶太(おおたき・びんた)
小説を書いたり、翻訳をちょこっとやったりWEBでコラムを書いたりしています。
じぶんのことをオシャレだとおもっているのですが、Tシャツのセンスをよく否定されます。
この大会でしか書けない小説が書ければいいなっておもってます!!!
Twitter:@BOhtaki(https://twitter.com/BOhtaki)
note:https://note.mu/bintaohtaki
大前粟生(おおまえ・あお)
大前粟生といいます。おおまえあお、という読み方です。現実やそのときどきの言葉や物語に対しての苛立ちが自分に小説を書かせているのかなと最近は思います。よろしくお願いします。
北野勇作(きたの・ゆうさく)
小説を書いています。朗読をしたりもします。
ツイッター上で【ほぼ百字小説】を書いています。
短い小説が好きなので参加しました。
齋藤優(さいとう・ゆう)
齋藤優です。小説も好きですが、今はラグビーも好きです。戦意で小説が書けたものかはわかりませんが、今回はマッチョな気持ちで、勝ちたいです。過去作には「たべるのがおそい vol.5」に『馬』など。
雛倉さりえ(ひなくら・さりえ)
1995年生まれ。小説を書いています。『ジェリー・フィッシュ』(新潮社)、『ジゼルの叫び』(新潮社)、『もう二度と食べることのない果実の味を』(小学館)発売中です。掌編は書くのも読むのも楽しくて大好きです。よろしくお願い致します。
■ジャッジ部門
【公募】
笠井康平(かさい・こうへい)
1988年生。いぬのせなか座。著作に『私的なものへの配慮No.3』。
QTV(キューテイーヴイ)
髙畑鍬名で映画監督を。QTVで小説を。清水エスパルス詩集に日々の詩を。
https://www.manetama.jp/category/culture-art/great-people/
松岡修造、小栗旬&山田孝之、村上春樹、
宇多田ヒカル&椎名林檎、雨宮まみ、
宮藤官九郎、リリー・フランキー、太田光の
仕事哲学について書いた連載、お読みいただければ幸いです。
帆釣木 深雪(ほつりぎ・みゆき)
自己紹介
平日はラムネをつまみながら、PC機器と向かい合ってわちゃくちゃしている。たまに定時で帰るタイミングを逃し、家に帰りたくもなくなるので、書店で暇をつぶすことが多い。基本的に深夜までなんとなく起きており、そのせいか、いつも眠たげな目をしている。
抱負
道に迷うことは、割と好きだ。ひたすら歩き回ると、やがて酩酊めいた愉しさが焦燥感を上回る瞬間がやってくる。制作者たちが文章で創り上げた小宇宙を彷徨いながら、地図をつくってみるのも面白いのかもしれない。見知らぬ街の駅に降り立っていく気分ですが、どうかよしなに。
道券はな(どうけん・はな)
「あっぱれ!」同人(小説)、「toolate」同人(短歌)、未来短歌会Twitter:@peter_pan_co
【招待】
仲俣暁生(なかまた・あきお)
文芸評論家、フリー編集者。小学館ガガガ文庫の創刊や、NPO法人HON.jp主催の創作合宿ノベルジャムの運営に関わる。著書『極西文学論』『「鍵のかかった部屋」をいかに解体するか』ほか。今回のレフェリー、ガチでやらせていただきます。
橋本輝幸(はしもと・てるゆき)
三十代の無害そうな会社員です。かつては兼業書評家でした。二つ名は「危険な読者」です。以前、それぞれ面識のある翻訳家二人が並んでいたので挨拶しようと近づいたところ「気をつけろ、そいつ本を読むぞ!!」と片方からもう一方に警告が飛びました。気をつけてください、読みます。
今でも趣味として英語や中国語でも日々読み続けています。ファイター諸君、日本大会だけで満足ですか? 私には世界大会観戦者の目があります。
樋口恭介(ひぐち・きょうすけ)
僕は普段、小説を書いています。僕は小説を書くことが好きです。でも僕は、それ以上に小説を読むことが好きです。特に、あまり評価の定まっていない、新しい作家の作品を読むことが好きです。多くの作家がそうなんじゃないかと思うのですが、名も知らぬ作家の、未知の小説を読もうとするときほど、わくわくすることはありません。そして今、僕はとてもわくわくしています。新しい小説が読めることを、とても楽しみにしています。
元文芸誌編集長 ブルー
「原稿用紙6枚」の可能性を楽しみにしております。
日程
10月1日前後 1回戦作品公開
10月13日 1回戦結果発表
10月20日 2回戦作品公開
11月3日 2回戦結果発表
11月10日 3回戦作品公開
11月17日 3回戦結果発表
11月24日 決勝作品公開
12月1日 決勝結果発表
予選選考の感想
編集Z
今回全作品を読ませていただき、嬉しい驚きだったのは、全体的な作品レベルの高さでした。残念ながら本戦に進まなかった作品も、それぞれ力作であり、他に負けない長所があり、ブンゲイの底力を感じるものでした。
予選選考も最後の最後までもつれる熱戦でした。本戦に進まなかった方も、またいずれお目にかかる機会があるのではないかと。そして本戦出場の皆さま、ご武運をお祈りします!
編集オメガ
予想を遥かに上回る数の応募作に驚きつつ、一作一作、楽しみながら悩みながら読ませていただきました。本当にレベルの高い作品が揃い、本戦に進まなかったことを心から惜しく思う作品が選考委員それぞれにあるような、白熱した予選選考となりました。
本戦出場の皆様、おめでとうございます! これはとんでもなく面白いトーナメントになると、皆様の作品を読んであらためて確信いたしました。これからの熱いファイトを心より楽しみにしています。
編集リドル
本当に苦しかった。かなり熱量の高い作品が集まってきたという感触でした。そのなかから選び取る作業は、苦しかったけれど、こんなにたくさんの才能があるということが大変うれしく、希望を感じました。私も熱中して拝読しました。頭がカッカするほどです。寝て起きて、それでも心を離さなかったものを推せたかと思います。
勝っても負けても、この祭りは踊らにゃ損損!です。ブンゲイ、みんなで盛り上げていきましょう。
ブンゲイファイトクラブ
文芸作品による殴りあいのオープントーナメント
賞金なし。手に入るのは名誉だけ
主催:惑星と口笛ブックス、編集Z、編集オメガ、編集リドル
お問い合わせ:past-pop-future@nifty.com
権利
作品の権利は各作者に帰属します。
