
故郷
オーディオブックURL:https://www.youtube.com/watch?v=kI5R9H_VtM0
以下、原文。
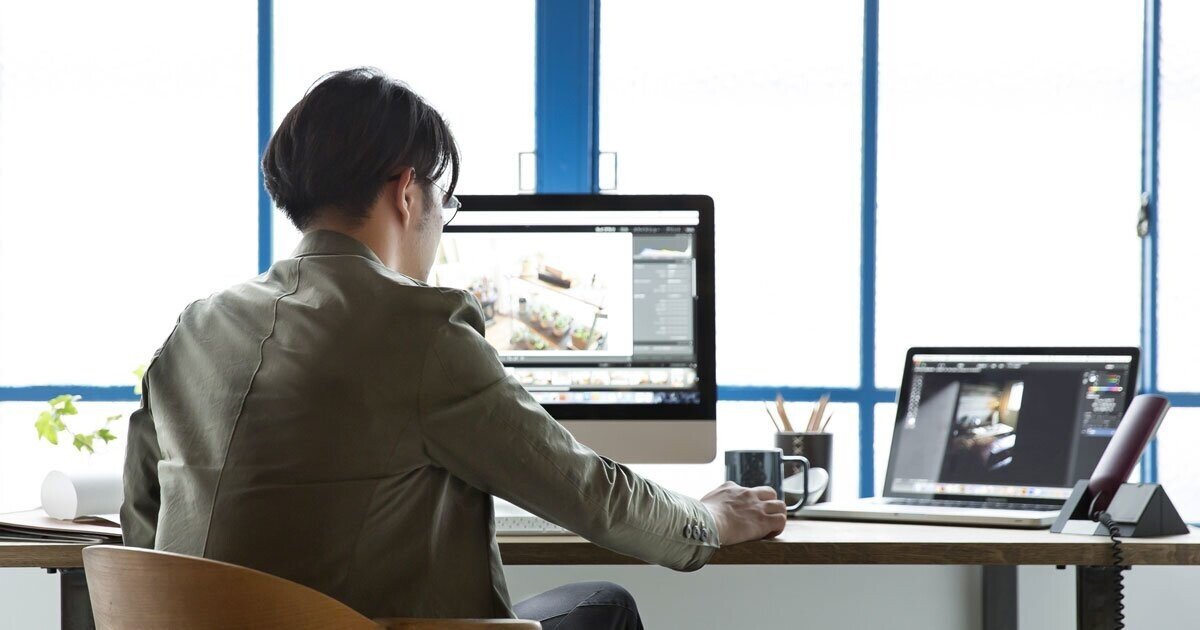
「じゃあ皆さんお疲れ様です」
そう言うと僕はビデオ会議を終えた。そして、すぐLineを開いた。
「もうすぐ仕事終わるけど、そっちはどう?」
そうメッセージを送った後、僕は顧客からの問い合わせメールを開いた。実家へ帰りリモートワークを初めて半年目、もう大した弊害なく業務を回せるようになってきた。
仕事にだいたい片がついた頃、Lineの通知が鳴った。稲村さんから返信が来た。
「今終わった、今から出る」
相変わらずそっけない対応だなと、僕は思った。彼女と僕は今日、おそらく10年ぶりに再開する。
稲村さんは僕の初体験の相手だった。高校時代、僕は彼女に対して淡い恋心を抱いていた。しかし、当時彼女には彼氏がいた。ただ、そんな僕の気持ちを知ってか知らずか、彼女は僕と何度かデートして、成り行きで僕は彼女と始めて肉体関係をもった。
この関係はたった3ヶ月だけ続いた。
それは僕の大学進学を区切りに終わった。彼女のことが忘れられなかった僕は帰省の度、連絡していた。
そんなある時、「もう会えないから」と彼女から返信があり、それ以降、彼女は僕の連絡先をブロックしたようだった。
そして僕が都会で就職した頃、彼女は結婚したそうだ。あれから10年、もう度々実家に帰ることもないし、もう彼女と会わないと思っていた。
しかし、コロナの影響で僕は都会から実家の田舎に帰りリモートワークをすることになった。
そんなある日、SNS上で稲村さんを見つけてしまい、僕から連絡をしたことで今回の再開のきっかけだった。
久しぶりに稲村さんと会う、何を話そうか。僕は久しぶりにドキドキしていた。
10代の盛り、彼女だけが僕に身体を許してくれた。そして僕は我を忘れ彼女に夢中になった。ただ、彼女は最後まで僕と今以上の関係を持たなかった。
彼女にとって些細なことだったかもしれないが、あの三ヶ月間の記憶は、その当時の情念は、今も僕の心の奥底に燻り、時々稲村さんへの想いを呼び起こさせる。僕は何としてでも彼女を手に入れたかった。
しかし今思えば、当時の僕は体ばかりを求め、彼女はそれに辟易していたのかもしれない。
ただ、僕はもうあの時の10代の高校生ではない。
僕は今や名の通った企業で、ある程度の管理職を任せられている。
そして僕はこの10年間、有名大学での学生生活、海外留学、上場企業への就職と海外駐在、そして海外部門の管理業務という、この田舎で暮らしている人間では到底味わうことのない経験を蓄積している。また独身なので、10代の時と比べ物にならない金銭的な余裕もある。
そうだ、前回のボーナスを頭金に買った新車で迎えにいってやろう。そして彼女を乗せて国道をぶっ飛ばしてやればいい。
助手席に座る稲村さんは、これまでの田舎暮らしで感じたこともないような、2.0 L直列4気筒エンジンが奏でる都会的で洗練された雄の雄叫びを全身で感じることになるだろう。
「今日は外で食べてくる」。そう僕は退職まもない両親に告げ、家の車の鍵を取り、勝手口から外へ出た。
家の車に乗ると僕はタバコに火をつけた。そして、僕はエンジンスタートスイッチを押すと、僕の愛車は、ヴォン、と低い唸り声をあげ目を覚ました。
昔の女と再開するコンディションとしては完璧である。しかし、どうも気持ちが落ち着かない。僕はもう一度タバコを深く吸い込んだ。
ハンドルを握り、待ち合わせてのショッピングモールの駐車場へ向かう途中、僕の脳裏に彼女の顔や姿が鮮明に蘇って来た。
「黒い羽、生えているかもしれませんね」
裸の稲村さんは、同じく裸の僕の上に覆いかぶさり、ショートヘアーを掻き上げ、その手で頬杖をつきながらこう答えた。
これは僕が童貞を稲村さんに捧げた日、バイパス沿いのラブホテル、ホテルシルクロードでの出来事だった。
あの時僕はことが終わった後、僕たちの初めての出会いを彼女に語っていた。
僕が始めて彼女を見た時、彼女は一人、クラスの片隅で本を読んでいた。
姿勢がよく、綺麗なショートヘアと新品の制服はとても清潔そうに見えた。新入学の興奮冷めやらないクラスで、一人大人しく本を読んでいる彼女が、「天使に見えた」と、僕は言った。
それに対して彼女は妖しくこう答えた。
このホテルシルクロードは、以前この建物を使っていた「ホテル勉強部屋」の看板と内装を改装しリニューアルオープンしたばかりだった。
ゆえに、室内の建具やテーブル、その他ラブホテル特有のアメニティは勉強部屋当時のままであった。これはこれで、今日から実技演習に入ったばかりの僕の探究心をくすぐる効果があった。
しかし、ベッドサイドにはこの勉強部屋的雰囲気と全く交わることのない大きな一枚の絵が飾られていた。
そこには三匹のラクダと、一体のスフィンクス、そしてピラミッドの絵が描かれていた。
この絵からホテル勉強部屋を買い取ってまで、ホテルシルクロードを作りたかったオーナーの意気込みが滲み出ていた。
今になって思うとこれはエジプトの絵画であり、エジプトとシルクロードの関係はそう深くない。ただ、当時の僕にそんなことを認識する余裕はなかった。
その絵は蛍光塗料で描かれており、電気を消すとラブホテルの蛍光灯の光を吸い込んだピラミッドが神々しく発光するのであった。その光量は童貞を失ったばかりの10代の脳を焼き尽くすためには十二分だった。
その薄緑色に輝くピラミッドパワーを背後に受けながら、稲村さんは童貞を失ったばかりの僕に語りかけたのだった。
「黒い羽、生えてるかもしれませんね」、と。
タバコを一本吸い終わるころに、僕は待ち合わせ場所のショッピングモールの駐車場についた。
「ついたよ」
そう彼女に連絡したら、「本売り場にいる」。とまたもそっけない返信があった。
僕は車に鍵をかけ、トイレで髪型をチェックし、そして待ち合わせの本売り場に向かった。
本売り場に着くと、それらしい女性がいた。何度か見たことのある地元の食品工場の制服を着ている。
僕はあまり自信がなく、もう少し様子を伺おうとすると、相手の方から声をかけて来た。その女性は久しぶりの友人に会った時と同じく、顔の上に驚きと親しみを表していた。
「宮崎くん」
そう一つ、はっきりと僕の名前を呼んだ。
僕はその声に、その呼び方に、僕ら関係が10年という時間の隔たりなく、細く続いていることを悟った。
久しぶりに見る稲村さんは相変わらず細身で、ショートヘアがよく似合う小顔の女性だった。違いといえば、高校の制服が地元の食品メーカーの女性社員用制服に変わったことくらいのように思えた。
「家のことしないといけないし、一時間くらいしかいられませんから」
そう、稲村さんはあの時のまま、基本的に僕に対して敬語で話し始めた。
####
「すごいですね」
助手席の稲村さんはそう呟いた。
そのセリフを聞いた僕はドライブモードを「Sports」に切り替えた。そしてクラッチを一速落とし、コーナーへ突進した。
「ひゃっ」、稲村さんは思わず声を上げた。
しかし僕のロードスターはその鮮やかなステアリングで、カーブのスピードに一瞬重心を崩した稲村さんをまるで抱き起こすかのようにコーナーから脱出する。
「結婚して、普通車ものったことないし、ましてこんな車乗ったことなかったです」
そう嬉しそうに稲村さんは言う。
普通車に乗っていない。そのセリフから、僕は彼女の現在の家庭を想像した。この地方の町の、2LDKの5万円くらいのアパート。そこで旦那と二人で暮らしているのだろうか。アパート前の駐車場には2台、型落ちモデルの軽ワゴン車が停まっている。
僕は一つ、彼女の変化に気がついた。それは10年前よりよく喋るようになったことだ。
「てか、聞いてください。今日仕事でめっちゃはらたつことがあったんですよ。そのおばさんなんですけど、こっちが何度も何度もラベルは右上に貼るように説明しょおるのに、全く聞いとらんで、挙句の果てに納期遅れそうなの私のせいにして…」
僕はその話をふんふん、と聞いていた。稲村さんの話す話題は、昨日オンライン飲みした、会計事務所で働く友人や、また、海外駐在時代に付き合っていたエミレーツ航空のCAとも違い、何というか、堅実で、標準化された規格を生み出し続けなければならない、第二次産業の産みの苦しみのようなものを吐露していた。それはあまり面白い内容ではなかった
しかし内容はつまらないにせよ、その愚痴は稲村さんの風鈴のような声帯を震わせ、その熟れた唇をかすめ吐き出されている。
僕は今、僕の童貞を奪った女が、再び助手席に座っていることに頭に血が登っていた。何を話そうがどうでもよかった。
アドレナリンが体の隅々をまるで飢えた野犬のように駆け巡り、それはアクセルを踏む足から、2.0 L直列4気筒エンジンに伝わり、発火した。
僕は今走っている県道から横道へ入り、ダムの方へと続く橋を渡り始めた。
この行為に、稲村さんは「はぁ、」と一つ困ったようなため息をついた。
「ダムに行く」
それが何を意味するか、僕たちは今も覚えていた。それは僕がまだ十代で、お母さんの車で彼女とドライブしていた時も、今、自分の車で既婚の彼女とドライブしている時も変わっていなかった。
目指すは湖畔に続く旧道。その途中、交通量がまったくない場所に工事作業用の駐車場がある。
「結婚しているんですけど」
と言う彼女に、僕は、「知っているよ」と答えた。クールに答えたつもりだった。だが完全に頭に血が昇っていた。僕はその駐車場めがけて猛進した。
湖畔に続く旧道は、以前ダムに沈んだ集落と県道をつないでいた。この道は湖底の集落へと通じ水面を境に途切れている。わざわざここへ来るモノ以外、この道を通らない。
なので、カーセックスに非常に適した場所となっている。
僕はダムの湖畔に面した旧道の駐車場に車を停めた。そしておもむろに外へ出た。助手席側へまわり、扉を開けた。カーステレオには、JAZZの名盤、ビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビーがかかっている。
「踊りましょう」
僕は彼女の手を引く。
「ワルツは踊れない」
そう言いながらも、彼女は僕の胸に抱かれながら、辿々しくステップを踏む。カーステレオから流れるワルツ・フォー・デビーと、時々回転数を上げるアイドリングのエンジン音が湖畔に響く。
高校時代、彼女は吹奏楽部だった。なので、基本的な音楽の素養がある。食品工場の制服を着た彼女は、僕の胸に抱かれ、ステップを踏みながら、徐々にリズムを合わせ始める。
僕の童貞を奪った、この食品工場の制服を来た女性があの時の少女に戻っていくようだった。そこで僕は彼女にキスをした。アイドリング中の車はまた回転数を上げ、エンジン音を響かせる。
僕は助手席側の扉を開け、彼女と倒れ込んだ。「本当に最低」、彼女はそう誰に対してか主語が曖昧な批難を述べていた。
「覚えている?」、僕は彼女に聞いた。「五分以内、○かせられるかどうかのゲーム」。
稲村さんは、また「はぁ」、と嘘くさいため息をついた。ただ、率先して僕のズボンをずらした。そして、なんの躊躇もなくそれを○わえた。なんだかんだ言って昔のままだ。僕はそう思った
ただ、彼女の技術力は以前と比べ物にならなかった。
彼女はまず唇を所定の位置に固定し、一瞬、間をおいた後、舌が作業にとりかかった。そして即座にツボを見つけ出した彼女は、その一点を念入りに○め始めた。
それはまるでオートメーション化が進む工場のプロセスのようだった。
センサーにより瞬時に測量され、有無を言う間もなく、洗浄機に通される。そんな高度に効率化、プロセス化された第二次産業的な○○○○オだった。
僕は完全に油断していた。これが、十年間の重み。結婚した後、何があったのか知らないが、これが僕と全く違う人生を十年間歩んだ重みなのか。
もうダメかもしれない。僕はたまらなくなり、彼女を離そうとした。フィニッシュモーションに入っていた彼女はまるで治具で固定された工作機械のように僕を捕まえていたが、辛うじて僕は離れることが出来た。
「久しぶりだし、ゆっくりやろうよ」
僕はそう言いながら、彼女をシートの足元から抱き起こし、倒した助手席に横たわらせた。
僕は稲村さんに馬乗りになり彼女を見下ろした。
彼女の、その姿が愛おしくてしかたなかった。はだけた食品工場の制服を着た稲村さんが今ここにいる。この10年間、何度も何度も、彼女とこうして再び会えることを夢想していた。
「いいの?」と僕が聞くと、稲村さんは「もうどうでもいいですよ」と、相変わらずそっけない口ぶりだが、熱が籠もった声色で答えた。
僕は作業着のような制服のスカートを脱がし、それを後部座席に投げ捨てた。
僕は彼女の具合を確かめると、その表層部はすでにナメクジが這ったような状態になっていた。
一体全体、内部はどうなっているのだろうか。僕は新発見に胸躍る考古学者のように我を忘れその中へと進んだ。あの素っ気なかった稲村さんが声を上げた。
しばらく僕がそこから出たり入ったりしている時だった。この穴蔵の内壁が急激に収縮したかと思うと、小刻み痙攣し始めたではないか。ついに隠された神殿が本当の姿を現し始めたのか。
とその時だった。この神殿の崩壊とともに僕の冒険は絶頂を迎えた。
僕は自身の一部を崩壊した神殿に残したまま、しばらく稲村さんに覆いかぶさり、息を整えた。
目を開け、のそりと起き上がり下を見ると、そこには地味で、なんの面白みのない食品工場の制服を着た女性がいた。その女性から以前感じた妖艶な魅力はもう無いように思えた。
油の匂いが染み込んだその紺色の上着を見ていると、僕はさっさと帰ってネットフリックスで韓国ドラマの続きが見たくなってきた。
「そう言えば、一時間くらいしかいられなんいだっけ?もう帰った方が良いんじゃない?」、そう僕はふと思い出したように門限について話す。
「もう少しだけならおれるけど、久しぶりだし、まだ話す?」。
珍しく稲村さんの方から僕を引き止める。しかし僕は咄嗟にこういった。
「ごめん、実は明日までに提出しないといけない報告書があるんだよね。リモートワークって言ってもなんだかんだ忙しいから」
そして、僕は服を着て、彼女の車が停まっているショッピングモールの駐車場を目指しアクセルを踏んだ。
最短ルートを選び、尚且ドライブモードは「スポーツ」ではなく「エコ」を選んだ。どうせ公道を法定速度で走るのだから、燃費が良いほうがいい。
「なんで彼女と会いたくてしかたなかったのだろう」。
軽自動車を運転し旦那のもとへ帰っていく、稲村さんの疲れた横顔を見ている時、僕はそう考えていた。
“私は今故郷に対してなんの未練も残らないが、あの美しい記憶が薄らぐことが何よりも悲しかった”
ふと昔、中学の教科書に出てきた、魯迅の『故郷』の一節が脳裏に浮かんだ。
あの小説も主人公が故郷の豆腐屋の元カノと再開して、賢者タイムの落差に啞然とする話だったか。
どんな話だったか思い出せないが、詰まるところ、わざわざ掘り起こさなくても良い思い出もある、という話だったように思う。
掘り起こしたところで、かつてのきらびやかな思い出はみんな芋や大根のようになっている可能性がある。
ただ、そんな今日の思い出も、10年後には僕を妖しく惑わしているのかもしれないが。
稲村さんの軽ワゴン車のテールランプはバイパスの向こうへと消えていった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
