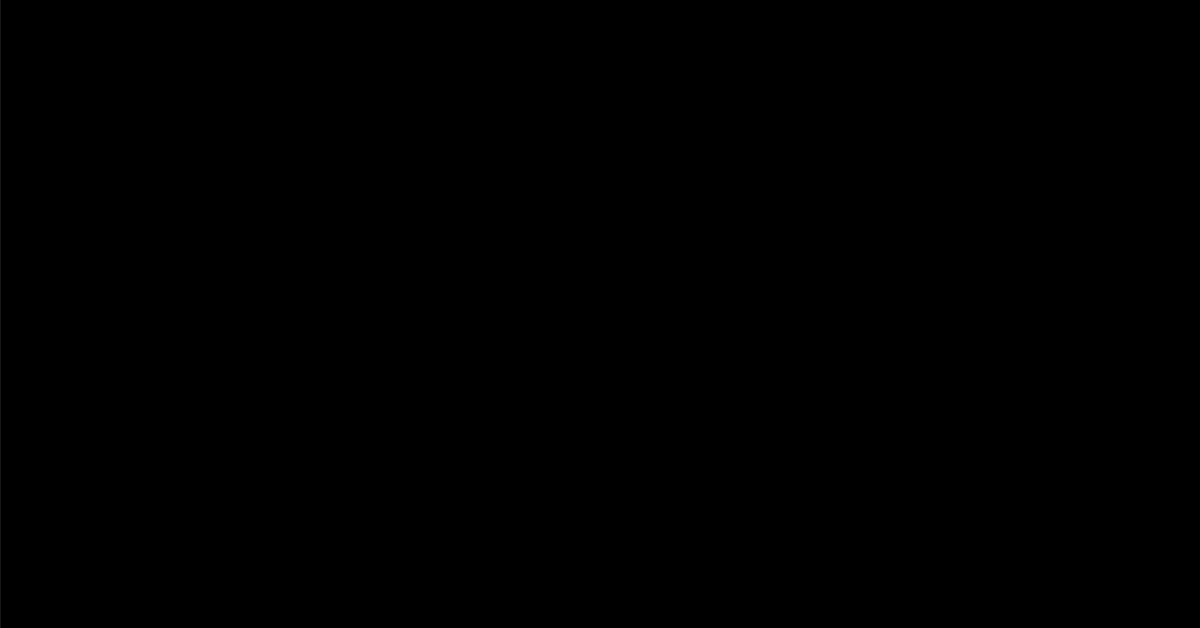
黒紙ズムの解説と白紙ズムとの関連性についての考察
黒紙ズムとは何か。わからん。多分白紙ズムから派生した、もしくは対抗する形で作られた概念だと思う。
終
制作・著作
━━━━━
ゆゆゆ
黒紙ズム
まあ、書き始めた以上はもう少し真面目に考えよう。
ひとまず、白紙ズムについてはこの記事を参照して欲しい。
読むのが面倒という人のために白紙ズムについて簡単に説明すると、何も描かれていない画像に意味を与える、無の表現である。
黒紙ズムの提唱者は恐らくんぷとら氏である。違ったらすみません。
んぷとら氏は『多様性が見えない』(あわでゃ氏作)という黒一色の作品に対し「黒紙ズムだなあ」と発言した。
加えて、自らのCMYKをテーマにした黒一色の作品についても「黒紙ズムにはこういうのもある」と言及している。
黒紙ズムだなあ https://t.co/dUzXr7GXbK
— んぷとら (@t0klr) February 15, 2024
黒紙ズムにはこういうのもある https://t.co/hwqEvkhnKf
— んぷとら (@t0klr) March 17, 2024
また、んぷとら氏は自らが発行しているフリーペーパー「週四現代」にも黒紙ズムについての批評を載せている。
現代4コマフリーペーパー
— んぷとら (@t0klr) February 14, 2024
2月号#現代4コマ #週四現代 pic.twitter.com/ivjgj2tNQY
言うまでもないことだが、『黒の正方形』が制作された時点では黒紙ズムどころか現代4コマも存在しない。
故に『黒の正方形』が黒紙ズム思想の下に制作された筈はないのだが、どうやらこれは黒紙ズムの到達点らしい。
最初から最後まで何を言っているのかよくわからない評論だが、それでもわかることはある。
黒の正方形はキャンパスの端から端まで黒で塗り潰されているわけではない。それが黒紙ズムの到達点たるということは、つまり黒一色でなくとも黒紙ズムは成立しうるのだろう。多分黒ければ何でもいいんだ。
黒紙ズム█ ←黒紙ズム
正直情報が足りなすぎて黒紙ズムについてわかることが少ない。もし今後黒紙ズム作品が増えたなら、それを糧に理解度を高めていきたい。
白紙ズムとの関連性について
先ほど私は白紙ズムについて「何も描かれていない画像に意味を与える、無の表現」と表現した。
ここで注目して欲しいのは「無」という部分である。
当たり前だが、「無=白」ではない。「何も描かれていない白紙」を無の代用品として使っているだけである。
そして無の代用品となるのは白だけではない。黒もまた、光が「無い」ときに感じる色であるため、無の代用品となりうる。
まとめるとこうなる。
「何も書かれていない」→白
— 桜桃 / 八止 (@oto_yusura) February 27, 2024
「何も見えていない」→黒
「何も情報が無い」→透明
どちらも無なのだから、黒紙ズムは実質的に白紙ズムと同じなように感じるかもしれない。しかしそれは違う。
白紙ズムには無という条件を飛び出し、「白」という色に着目した作品も多くある。
『カレーうどんを食べに行く』#白紙ズム pic.twitter.com/ZfDu81rPCa
— 白紙ズム (@Hakushism_) December 14, 2023
この作品の場合、黒紙を使っては何の意味もない。ただ準備万端でカレーうどんを食べに行く人である。白色だからこそこの作品は価値があるのである。
白紙ズムにしかできないことがあるのだから、当然黒紙ズムにしかできないこともある。
色々あるだろうが、私が真っ先に思いついたのは「闇」の表現である。

この無光状態の表現は黒紙ズムならではのものであろう。
また先ほど紹介した、んぷとら氏によるCMYKをテーマとした作品も黒紙ズムでなければ不可能なものである。白一色ではRGBの3コマである。
黒紙ズムにはこういうのもある https://t.co/hwqEvkhnKf
— んぷとら (@t0klr) March 17, 2024
白紙ズムの起源は『馬鹿には見えない4コマ』である。
もしここで私が4コマの範囲に背景の白色も含んでいれば、白紙ズムは黒紙ズムだったわけだ。
『馬鹿には見えない4コマ』
— 現代4コマ (@gendai4koma) July 23, 2023
作:桜桃( @oto_yusura )#現代4コマ pic.twitter.com/DXXuBg8Zta
まとめ
白紙ズムと黒紙ズム、白と黒で相反する特徴を持ちながらも、似た性質、そしてそれぞれにしかない強みを持っていることがわかった。
黒紙ズムが何なのかに結局はっきりとした結論は出なかったが、多分黒いものなのだろう。
では、さらば。

