
OT1年目から3年目にできる効率の良い勉強法
自己紹介
僕は11年目の作業療法士(OT)です。急性期から回復期、療養病棟、デイケア、訪問を持つ総合病院で6年間働いた後、大学病院に移り、急性期と外来リハビリを行いながら研究活動を始めました。
僕は1年目から3年目の時期を総合病院で過ごしました。この頃、僕には作業療法が何なのか分からなかったし、PTのお手伝いなんじゃないかと思うくらい、二番煎じ的なことをやっていたと思います。
そう。作業療法の専門性については説明できなかったですね。
11年目になった今、あの頃とは違い、作業療法の専門性についても理解し、説明ができるようになりました。そして、講演活動も依頼されるようになりました。
現在
最近、僕は #メディッコ というコメディカルサイトの運営に関わっています。
ここでは、1年目から3年目の方々を対象に、役立つサイト作りを考えています。
そこで、疑問がわきました。
今の1年目から3年目は、どんなことに興味があるんだろう?
というわけで、Twitterでつぶやいたのがこちら。
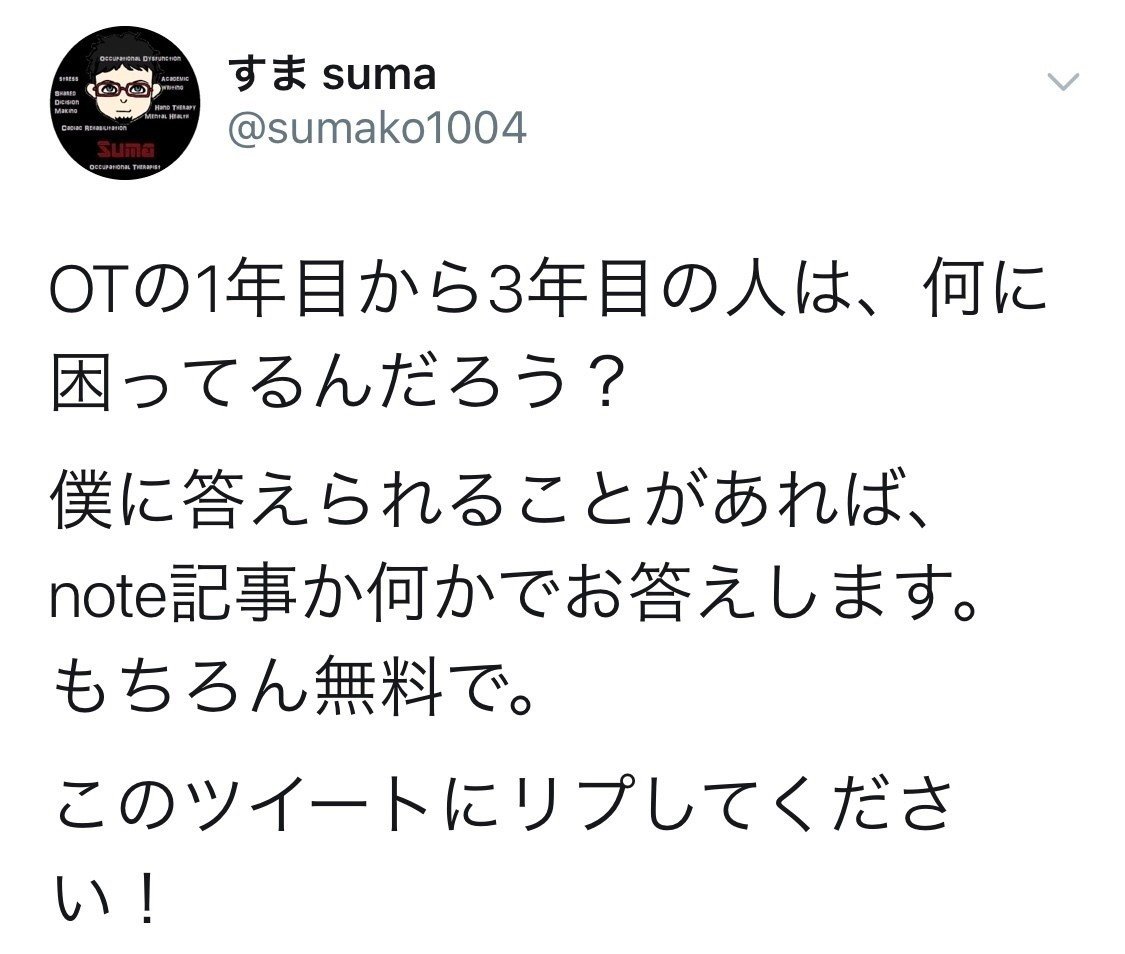
こんな感じで簡易募集をかけたんです。
そしたら、ちょこっと反応がありました!

わからないことがわからない!
こんな時期、確かにありましよね。
何したら、
どうしたら、
何から手をつけていいか、、、
本記事は、そんな悩みに答えていきたいと思います。
国家試験に合格したら
この時は、わからないことだらけですよね。
1年目にやるべきことは、まず慣れることです。
でも、それでも何かしなきゃいけないという不安に駆られる。
この時期に頭からついて離れないのは、「早く一人前にならなきゃ」という考えではないでしょうか。
一人前になるにはどうしたらいいの?
ここからは戦略の話です。
時間はかかりますが、闇雲にやっても自然と達成できるものなので、焦ったり、空回りしていなければ特に問題はないのです。
ただ、効率のよい道筋だけ押さえておきましょう。
一人前の定義は様々だと思いますが、簡単にまとめると以下の通りです。
①仕事の流れを覚える
②疾患ごとのリスク管理、評価、治療を理解する
③不安なこと、疑問を定期的に先輩に質問する
ここは基本的なところです。
①と②は、clientに提供するにあたり必須なので、担当が決まったらまず、疾患ごとの一般的なリハビリテーションについて調べ、自分の中にインストールしておきましょう。
③は分からないことがわからないと、できないんですが。。。
まずは①と②を行う上で、不明なことをきちんと整理していきましょう。
次のステップは?
仕事を覚え、なんとなくいくつかの疾患に対応できるようになってきたら、次のステップに移りましょう。もちろん、初めての疾患に出会えば、いつでも①、②に戻ってくださいね。
では、ICFを思い浮かべてください。
今のところ、②の疾患についての知識で対応できるのは、ICFでいうと健康状態の理解と、心身機能ぐらいです。
活動や参加、個人因子の枠は埋められていますか?なかなか、思いつかないのではないですか?
次のステップでは、少し幅を広げて、活動と参加、個人因子に焦点を当てた学習を進めていきましょう。
おそらく、①と②はできていても、「あれ、なんか違うな」「なんでうまくいかないんだろ」「これでいいのかな」という違和感が出てるだろうと思います。
その違和感の正体は個人差にあると思います。
つまり、同じ脳梗塞、右片麻痺、女性であっても、自宅の環境や生活、そして目標は異なるのです。
片麻痺だから麻痺が治ることが目標だ、なんて言っていたら、いつになってもclientの健康と幸福は促進されません。
作業療法は、薬とは違って疾患や症状に対応するのではなく、疾患や症状を持つ人の生活や経験に対応するのです。この点はスマートに理解しておきましょう。
④作業療法は、人の生活や経験に対応する
なぜ、初めからこれを勧めなかったのかと言うと、やり方を間違えれば事故につながる可能性があるからです。
疾患を知らずに見当違いなことをやってしまうと、心不全を引き起こしたり、転倒を誘発させてしまったり、おかしな運動パターンを学習してしまう可能性があります。
なので、疾患に対して必要なことは押さえておかないと、他職種との方針がずれてしまうので、注意が必要です。
それを踏まえてベターなやり方が、「疾患や障害を踏まえた上で、本人が望む生活への支援を行うこと」となります。
この意思決定プロセスは、EBM・EBPそのものです。
ただし、これだけですんなりと出来る人は多くありません。ここからの学び方が重要になるでしょう。
⑤日々の疑問を書き留め、調べる習慣をつける
初めのうちは、③がなかなかできません。
聞きたいことがあっても、聞いていいものかどうかで悩み、聞きそびれてしまうのです。
その場合は、まず書き留めておき、調べることに集中してみましょう。
調べるプロセスで理解が深まることもあれば、先輩に聞く際に「調べたんですが」というプロセスを付け加えることで聞きやすくなります。
いきなり聞くよりも、自分の悩みや疑問を明確にするプロセスとして⑤を使用してください。
一旦、この習慣が身につけば、主体的な学びのサイクルが回り始めます。
⑥良い実践の真似をする
始めから理論や手技等を学んでも、理解がなかなか進まず、泥沼にハマってしまいます。
だれでも・どこでも・すぐに始められる学習方法として、日々の臨床実践をしながら学習する方法があります。
注:これは患者さんを実験台にすることを意味していません
良い実践の真似をする、ということは、前提として良い実践を知っていることが必須です。
これは自分の知る限り、という制約が必ずあるわけですが、より多くの実践を知ることが、自身にとって最良の実践をアップデートすることに繋がります。
それは近くの同僚、先輩方の実践を見ることで得られるかもしれないし、近隣の施設で行われる実践の見学が必要かもしれません。
それらが困難な場合は、教科書や症例報告を参考にしても良いかもしれません。
真似をするポイントは、こちら⬇️
☑︎情報収集を真似する
☑︎評価項目、方法を真似する
☑︎目標設定を真似する
☑︎作業療法計画を真似する
いかがでしょうか?
これを真似しても、上手くいく保証はありません。なぜなら、同じ患者、同じ状況は二度とありませんし、その目的も異なるからです。
そして全ての実践には、「やってみないとわからない」という原理が含まれてます。
なので、いくら事前に良いと考えていても失敗することはありますし、意味がなさそうだと考えていても大成功を収めることもあるのです。
なので、いくつかの方法を試し、より効果のありそうな方法を選択していく、というプロセスは倫理的に否定されるものではありません。
逆に言えば、効果がないことが明らかであるのに、何も考えずに惰性で続けていくことは、倫理的に否定されるべき事案に挙げられます。
常に良いものを選択し、提供しようという意識を持って臨床実践に取り組むことが、自分の学びにとってもベターな選択だと思います。
⑦自身の限界を突破する
①から⑥まで達成していれば、きっと職場内では教える側になっている方もいると思います。
ただ、自分一人で学習していく方法には限界があります。
これまでは「わからないこと」は誰かに聞いたり、調べれば大概は分かることが多かったと思います。しかし、徐々に「だれもわからない」問題にぶつかる事が増えてきます。
⑤の習慣がついている人は、解決できていない問題がリストになっているかもしれないですね。最後に、その難渋問題を解決する方法をお伝えします。
難渋問題を解決する方法
☑︎自分の仮説を実践して検証
☑︎学会参加で似た疑問を持った発表を聞く
☑︎学会発表をして意見をもらう
☑︎研究を計画し、検証する
これはぜひ、チャレンジしてください。
上2つは、1年目からでも取り組むことができると思います。
1年目から3年目の方々は、ちょっとずつ試行錯誤しながら、①から⑥を実践してみてくださいね。
これが生涯学習の始まりです。
