
青いカメラはいかがでしょう【コニカ】
またしてもジャンクコーナーから一台、中古カメラをぴっくあっぷしてきました。
今回も、訳ありといえば訳ありな個体ですけど…
動作には問題なさそう
いつものカメラ屋さんにも、ジャンクコーナーはあります。
フィルムの現像をお願いしに行っただけでしたが
そこでなにかあたしに向かって訴えかけてくるものあり。
手にとると、一度以前に使ったことのあるコニカⅡ系列のカメラでしたが、なんか毛色が違うというか、ボディが控えめなんだけどブルー、前面にビス留めされてるパネルがアイボリー。
動作に問題あんの?と思い見ていく。
裏蓋が固着? と思うもそれは間違い、開け方からしてお作法がある(後述)。
開け方ググって内部をみる。
空シャッターを切る…あれ? 特になにも無さそうだけど。
これ2,200えんでいーの?
ジャンク扱いになる理由
ともかくレジに持ってって
「これ、オリジナルペイントですか?」と聞くと、前のオーナーか誰かが塗り替えたらしいとのこと。
お店のお兄さん曰く、たとえプロが塗り替えたものであっても、ブラックペイント以外は基本ジャンク扱いになるというのね。
なるほど、よくみると張り革も剥がしてあるし。
過去に本でみた、旧ソ連製のコピーライカであるゾルキーをプロにブラックペイントしたものも、査定不能だかなんだかと言われてたっけ。
依頼したのが、かの赤瀬川原平さんですからね…洒落がきついですね。
鎌トンカチの刻印にも赤く色差ししてあったはず。
氏の「中古カメラウィルス図鑑 新版」という本でみたのです。
みたい方は探してみてね。
その名は Konica ⅡB
前置きが長いよ!
そういうわけで、コニカⅡBというカメラをお買い上げしました。
帰宅していつものように写真撮りましたので
細部をみていきましょう。
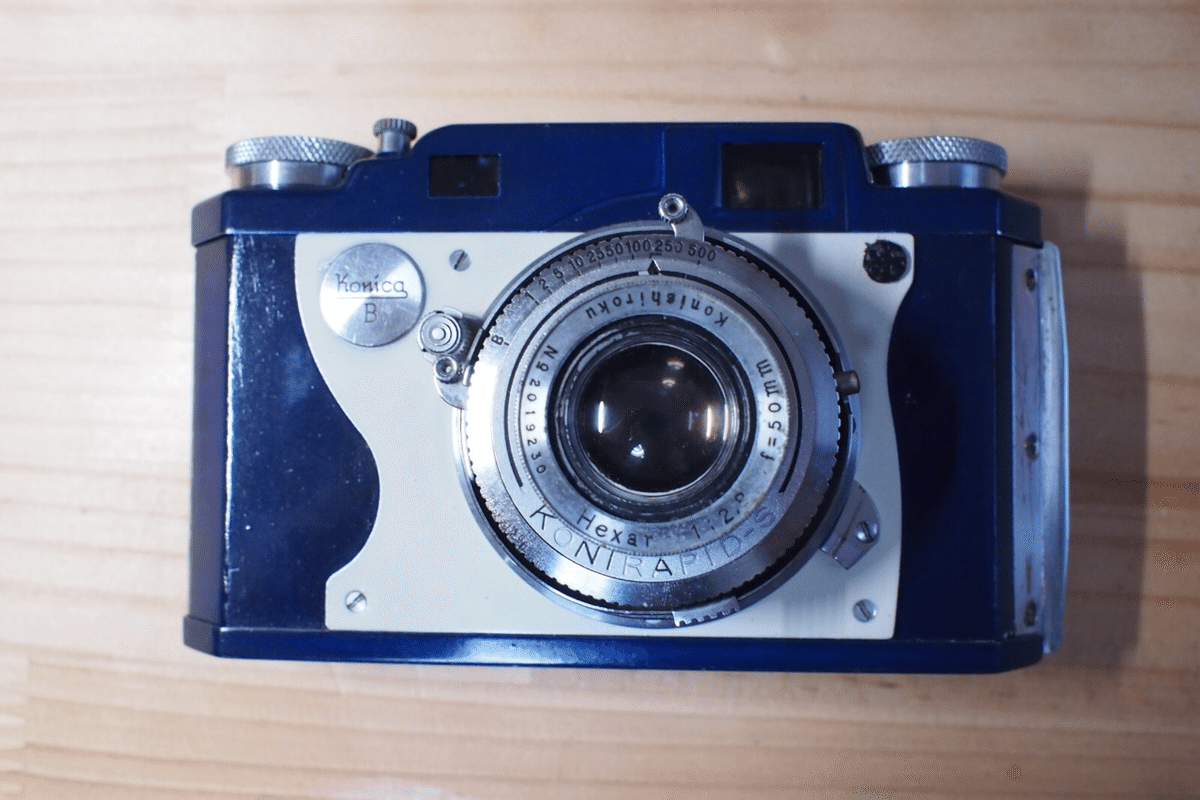
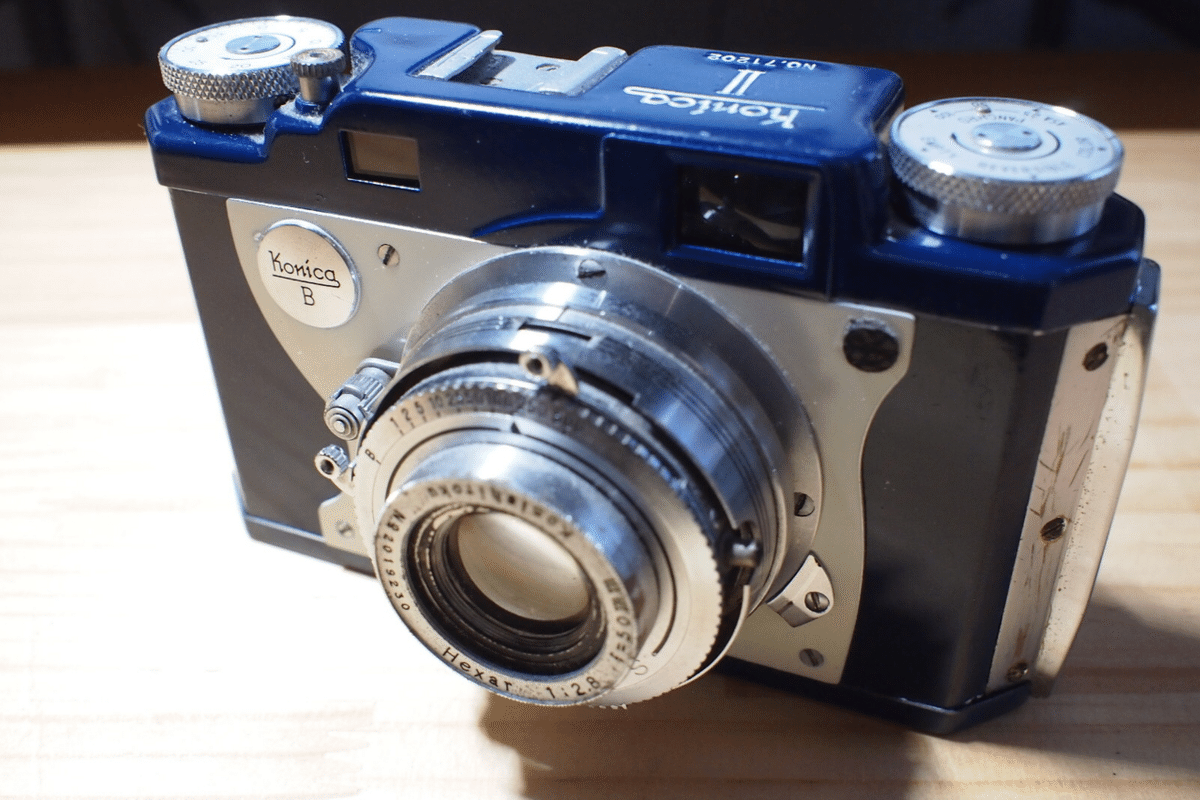

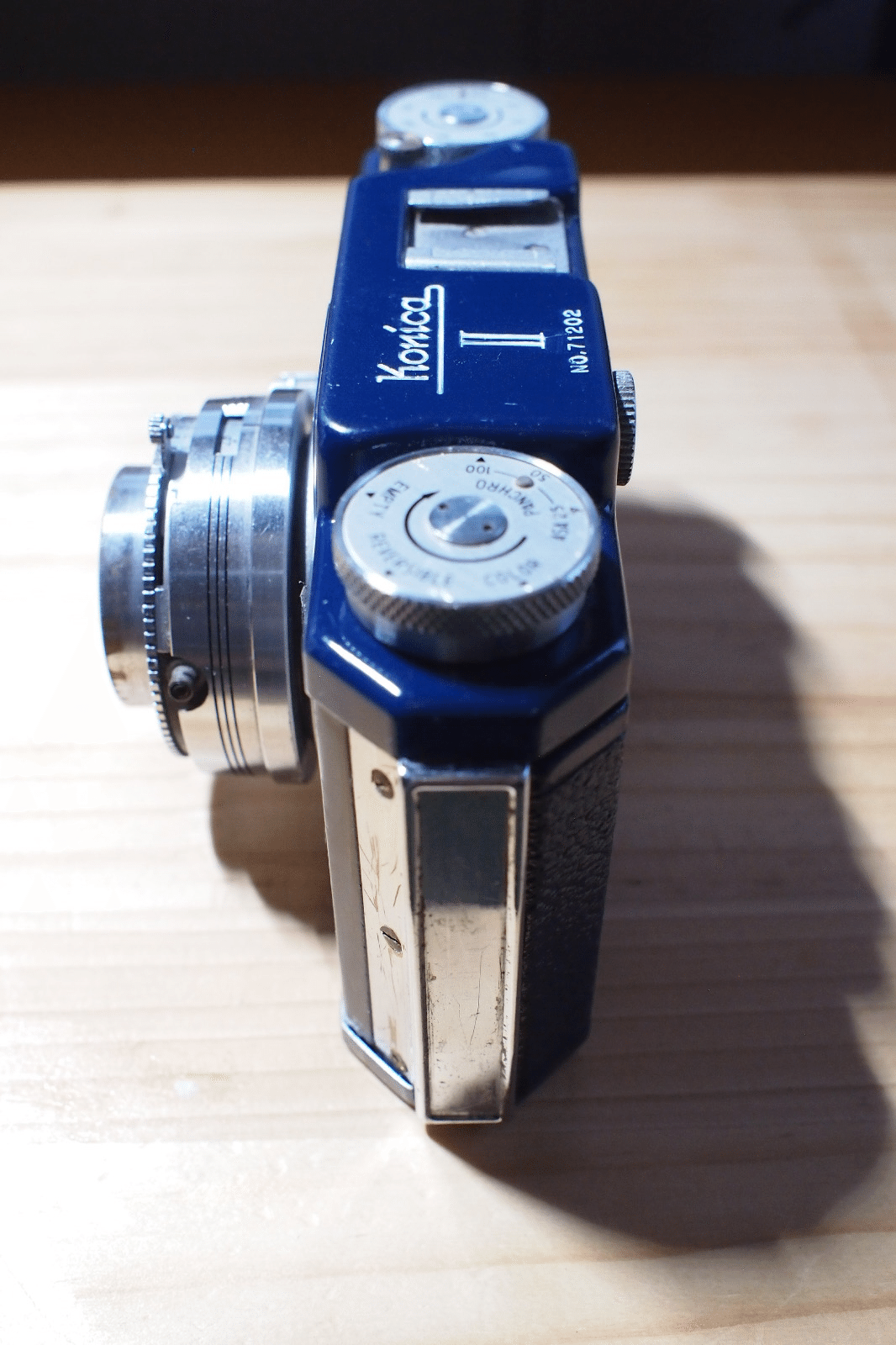
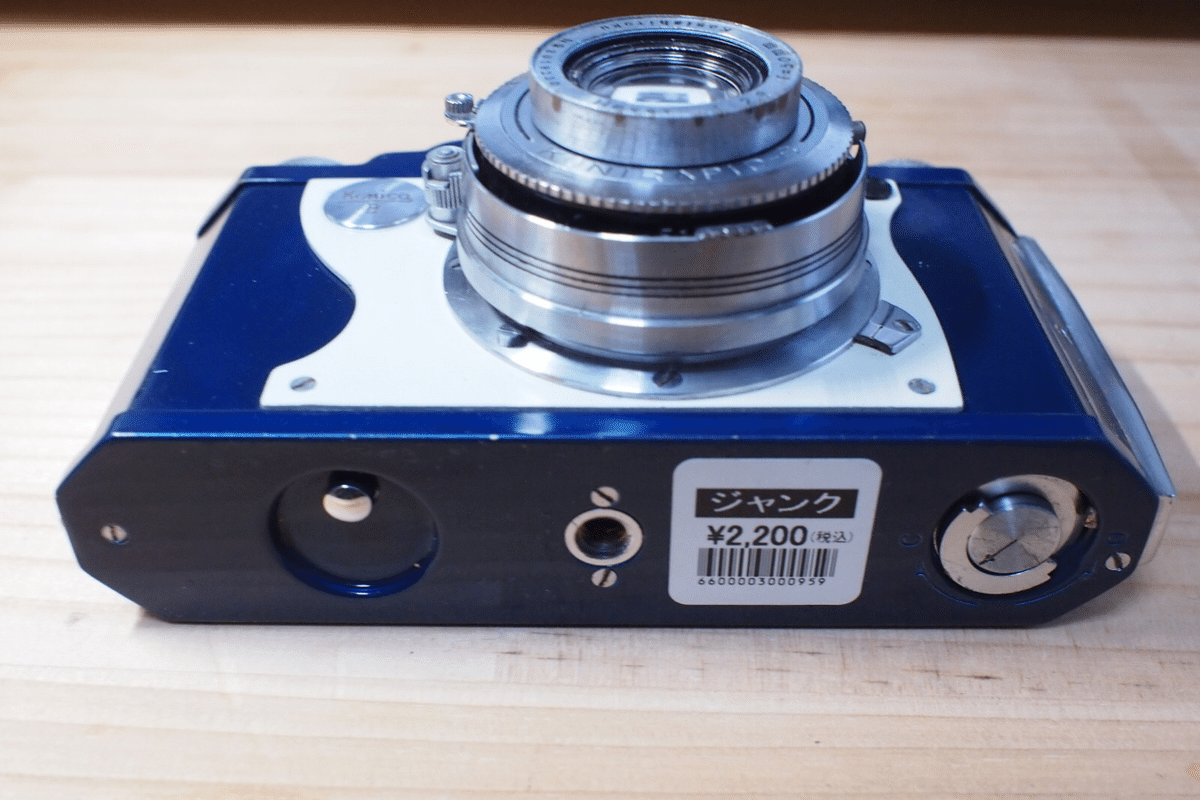
隅々に埃がついてますが、レンズ拭いてから軽く落としました。
そしてあとで思い出したのですが、これレンズは沈胴式でしたね。
と書いて、先人の記述をみると、沈胴式ではなくダブルヘイコイドというらしい。
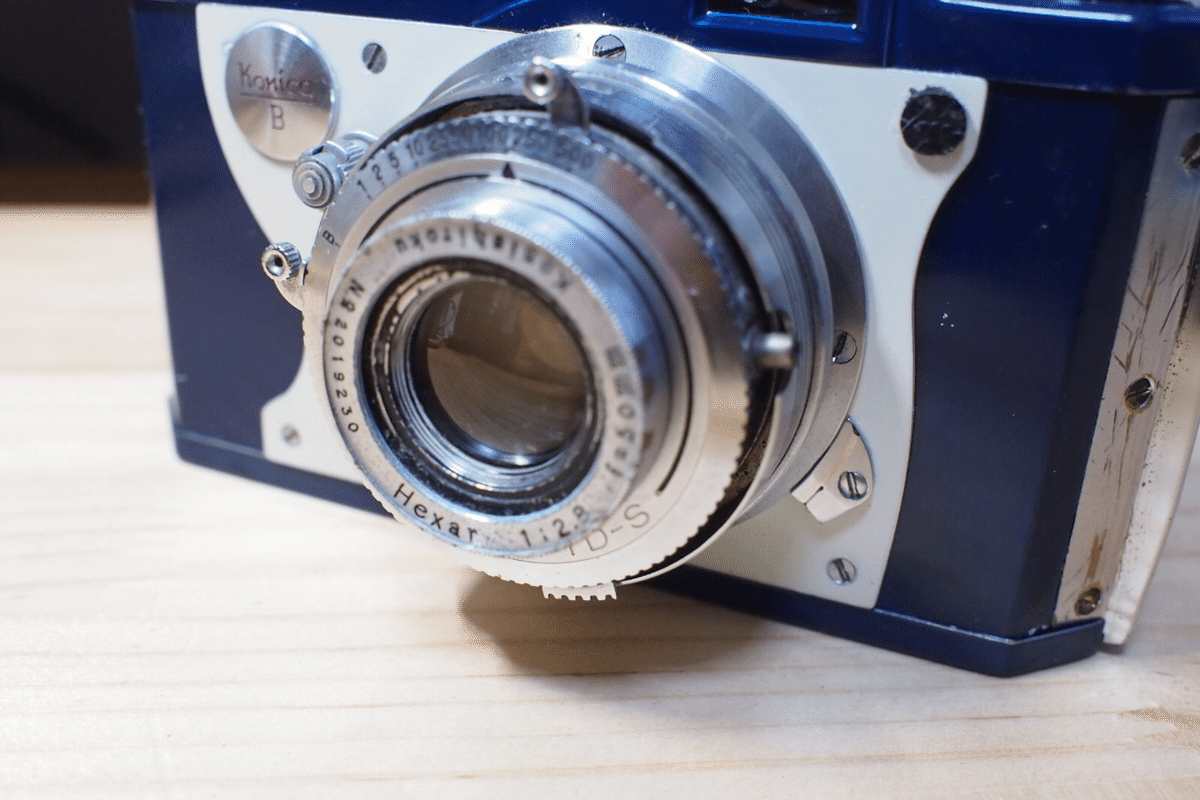





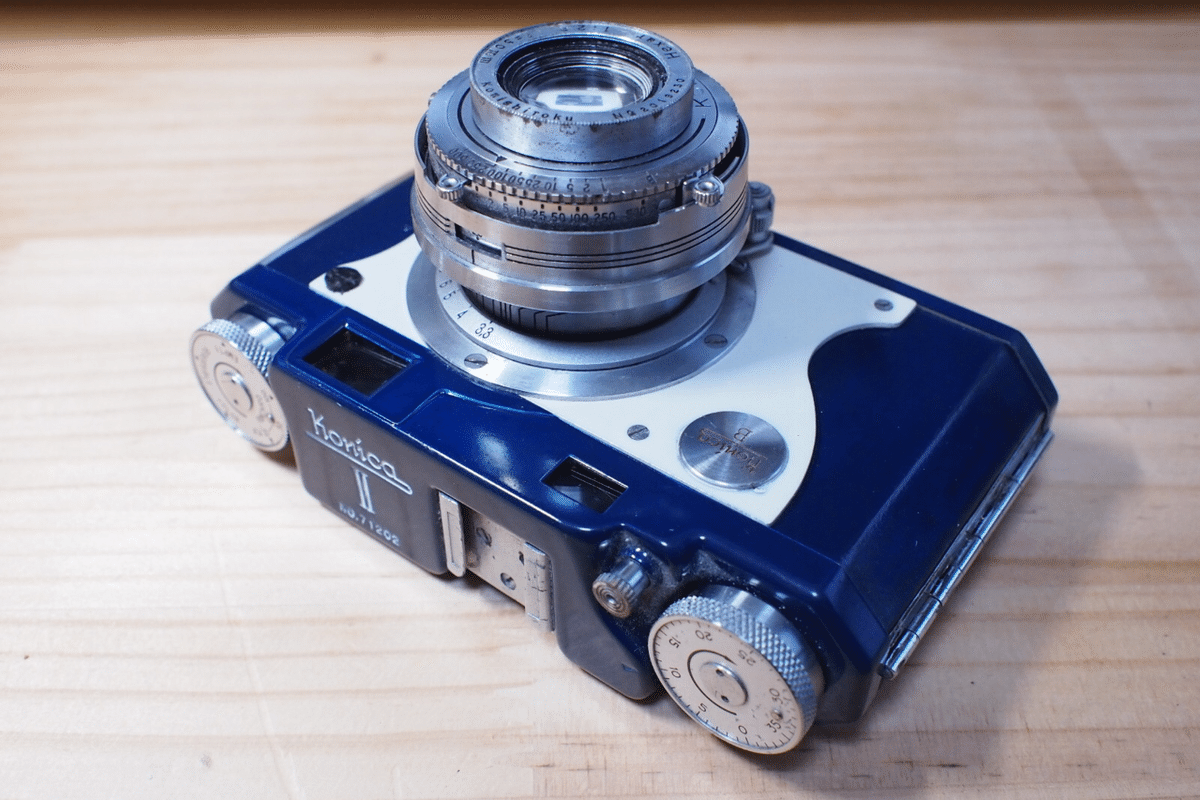

レンズはHexar50mm f2.8
Konishirokuの刻印もありますが、はい小西六時代のカメラです。
発売は昭和30年。
シャッターはB・1~1/500秒までありますね。
とはいえ、まだ数字の刻みが微妙にちがいますね。

絞りは開放2.8・4・5.6・8・11・16・22まで、こちらは現在と同じ倍数系列です。
左下のツマミで回します。
最低撮影距離は3.3フィート、1mですな。

シャッターチャージは、巻き上げと連動しない。
セルフコッキングではないということですか。
鏡筒にチャージレバーと、シャッターレリーズレバーなるものがあり
巻き上げノブ横の通常のレリーズボタンと、どちらでもシャッターは切れます。
二重写し防止機構は、ボタン側でないと動作しませんので
レリーズレバー側でシャッターを切れば、多重露光し放題?

下の写真、巻き戻しノブには、リマインダーというやつ。
フィルムが入ってないか、リバーサル、カラーネガ、モノクロのいずれかを表示できる。モノクロはASA25・50・100と感度までわかる。親切。




そして、裏蓋の開閉。
開閉ノブを引き起こし、矢印とO(オープンね)位置をあわせて…

ツマミで押してやると、開きます。

閉めたら必ず矢印をC、クローズ位置に戻しましょう。

この状態だと不用意に裏蓋が開いて感光する恐れがあります。



裏蓋のロック金具にも塗料が薄く回っているのが、素人仕事っぽい。

お楽しみは、始まったばかり
光学系は、素人目には、とくに問題ないようにしかみえません。
きれいきれいなほどクリアにはみえませんが、撮影には影響ないかな…そう願いたいです。
過去に紹介したマミヤ35メトラは、診てもらったらやはりクモリがあると言われましたし、そんな節穴なあたしの目ですから、撮ってみないとわからないので、早速試し撮りをしてみます。
フルマニュアルの機械式、露出計なしなので、また別に露出計で測ってやる必要がありますね。
ISO100のネガなら単純にサニーシックスティーンで「だいたいこんなもんだよね」も可能ですが、いま富士はあまり見かけないし、ロモグラフィーもいまや安価とはいいがたい。
手許にあるのがいつものColorplus200ですし。
2倍すればいいじゃん! と言わないでください。
まあシャッター速度の刻みがあれなので、アバウトなことに変わりはないか。
カラフルすぎるものは、商売としてはどうか
あたし個人としては、気に入ってます。
だって誰も持ってないよ、こんな古式カメラで青いのなんて。
だいぶ前、ペンタックスQ-S1だったかな、カラーオーダーできるようなのがあったよね。なんかすごい色数あったけど、うーむ40パターンですか…実際それで買った人いますか?
中古市場に出回ってるのもめったにみないし。
カラーオーダーといっても、なかなか突飛な組み合わせをする人はいないようですね。他の業界でもね。
それこそ文字通り色物扱いか。
お読みいただき有難うございました。
