
昔の医師国家試験を調べてみた 【後編】
1. はじめに
前編・中編にわたり、第1回医師国家試験をはじめとした昔の国家試験の問題を振り返ってきました。今回は取りこぼした面白い問題を少しと最初に出題されたCT読影問題などを見ていこうと思います。
2. 医師国家試験過去問題
早速見ていきましょう。
第3回医師国家試験
第18問
次の寄生虫卵の特徴を簡単に図解し、併せてその駆虫法について述べよ。
(1) 蛔虫 (2) 十二指腸虫 (3) 東洋毛様線虫 (4) 無鉤条虫
感染症の問題です。昔の国家試験では、今と比べて寄生虫に関して問われることが多いです。時代を感じる問題でした。
第4回医師国家試験
第24問
睡眠、昏睡(Coma)及び昏迷(Stupor)の差を問ふ。
精神科の問題です。結構な良問なのでは無いでしょうか?精神症候学の用語に関して深く触れることは医学生では少ないですが、精神状態を客観的に描写するには必要不可欠で、特に意識に関しては精神医学以外のシチュエーションでも重要になることが多いと思います。
第25回医師国家試験
次のI群の各項目毎にそれと最も関係の深いII群の中の一つを引用して、簡単に説明せよ。
( I群 )
1. Adams-Stokes 症候群 2. L.E.細胞 3. Froin症候群 4. Ellis-Damoiseau の線 5. Hunterの舌炎
( II群 )
1. 脊髄腫瘍 2. 湿性胸膜炎 3. 悪性貧血 4. 房室ブロック 5. 急性エリテマトーデス
この時期の国家試験は、しばしばこの様な医学用語の理解を聞く問題が出題されていました。
LE細胞は、本来の細胞核とは別に核成分を貪食している成熟多核好中球のことです。この貪食された核を染色して見られる構造体をLE体と呼んでいます。特にSLEに見られて、活動性が高いSLEのおおよそ9割で陽性になるとされています。
Froin症候群は、髄液がキサントクロミーを来し、凝固する場合を指します。特に脊髄腫瘍などがあって脊髄管腔が閉塞している場合にその下部の髄液に見られることがあります。
Ellis-Damoiseauの線というのは、胸腔に液体が貯留するときの濁音の境界の曲線のことを言います。液量が極端に多くないときは濁音の上界は水平ではなく曲線を描きます。
3. 初めのCT読影問題
ここでは、最初に出題されたCT画像の読影問題を紹介します。
CTが臨床で初めて利用されたのは1971年10月1日のことでAtkinson Morley Hospitalにて撮影されました。このときの患者はイギリス人の女性で前頭葉の腫瘍が疑われていたそうです。その後、日本では1975年に東京女子医科大学病院に初めて頭部X線CTが導入され、次第に広まっていくことになりました。
そして、医師国家試験でCTの読影が初めて出題されたのは、自分が調べた限りでは、1979年に行われた第67回医師国家試験になります。
67C25
51歳女性。3年前から高血圧があった。ある日の夕方路上で気分が悪くなり、右頭痛が出現した。家に帰り夕食の仕度中突然、左不全片麻痺が出現、嘔吐があり、横臥した。そのまま入院。血圧230/110 mmHg、意識はほぼ清明。発病5日目のコンピュータ断層撮影像(CTスキャン)(別冊 No. 16~17)を別に示す。
本例の病巣はどれか。
a. 脳室出血を伴う視床出血
b. 脳室出血を伴わない視床出血
c. 脳室出血を伴う被殻出血
d. 脳室出血を伴わない被殻出血
e. 上記のいずれでもない
以上が最初のCT読影問題です。これ以前は気脳撮影の読影が出題されていました。当然、いきなりCT画像しか出題されなくなるわけではありませんが、次第にその比率は高くなっていくことになります。
4. 昔の広告
昔の国家試験の問題を調べているとしばしば面白いものが目に入ります。特に興味深かったのが広告です。そこで、ここでは昔の医学雑誌に掲載されていた広告を紹介しようと思います。
ヒロポンの広告
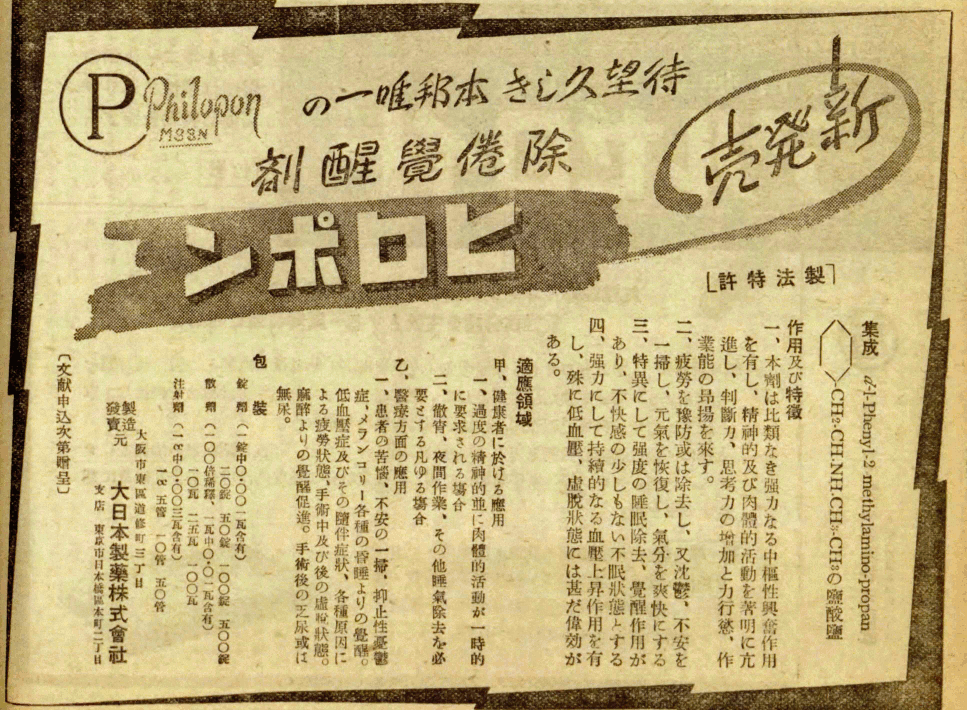

それぞれ、日本医事新報の1008号と1058号に掲載されています。
昭和26年に覚醒剤取締法が施行されるまでは一般に販売されており、この様に広告も掲載されていました。
ビオフェルミンの広告

同じく日本医事新報の1058号に掲載されています。
ヒロポンとは逆に、今でも広く知られているビオフェルミンの広告です。こんなに昔からあるとなると何だか感慨深いものがあります。
第1回レントゲン講習会

こちらは日本医事新報の12号に掲載されています。
大正10年と随分昔からレントゲンの講習会といった類のものが行われてきたのだとなると(以下略)
また、1週間毎日3時間の講習というと大分詳しく勉強していたのかもしれません。きっと最初はレントゲンの歴史から勉強していたのでしょう。
5. おわりに
内容は以上となります。
当初は一回限りの記事となる予定でしたが、調べているうちに随分と長くなってしまいました。しかし、色々と面白いものを見ることができ、個人的には大変満足しました。この記事に対して、「国家試験の勉強をした方がいいのではないか」「セルフ・ハンディキャッピングなのでは?」などと多々指摘があるとは思いますが、全くもって反論の欠片もありません。そろそろ観念して国家試験の勉強と向き合うことにします。
最後までご覧頂き誠にありがとうございました。
6. 後編の参考資料
日本医事新報社. 日本医事新報(12). 日本医事新報社, 1921.
日本医事新報社. 日本医事新報(1008). 日本医事新報社, 1942.
日本医事新報社. 日本医事新報(1058). 日本医事新報社, 1943.
日本医事新報社. 日本医事新報(2869). 日本医事新報社, 1979.
原義雄. 医師国家試験問題集 [第2]. 診断と治療社, 1966, 354p.
日本医学雑誌株式会社 編. レ・ザルプ : インターンのための問題集. 日本医学雑誌, 1949, 148p.
