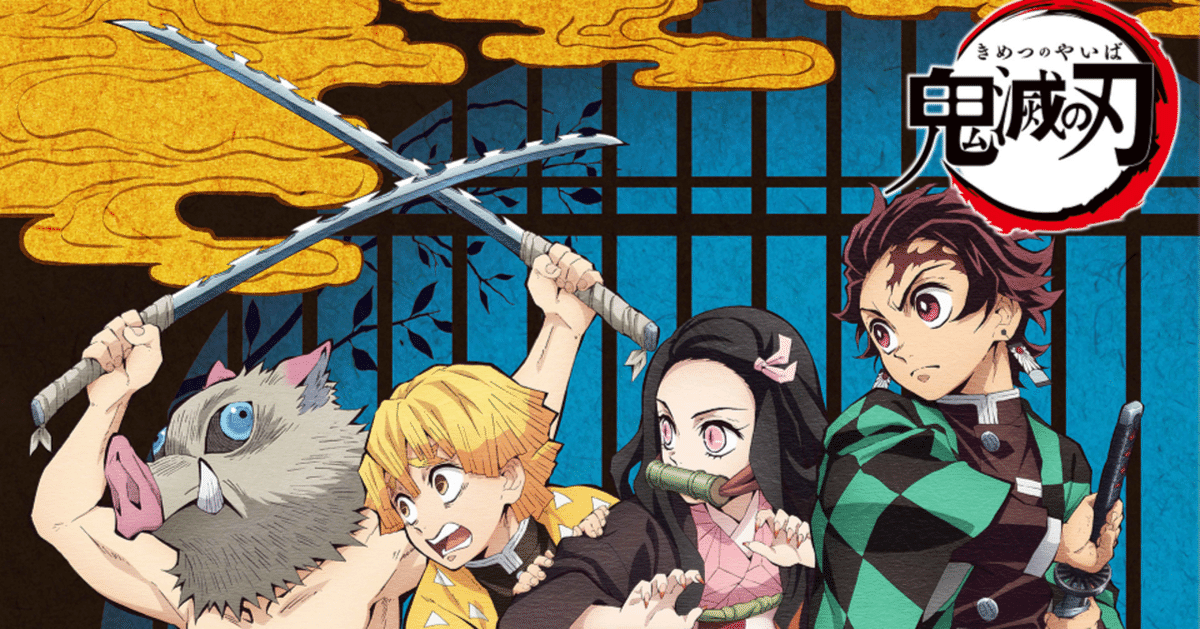
◆読書日記.《吾峠呼世晴のコミックス『鬼滅の刃』1~6巻》
<2023年2月13日>
先日、吾峠呼世晴の『鬼滅の刃』1~6巻を初めて読んだので簡単に今の所の所感を書いておこうと思う。
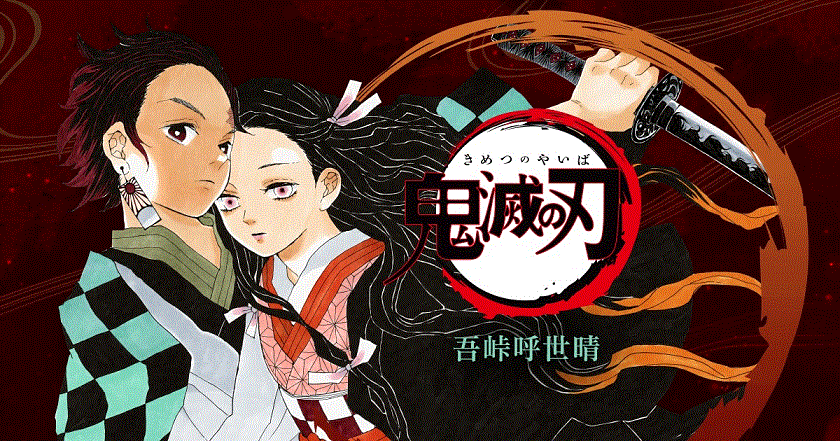
因みに言うとぼくはアニメの『鬼滅の刃』はスルーして見ていないし劇場版もテレビスペシャルも見ていない。雑誌のほうでも単行本のほうでも『鬼滅の刃』は読んでいなく、あらすじさえもほとんど知らないという、ほぼまっさらな状態で読む事ができた。という事でそんなぼくの所感を述べようと思う。
最初の絵柄の印象は「繊細」であった。
……というのも、非常に細い線を使っているというのがある(巻を追うごとに多少輪郭線が太くなっていっているようではあるが)。
それに、アミカケや細かいタッチを入れて、トーンやCGで処理している雰囲気はない。陰が少なくて画面全体が「白い」。キャラデザも優しげで、主人公の炭治郎の顔も中性的で、男性的な脂っぽさ、毛深さ、嫌らしさがない。
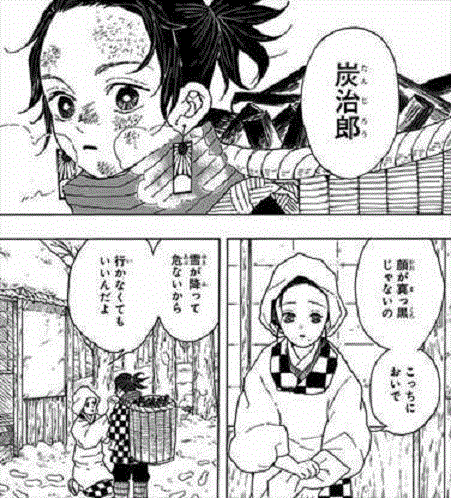
「こんな繊細な絵で血みどろの残酷絵巻をやるのか!?」と思ったほどだった。
芥見下々や藤本タツキの絵で残酷な展開が待っているのは分かるが、この絵柄はどうにもダーク・ファンタジーっぽさを感じない……というのが最初の印象であった。
アクション・シーンも慣れている風ではなかったので、「この人は元々バトル漫画を志向していた人じゃないんじゃないか?」と思ったが、意外に吾峠は『鬼滅の刃』と似たような大正ヴァンパイア・ハンターものの作品でデビューしているという。変わった人だ。
「アクション・シーンも慣れている風ではなかった」と思ったのは、特に1巻では不審に思えるほど煽情的な演出をせず、コマの形もあまり変化させずにほとんどが長方形を保って静的なコマ運びをしているからだった。分かり易く派手な見せ方をしていないのだ。
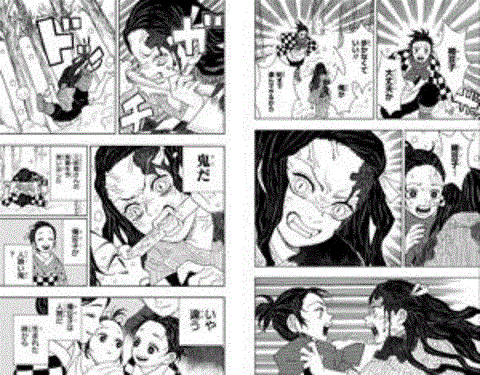
1ページ1コマというアップの仕方をせず(少年ジャンプでは「ここぞ!」という見せ場を作る時の常套手段だ)4話あたりになるまでは1ページに必ず2コマ以上は入れてきている。
1ページにコマを幾つも詰め込むと、スピード感は出ても「ここぞ」と言う時の迫力に欠けるきらいがある。
だから、1話目は構成は巧いのに、何故か話の緊迫度に比べて迫力不足の感があるのだ。
1話はかなり情報量を詰め込もうとしているが(ネームも多い)、窮屈さを感じさせないので、構成はスマートだと思う。
大ゴマを使い過ぎても、連載ページは毎週決まっているのだから、自分の語りたい分量まで物語を詰め込む事が出来ない。かといって、1ページにコマを詰め込み過ぎても、1コマが小さくなって迫力不足になるし、窮屈さも感じられてしまう。
だから、自分の思った分量のストーリーが1話分にまとまって、その上でコマの構成上もちゃんと緊迫感、スピード感、迫力が出るだけの大ゴマも用いられている……というバランス感覚がこういう週刊連載のマンガ家に必要な構成力となってくる。
1巻の頃の吾峠は、しっかりと自分の語りたい事を1話分に収める事ができているが、その分アクションで迫力を出す事までは出来ていないと思えた。そこら辺が「アクション・シーン慣れしていない」と思えた部分であった。
また「これ不用意にイマジナリーライン超えてない?」というコマも見受けられたので、連載当初はまださほど基礎を積んでおらずアクションシーンも不慣れな状態の新人だったのかもしれない。
◆◆◆
本作はヒット作『呪術廻戦』や『チェンソーマン』と同じく少年週刊ジャンプで連載されていたダーク・ファンタジーである。
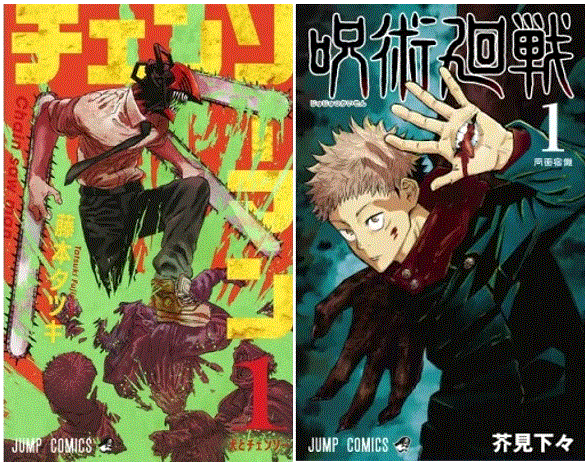
『チェンソーマン』の物語構造については以前も書いたが、なりゆきで「悪」を自らに取り込み、主人公が「人間と悪とのマージナルな存在」となる事で「力」を得て、他の「悪」と戦っていく……という『デビルマン』『寄生獣』とほぼ同じ構造になっている。そして、これは『呪術廻戦』も同じ構造になっている。
ぼくとしては『呪術廻戦』や『チェンソーマン』だけでなく『鬼滅の刃』も、『デビルマン』『寄生獣』等の流れを受け継ぐ日本マンガ界に流れる正統派ダーク・ヒーロー作品なのだろうと思っている。
「炭治郎は自らの中に『悪』を取り込んでいないのでは?」と思うかもしれないが、本作の場合は炭治郎ではなく、炭治郎と一心同体で、炭治郎が「命よりも大事」と言っている妹「禰豆子」が「悪」を取り込んでいるのである。
禰津子は「鬼の血」を自らに取り込む事で「鬼=人間の敵=この作品世界の敵性存在」となった。
本来禰豆子は鬼になった事で鬼殺隊に討たれる運命にあったが、二年以上に渡って人間を襲わず、炭治郎に協力して鬼と戦ってきた事情があるから特別に許されている「敵性存在」なのである。
だが、これは人間に敵対せず、鬼を討ち続けるという条件付きで、これが破られればすぐさま殺される運命にある。
昨今ヒットしているジャンプ系列のダーク・ファンタジーにおいて、このように主人公らが自らに取り込む「悪」は、ある意味「負い目」のようなものとして機能している。
『呪術廻戦』の主人公・虎杖悠二は、特級呪物「宿儺」を自らに取り込み「宿儺の器」と化した事で呪術師らに危険視されているが、「20本の宿儺の指を全て取り込む代わりに、それまで死刑は保留する」という条件で特別に許され、呪術高専に転入する事となった。
『チェンソーマン』の主人公のデンジは、心臓を「ポチタ」なる悪魔と融合させる事で悪魔の力を得ながらも人間の頭脳を保持している。が、これも大まかには人間に敵対しない事を条件に公安で悪魔狩りをする事を許されている存在で、その力が役に立たないとか人間に対して害悪になるとか判断されれば「悪魔」として処分される存在だ。
つまり、彼らが自らに取り込んだ「悪」は自分の力にもなるが、一歩間違えば自分を死に追いやる存在なのである。
自分の中の「悪」が悪さをすれば、すぐにそれは「悪=罪」に転換する。自分は人間ではない「罪人」となり「罰」が与えられる事となる。
彼らにとって生きる事とは、常に死と隣り合わせのサバイバル状態になっているのである。
自分の中には「悪」がいて、常に周囲から厳しい監視の目を向けられている。だから、自分が「悪」でない事を証明するために、常に人の役に立つ事をし続けなければならない。
彼らが戦う理由は、それによって凄いご褒美にありつけるからではなく、自らの安全を確保するためにあった。これは「サバイバル」なのだ。
――『呪術廻戦』『チェンソーマン』『鬼滅の刃』に共通する世界観と言うのは、そういうものなのである。
文字通り「善」と「悪」との定義が裏返るマージナルな存在であった『デビルマン』
「悪」は我々とまったく同じ顔をして我々の中に入り込んでいる……という恐怖を描いた『寄生獣』
それに対して、昨今流行っているジャンプ系ダーク・ファンタジーのヒーローは、自分が周囲から「敵ではないのか?悪ではないのか?」という疑いを持たれ、そうではない証として自分が役に立つ存在である事をアピールしなければ生きていけないという環境に身を落とした人物たちを描いてきた。
罪もない人間が、突如として理不尽な不幸にあい、必死になって生きていかねばならなくなった……そういう人物像が共通しているのである。
何故彼らは、そうも生きる事に負い目を感じているのだろう。「人の役に立たなくてはダメだ」というこの感覚は何なのだろうか。
……この感覚は、やはりぼくには藤本タツキの単行本『藤本タツキ短編集17-21』のあとがきの一節を思い浮かべてしまう。
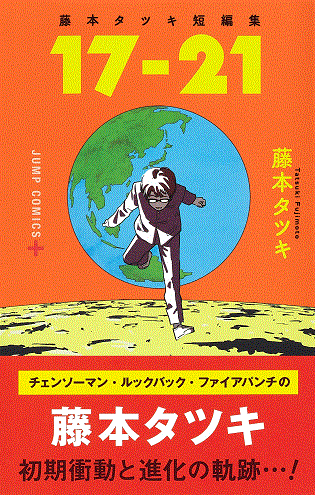
「17歳の時に僕は山形の美術大学に入学しました。東日本大震災が起こったすぐ後だったので、このまま絵を描いていていいのだろうかと皆思っていたはずです。絵を描いていても意味がない気がして、何か少しでも役に立ちたいと石巻に復興支援のボランティアに行きました。行くバスの中で僕と同じように考えている美大生や、体育大学の学生達がたくさんいました。石巻につき、住宅街一区画の側溝に詰まった土を除ける作業をしました。土を袋に入れ、トラックまで運ぶという作業を一日しましたが、側溝の土を全て取り除く事ができませんでした。30人くらいで一日中やったのに全然できなかった事に無力感を感じ、帰りのバスの中でも皆沈んでいました。作業中一緒に作業していた体育大学の学生が「俺達が来た意味なかったですね」と言っていました。
復興支援にはその後もう一度行きましたが、それきりもう行かなくなりました。油彩をやっていたのでお金がかかり、そのために漫画を描くしかなかったからです。17歳からずっとその無力感のようなものがつきまとっています。また、何度か悲しい事件がある度に、自分のやっている事が何の役にも立たない感覚が大きくなっていきました。」
藤本タツキと同い年であり、同じく東北育ち(岩手県出身)の芥見下々(彼も高校生の頃に東日本大震災を経験していたという事になる)、そして彼らとは3つ違いで芥見下々と同じ号で商業誌デビューを果たした吾峠呼世晴。
彼らが描くダーク・ファンタジーの主人公らの境遇に共通点が見られるのは、彼らがほぼ同世代であり、何かしら同じ時代を生きてきた世代に共通する感覚があるのではないか――ダーク・ファンタジーという物語形態が、彼らの暗い心性を炙り出しているのではないか。
昨今のジャンプ系ダーク・ファンタジーの流行の理由について、今の所ぼくはそういう風に検討をつけて見ているのである。
