
◆読書日記.《山鳥重『脳からみた心』》
※本稿は某SNSに2020年5月8~11日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
山鳥重『脳からみた心』読了。
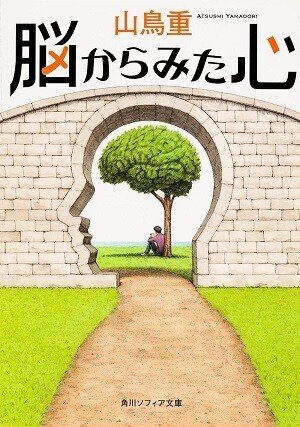
主に失語症の診察/研究を行っている神経内科医の著者が脳と心の関係について一般にもわかる形で書いた本。
著者はボストンで高次脳機能障害の臨床に従事して以来、失語症などの診察/研究を行っている神経内科医なのだそうだ。
本書はあの精神科医の中井久夫から「その立場(神経心理学)から脳と心の関係についての啓蒙的な本を書いてみないか」と勧められて書いたものだという。
本書の初版は1985年で、それを2013年に角川ソフィア文庫から文庫化したもの。
という事で本書は既に35年も昔の脳科学の解説書という事もあって、情報が古くなってはいやしないかと若干心配ではあったのだが、本書に書かれている脳科学的な知見は現在でも否定されているものは左程見られず、「古くなった」というよりかは「基礎知識」的なものになった情報だという印象があった。
本書の構成は1章「言語の世界」2章「知覚の世界」3章「記憶の世界」4章「心のかたち」という四章立てで構成され、章ごとにそれぞれ脳機能についての解説を具体的な症例研究から説明し、章終わりにそれぞれの章まとめを入れるというスマートな形式を取っている。
この構成方法も現在良く見られるビジネス書のように情報がすっきり整理されていて読み易かった。
◆◆◆
昔は現代のようにfMRIやCTスキャンを使った非侵襲型検査が出来なかった分、脳機能の働きについては脳機能障害患者の症状観察によって研究していくという方法が取られていたのだそうだ。
著者もこのような自分の患者の症例研究と、世界の脳障害の症例研究の文献研究との併用によって研究を進めているという事なのだが、ちょっと驚いたのがその方法がフロイトの精神分析の研究方法とちょっと似ていると言う事。
フロイトの研究方法もまた患者の診察にあたりながら症例研究によって「無意識」というブラックボックスの機能の地図を作っていくという手法だった。
本書の脳機能研究も、患者が脳梗塞や脳動脈瘤などによって脳組織が破壊された場合に、どのような機能障害や意識障害が起こるかという症状を見て、それが健常者の知覚や思考能力とどう違っているかの差分から脳機能というブラックボックスの地図を作る手法をとっている。
無意識も同じく脳機能の一種だから、両者の方法が似通っているのかもしれない。
例えば「脳障害のために失語症を患った患者は、言語能力は著しく落ちるが、絵を描く能力や歌ったり作曲したりする音楽的な能力は全く支障がなかった」という症例報告を踏まえると、言語能力と絵画的能力と音楽的能力というのはいずれも独立していて、その部分に損傷を受けても他に影響が及ばないと推測できる。
また、言語機能についても、単語は分かるが単語とそれが指し示す実際の物体イメージとが結びつかないという症例があり、またその逆の症例も存在する。
その他にも言語機能は、低次機能の能力低下が即、高次機能に影響を与えないし、高次機能の低下が即、低次機能に影響を与えるというわけでもないのだそうだ。
つまり、脳機能というのは全体が繋がっていて一つの機能が損傷するとガラガラと全体が崩壊してしまうといったものではなく、それぞれの機能がモジュール状に独立しており、それぞれの機能の処理結果をそれぞれのモジュール間のやり取りによって「統合」し、それによって最終的に我々の脳内の意識が出来上がっている……と言う風になっているらしい。
こういった脳機能はフッサールが超越論的現象学で提示した「ノエシス-ノエマ構造」と似たような事が行われているらしいと分かる。
脳科学の茂木健一郎氏も、脳の志向性が現象学の提示した志向性の概念と一致している事を知って「昔からの知見は馬鹿にならないな」などと述べていた。
こういった脳の基本的知覚機能や意識の成立の仕方や運動感覚(現象学的には「キネステーゼ意識」)や記憶システムといった諸々については、ぼくが予想していた通り、フッサールの超越論的現象学の理屈との類似性が見られた。
◆◆◆
超越論的現象学の理論との類似性は他にも見られる。
例えば、著者が診た患者の中に「Cさん」という失語症の患者がいたという。
Cさんは普通の会話や書きものはそれほど不自由はないそうなのだが「物の呼称や理解に強い困難を示した」のだという。
医者が「机がどれか指さして下さい?」と言うとCさんは「机?机?これが机ですか?」と疑問形で机を指さすのだそうだ。
何故問い返すのか? Cさんにはそれが机であるか確信が持てないのである。
Cさんによると「私の使い慣れてきた机とまるで違うので自信がない」という。
我々はどんなメーカーが作った机でも初めて見るタイプのデザインの机でも、見れば即座にそれが「机だ」と理解できる。だが、Cさんはそれができないのだ。
これは我々が様々な事物を見て学習していく事でその「本質」を理解しているからこそ出来ることで、例えば松を見ても杉を見ても欅を見ても「あ、木だ」と理解できるのは「木の本質」を我々が理解しているからだと言えるだろう。
この能力を神経学者のゴールドスタインは「範疇的態度」と呼んでいる。
著者はこれをあくまで「能力」であるから「範疇化機能」と読んだほうが適切かもしれないと言っているが、この「範疇化機能」の言っている事と言うのは、超越論的現象学の始祖エトムント・フッサールの現象学の重要概念の内のひとつ「本質観取」と似通った内容だと思う。
フッサールもフロイトも現代では「科学的ではない、過去の遺物」とする意見のほうが多いように思われるが、脳科学的にこれら過去の偉大な思想家の考え方の一端が肯定されるというのは、なかなか感動するものがある。
その他、著者は人間の言語機能についてソシュールの構造言語学を踏まえて言及している。
失語症を患った患者には「靴」という単語は知っているものの、実際の靴を見せて「これは何ですか?」と聞くと全く答えられないという人がいるのだという。
この患者は、単語の「記号としての聴覚イメージ」は理解しているし記憶しているが、それが対象物の概念イメージと繋がっていないのだそうだ。
つまり、人の脳機能のうち言語機能というのは、ソシュールが言うようなシニフィアン(記号表現)~シニフィエ(記号内容)の構造を持っているのである。
意外な事に脳科学というものは、そちら方面から相手にされていない現象学や精神分析、言語学などの知見とリンクしている点があるようなのだ。
これは近ごろ西洋思想の勉強を強化しているぼくにとっては、なかなか興味深い情報であった。
◆◆◆
脳科学的な知見として昔からよく言われている事に、「我々は我々がいま意識の中に表象されているそのままのイメージとしてものを見ているのではなく、あくまで<脳が編集した表象>を見ているのだ」というのがあるが、これも本書では非常に具体的な事例を挙げて説明していて分かり易い。
本書に挙げられているような脳障害の症例を見ていて分かるのは、いかに我々は意識せずに様々な知覚情報を高度に処理しているのか、という事だろう。(因みに、ここで「意識せずに」と言ったのは勿論、フロイト的な「無意識」のプロセスというのは、脳機能的にも存在しているという事を意味している)
ぼくが特に興味をひかれたのは、脳の「見当識」という機能であった。
医学では自分を場所や時間の中に位置づける能力、即ち「私が誰であって、いまどこにいて、『いま』というのは何年何月何日なのか」という事を理解しておく能力の事を「見当識」と言い、そのそれぞれを自己見当識、場所見当識、時間見当識と呼ぶのだそうだ。
この見当識は普段、我々は何の意識もせずに使っている能力なのだが、この能力が損なわれると実にホラー映画的のような認識の混乱状態が発生するようなのである。
例えば「場所見当識」が時折発症する発作によって損なわれると、町中で突然自分の居場所が分からなくなり、自分の家の方向も分からなくなるのだという。
この時、その他の認知能力には問題がないそうだから、例えばバス停の駅名や商店街の店々の看板や行きかう人達が知り合いかどうか等も問題なく分かって、全て自分の馴染みの町のもののはずだと分かっているのに、どの方向へ行けば自分の家があるのかという事については分からなくて彷徨ってしまう……という状況がになってしまう。
このような症例が分かっているからこそ、現在の脳科学では「見当識」という脳機能の独立したモジュールが存在していて、その部分のみ障害が発生しているとわかるようになっているのだ。
このような脳の機能が分からなければ、我々は普段無意識にどのような知覚をどのように認識しており、それを脳がどう編集しているか分からないのである。
そういった脳の意識機能を人間の「外側」から研究したのが脳科学だとすれば、それを「意識の内側」から研究したのが現象学だと言えるのかもしれない。
その二方向からのアプローチがだいたい似たような結論になるというのは、どこか自分には、両方から掘り進めたトンネルが繋がったかのような感動があった。
しかし、分かり易いが故にわざわざ過去読んだ現象学関連の本を引っ張りだして復習しながら読み込んでしまったので、読了するのに随分と時間がかかってしまった。
