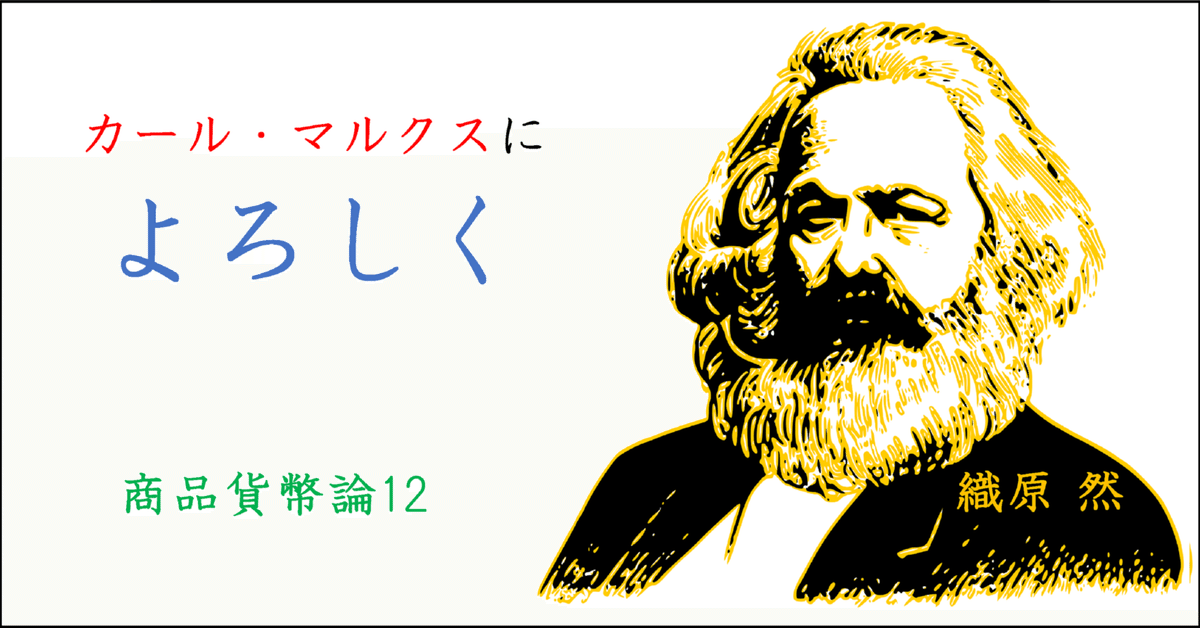
商品貨幣論12 ―マルクスの啓蒙理想思想―
前回述べたように、このイギリスに端を発した産業革命の強烈な貧富の格差はマルクスにこれまでにない経済学の境地を見出させました。
私は「レッセフェール」という用語をこれまで用いてきましたが、実はこれには他にもいくつかの呼び名があります。
イギリス人、アダム・スミスによって述べられた「(神の)見えざる手」。
フランス人、ジャン=バディスト・セイにより論じられた「セイの法則」。
共に「富の不均衡の是正のためには、市場に介入すべきではない」とするフランソワ・ケネーに端を発する「レッセフェール」を解説する経済学の用語です。
マルクスは、ケネーを評価し、レッセフェールを受け継ぎつつも、その「レッセフェール」に逆らった第一人者といってよいでしょう。
「神の手を振り払い、私たちの手で富を得よう」
というのが、マルクス経済学の真骨頂です。
マルクスはイギリスに渡った後、産業革命により引き起こされた貧富の格差に愕然とし、これがいずれヨーロッパ中に伝播してゆくことを予見し、既存の古典派経済学の「レッセフェール」の無力さを痛感したわけです。
そして、
貧困層を救うために「自らの富を采配をする『見える手』を得よう」
としたわけです。
この格差是正の思想こそがマルクス経済学の目的であり
「共産主義」と呼ばれる経済思想
となったわけです。
かつて、聖職者や王侯貴族が独占した富は、フランス革命後ヨーロッパ各地で起こった身分崩壊の気運(ナポレオン戦争等)により、ヨーロッパ中で王侯貴族が没落し、結果、特権階級の専有物ではなくなりました。
では、
その富はその後、貧困層たちにトリクルダウンしてきたでしょうか?
そんなことはなく、実際には商人たちが
「貨幣」という小賢しいツール
を使って、貧困層を労働者として雇い、そこから富を生産させ、それを奪うことで
「資本家」という王侯貴族の代わりの支配者階級となりました。
しかも、ケネーに端を発する古典派経済学はその「資本家の誕生」に対しては無力でした。「富の代替物」であり本当の富ではない「貨幣」の使い道が「小麦の生産のため」であるならば、
資本家が貨幣を蓄財するのは貧困層のため、ということになります。
それを阻む理由は古典派経済学にはありませんでした。
結果、貨幣の格差を通じて、富の格差は寧ろ拡大したのです。
「第二の貴族」である「資本家」の支配は、王侯貴族時代の不合理な伝統的倫理観を捨て去り、寧ろ苛烈さを増した貧富の差は古典派経済学により肯定され、貧困層を苦しめました。
古典派経済学は経済学であるにもかかわらず「経世済民としての学問」=「民を救う学問」ではなくなってしまっていたのです。
そこに、燦然と現れたのが
経世済民としての学問
「マルクス経済学」
だったわけです。
多くの人が、それに希望と見出し、賛同し、その結果、我々を苦しめる資本家を打倒するための学問は、それこそ経済学の本流として、大いなる正当性をもって支持されたことだろうと思われます。
正直申し上げて、私が当時の貧困層だったとして、マルクス経済学に触れた場合、マルキシストにならない自信は全くありません。
私にとってマルクス経済学とは、それほどまでの正当性を帯びているように見える経済学だということです。
では、ここで私は敢えて問います。
