
経理未経験者が2ヶ月半で簿記3級・2級に合格した体験談【前編】
最近めっきりnoteを更新してなかったのには理由があって、この間ずっと日商簿記3級・2級の勉強をしてました。
今回は、そもそも何で簿記の勉強を始めたのか、この勉強期間中の過ごし方、勉強方法、受験当日の話、などをまとめていきたいと思います!
1.なぜ簿記の勉強を始めたのか?
簿記の勉強を始めたのは本当に思いつきでした。
こちらの記事で詳しく書いていますが、自分は会社を辞めた後はずっと休職していて傷病手当金を受給して過ごしていたんですよ。
でも傷病手当金は最大1年半(18ヶ月)までしか受給できないんですよね。
自分にとって、この期間の満了日が今年の1月末まで、でした。
だから去年の11月辺りから傷病手当金の受給期間が終了した後のことについて考えてました。
「とりあえず傷病手当金の受給期間が終わったら、ハローワークに失業保険の受給延長手続きを解除しにいって3ヶ月間の失業保険は受給する。でもその後は?就職?それともフリーター?ネットなどで個人事業?
んーーー、どうしよう、、、」
↑その時の脳内はずっとこんな感じ。
その時にまず思いついたのが「職業訓練学校」です。
確か、失業保険の残日数が1/3以上残っている状態で職業訓練学校に通えば自分の失業保険の受給日数が90日の場合でも、職業訓練学校に通ってる期間は失業保険保険受給期間が延長される、という話を聞いていたので、一旦この方向性で考えることにしました。
つまりどういうことかというと、自分の失業保険受給日数が90日(3ヶ月)だったとすると、、、
90日(3ヶ月)の1/3にあたる30日(1ヶ月)以上受給日数が残っている状態で、6ヶ月の職業訓練コースに申し込み晴れて受講資格が得られれば、本来なら90日(3ヶ月)しか失業保険は貰えなかったはずなのに、失業保険保険満了後も訓練学校に通っている間は同じ金額の失業保険を受給することができるんですよね。
上記の例の場合だと最大5ヶ月分(150日)失業保険の受給期間を伸ばすことができるわけです。
訓練学校のコースによっては1年とか2年間行うので、そういうものを選べばその分延長期間は伸びます。
ただここまでの話はあくまでも理論上の話ですけどね。
厳密には、失業保険の残日数が1/3を迎えるタイミングにどういう職業訓練学校のコースにがあるのか、にも左右される話です。
それに「希望した職業訓練学校のコースが見つかり、ここに通いたい!」と思っても、まずはハローワークに行って申し込みの手続きを済ませる必要があります。(これに大体半日かかる)
そこですぐに申し込みができるのかというとそうでもなく、その後は訓練学校への見学(これは任意らしいけど行ったほうが合格しやすいらしいとのこと)に行ったり、訓練学校側に提出する履歴書的な書類を書かされたり、その後に訓練学校側の行う選考会(面接や試験など)に合格しないと、そもそも職業訓練学校に通うことはできません。
結構時間掛かるしめんどくさいんですよね。
まぁそれはそれでしょうがないとして、まずは自分の住んでる都道府県で行っている職業訓練コースにはどんなものがあるのか調べてみることにしました。
保育士系、介護士系、プログラミング系、ウェブデザイナー系、結構色々ありました。
まぁ自分としては、どうせ通うなら何かしら役に立つ資格も取りたいよなぁ〜と思ったので、実際に就職などに役に立ちそう度合いで序列を考えた結果、電気工事士系の資格が取れるコースと日商簿記の資格が取れるコースに絞りました。
どちらにするか悩みましたが、
(どうせ就職するならオフィスワーク系のほうがいいし、だったら簿記のほうがいいかも)
という結論に至り、簿記の資格が取れそうなコースに絞って職業訓練コースをさらにリサーチしてました。
そして自分にとっては開校時期も重要です。
失業保険を延長させる、という意味においてはタイミングが合う&日商簿記2級まで目指せる訓練コースである必要があります。
そしたらこの2つの条件に該当する訓練コースが見つかりました。
そこからの行動は早かったですね。
(よし、ここにしよう)と決意してすぐに職業訓練にも一度見学に行ってきました。
授業風景とか実際に見させていただいたら、 結構ちゃんとしてそうだったのでここに通う決意が固まりました。
ここまでが日商簿記を勉強しようと思った経緯です。
つまり、日商簿記の資格が欲しかったというよりも失業保険の受給日数を増やしたかった、といった方が正しいかもしれないですね。
そして、ここまで職業訓練学校に通うやらなんやら書いてきましたが、結局職業訓練学校に通うことは辞めました。
「何でやねん!!」
って感じですけど、これには理由があって簡潔にいうと、「就職困難者」というものに区分されて、失業保険の受給日数が300日になったからです。
当初考えていたようなわざわざ訓練学校に通って失業保険の給付日数を増やす、という目的を達成する必要性がなくなってしまったんですよね。
だから結果的に職業訓練には通うことは辞めましたが、これがきっかけで簿記の勉強を始めることになりました。
経理未経験者が日商簿記3級に挑戦してみた結果
ここからは実際に勉強したときの体験談です。
ネットで注文した日商簿記3級のテキストと問題集が去年の12/5に届いたので、そこから勉強を開始しました。
買ったテキストと問題集はTAC出版の「みんなが欲しかったシリーズ」です。
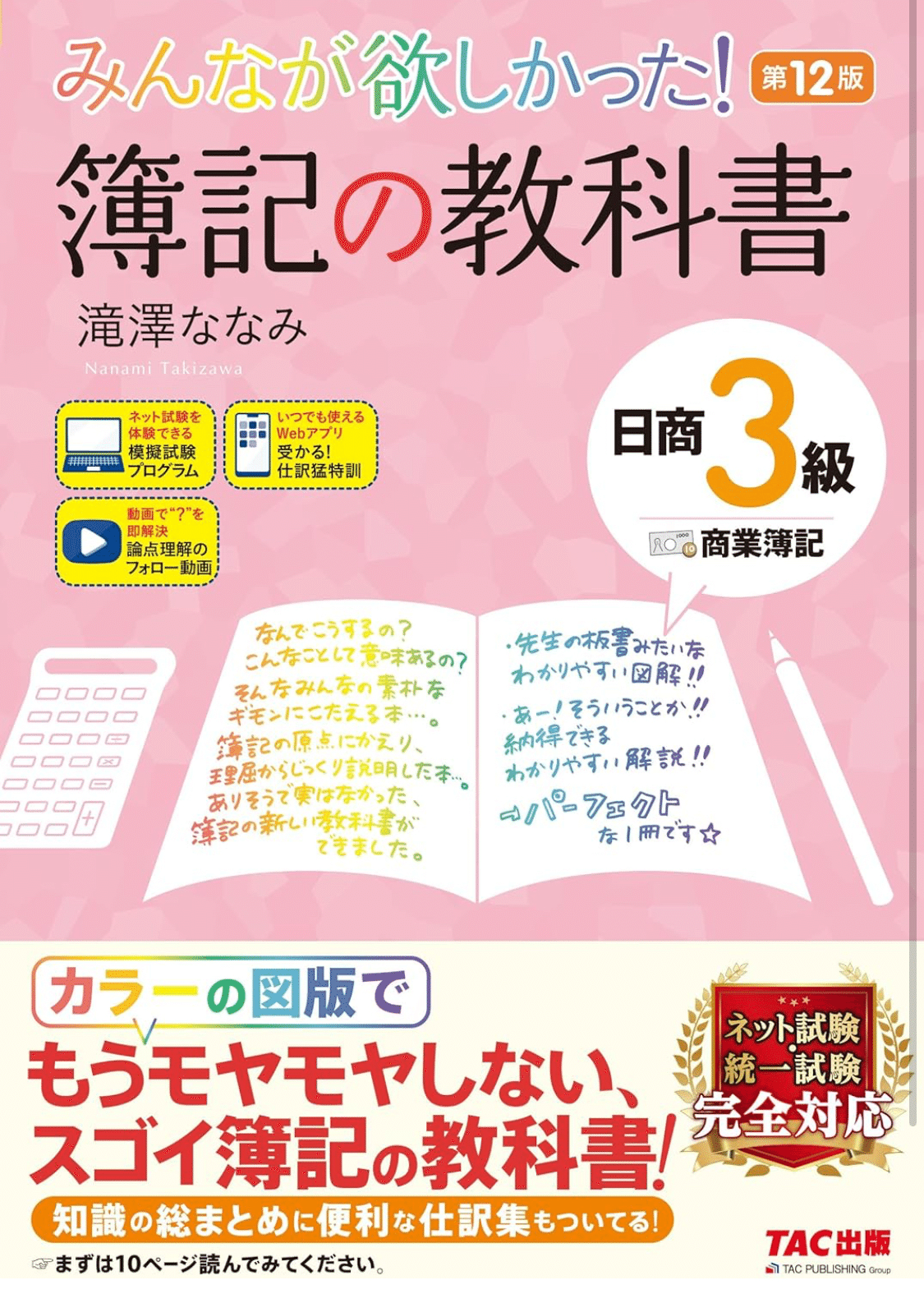
あとはYouTubeで「公認会計士たぬ吉の資格塾」というチャンネルも使わせていただきました。
このチャンネルでは3級の内容が全部無料で解説されているので助かりました。他にも簿記系だと「ふくしままさゆき」さんとかのチャンネルとかが有名ですよね。
自分はこの時点では「ふくしままさゆき」さんの存在を知らなくて、たまたまYouTubeのおすすめに上がってきたこの動画↓をみて!たぬきちさんのチャンネルにお世話になることになりました。
この「日商簿記3級に2週間で合格する方法」という響きにやられました。
2週間ですよ、2週間。
14日なら挫折せずに続けられそうだし、たぬ吉さんの、自分でもイケそう、と思わせてくれる口調や雰囲気もあってモチベも高まりました。
なので自分の3級の勉強方法はこの「日商簿記3級に2週間で合格する方法」の内容そのまんまです。
ずっとこれに沿って勉強しました。
ちなみにですが、自分が受けた試験はネット試験のほうです。
正式名称は「CBT-Solutions」と言うらしいですね。
だけど一般的にはネット試験って言われているのでここでもネット試験という言い方で統一させていただきます。
試験日はこの勉強を開始する前に予約しておきました。
その方がなんか追い込めそうですしいいですよね。
それにネット試験は試験日3日前までなら日時を変更できるみたいです。
だったら尚更先に予約していても別に問題ないかなと思いました。
日商簿記3級の勉強をしていて印象的だったのは、内容の後半にあたる決算整理辺(貸倒引当金とか減価償却とか)から急に難しく感じたことです。
それまでは単にその都度発生した商品売買などの仕訳を学んできた感じだったのに、決算整理の内容からいきなり、前期やら翌期やらというワードが頻出してきて、単語(勘定科目)も普段馴染みのない言葉ばかり出てきて、簿記の世界観?に慣れるのに苦労しました。
だって、今まで引当金とか貸倒れとか、減価償却とかって概念、意識して過ごしてきたことないし、言葉自体も専門用語みたくちょっとお堅くて一気に難しく感じました。
だから決算整理辺りの内容からは、試験日当日まであんまり理解できていないままでした。
というか、試験日まで問題の解き方や仕訳の処理方法はなんとなく分かったけど、何でこうするのか?っていう理論的背景とかは腹落ちして理解できてないまま、みたいな感じでしたね。
そんな感じで3級の全範囲の論点のインプットが終わり、試験日前3日間からは総合問題演習や今までやった範囲の総復習に入るわけですが、自分はこの期間にTAC出版が行っている「書籍ダウンロードサービス」のネット試験対策の模擬試験プログラムをパソコンで時間配分を気にしながら計5回分くらい解いてました。
この時の感想は、(え?問題集までのレベルと全く違うんだが!?試験ってこんな難しいの!?)でした。
この時はよく分からなかったですけど、どうやらこの模擬試験プログラミングの方は本試験レベルよりも1〜2段階ほど難易度を上げて作られているようで、自分のようにそれを知らない人がこの模擬試験プログラムを初見で解くと、それまで触れてきた問題集とかとの難易度の差にかなり驚くみたいですね。
ちなみに今だから言えますけど、この模擬試験プログラムはネット試験を受ける人が本番を想定して実際にパソコンを操作して解答する、という感覚を掴むために用いるべきなので、自分のように5回分も解く必要性はないと思いますね。だから本番を想定して1回分解けば十分です。
もし多くの総合問題演習を行うなら、本試験問題集を時間を測って解くほうがいいと思います。↓

実際に試験勉強終えて合格した今だから思う3級の攻略の方法
実際に15日で簿記3級に合格した今だから思う、3級の攻略の方法についてに話します。
個人的に主に3つありまして
①とにかく第1問の仕訳問題10問(45点満点)を全問正解するつもりで多くの仕訳問題を解くこと
②第2問でよく出題される「補助簿」の作成とか「総勘定元帳」への記入&締切、系の問題は問題演習を繰り返して慣れること
③第3問の貸借対照表、損益計算書、精算表作成問題も問題演習を繰り返して慣れること
結局、これだと思うんですよね。
自分はテスト前日まで第2問の「補助簿」の作成とか「総勘定元帳」への記入&帳簿の締切、という問題に強い苦手意識を持っていました。
第1問は仕訳だけなので、ここは繰り返し仕訳問題に触れれば大丈夫そうだな、と思えましたし、第3問に関しても(仕訳力があればあとは数値の集計ミスに気をつければいいよね〜)という感じで苦手意識はそこまで抱かなかったんですよ。
でも、第2問でよく出題される「総勘定元帳」への記入&帳簿の締切問題とかってなんか癖ありません??
補助簿の作成は、やたら種類が多くて表も一つ一つ違うから頭がこんがらがってくるし、総勘定元帳では仕訳で用いて相手勘定科目を書くこととか、損益科目は損益勘定へ持っていくために貸借を反対側に持って行って「損益」科目を計上して振り替える、とか。
貸借科目は貸借差額を反対側に「次月繰越」をして、一旦締め切って、翌期首にホームポジション側に「前月繰越」とする、とか。…etc
まぁこの辺って、問題演習の中で慣れる?しかないと思うんですよね。
誰かが「簿記って使ってく過程で段々理解度も上がっていく。簿記は利用する学問だ。」的なことを言っていて、自分も第2問とかに関してはほんとにそうだなーと思いますね。(2級の工業簿記とかも特に)
だって、第2問の解説動画とか見てるだけだと、何してるのか全然頭に入ってこないもん。
実際に自分で手を動かして間違えながら、再度解説とかを見る&読む、っていうトライ&エラーの繰り返しで、「あ、そういうことか!」ってわかる感覚なんですよね。少なくとも自分は、です。
この、実際に自分で手を動かしてトライ&エラーを繰り返す中で理解度が上がっていく、っていうのは2級の勉強でも強く感じたことです。
(2級の時に詳しく書きます)
だから第2問はテキストの参照に載っている「第2問対策コーナー」的な部分を何回も読みながら、問題集の「総勘定元帳」への記入&帳簿の締切系の問題を実際に手を動かして解いたり、たぬ吉さんの動画を何回も見て&解いて、というのを繰り返してました。↓
仕事やスポーツでいう、まずは身体で覚えるって感じです。
試験日当日は、あえて一番遅い時間帯で予約していた(これ大事)ので、これまで間違えてきた問題をもう一回解き直したり、たぬ吉さんの第1問〜第3問の集中特訓問題を繰り返し見てました。↓
このテスト直前までの詰め込みが功を奏したのか、出題された内容が試験本番の直前対策で触れてた問題と似ていたからなのか、とにかく運にも恵まれて本番では2問ミスの95点で合格することができました。
内訳はこんな感じ↓
・第1問45点(配点は45点)
・第2問18点(配点は20点)
・第3問32点(配点ら35点)
テスト本番の話をすると、模擬試験プログラムの問題が難しすぎたこともあって、簡単で解きやすい問題ばかりでちょっと拍子抜けしましたね。
あと第二問では穴埋め問題(語群選択)も出てきて、これはテキストの内容を隅々まで理解してないと解けないというか、まぁ落としてもしょうがないよなぁ、的な問題が出できたのが印象深かったです。
あとは時間配分ですね。
自分は第1問→第2問→第3問の順で解いたんですが、第2問を解き終わるときには多分残り時間が35分以上余ってて結構余裕あるな〜と思ってたんですが、第3問の集計ミスに気をつけるのにかなり慎重になって、何度も確認とかをしていたらあっという間に残り10分にまでなっていて内心ヒヤヒヤしました。
3級は60分制限なので、問題のどこかでずっと詰まっている暇はありません。
結構時間配分に気をつけないと時間オーバーになって、解ける問題を解き残してしまったり、落ち着いていれば簡単に解ける問題を焦って凡ミスしてしまうこともあります。
なので、第1問なら15分、第2問なら20分、第3問なら20分で解き切る、というように常に時間配分は気にして解いた方がいいのは言うまでもないです。
ネット試験の場合は、画面上に残り時間がカウントダウンされていくので、意識しなくても時間を気にすることにはなると思いますけど、仮に分からない問題に遭遇した場合、例えば2分くらい考えてもわからなければ一旦別の問題に進む、とかっていう選択もアリだと思います。
まずは解ける問題を先に潰すというのは、試験合格の戦略において大事ですからね〜。
総括:日商簿記は結局「仕訳力」だよねっていう結論
ここまで書いてたら思ったより文字数が増えていたので、2級の体験談は違う記事でまとめたいと思います。
あと、やっぱり簿記に求められるのは、行き着くところ「仕訳力」だと思うんですよね。
正しい仕訳ができなければ、勘定記入の問題も正しく出来ませんし、貸借対照表とか損益計算書の内容も間違えたものになってしまいます。
結局、仕訳力なんですよね。
「仕訳に始まって、仕訳に終わる」
簿記界隈では有名な言い回しだそうですが、実際やってることそうですもんね。
この仕訳が単に暗記で切ってるだけなのか、なぜそう処理するのか?っていう行う目的とか背景も理解して切ってるのでは雲泥の差があるんでしょうけど、行き着くところは正しい仕訳ができる力、が簿記でいう基本であり土台なんでしょうね。
ではまた。
