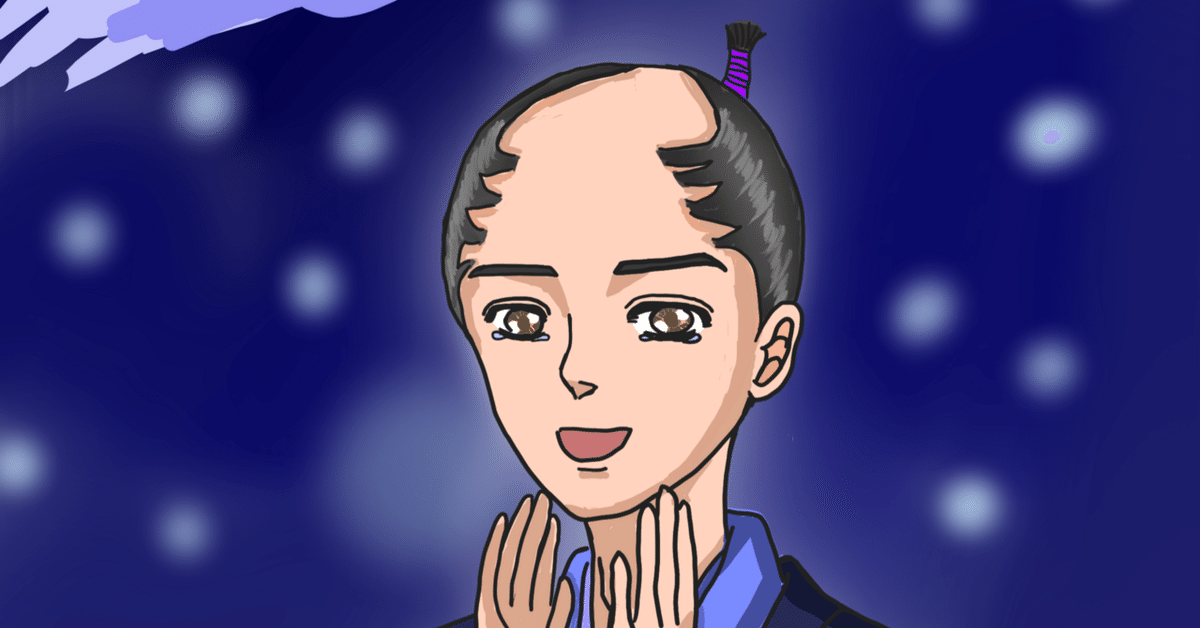
愛を伝えたいんだ
お父さん、お母さん…於次のために出会ってくれてありがとう。於次をこの世に産んでくれてありがとう。短い間だったけど於次を愛してくれてありがとう。於次は二人が繋いでくれた愛と勇気のたすきを次の世代に、後世の平和のために繋ぎます。
天正十二年(1584)十二月末。もう一月すると春の芽吹きを聞こうかという季節がやって来るが、もうすぐ天下人になろうとする羽柴秀吉の居城・長浜城とその城下では、まだ冬の香りが強く漂い、青々とした空はまだ春の訪れを告げるのは遠いよと語りかけてくるようだった。
「さみーなぁ三成、これでも春は来るんだよなぁ…」
長浜城の廊下で、羽柴秀吉の若き近習である大谷吉継は、朋輩で親友である石田三成に小袖の両脇を腕で抱え込みながら、さも寒そうに聞いた。
「来るさ。この世が終わらない限りはね」
三成が吉継に冷静に返答しているとドタバタと二人の元へ走り寄ってくる人影があった。それは彼らの主筋にあたる秀吉の後継者、羽柴秀勝であった。秀勝は自らより八歳から九歳年上である三成や吉継を兄のように慕っていた。
「三成、吉継、みーつけた!!」
「おっおはようございます、秀勝様。何やらご気分が高揚していらっしゃるようですが今日は何か特別な日でしたか?」
「おう、吉継いいことを聞いたね。今日が特別ってわけじゃないけどあと二十日すると特別な日が来るんだなぁ!君たちも愛する妻がいる身なんだから知っていて損はないと思うぜ」
「秀勝様、それはもしかして…南蛮のお祭りでしょうか?」
「さすが冴えてるねぇ三成。そう、南蛮のお祭りだよ。愛し合う恋人や夫婦が贈り物をし合って感謝し合う日なんだよ!」
秀勝が力説しているとその背後からヒソヒソと陰口を叩く声が聞こえた。
「何が南蛮の祭りじゃ。まだ徳川との戦いの決着もついていないというのに。愛し合うもの同士が贈り物を贈り合う?愛だの恋だの女子のように呑気じゃのう近江衆は!のう清正?」
「まったくよ正則。そんな風に女子らしい呑気ものだから近江衆は我らのように戦場で立派な手柄も立てられぬのじゃ…」
三成や吉継と同じ秀吉の近習である「賤ケ岳の七本槍」で世に喧伝されている、福島正則と加藤清正である。二人とも秀吉とは血のつながりがある親戚で、特に正則は秀吉のいとこという立場から態度が横柄で、日頃から秀吉に重用される三成や吉継を煙たがり、秀吉の後継者もどうせ同じ養子なら秀吉の主筋とはいえ他家から来た秀勝より、秀吉の姉ともの息子である秀次が良いという立場であった。羽柴家では便宜として秀勝派を近江衆、秀次派を尾張衆と呼んでいた。ちなみに秀勝も秀次も年齢は同じ数え十七歳である。三成はいつもの彼の役目であるように「主君に対して無礼であろう」と言おうとしたが、それをさえぎるように秀勝が正則たちに嚙みついた。
「呑気ものとは何事じゃ!戦、戦とそれしか頭にないものは無粋で困るの!お前たちはそんなんだから女子にモテぬのじゃ。父秀吉が天下を統一すれば戦の世は終わる、いや終わらせなければならぬ。皆そのために懸命に命を尽くしておるのじゃ。戦しか脳のないお前らは太平の世になにをするつもりなのじゃ?バレンタインの祭りはな、俺の実の父上と母上にまつわる思い出がある俺にとっては大切な祭りじゃ!そんなに俺よりも秀次が良ければ秀次と一緒に武器の手入れでもしてろ馬鹿!」
秀勝が投げ捨てるように言うと正則と清正は何やらもごもごと口にしたが面目なさそうに去っていった。秀勝は陽気で元気一杯の大柄な少年で気が強く負けず嫌いな一面があるとはいえ、今日のような怒りを見せるのは稀であった。三成や吉継は自分たちでは分かちようのない秀勝の心の傷口を垣間見たような気持ちで複雑そうな顔をした。そういえば秀勝は、秀吉の実子である石松丸秀勝が夭折した後入れ替わるように羽柴家へ養子に来て、石松丸と同じ秀勝と名づけられたのであった。しかし秀勝の出自はけして羽柴家へ養子に出されるような格の低い信長の息子というわけではなかった。秀勝は幼名を於次丸と言って信長の正室である濃姫(斎藤帰蝶)が三十四歳でようやく授かった待望の息子なのである。しかしその時には側室の生駒吉乃が産んだ長男信忠が織田家の後継者として内外に認知されており、家中の争いの種になるよりはと濃姫は一粒種の息子を養子に出すことを望んだのだ。風聞によれば「織田家に残るよりも他家へ出た方が於次様の未来は開ける」という南蛮の占い師の助言に従ったのだという…けれど秀勝としては内心傷ついているのだろう、と三成と吉継は見ていた。何故なら濃姫はもちろん彼ほどあの第六天魔王とさえ恐れられた信長に愛された息子はいなかったからである。そして三成も吉継も家族はつつがなく生きているが、秀勝を最も愛した両親は今はこの世にいない。日本人なら知らぬ者はいないであろう本能寺の変で信長と濃姫は横死したのである。信長の死も世間を震撼させたが、信長を正室として裏からサポートしてきた濃姫の死は南蛮の宣教師に「日本の聖母が死んだ」と嘆かせた。秀勝こと於次にも当然自慢の母だったのだ。
「秀勝様、お父上とお母上の思い出深いバレンタインの祭りとはどのようなものでしたか?」
三成は傷心の弟を慰める兄のように秀勝にたずねた。すると秀勝は遠い目を空に向けながら懐かしそうに「バレンタインの祭り」について話はじめた。
今から遡ること八年前の天正四年(1576)一月半ば、午の刻を三時間ほど過ぎた頃。岐阜城の奥御殿では城主織田信長と正室濃姫の一粒種である於次丸こと於次が母濃姫の膝枕でスヤスヤと昼寝していた。
「於次、於次…もう起きなさいな。もうすぐ父上がお客様を連れていらっしゃいますよ」
母濃姫はいつものように優しく諭すような声音で一人息子を起こそうとしたが無駄だった。もうすぐ養子に行くかもしれないのにこんなことで大丈夫かしら?と、いつもは鷹揚に構えている濃姫もさずがに少し気にならないわけではなかった。そこへ濃姫から今日のために岐阜城に招かれていた信長の妹お市の方がその三人の娘、茶々、初、江(ちゃちゃ、はつ、ごう)を連れてやってきた。
「義姉上様、今日はお招きいただきありがとうございます」
「あらそんな格式張ることでなくてよお市殿、何やら南蛮のこじゃれた伝統の祭りをわらわたちにも見せてくれるということだったので、お招きしただけですわ。お茶々殿たちも将来何かためになることがあるかもしれなくてよ」
「まぁ!楽しみです、ありがとうございます濃姫様。茶々と佐吉の恋が上手くいくおまじないでも教えてもらいたいですわ」
そういうと於次より一つ年長の数え十歳の茶々は喜んで飛び跳ねた。
「…うるさいなぁ茶々!せっかく俺がいい気持ちで寝ていたとこなのに!そんなお転婆でおしゃべりな茶々なんか、佐吉だってお嫁に欲しくないよ!」
「なんでそうなるのよ、於次の馬鹿ぁ!あんただってお母様のようなお嫁さんなんてもらえないんだからね!」
「うるさい!」
茶々と於次が取っ組み合わんばかりのケンカを始めると、二人の上から威厳ある大人の声が二人をたしなめた。
「これこれ、よさぬか二人とも。南蛮の客人に日ノ本の子ははしたないと思われるであろう」
於次の父信長の声であった。
「父上!」
「伯父上!」
「ほう、これが信長様のお子様ですか?」
信長の後をついてきた金髪碧眼の南蛮の宣教師が信長にたずねる。どうやら彼が信長の言う南蛮の客人のようだ。信長が目を細めて嬉しそうに説明した。
「いやいやセバスティアン殿、女子の方は茶々と言って妹のお市の娘じゃ。男の方が於次と言ってわしとお濃の息子じゃ。茶々はともかくわしとお濃の秘蔵っ子の於次に会えるのは南蛮人広しといえどもセバスティアン殿くらいじゃ」
「それは光栄な歓待ですな。あれだけの品をご献上して差し上げるのに相応しい。だが、そんなに大切なお子さまなのに信長様は信忠様という後継ぎがいらっしゃる。於次様はいったいどのように処遇されるおつもりで?」
「それはのうセバスティアン殿、於次は織田家の跡取りなどという小さな器に収まる子ではないのじゃ。なんと言っても於次はわしとお濃の血を引いているだけあって賢さといい人徳と言い申し分がない。だから惜しいのじゃ、わしは於次に織田家の跡取りではなく天下人の跡取りになってほしいのじゃ。織田家はわしがいなくなれば屋台骨が揺らぐ。だから於次はわしの次に天下人になる器量のある男に預けようと思うのじゃ。今は見極め中じゃがの」
「まぁまぁ殿ったら於次のことになると甘い評価で困りますわ。本当はね、セバスティアン殿、於次はわらわが34の時に産んだ子でその時には信忠様が家督と決まっていましたのよ。わらわはあまり子供運がなくてこの於次だけが唯一の子供ですけどお家騒動のもとですからね。ゆくゆくはしかるべき家に養子に出してほしいと言っているところですわ」
濃姫は慌てて夫の説明を訂正した。
「なるほど。北の方様は本当に賢く思いやりの深いお方だ。仏も恐れぬ信長様が自慢される女房だけはある。今日お持ちした品物は濃姫様に相応しい一品ですぞ」
「あら、なんですか、殿?今日は私の誕生日でもありませんのに…」
すると信長は照れながら濃姫に説明した。
「今日はの南蛮では愛する者同士が贈り物をし合うバレンタインという祭りだそうじゃ。なかなか面白いと思っての、日頃の感謝をそなたに伝えたいのじゃ」
「まぁ!素敵なお祭りね!茶々も佐吉とそんな仲になりたいわ!」
「懲りない女だな、佐吉の気持ちだってあるんだぞ。茶々の方が身分が高いから佐吉は拒否できないかもしれないけど、心の底から愛してなんてもらえないぜ。あー佐吉可哀想!」
「うるさいわね於次!茶々にだって夢を見る権利はあるのよ!」
「だって俺は茶々の言う恋なんて信じられないもん」
せっかくのいい場面に於次と茶々がまたしても水を差したので、信長はゴホン、ゴホンと咳払いする。
「まぁまぁ、お茶々殿、於次、今は大事なお話があるみたいだから静かにしましょうね」
濃姫が優しい口調でやんわりと子供たちを黙らせた。
「ごっごめんなさい…濃姫様」
「母上ー」
信長はさずが母は強しじゃなと改めて濃姫に感謝したように眼差しを向けて、セバスティアン殿に「それで例の品はどのような一品なのじゃ?」と聞いた。
「驚かれて腰を抜かされぬよう覚悟して御覧なさいませ。黄金が豊富に出るジパングにおいてもこれ程までに美しい石はなかなかお目にかかれますまい。遠きコロンビアという国の鉱山で採れたエメラルドなる石を研いたものでござりまする」
セバスティアン殿は、もったいないものを扱うような低調なしぐさで木の黒箱を開けると、中には赤いビロウド調の布の上に爽やかな森の緑を連想させる緑色の透明なうずらの卵くらいの大きさの石が鎮座していた。
「まぁ綺麗、これを殿はわらわに贈るのですか?」
「そうじゃ。そなたは日本一の女房じゃからの」
「まぁ嬉しいことをおっしゃいますのね。でもバレンタインは愛する者同士が贈り合うものなのでしょう。わらわにはこんなに美しい石に払える対価あるものが用意できませぬ」
「ハハハハハ、そんなことを案ずる必要はない。お濃は天下人の妻としてわしを常に裏から支え、
於次という宝物を生んでくれた。わしにとってはお濃がエメラルドに匹敵するかけがえのないいやそれ以上に価値ある存在じゃぞ」
そんな天下人夫婦の他愛もないけれど絶対に他では見られない仲睦まじさに当てつけられたように、信長と濃姫そして二人の子である於次を残して岐阜城の奥からは人が消えていた。
「父上、母上、どうしたのでしょう茶々も含めて皆いなくなりましたよ」
「あらやだみんなに気を使わせてしまったわね」
「みずくさいことよ。でも折角だから今日はこのまま三人で夕餉を取り川の字になって寝るのもよいのう」
「本当ですか?!今日の父上と母上は於次だけのものなのですね!」
於次はやったーと言うなりはしゃいで父と母の周りを駆け回った。
「於次…」
濃姫と信長は複雑な表情で我が子を見た。もうすぐ養子に出さねばならない息子、本人にも言い聞かせているが両親に誰より溺愛されているこの息子には辛い現実だろう。それでもこの子は泣かないし愚痴一つ言わずに笑顔を振りまいてくれる。
「ここへ来い於次!」
信長は於次を呼んでちょこんと自分の膝の上に座らせた。
「いいか於次、これからどんなに辛く悲しいことがあっても、くじけてはならぬぞ。希望だけは常に持ち生き延びることだけを考えよ。生きてさえいれば必ず好機が来る。それを逃すな。そして
日ノ本にも世界にも誇れる天下人になってくれよ」
「そうですよ、於次、母はあなたが誰よりも幸せになってくれることを祈っています」
秀勝が見つめる空はただ無言に青く染まっているが、次第に優しい光が心持ち増して温かくなってきた。それは常に秀勝を照らす優しい太陽であった母濃姫の愛のように秀勝は思いたかった。
「お父さん、お母さん…」
「秀勝様っ」
少し想い出の世界で感傷的になっているような秀勝に吉継が声をかけたその時、ぐすんぐすんという秀勝より一層感傷的な涙声が聞こえた。
「どっどうしたのさ、三成!バレンタインは素晴らしく素敵なお祭りだってお話だよ、何も泣くようなことじゃないよ」
「だっていつもはいたずら好きでちょっとおせっかいかなと秀勝様のことを見ていたのに、そうですよね、秀勝様はご両親をお亡くしになってそれもあんな形で……いつもは我慢して笑顔を振りまいてくださっているのかなって思ったら涙が止まらないんです」
泣く三成に秀勝は慌てて彼の話を打ち消そうとした。
「戦国の世だもの。そんなことで泣いていたら生きては生けないよ、三成。それに戦で両親を亡くしているのは茶々も一緒だよ。佐吉のお嫁さんになれて嬉しいだろうけど慰めてあげなよ、あれで繊細な子だからさ………多分ね」
数日後の早朝秀勝の屋敷の寝殿、秀勝は良く寝たとあくびをしているとバタバタとただならぬ走ってくる侍女の足音に驚かされた。
「秀勝様、秀勝様、お客人でございます!」
「客人?また福島と加藤か、朝から無礼だと追い払え!」
「それがその…女性の方でして」
秀勝の顔がさっと青ざめる。
「分かったすぐ行くっ」
秀勝は小袖の上にささっと羽織と袴を身にまとうと駆け足で対面の間に向かった。果たして秀勝がそっと気づかれぬようふすまを開けその視線の先に見た女性は…今は三成の正室となっている
従姉妹の茶々であった。
「なんだ茶々か。なんか用?ひょっとして三成と喧嘩でもしたぁ?」
秀勝がお道化て聞くと茶々はただでさえプンプンしているのにますますいきり立って秀勝を怒鳴りつけた。
「秀勝!あんたまた余計なことを三成に吹き込んだわね!おかげで三成は夜も茶々を可愛がってくれないのよ!」
秀勝は茶々の猛烈な怒りっぷりに内心呆れながら、茶々が自分の従姉妹であることをいいことに相変わらず「秀勝様」ではなく「秀勝」と呼び捨てにすることにいつもながら不愉快な気分になった。
茶々と三成の結婚を後押しをしたのは自分ではないか、もし自分が助け舟を出さなければ茶々は養父秀吉の側室にされたかもしれない。それをまあ母濃姫と父信長の遺志ということで三成の嫁にしてやったのだ。もう少し感謝と尊敬の念を持ってほしいものである。なんで茶々はそこら辺に思い至らないのであろう、この女馬鹿なのか−しかし秀勝は幼い頃のように茶々と張り合うのは徒労であることは理解していた。
「あれー変だねぇ、三成には茶々を慰めてあげてって言ったけどな…忘れちゃったのかな」
「……そ、そりゃバレンタインの話をした夜は珍しく三成から茶々を求めてきてそれはしっぽりと愛し合ったのよ。でもそれきりなの。それ以外書斎に籠って何かしてるわ」
茶々は三成と愛し合った夜を思い出したように顔を赤くしながら落胆したように肩を落とした。
「ほーそれはそれは」
「なによ秀勝、知ってるなら教えて頂戴!」
「ほらアレだよ、男の甲斐性って奴さ。三成だって男だし相手が茶々一人じゃ飽きちゃったんじゃない?」
「あんたと一緒にしないで!三成は茶々が初めての女なのよ、茶々が成長するまで待っていてくれたんだから!」
三成が真面目なのは確かだが…それは茶々の身分が高かったせいではないかと秀勝は思った。が、生意気な茶々をもう少し懲らしめてやろうと思い、さらに追い打ちをかけるように冷やかに告げた。
「そっかじゃあ本気だね。可哀想に茶々捨てられちゃうかもねぇ」
いきり立っていた茶々はあまりの言葉に衝撃を受け顔面を蒼白とし腰を抜かしたように座布団に沈み込んだ。
「そっそんな…茶々には三成しかいないの よ、居なくなったらどうすればいいのー!!」
そう叫ぶなりわんわんと泣き出した。そんな茶々を見て秀勝は、やりすぎたかなと少しだけ反省した。
「茶々、そんなに三成が好きなら三成を、いや自分自身を信じなよ。母上だったらきっとそう言っと思うよ」
「……濃姫様が?」
時はもう一度八年前に巻き戻さねばならない。秀勝こと於次の父織田信長が妻であり天下を運営する上での影のパートナーでもある濃姫に、日頃の感謝の印として見事なウズラの卵ほどの大きさのエメラルドを贈ったあの日、皆の気遣いか信長と濃姫とその子於次だけが岐阜城の奥御殿に残り、夕餉を共にした後のことである。奥御殿の縁側に信長と於次が座りその居室のもう少し奥の方に妻であり母でもある濃姫が座っていた。
「ねぇ父上…」
「なんじゃ於次?」
「父上にとって母上は一番大事な人ですよね?」
「?」
「父上にはたくさんのお子がいて、大勢の側室もいらっしゃいます。でも於次にとっては母は母上一人だし、於次には於次の母が一番大事です。でも…於次は母上とはずっと一緒にいられない運命です。だから父上は於次の分も母上を幸せにしてください。誰よりも一番大事にしてあげてください」
「……」
信長と濃姫は神妙な顔で於次を見た。
「大丈夫じゃ於次。そなたがこの家を旅立つ日が来ようとも、於次の母はお濃だけだしそなたの母は天がわしに遣わした女神じゃからの」
「まあ女神だなんてたいそうな持ち上げようでございますこと。でもわらわは自分が幸運だけで生きていると思わないし、殿のご寵愛が第一だなんて自惚れているわけではありませんよ」
「?」
思いがけない濃姫の言葉に今度は信長と於次の目が点になる。
「わらわはわらわを愛してくれる殿を信じているというより、殿を愛し愛されている自分自身を信じているのでございます。この世の中女の身はどうしても殿御に振り回されがちですが、確かな自分の意志で歩んでいると信じられるなら幸福に少しでも近づくのではないでしょうか。少なくとも濃は幸せだし、殿に娶られて良かったと信じていますわ」
「……だそうじゃ於次。於次もお濃のような女子を娶ると良いぞ。わしの方こそ幸せであった。こんな男にも動じずいつも寄り添ってくれるお濃が正室でよかったと心から思っておるぞ」
(思えば父上はえらいことを言ったものだ。母上のような女人なんて簡単に…いや絶対にみつけられないのに…)
秀勝が我に返るともうそこに茶々の姿はなかった。
天正十三年(1585)一月半ば。ついにその日が来た。秀勝は近習の三成と吉継を引き連れ活気を見せる大阪の市にやってきた。羽柴秀吉の次の居城となるであろう大坂城は去年から絶賛工事中である。
「まったく秀勝様も大人げないですよ、茶々はそんじょそこらの野郎じゃないんだから、家に着くなり大泣きして走り込んできて『三成行かないで。茶々を捨てないで。茶々の最後の誇りを奪わないで』って抱きつかれましたよ。茶々は今妊娠中みたいでただでさえ感情がぶれやすいんですからね」
「えっ妊娠?!」
秀勝と吉継の声が同時に重なった。
「へーラブラブなんだね、三成と茶々!吉継も恋愛結婚だし羨ましい。あの子さぁ政略で人質に来たと思ってんのか中々心を開いてくれなくて…せっかく天下人の影の女ではなく未来の天下人の嫁になったんだけどなぁ!」
「秀勝様、摩阿姫様だって賤ケ岳の戦で佐久間十蔵殿という未来の夫君をなくされたんでしたよね。お互いに歩み寄らなくてはダメですよ。摩阿姫様のお悲しみを理解できるのは秀勝様だと思いますし、秀勝様の淋しさを受け止められるのは摩阿姫様しかいないと思います。母君を思いがけない形で喪って傷ついているのは分かりますがいつまでも母君の面影を追いかけていては大人になれないし、ましてや天下人の後継者にはなれないですよ」
「……痛いとこつくねぇ、吉継。それは俺だって分かっているのさ、分かっているけど、どうすりゃいいのかなぁ、うーん」
「秀勝様らしくないですよ。俺も吉継も秀勝様には期待しているんですからね、あっ秀勝様、吉継見てごらんよ、南蛮人の石売りだ。あの人にそれぞれ見繕ってもらって茶々、小石殿、摩阿姫様へのお土産といたしましょう!」
イスパニアから来たというその商人は、気が強いが一途で深い愛情を持つ茶々には情熱の赤い石と呼ばれるルビーを、貞潔でしっかり者の小石殿には明るい水色の石アクアマリンを、最後に秀勝の正室摩阿姫には少し考えこんだ様子で大量の美しい石の入ったざるのなかから深い青色の石を取り出した。秀勝、三成、吉継の三人はその青のあまりの美しさに息をのんだ。
「これはセイロン島と呼ばれるところで取れた見事なロイヤルブルーサファイアです。サファイアはキリスト教では神の石とも言われる尊い石ですぞ。古くは大地の色を映しているとも言われてましたな、石言葉は霊魂の鎮静。どうです、ちょっと値は張りますが秀勝様とその奥方様が抱えておられる状況にはぴったりじゃないですかね」
「なるほど霊魂の鎮静か…いいだろう、この秀勝、そなたの言葉を信じて買ってみよう」(父上も母上のためにエメラルドを買った時似たような気持だったのかな。母上の喜ぶ顔が見たくて買ったのだろうな)
こうして三人はそれぞれの妻の顔を思い浮かべながら家路についたが、秀勝だけは摩阿姫がどんな反応をするか怖いような楽しみなような気が相半ばしていたので帰途の時間が夜にまでもたついてしまった。
「秀勝様!ようこんな時間まで何の連絡もなく。どれだけ心配したことか」
真っ先に乳母の宰相の局がそう言ったが、秀勝は目の前の光景にあっと息をのんでどうしたらいいのか分からなくなった。廊下の一番奥の方に今年数え十四歳になったばかりの摩阿姫がいた。
「…お帰りなさいませ」
摩阿姫は抑揚を殺したような小さな声で挨拶をした。
「た…ただいま」
いつもはすこぶる陽気なお調子者の秀勝も摩阿姫のこの堅さの前では同じように硬直してしまう。
なんでこんな夫婦になってしまったのだろう。賤ケ岳の戦の帰り道、養父秀吉に同行した秀勝は、摩阿姫の父前田利家居城の金沢城に立ち寄った際、当時十二歳の絶望した姫の顔を見て「この
子を救わなくては」と政略を思い立ったのに。実のところ並外れた女好きの秀吉は、摩阿姫の父利家の信義を試すために彼女を「人質」として側室にするつもりだった。父信長の死後、養父の秀吉の下にはたくさんの富と同時に見目麗しい姫たちも献上されていて、秀吉と利家は旧知の親友であったが、利家は賤ケ岳で秀吉に滅ぼされた柴田勝家の傘下であったために中立っぽい姿勢をとった利家を秀吉はただで許すつもりはなかったのである。しかも近頃の養父は秀勝の養母でもある正室のおねもそっちのけで新しく側室になった、絶世の美女京極殿こと京極竜子に夢中だった。京極家は室町幕府の時代には北近江の守護職にあった源氏の名門である(ちなみに京極竜子は茶々の父方従姉でもあった)が、同じように数多の側室を抱えていても父信長は秀勝の母である正室の濃姫の優位は動かさなかった。それなのに秀吉は…とまだ少年の青ぐささが残る秀勝には到底理解できないのだった。まして未だ大人になったかならないかの年齢の少女まで側室にしたいという…そう言えば三成と茶々を結婚させたのはいいけど俺の嫁さんはどうなってるんだっけと秀勝はその時思い出した。だから秀吉が「摩阿姫を…」と金沢城での宴で口にしかけたとき秀勝は秀吉も驚くような間髪入れないスピードで「俺の嫁に下さい。必ず幸せにします」と利家とまつ夫妻に申し出た。秀勝はその時おとぎ話のヒーローになったような気分だった。すごい、俺よくやったじゃんと自分で自分を褒めてやりたかった。が当の相手の摩阿姫がすこぶるぎこちない感情を全く見せない娘だった。夜の閨事もまあ当の摩阿姫が幼いことをいいことにおざなりにしていた。そんな自分も秀勝を苛立たせた。
「…めっめずらしいね、出迎えなんて。なんか変なものを食った?」
あ自分最低じゃんと秀勝が思った瞬間だった。いつも無表情だと思っていた摩阿姫の頬をキラリと光る何かがつたった。
「だって心配で。もし秀勝様が帰ってこなかったら私はまた…。あっ今のは忘れてください。秀勝様も名ばかりの妻なんて顔も見たくないんですよね。馬鹿なんです私は助けてもらったのに人見知りが強いせいでありがとうの一言も言えなくて。秀勝様は自分のお好みの女人とわこをお設けなさいませ。私のことなど構われますな」
そういうなり摩阿姫は自室に踵を返そうとした。
「待って、助けてくれたと思ってくれていたんだね、それだけでも嬉しいよ。ねぇもう少し話さないか。君は大切な婚約者を、僕は最愛の両親を戦場で亡くしたんだ。同士だよ。たとえ三成と茶々のようになれなくとも、俺たちは大切なものを亡くしたもの同士として人生を歩んでいこう」
「……待っていました。待ちわびていました。あなたがそう仰ってくださるのを…」
摩阿姫は、小柄な体をじりじりと大柄な秀勝のもとに寄せ始め、秀勝も自然と同じように摩阿姫に寄っていった。
「摩阿姫!」
「秀勝様!」
「ずっと前からこうして君を抱きたかった」
「ええ…私もずっと…」
「あっ大事なものを忘れてた。君にプレゼントがあるんだ」
「まあ何でございましょう」
「セイロン島で取れたロイヤルブルーサファイアっていうんだって。石言葉は霊魂の鎮静。俺たちは二度と戦乱を起こさない平和な国を造り、そのために散っていった霊魂の弔いをするんだ」
「…秀勝様、私も秀勝様の大事なものを見せていただきました」
「俺の大事なもの…」
「本能寺からお使者が運んできたご両親からのお手紙ですわ」
「え…俺それ読んでない。読んだら本当に父上と母上が死んでしまうような気がして怖いんだ」
「ま、摩阿と一緒に読みましょう。ご両親が最後に何を伝えたかったか確かめなければいつまで経っても吹っ切れませんよ」
そういう摩阿姫の口調はまるで亡き母濃姫にそっくりだった。
(ああ母上、ここに生きておられたのですね…それなら秀勝は何も怖くありません)
それは父信長と母濃姫の肉筆の手紙だった。それは日付からして本能寺の前に書かれたものだった。
父は言う。この度は猿が中国征伐を終わらせてくれとのことでそちらに向かう所存である。明智に援軍も出させたのでわしがつく頃には物見遊山になるかもしれん。だが、わしは大変楽しみにしている。秀勝、お前が一人前に戦った武将としてわしの前に現れてくれることが今から楽しみで仕方がないのじゃ。お前は間違いなくわが子たちの中で一番優秀じゃ。わしが与えた何物をも恐れぬ勇気とお濃がくれた全てを包み込むような寛容な心でわしとお濃が目指している天下静謐の思いに助力してほしい、期待しておるぞ。
母はこうつづった。
於次…いえ秀勝、あなたはちょっと負けん気が強く人騒がせなところもあるけれど、本当はどんな境遇に置かれても不平を言わない誰よりも意志の強い子です。でももしどうしてもどうしても倒れそうなくらいに心と体に不平をため込んでしまったなら母のところに来なさい。母がなんでも受け止めます。母はいつかあなたの父上の夢が成就することとあなたが幸せになってくれること、それ以外に天に願うことはありません。秀勝、どうか幸せに健やかにありますように。母はいつでもあなたの
背中を見ていますよ。
「……もう、親ばかなんだからぁ!!」
秀勝の頬を滂沱の涙が流れた。いつ以来だろうこんなに泣いたのは…そう羽柴家へいよいよ養子に行くという最後の日だった。秀勝いや於次は涙が止まらなかった。母と一緒に寝ていたので母に悟られぬように必死に歯を食いしばって泣いた。ただ母から離れるのが怖く淋しかった。でも母はあの時知っていたのかもしれない。だから母は小さな息子の背を何度もさすってくれたのだ。
「秀勝様、秀勝様は一人ではありません。摩阿もいます、三成殿も吉継殿もいます、茶々様だって秀勝様の味方です。だから一人で抱え込まないで…」
それから三年後の天正十六年(一五八八年)五月九日、羽柴改め豊臣となった秀勝と摩阿姫の間に待望の男児が生まれた。関白秀吉と北政所おねはもちろん、世の下々の者まで天下人の跡継ぎがまた新しく生まれたことを喜んだそうな……
さようなら秀勝、摩阿姫といつまでも仲良くね。
