「永井哲学と私 - ネルケ無方(2019-9-19)」について
表題のとおり、禅僧であるネルケ無方さんの2019年9月19日の日記「永井哲学と私」について、かなりインパクトがあったので感想というか思ったことをだらだら書いていこうと思います。前提として、永井哲学や仏教に多少の興味や知識が必要な話なので、Twitter に書いたらまたフォロワーが減ると思いとりあえずnoteに書き残しておきます(感想なので上述の記事を読んでいる前提で話を進めます)。
まず、発端となる永井先生のツイートはこちら。
ふつう承認欲求といわれるのは自分の価値を認めてほしいというものだが、最低限の承認欲求は自分が存在していることを認めてほしいというものだろう。自分が存在していること自体を誰にも知られずに(普通にあるいは楽しく)生きることは可能だろうか?
— 永井均 (@hitoshinagai1) September 14, 2019
以前、ほぼ同趣旨のことを知人(顔見知り)が誰もいない状況として書いたが、それだと刹那的な存在承認が生じてしまう余地があるので、AIによって管理される終身刑のような状況を考えた方がよいだろう。ネット、テレビ等による外界の閲覧は可能という条件を付けたほうが論点は明確になる。
— 永井均 (@hitoshinagai1) September 14, 2019
はじめ、承認欲求といっても一般的な承認欲求(たとえば自分の外見とか才能とか…)ともっと根源的な存在に対する承認欲求があるだろうという話から始まります。一般的には、後者の欲求より前者(俺はすごいとかモテたいとか…)のほうが分かりやすい「かわいい」欲求で、「あいつは承認欲求が強い」といったらこちらの意味ですね。
ここでは前者を価値承認、後者を存在承認としますが、まず後者の存在承認が満たされず前者の価値承認だけが満たされるような状況はどんなものかと考えてみます。ぱっと思いついたのは、死んで霊魂になった自分がかつて書いた本が「素晴らしい!」と絶賛されているのを見ているようなイメージでしょうか。
表題のネルケ老師の記事ではこの「存在承認が与えられない」状態を「宇宙船」に例えています。以下、引用。
先生の比喩を少し変えれば、こういうことでしょう。 寿命が尽きるまでの食料品は宇宙船に乗せて、私はたった一人で宇宙に向かって旅立っている。四六時中、地球と交信ができてあらゆる情報は入手できる。ところが、ある日に気づくことがある。地球からの受信がちゃんと届いているのに、こちらからの送信はどういうわけか、地球には届いていないらしい。地球側から私の存在がまったく承認されていないのだ。当然、そのうちは地球の役所では勝手に「死亡届」が出されてしまうのだろう。そう気づいたときに、私が普通に、あるいは楽しく生きることはできるのだろうか?
さらにこの比喩に「私(=ネルケ)の考えでは、この例えはある意味では私たち人間の普通の状態を表わしているのではないかと思います。」と続きます。つまり「宇宙船に乗っていて地球(他人)に対するメッセージを受け取ってもらうことができず、受信する一方」だというのが「普通の状態」だというわけです。
ここで「出ることのできない宇宙船」に例えられているのは「私にとっての全世界」、つまり私の認識という膜(あるいは壁)にすっぽり覆われている、私に知り得る限りの全世界だと思います。つまるところ、私たちは自分の認識という能力によって世界を捉えている以上、その認識の外に出ることはできないという意味で絶望的な孤独にいるわけですが、この「出られない認識の世界」が宇宙船の内部に相当しているというふうに。私にとっての他者は、全てこの「認識という膜」を通過して捉えられたものーーーつまり、「私の世界にあらわれている限りでの他者」でしかなく、それは直接的な意味での他者ではありません。他者は「私の宇宙船」に入り込んでくることができず、ただメッセージ(言葉)をやり取りするだけです。
私は、自分がこの宇宙船の中にいることを手にとるように分かっており、「ここにいる」というメッセージを送りたいのですが、実はこのメッセージは意味をなしません。どんな意味でも、「私は現にここにいる、他人が皆同じようにそうだと言えるのとはまったく違う意味で、私はほんとうにこの宇宙船の中にいる」というメッセージは成立しません。そのメッセージが宇宙船から発せられた瞬間に、あるいは受け取られた瞬間に、それは「誰にとってもそうであるように、この宇宙船の中に人がいる」というメッセージに変質してしまうからです。
宇宙船の比喩をたとえば私の肉体とか特徴に対応させてみたらどうでしょうか。「その宇宙船、カッコいいね」「いいデザインだね」と褒められることはありますが、それは宇宙船の中にいる「私の存在」とは関係ありません。他者によって捉えられた私は、他者の世界に現れているかぎりの私であり、私の存在なるものは実はその現れ(=さまざまの性質)とは無関係なのです。
ということは、これを反転して私の世界に現れる他者、この比喩を少し改変して皆が宇宙船に乗っているとすれば、「宇宙船ではなくそれに乗っている他者そのもの」に「私は知っている、あなたが乗っていると!」ということもまた意味をなしません。他人の宇宙船について言えるのはやはり「デザインがいいね」「丸っこいね」「他より速いね」というように、他との比較によって捉えられる特徴だけで、「現にそこに乗っているその人」の存在とは関係ないことのみです。
私がこの宇宙船に乗っているということは、そういった特徴(宇宙船のデザイン)とは関係なく、「現に乗っている」という事実によってしか捉えられません。私は現に乗っているということによってだけ、この宇宙船が自分の宇宙船だと知っているのです。
であれば、「このかっこいい宇宙船の中にあなたが乗っているのですね」と伝えることは、厳密に言えば常に嘘であるはずです。このために私は「私はこの宇宙船に乗っている!」という強欲な存在承認をあきらめ、「この宇宙船は速いだろう、カッコいいだろう」とかいう「かわいい」価値承認に置き換え、代わりにそれで満たすことしかできなくなります。余談ですが、感覚としては宇宙船に乗っているのが私で、他者はみな地球にいるという原形のほうが「孤独」の感覚に近いのではないでしょうか。「他者と他者」は同じようであるのに、なぜか私だけのあり方が違っているからです。
順悩み
ここまであまり意味のない表面的な説明をしてしまったので、以降は筆者(ネルケ老師)への私信のような感想になりますが、この記事を読むまえに個人的に考えていたことを書き留めておきたいと思います。個人的に考えていたこと、とは「悩みは全て逆なのではないか」という問題です。いわば「逆悩み」の問題です。
それがたまたま記事中の「順修行」と「逆修行」の問題と関わっている気がしたので、読む前の段階で考えていたことをそのまま書こうと思います。
「悩み」というのはなんでしょうか。だいたい「私は〇〇じゃない」とか「××すぎる…」たとえば貧乏だとか背が高くないとか、当然ながら自分の“特徴“を介して説明できるものです。そうでなければ、「私は悩んでいるんだが、自分でも何に悩んでいるのか分からないんだ」という話になってしまいます。
だから、冒頭の基準に合わせていえば順悩みというのは「価値承認」の不足だと位置付けることができるはずです。これが「私は○○が足りない」という一般的な悩みの形式であり、また人によっては「私は○○を求めている!」というポジティヴなエネルギーの源泉にもなり得るものだと思います。
しかし、これは根拠のない個人的な思想に過ぎませんが、この「価値承認」の不足という悩みより「存在承認」の不足のほうがもっと根源的なのではないかと思うのです(実存は本質に先立つ?)。「存在承認の不足」とは、つまり「私はこの世界に本当に存在しているのか?」という存在不安です。ある精神分析家の文章を読んでいると以下のような例え話がありました。患者が「自分はこの世界に存在していない」と訴えてきます。医者は「何を言っているんだ、君はここに存在してるじゃないか」と理屈にならない理屈で説得します。しかし本当に真理を語っているのは患者のほうだからこそお手上げなのだ、と。
「まず世界があり、その中に私が(他人と同じように)ある」と客観的に考える場合、「私がいないのではないか」という不安を説明づけるものもその客観世界の内部にしかあり得ません。これが一般的な意味の悩みであるはずです。
悩みを客観世界の出来事で説明できればーーーたとえば、「私は醜い!」「年収が低い!」「あいつに愛されない!」「あの国が悪い!」ともかく不安は具体的な対象を持つことができます。つまり、私の不在それ自体に客観的な世界の内部の地位が与えられるわけです。
そして、ここからが私の論点ですが、多くの人は「そう(客観世界の中に足場を固め)して生きている」のではないでしょうか。不安の真の原因がなんであれ、「私は××がないんだ」とか「○○が欲しいんだ!」と言うことで、私はそれを他者に伝え、他者と「同じ世界の基準で」不安を説明することができますーーー「どういうわけか、私は存在しないんだ」とか「むしろ私だけが存在して、他者はいないんだ」あるいは「私だけ表と裏が逆になってるんだ」とか言わずに。そして、このことは社会的に重要な意味を持っているように思えます。「この人は〇〇を欲している」とか説明がついただけで、他者は一気に理解可能な、安全なものになるからです(この人は愛されていないんだ、というのでさえそうかもしれないと感じます)。
逆悩み
そして、上のようなシンプルな悩み方とは反対に、「私は○○がないんだ!」という欲望や、「××のせいなんだ!」という位置付けができないという悩みがあるのではないでしょうか。つまり「これがない!」という欲望を持ったり、「あいつが悪い!」という不安の説明づけにどうしても「ノレない」人々のことです。
欲望を持つためには、他人が自分と同じようにひとつの世界に並んでおり、その他人と競争するーーーというようなゲームに「ノる」必要があるように思えます。このゲームにはヴィトゲンシュタインの比喩にあるチェスのある駒に乗せる白い冠(下で引用)、<私>のようなものは必要ないはずです。つまり、「両親が性交をした結果このような遺伝子を持った自分が生まれた、以上!」のような世界。
この世界では「山田太郎と田中花子が結婚して山田一郎が生まれた」というとき、「俺は山田一郎だ」と思って生きていけばよいはずです。ところが、ここに<私>を持ち込むと「山田一郎は<私>でないことも可能だった」となります。ということは、たまたま山田一郎であっただけの<私>がなぜ「山田一郎」の人生に加担しなければならないのか、と考えることが可能であるはずです。(<子ども>のための哲学に、ここまでの話がありました。)そして現に私はそう思うのです、「確かに私はこいつだが、なんでこいつに加担しなければならないのか」と、そして「同じように『私』とはぐれている人間が他にもいるのではないか」と。
そして、この地点から考えると「順悩み」の人は誰でも「逆悩み」を経て、生きるというゲームに参加するためにあえて「順悩み」、あるいは「逆ー逆悩み」を創造している修行者でありうるではないか、という気がしてきます。
私の周りには、生きていること自体にはなんの価値も感じられず、「生きる理由になるのであれば」と無理にでも欲望を持とうとし、そして挫折しているような「逆悩み」タイプの人が多いように感じています。この「逆悩み」な人々をどう受け止めればよいのでしょう。「欲望を捨てなさい!」「いや、私の悩みは“逆”なんだ。」
紙の冠
長すぎて翌日になってしまいました。ここでいったん、チェスの「白い冠」の比喩の話に戻りたいと思います。
永井 何を説明しようかな。ウィトゲンシュタインのこと言っちゃったから、僕の大好きなチェスの比喩の話をしていいですか? ウィトゲンシュタインの比喩の中で一番好きな比喩があって、それはチェスのゲームの比喩なんです。チェスの駒がこうあるじゃないですか。チェスはいろいろなルールに従って成り立っているわけですが、ところが、ある人がチェスのこの一つの駒の上に、白い紙で冠をかぶせるわけですね。それで、これは、このチェスのルールとは何の関係もないけど、私にとっては特別な意味があるんだというふうに言うわけです。私にとってはこれは特別の意味があるけど、チェスのゲームには関係ないから、対戦相手のあなたは関係なくやっていただいて結構ですよ、というふうに言うんですね。(<仏教3.0>を哲学する)
「<仏教3.0>」の中で語られているように、このチェスに被せる「白い紙製の冠」を<私>に置き換えて考えてみます。
人が生きるというのは、動物や原始人のように鹿を追いかけたり木の実を集めたりといったふうにはいかないので、まずは「生きゲーム」をするという側面があると思います。赤ちゃんがオギャーと生まれて学校に通い始めると何よりもまずこの「生きゲーム」を叩き込む工程が始まります。そして、人をだしぬけに殴ってはいけないとか、お金を稼がなければならないとか、経費を計算して税金の値を減らすとか、そういう「生きゲーム」を学習することでとりあえず「生きる」方法を学びます。
だからどんな人も、チェスを遊ぶことは生きるうえでは避けられません。一方で、私や先の友人などの人種がそうですが、「なんだこれは」「何でこんなことをしなければならないのだ」と圧倒されつつも、「なぜ他の人はこんなゲームに熱中できるのだ」という、純粋な驚きを感じるような人もいます。
今日的には、「生きる意味を持つ」とかいうことは、まずこの盤面(言語ゲーム)の中で起きていることのように思えます。「家族を持ち、その家族のために身を粉にして働く」「美味しいものを食べていい暮らしをするために生きる」「国家のために命をかけて戦う」でもなんでも、この盤面の上で起こっているのに変わりないはずです。そして、先の友人も私も同じように、「どうにか生きる意味を見つけたい」と盤面の上を彷徨います。面白い映画を見るとか、話題の店でパフェを食べるとか、そんな些細なことでも、生きる意味になるのであれば何でも取り入れようとしますが、…
しかし、ここで私たちがやっていることは「ゲームを遊ぶ理由をゲームの盤面の中で見つける」というようなことではないでしょうか。もともとゲームを遊ぶ理由のない人が、「このポーンを取ったら面白くなるかもしれない」「今は大負けしているけど逆転したら楽しくなるかもしれない」と考えるわけですが、そんなことが本当に起こるのでしょうか(いや、起こることもあり得る。問題は、それが起こらない人がいるということ!)。
私が気付いた頃には日本は小さな子どもに「夢」や「希望」を叩き込む国でしたが、夢や希望というのも結局この「盤面の中」のできごとに過ぎないように思えます。それはたしかに生きていなければできないことですが、生きていることそれ自体の意味になるのかは疑問です。
それで、紙の冠の話に戻ります。こうしてチェス・ゲームの盤面から見渡したときにまったく盲点になるのが、ひそかに「紙の冠」を被せて遊んでいる人と、ゲームの成否に関係のない冠を「ないものとして」遊んでいる人が実は混じっているのではないかということです。行われているゲームの内部には白い紙製の冠はありませんから、それを被せている人や被せていない人(厳密にいえば見失っている人?)の差が見つかるはずがありません。それで、「紙製の冠の存在に違和感をおぼえ、揉み消そうとしている人」や、「紙製の冠を得ようと盤面の内部をかけずり回る人」のように逆方向の悩みが展開するかもしれない。当然、行われるチェスのゲームはそのままで。(「先生、紙製の冠が見つからないんです。」「何を言っているんだ患者くん、黒のポーンはここに存在してるじゃないか。」)
チェス・ゲームを遊ぶのに「紙の冠」が必要ないということは、人が「生きゲームをする」ことに関していえば「感情のないゾンビでもゲームに支障はない/むしろ好都合である」というふうに考えられないでしょうか。そして、そのうえで自分をゾンビ化するということは実に一般的なことなのではないでしょうか。
しかし、ここには何かパラドックスが隠れているように思います。第一に、紙の冠のない(ように思われる)ゲームは「遊ぶ意味がない!」。第二に、紙の冠をなくすとなぜだかゲームの盤面ごと消滅する!
こうしてゲームのためにゾンビ化した人間というのは、ちょうど死んだ貝の貝殻のようなもので、中身などとっくに無くなっているのにそれを守る部位だけが残っている状態に似ているのではないでしょうか。以前、そういうマンガを描いたことを思い出しました。それを貼って終わります。
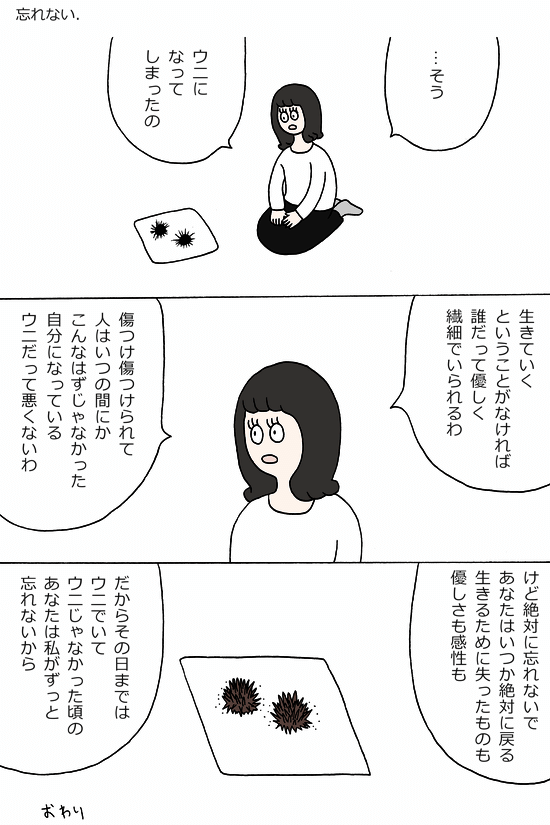
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
