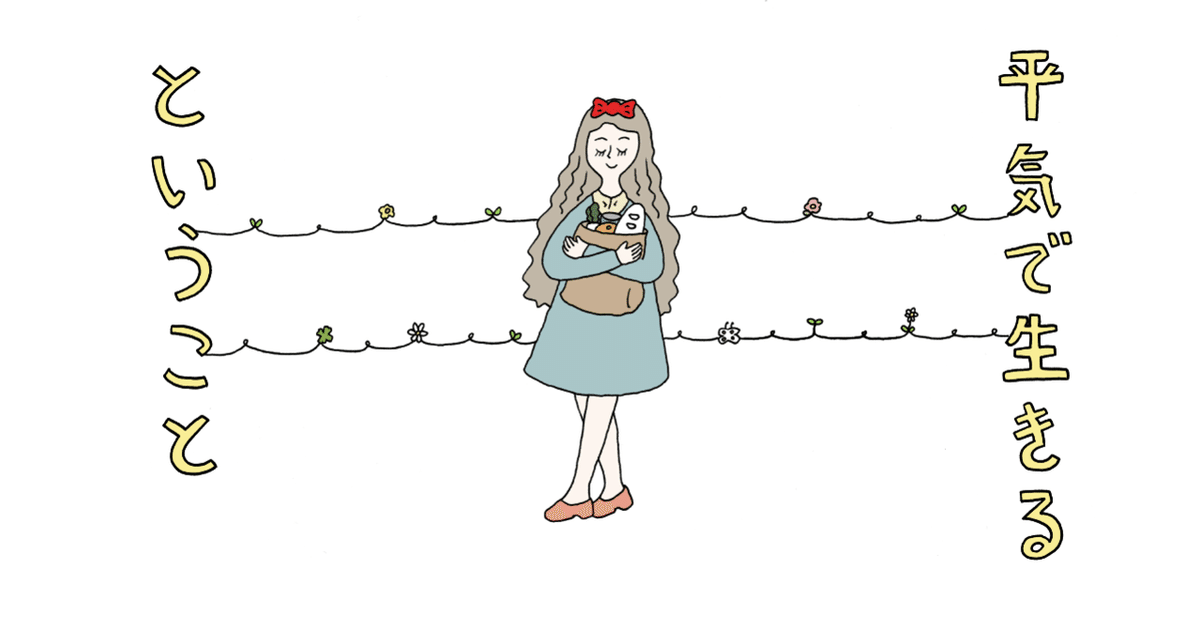
「漠然とした不安」はどこから来るか?
パブロフの犬を思い出してみよう。この犬はまず繰り返し、ベルを鳴らしたあとにえさを与えるという訓練をされる。すると「ベルの後にえさが与えられる」と条件付けを受けたこの犬はやがて、ベルの音を聞くだけで唾液を出すようになる。
人間の場合も、繰り返しによって無意識にまで浸透した条件付けは、それが正しい予期であれ、間違った、役に立たない予感であれ、特定の条件を満たす限り何度でも反復され、その間違った予感は場合によっては耐え難い苦痛、慢性的な恐怖・不安をもたらしたり、生活を困難にする。
特に、乳児や幼児、子ども期のような無力な段階での苦痛は無意識の深淵に刻まれ、条件と「痛みの予感」の関連付けは「ベルとえさ」のように単純明快に解明されるとは限らない。
シュテットバッハ―は乳児が虐待を受ける場合に、精神にどのような損傷が起こりうるかの例を以下のように示している。
損傷の例=赤ん坊は空腹である。赤ん坊は呼び、叫ぶが、母親は気短かな反応しか示さない。急いでほ乳瓶に熱いミルクをつくり、ろくに温度も試さないで、しかめ面をして赤ん坊を乱暴に抱き上げる。赤ん坊は泣きながらいやいや口を開き、熱いミルクを拒もうとして、それに多少は成功する。ミルクが熱すぎると口内の粘膜はただれたり、火傷を負ったりする。口内の熱および痛みに対する許容度は不自然に拡張され、「鍛錬」によって生理学的条件に全く適合しない「慣れ」が生じる。
(「こころの傷は必ず癒える」シュテットバッハー)
この例は誰の目にも虐待であると分かりやすいが、ゆがみのない、素直な欲求や不満の表現が阻害される関係はもっとありふれた形で受け容れられている。たとえば、子どもが何かを欲しがる時や、構ってもらおうとするとき、それを「しつけ」と称して厳しく罰したり非難すること、不安や恐怖をちらつかせて子どもが感情表現を「控える」ように仕向けることも、欲求と充足の正常なサイクルを破壊し得る。そして、欲求を表現することによって充足の代わりに苦痛を与えられつづけた子どもはやがて欲求そのものに恐れを抱くようになる。
痛みと幻滅のために、子どもは不安と罪責感を抱くようになる。子どもの内部にある監視装置はこれ以後、自分の系(筆者注:自己保存系、自分の肉体精神を守ろうとするシステム)は上手く働かなかったと警報を出しつづける。このような子どもは以後、自分の欲求を恐れるようになり、欲求を感じるとひきつけをおこすようになる。子どもの系が、損傷が待っているぞと警報を出すのだ。同時にこの子どもは自分の養育者を恐れるようになるが、同時にその養育者をできる限り理想化しつづける。子どもは生き延びるためにそれが必要なのだ。しかし、同じような経験が繰り返されると、子どもの自己信頼は不信に変じる。こうなると子どもの自信、あらゆる行動の基盤が失われる。こうして健康な生活は不可能になる。何度も自信を傷つけられた子どもは、もはや本当の意味で安らぐことがない。子どもはこれ以後つねに無意識の罪責感を抱いて生き、苦しむ。
(同上、シュテットバッハー)
ここから先は
2,104字
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
