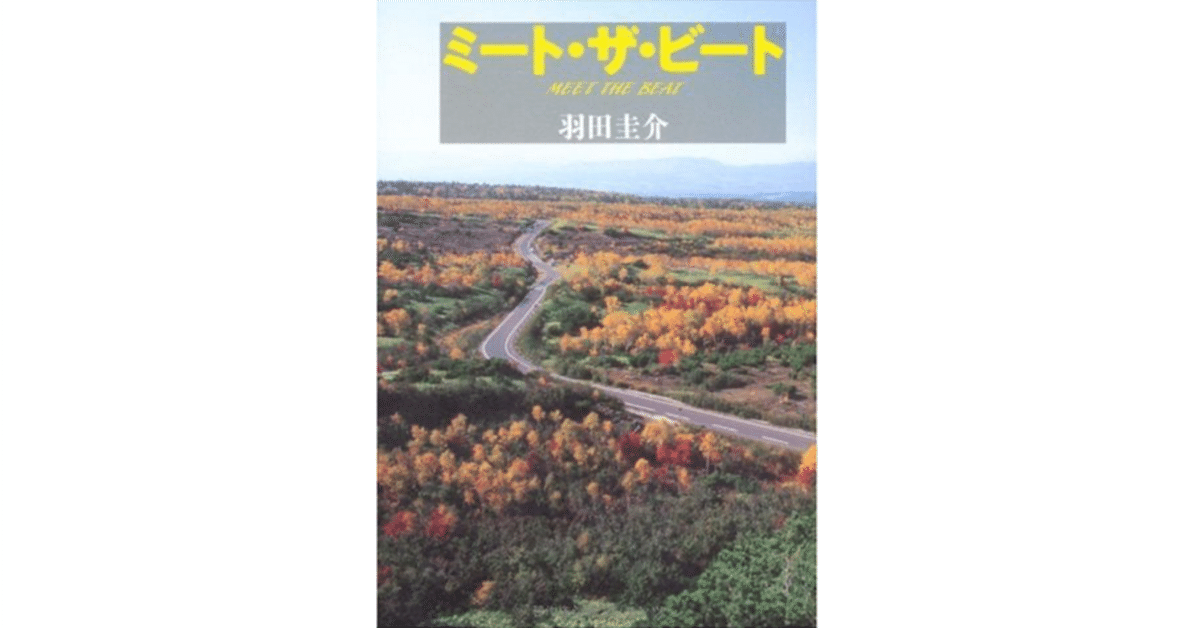
ミート・ザ・ビート 羽田圭介 感想
どこが面白くないのかを考えていくと、小説とはなんだろうという疑問にたどり着く。まずは芥川賞候補時の選評をチェックしておきたい。2009年下半期、第142回は受賞作なし。その時点で羽田氏は24歳であった。
青春=生活路線(池澤夏樹)
もしこれが、改造車で田舎の産業道路を時速百キロで飛ばしているような、疾走感あふれる文体で書かれていたとしたら、もっと本来の魅力を発揮できたのに、と残念に思う。(小川洋子)
論外として最初から選から外された。(石原慎太郎)
主人公が予備校に通う浪人中の若者であるとの設定に無理がある。(黒井千次)
作者の幼さだけでなく、実人生からの体験の少なさが、はからずも小説のなかに露呈されていた。(宮本輝)
この作者が、「文学的」描写と思い込んでいる箇所は、すべて、おおいなる勘違い。どこぞの編集者に入れ知恵されたのではないかと勘ぐりたくもなって来る。全部外すべき。あ、それだと〈すべてのものが、無に返〉っちゃうか。(山田詠美)
問題は、「売春婦っぽい」という言葉の使いようです。そのような流通している「売春婦っぽさ」に対して、いちいち「あれ?」と思いながら書いてゆくのが、小説を書くということなのではないかと思うのです。たとえある種の典型的な登場人物たちを書く場合でも、です。(川上弘美)
もう本当にボロクソ。箸にも棒にもかからないという感じだ。村上龍氏の総評も紹介しておこう。
今回は全般的に低調で、選考会も盛り上がりに欠けた。本来文学は、切実な問いを抱えてサバイバルしようとしている人に向けて、公正な社会と精神の自由の可能性を示し、「その問いと、サバイバルするための努力は間違っていない」というメッセージを物語に織り込んで届けるものだった。ダメな文学は、「切実な問いを抱える必要はない」という「体制的な」メッセージを結果的に送りつけてしまい、テレビのバラエティのような悲惨な媒体に堕してしまう。
諸氏の選評は危機感すら伝わる感情的な表現なのだが、僕は、少し違う視点から考えた。この小説はどこが面白くなかったんだろう、面白くなりそうな感じはしたんだけど、というところをクリアにしたいのだ。
小説とは、物語を文字によって描写したものであるので、まずは物語とは何か、ということをChatGPTに聞いてみた。その回答を自分なりにごく簡単にまとめるとこうなった。
一連の出来事の集まりである。
登場人物が存在する。
テーマ性がある。
起承転結の構造をもつ。
語り口による演出がある。
『ミート・ザ・ビート』においては、登場人物はそこそこ魅力的だし、それ以上に特徴的な語り口が印象的だった。一方、一連の出来事はあるが、それらが羅列されているだけのように感じ、起承転結のような盛り上がり部分や結末部分がなく、小説全体からテーマ性を見出すことができなかった。
それでも何かしらの転換点を探すとするなら、主人公が中古の軽乗用車、ホンダのビートを譲り受けた場面だろう。この自動車は軽なのにオープンカーで、物語の時代設定では既に生産終了でかなりの旧車という異彩を放つアイテムだ。しかし、村上龍氏が指摘するように切実な問いに結びつくことはなく、単にちょっとレアな体験をYoutube動画のネタにしてみた程度にしか機能しない。
動画コンテンツなら暇つぶしにはなるが、物語として見ると、だから何?それがどうした、という感想しかでてこない。いつまで経っても物語が動かず、主人公の自撮りの連続で小説は終わる。
これはつまり、筋が弱いのだ。物語の基本的な構成要素である「筋」という骨組みが弱いため、出来事を時系列で並べた「筋書き」も弱い。だから、読後に、この作品のあらすじは何?と問われても、何も出てこない。タイトルに掛けていうなら、ビートだけの音楽で主旋律がないので、歌心を感じられなかった、というところだろうか。
しかしながら、作者の羽田圭介氏のその後の活躍や、近年の文学界全体の充実ぶりを視野に入れると、この時代の低調ぶりは通過点として必要悪だったのかもしれない、とも思う。かつての、普遍的人間性に直結した物語と、現在の、多様な人間性を取り込んだ物語の、端境期的な空白の時代だったのかもしれない。
単行本には『一丁目一番地』という書き下ろし短編も掲載されている。こちらは主人公が何かを発見し、観察し、思考する、という過程が物語の構造を成していて、コミカルなファミリードラマとして読めるものになっている。
