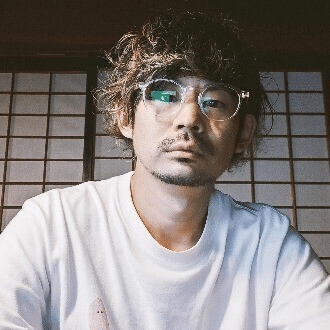猫とくらせば / 手は火だと知る
この手が何をするのか、こいつらはわかっている。
なでる、くすぐる、ときには、悪さをしてたたかれることもあるのだけど、それ以上に、気持ち良くなでてくれる手を信頼してるのか、その手をみつけるとゴロゴロと喉を鳴らしながら猪突猛進で頭をこすりつけてくる。もっとなでろ、と。
机の上でパソコンをいじってるときに、キーボードのうえに乗ってきてまで、手につきまとうこいつらの執念にはあきれてしまうことも多いが、すべてひっくるめて充足を感じる
その手に向かって集まってくる猫たちの様子をみると、何かに似てることを気づく。火、の存在だ。
昔から人間は、寒くなると自然と火を囲むように集まる。それは、生存戦略的なものもあったのだろうけど、その距離感がコミュニケーションをはぐくみ、対話を生み、文化の炎を燃やしてきた。
数年前、石川県の輪島市にある築170年を超える茅葺の家を友人と訪れたことがあった。時期は、冬だったか、雪も降り積もり、えらく寒かったのを覚えている。
そこでは能登でとれた魚をつかった食事を提供していて、昼食をと思ってボクらは立ち寄ったのだけど、飲食スペースが、囲炉裏のそばだった。囲炉裏で冷え切った手をかざしぬくぬくと待っていると、定食がやってくる。体を芯からあたためる味噌汁が死ぬほどうまかったし、「寒い=生きてる」という証拠なのかもな、と思ったほどだった。
また、ボクも含め、数人が大きな囲炉裏を囲んでいたのだが、そういう”囲む暮らし”こそが人間の原点なのだぁ、と感慨深いものがあった。なつかしく、忘れがたい記憶だ。
今住んでる家には、囲炉裏はないのだけど、ときどき人が集まり、食事や麻雀などで卓を囲むことがある。だけど、人がだれも来ない日でもあっても、ボクが手をかざせば、その火に向かって、猫たちが集まってくる。年中、あたたかい暮らしができているようだ。
何も成し遂げず、たいした人間でもないボクの手に、火を感じるように集まってくれるやつらがいる。それを知れただけでも、生き延えてみるもんだなぁ、とつくづく思う。
あ、でも、手を”枕”にしてくるのだけは、遠慮願いたい。
いいなと思ったら応援しよう!