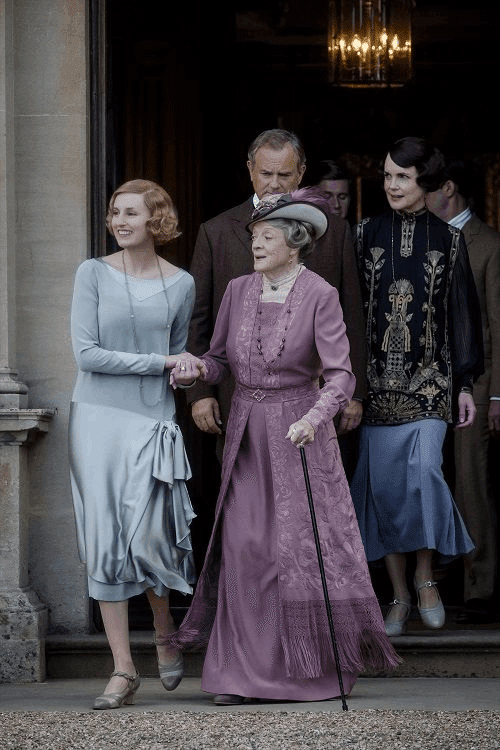「世界史は化学でできている」に出てくる化合物の構造式(3) ベンゼン、アニリン、キニーネ、モーブ
第12章 最初の合成染料
「化学者たちはコールタールにふくまれる成分に興味を持つようになった。ホフマンは、コールタールから化合物ベンゼンを取り出し、さらに化合物「アニリン」を作った」
ベンゼン
ベンゼンは炭素6個、水素6個から得られる6角形の化合物。いわゆる「亀の甲」の語源である。ただし、この構造が解明されたのは1865年、ケクレによる発見まで待たなくてはならない。

アニリン
アニリンはベンゼンにアミノ基NH2がついた化合物。ただしコールタールから「取り出された」化合物の元素分析をホフマンが行って同定したもので、「つくった」のではない。最初にアニリンを合成したのはロシアの化学者ニコライ・ジーニンで、方法は現在でも工業的製法として用いられているニトロベンゼンの還元である(1842年)。

キニーネ
「ホフマンには若い助手パーキンがいた。パーキンはアニリンを使って、高価なマラリアの特効薬キニーネとつくろうとした。」
キナは南米のアンデス山脈に自生する植物であり、原住民のインディオはキナの樹皮を解熱剤として用いていた。マラリアはヨーロッパ人の渡来とともにアメリカに持ち込まれたが、このときにキナ皮にマラリアを治療する効果があることが発見された。1811年にポルトガルの軍医ベルナルディーノ・アントニオ・ゴメスはキナ皮から得られた結晶をシンコニンと命名したが、1820年にフランスの化学者ピエール・ジョセフ・ペルティエとジョセフ・ベイネミ・カヴァントゥはゴメスが単離した結晶が単一物質ではなく、2つの物質、キニーネとシンコニンからなることを発見し、キニーネのみが抗マラリア活性を持つことが分かった。

現代の化学を知る人間から見ると「なぜアニリンからキニーネが作れると思ったのか?」という疑問がわく。パーキンは当時知られていたキニーネの分子式 (C20H24N2O2) を元に、アリルトルイジン (C10H14N) を酸化してやれば合成が可能ではないかと考えたのである(キニーネの立体構造は1944年にウラジミール・プレローグにより確定された)。
モーブ
パーキンはアリルトルイジンをクロム酸で酸化してみたが褐色のタール状混合物が得られただけであった。そこで今度はアニリンを同様の方法で処理し、得られた黒色物質をエタノールに溶かしてみたところ紫色の溶液が得られた。当時のヨーロッパでは紫色の染料は極めて高価な貝紫しか知られていなかったので、パーキンはこの溶液を染料として用いることを考えた。これが世界初の合成染料「モーブ」である。パーキンの使ったアニリンはかなりの量のトルイジンを含んでいたため、構造中にはトルイジンに由来するメチル基がある。

モーブ色は薄紫色でラベンダーに近い。