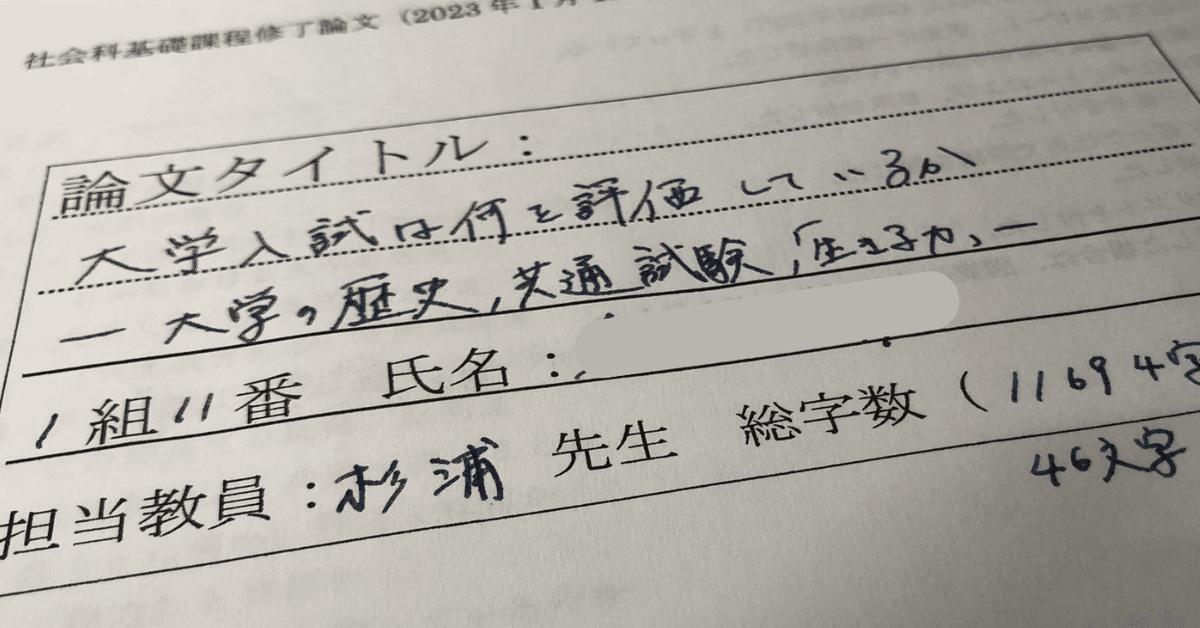
大学入試は何を評価しているか―大学の歴史、共通試験、「生きる力」―
適当なところまでお付き合いください。
― 序章 ―――――――
まず、私が表題のテーマに関心を持った理由を示しておこうと思う。現在、私はいくつかの教科における定期試験について意義を見出せずにいる。特定の教科を批判するつもりはないが、とにかく例文を一言一句覚えることを求める定期試験のどこに勉学面での価値があるのか今一つ理解できないままである。
もちろん、知識がその教科の「能力」となることもあるため、暗記勉強を否定するつもりは毛頭ない。しかし、その「能力」は果たして何のために必要とされているのか。我々が学んだり、力を測ったりする目的は大学入学のためだけではないのではないか。そもそも、大学へは何のために進学するのか、学校で学ぶことだけが「能力」なのかについてすら議論が必要ではないだろうか。
少し話は変わるようだが、文科省の調査によると、日本の18歳人口のうち大学に進学する人の割合は21年度のデータで54.9%にのぼる。また、同年の大学入学共通テスト(以下、共通テストと呼ぶ)の現役志願率は全体の18歳人口のうち44.3%であり、大学に進学する人の多くが共通テストを受験していることがわかる。
本論文では共通テスト、また前身の大学入学者選抜大学入試センター試験(以下、センター試験と呼ぶ)、さらにその前身である国公立大学入試選抜共通第一次学力試験(以下、共通一次と呼ぶ)をまとめて「共通試験」と称することにする。いわゆる個別試験(2次試験)とは別に行われる共通試験が導入されたのは1979年、今から44年前のことである。それ以降の変遷については表1にまとめたが、果たしてこれらの「共通試験」はどういった目的をもって導入されたのか。

こうした疑問、また冒頭で述べた違和感に基づき、本論文は以下の通り展開していくことにする。
第1章では、そもそもはどう誕生したのか、世界についてと日本についての両面についてまとめる。
第2章では、大学入試において共通一次の導入に至った経緯、またその目的、悪影響について見ていこうと思う。
第3章では、大学入試で測られている「能力」とは何かを考える。我々はあのマークシートの試験に何を求められているのか、そしてそれらは正しく測定されるものなのか。
第4章では、大学のこれからの在り方について、そしてこの時代の大学の存在意義を論じたい。
終章では、ここまでの内容を総合し、高等教育はどうあるべきか、その入り口となる入試はこのままで良いのかについて検討することにする。
― 第1章 大学の歴史 ―――――――
― 1-1 大学の発生 ―――
まずは、そもそも大学は何のために存在するものなのかという問いから解決していこうと思う。
これを考えるには、まず大学という組織の歴史を考える必要がある。起源は中世西欧にさかのぼる。この時代はヒトやモノの広域的な往来が活発になってきており、その中で移動する人々は「新しい知識を伝え、集積する最大のメディアであった」[1]。この移動する人々の中で誕生した大学の原型は、特定の場所、そして都市に縛られないため公権力の影響を受けにくかった。これが大学において自由が重要視される根本にあることは確かであろう。
その後、ユニヴァーシティと呼ばれる、出身地によってまとめられた学生組織、「大学団」の編成によって、学生が教師に対して優位に立つ構図が発生した。一方、カレッジと呼ばれる教師組織は、学位授与権を担保として団体化を進めていくことになる。
この後のキリスト教との関係については本論の主軸と合わないため割愛するが、吉見が「大学の第一の死」とする出来事については触れる必要があるだろう。16世紀、大学は宗教改革による対立に対抗することができず、その流れを受け大学内にも分断が生まれてしまうこととなった。
先に述べた移動の自由による大学の自由は薄れ、その地域を統治する君主の権力が強まった。その結果「英国の二つの有名大学は、貴族的な規範を選ばれた若者たちに伝授する訓育機関としての性格を強めていったし、そのような機能を持ち得なかったフランスの大学は、没落への道を歩んでいった」[2]。この時代、大学の誕生時から守られていた根本が一度揺らいでいるのだ。
― 1-2 「アカデミー」と「フンボルト理念」 ―――
この後、現代の三大発明の一つに数えられる「活版印刷」の誕生により、大学ではより効率的な教科書の製本が進むことになる。一方、印刷業を営む者が作家や芸術家と直接つながることにより、現代で言う編集者的な側面を持つようになる。いかに高質な情報を出版し、またその情報を更新するかについて出版社はしのぎを削り、その結果、出版社を中心とする情報ネットワークは大学をしのぐまでに成長した。
大学に関連する組織の形態について言えば、「アカデミー」に触れないわけにはいかないだろう。説明は前掲書より引用する。
これらの新しい知識人が向かったのは人文主義と自然科学であり、それは中世以来のスコラ学[3]とは前提を異にしていた。逆に言えば、スコラ学的な伝統を捨てきれない大学は、新世代の知識人からすれば時代遅れの旧套的な体制と見えがちだった。人文主義者や自然科学者は、「大学」とは異なる、新時代に適応した新しい知の制度が必要と考えていた。
こうして近代初期、人文主義者や自然科学者がしばしば新興の有力者の保護を受けて設立していったのが「アカデミー」であった。[4]
16世紀のうちにイタリアでは400のアカデミーが設立され、17世紀には王立のアカデミーが設立され、大学からアカデミーへの移行はより一層進行した。このまま廃れゆくに見えた大学だが、19世紀に再度「誕生」することになる。
ナショナリズムが高まるこの時代に、「一九世紀初頭のドイツで、研究と教育の一致という『フンボルト理念』に沿うように」[5]復活したのだという。
「フンボルト理念」が、今日の大学における「研究室」システムにつながっているため、少しふれておこうと思う。この理念は、考え、研究することを基本とした学びの形を推奨するものである。いわゆる教科書丸暗記一辺倒の学びではなく、である。
驚愕するのは、フンボルト理念導入前の二十世紀初頭まで、日米の有名大学でも復誦講義、筆記学問、帳合的試験が行われていた。その裏付けとして1909年、ドイツから東京帝国大学に招聘されたHeinrich Waentig教授の興味深い印象記を引用する、「日本の学生はドイツの学生と異なって、常に子供のような試験恐怖病の圧迫の下に置かれている・・・学生の頭の中にあるものは、どうしたら上手く学年末の試験をパスできるか、それだけである。およそ将来のことを考え、様々な勉強をすることは全くない・・・学生達はそれだけ頼れば済むような教科書を指定してくれと、しきりに要求した・・・試験答案に共通する特質は、できる限り自分の独立した判断を避けようとする傾向である・・・暗唱が通用しない試験問題を出すとなんら解答もできない」[6]
こうした新しい大学の形はフランス革命によってもたらされたと、吉見は分析する。フランスと対立関係にあったドイツは、文化面において他国の追従を許さない勢いで成長していく。これらの流れが、19世紀における大学の再興である。
― 1-3 日本における大学の歴史 ―――
ヨーロッパの大学の歴史についてこれ以上語っているとそれだけで紙面が尽きてしまうため、少し時代を進めて、日本における大学の歴史に目を向けることにする。
江戸時代末期の日本において、学問の初動は「翻訳」である。19世紀初頭、幕府は西洋の知識をいち早く取り入れることを目指し、蘭学書を次々に翻訳していく。というのも、この時代は外国、特にロシアとの関係が悪化していた時期であり、いつまでも鎖国によるトラブル回避が続かないことを悟ったためである。1806、07年の「文化露寇」(対ロ)、08年の「フェートン号事件」(対英)、11年の「ゴローニン事件」(対ロ)など枚挙に暇がない。
こうした事件を経た日本では、私塾が主なエリート養成機関となる。大学南校・東校が合併して成立していく帝国大学、後の東京大学などが完成するのは19世紀の終わりである。

右に載せた図1は、前掲書、116頁にある図である。東京大学の成立の経緯自体についてそこまで触れるつもりはないのだが、日本における大学の歴史を考えるうえで「帝国」大学と呼ばれた意味について考える必要があるためだ。先に掲げた苅谷の本の139頁において、森有礼が帝国大学を「インペリアル・ユニヴァーシティ」と呼んでいたことが紹介されている。
「インペリアル」とは、「帝国の」を含意する。森にとっての「皇帝」とは、もちろん「天皇」その人であった。つまり、「インペリアル・ユニヴァーシティ」とは、「帝国」の大学であると同時に「皇帝=天皇」の大学たるべきだった。(中略)自由民権派が標榜する「自由」の知に対し、森らが構想したのはあくまで「天皇」のまなざしの下で編成される「帝国」の知、その牙城としての帝国大学だった。[7]
このように、純粋な知識習得のためではなく、天皇の学校がある、という事実によって外国に対する権威付けの意味が強い「帝国大学」が一時代の日本における大学の形であった。
時代を戦後まで進めよう。様々な種類のあった高等教育機関が、大学に一元化されていく時代である。いわゆる「旧制高校」の廃止、一元化に尽力した南原繁は、東京大学の特徴的なスタイルである「教養学部」について、新たな可能性を賭けていた。
南原が強調したのは、ここに導入される「一般教養」と、旧制高校のエリート文化の中にあった「教養主義」との本質的な違いである。(中略)そこで習得されるべきなのは、従来的な意味での教養知識ではなく、異なる専門分野を総合する力である。[8]
ここに、教養学部の意義が示されていると言えるだろう。学ぶ物事がいわゆる科目、あるいは学部ごと、もっといえば文理に分断されたものではなく、相互に連携していることを会得することが、教養である、ということだ。こうして誕生した新たな「教養主義」は、考え方として日本に普及していくことになる。
ここまで、時間をかけて大学がいかにして発生したかを見てきた。ここから、大学がいかに変革していくのか。その目的はどこにあるのか。
― 第2章 大学入試、共通試験の歴史―――
― 2-1 「大衆教育社会」と共通試験 ―――
序章でも触れたが、日本における大学進学者の割合は年々高まっている。こうした状況を「大衆教育社会」と苅谷は呼ぶ。
大衆教育社会とは、大衆社会(マス・ソサエティ)の特徴と、大衆教育(マス・エデュケーション)をかね備え、さらにそこに「メリトクラシー[9]の大衆化状況」と呼ばれる特徴を加えた社会である、というのが私たちの問題の出発点である。[10]
果たして、大学入試は変遷するこの状況に対応できているのか。全員に一律で「共通試験」を課すことの意義はどこにあるのか。それによる弊害がどこに発生していて、だれがそれを認識しているのか。
これらについて、見ていくことにしようと思う。
― 2-2 共通試験⑴ 進学適性検査/能研テスト ―――
大学入試において、共通試験が最初に本格導入されたのは表1で見た通り1979年の「共通一次」である。というのも、これ以前にも同様の試みはあったためである。まず、GHQによる勧告からはじまった「進学適性検査」。これは、わずか8年で廃止されている。戦時中、特に終戦直前の1944年ごろの学校では、まず間違いなく通常授業が行えていなかった。その結果、特別な勉強の必要のない、この試験が導入されたのである。
その「進適」の廃止の理由として、文科省は以下の5点を挙げている。
(1)進適のための準備が激しくなり,受験者は学科試験の準備と二重の負担となり,高校教育に支障の生ずる恐れがあるとされたこと。(2)苦労して出した進適の成績を大学は積極的に利用していないということ。(3)進適実施の予算,とくに謝金が少なく実施上の困難が生じたこと。(4)進適の科学的検討の資料が当時発表されていなかったこと。(5)国立大学協会,高等学校長協会からそれぞれ中止の要望があったこと。
これらについて、腰越は以下の通り分析している[11]。
まず、⑶、⑷については肯定できる。また、そもそも作問に膨大なエネルギーをかけることが現実的でないという点についても理解ができる。しかし、進適が廃止されたところで学生の負担が減ったとは言い切れない。なぜなら、有名大学が学生の二段階選抜を行うようになったためである。
また、(2)について、72校の国公立大学のうち32校が利用していたことを考えればそこまで少ないとも言えず、また私立大学が進適を利用していなかったとしても、なぜ信用されなかったのが不明である。
さらに、(5)について。全国高等学校長協会側から提出された意見書において「進適の成績と高校における教科成績,または入試の学科成績との相関度は極めて低く,知的能力測定の目的に沿い得ない」とされているが、そもそも進適と学科試験は求める能力が異なるので、むしろ実施の必要性があるのではないか。
ここまでを見てわかるのは、共通一次以前の共通試験において、問題点が高校、大学の双方から指摘されていたこと、ただその問題点についてもいまだ議論の余地がある状態であった、ということである。
こののちに、学力テスト、適性能力テスト(2年目からは職業適性テストも追加)のセットで実施された「能研テスト」(いわゆる外部試験である)については、高校の教員、大学、大学生の猛反発に遭い、64年に始まったこのテストの利用は68年にテスト自体の廃止という形で早々に幕を下ろすこととなった。
― 2-3 この時点での反発、疑問点 ―――
能研テストの実施下において、大河内一男・東大総長が「入試は全国一本にしぼるべきではなく、大学の自主性を活かすべきだ」と発言している[12]。これをはじめとして、東大、また京大もこうした共通試験の導入には反対の立場を取り続けていた。「難問・奇問」として批判される入試を課していたのは彼らも例外ではなかったから、対立構造となるのはある意味自明である。
「難問・奇問」とは具体的にはどういうことなのか。文科省の資料によれば、「高等学校教育の程度や範囲を超えたいわゆる難問・奇問」[13]とある。なるほど、高校での履修内容を超えるものは排除されるべきという考えである。この場合、確かに大学の個別試験以前に共通試験を課し、大学に共通試験を利用させることで半ば強制的に高校範囲の試験を行える。
しかし、果たして難問・奇問は排除できるのであろうか。二次試験が残っている以上、高校範囲を超えた出題の余地は残されているし、実際、文科省も「各大学の第二次試験の改善が必ずしも十分でな」かった、としている13。
さらに、これらによって大学の序列化が進んだ、というのは有名な指摘である。86年、国立大学協会入試改善特別委員会は受験生の最終的な志望校決定に「受験産業が介入し、また、高等学校の偏差値中心的な進路指導の傾向の増大とも相まって、受験生が『合格可能な大学』に割り振られる事態となっていた」と指摘している。
― 2-4 共通試験⑵ 共通一次・まとめ ―――
実際、序列化は共通試験導入以前の49年導入「一期校・二期校」制度の導入から始まっていたし、これを解消するために共通試験が必要とされていた。しかし、それらが成功しなかったのもまた事実だ。もっと言えば、国立大学の受験日程が1日に制限されたことにより私立、公立大学との併願が促進された。これにより受験業界は併願プランを受験生に提示し始め、結果的にそうした大学の「偏差値」が明らかになり、今まで一期校、二期校、私立の順で固定されていた序列が崩れ始めることになる。
こうした状況を経て、「共通一次」が導入されることになる。この時の状況について、昭和61年の国立大学協会入試改善特別委員会の資料[14]を基に整理する。
まず、旧二期校において⑴スケジュールに無理がある⑵志願者数は多いが実際に受験する受験生は一期で満足な結果を得られなかった場合のみであり差が大きく試験準備の問題があったこと⑶「旧二期コンプレックス」が教育上の問題となっていた―――という問題点が指摘されている。そのうえで、国立大学協会は以下の目的・理念を掲げた。
大学入学者の選抜は、基本的には、入学志願者の高等学校における主として必修科目による基礎的な学習の達成の程度を評価することによって、大学教育に必要な基礎的能力・適性を判定するとともに、高等学校における個人の適性・能力に応じて選択した選択科目による学習の達成の程度を検査することによって、志望する大学・学部の目的、特色、専門分野等に応じて重視される能力・適性の程度を判定するなど、学力検査の成績、調査書の内容、実技検査の成績、面接の結果、小論文の評価等の多元的な資料によって、入学定員を考慮しつつ、当該大学・学部の教育に、より適する者を決定するために実施されるべきものである。14
この理念のもと、共通一次が導入されることになった。しかし、結果として問題点も残っている。先の資料では、いわゆる「輪切り現象」、「大学の序列化」、「受験生の負担感」、「受験教科・科目の画一性」、「偏差値の重視」が挙げられている。先に挙げた前身の際にも指摘されていた項目が残っているように見えるが、これらについて国立大学協会はこう返答している。
これらについては、そのすべてが共通第1次学力試験そのものから生じたというより、むしろ、現代の社会的背景の中で派生したものであると思われる。しかし、共通第1次学力試験の構想段階で、これらの問題が生じ得る社会的側面について予測し、かつ、その対応についても検討を行ったにもかかわらず、結果的にはその予測をこえた弊害が生じてきたことにも関連するといえるのではなかろうかとも考えられ14
「社会的背景の中で派生した」―――。果たして、その社会的背景とは何なのか。第2章では、大学入試における共通試験の導入経緯、そしてそのデメリットについてまとめてきた。次の第3章では、いよいよ入試を取り巻く社会環境について考察する。
― 第3章 能力を正しく評価するとは何か ―
― 3-1 「能力」とは何か ―――
ここまで、大学、大学入試のシステムがどう変化してきたのかを見てきた。ここからは、さらに広い視点で「大学入試」をとらえることにする。具体的には、大学入試で測られるべき「能力」とは何か、という点だ。
齋藤は、課題を解決するために必要な思考力・表現力・判断力を中心とした学力を「新しい学力」と呼ぶ[15]。それらが求められる要因を、⑴現代社会に生きる以上、「変化の中に生きる社会的存在」として生きることが必然であるため⑵グローバル化する社会に対応する必要があるため―――の2つだと分析している。そのうえで、「問題解決型学力」を、問題を理解する意欲、主体性などの点で「伝統的学力」とは全く異なるものと定義する。
本田は、近年の社会状況を「ハイパー・メリトクラシー」と形容する。そのうえで「意欲や独創性、対人能力やネットワーク形成力、問題解決能力などの、柔軟で個人の人格や情動の深い部分に根差した諸能力」を指す言葉として「ポスト近代型能力」という言葉を用いている[16]。
これらの「能力」には聞き覚えがある。文科省が共通テストの導入に際し、今後求められるとしていた能力、あるいは「生きる力」として掲げられているものである。図3は1980~90年代における「学力」の意味変容プロセスである。もともと学力と呼ばれるものが更新され、拡張されていっていることがわかる。
「生きる力」を定義こそしたものの、実際に高校で教える内容がわかりやすく変わることはないし、当然元の教育を否定したわけでもない。では、大学入試において測られている「能力」とは何なのか。
― 3-2 大学入試は何を測っているのか ―――
第2章において確認した通り、共通試験は高等学校における履修が問題なく完了しているかどうかの確認に用いられる。では、二次試験は何を測っているのか。基本的には、「学力」が大学の求めるレベルに達しているか否かを判断することになる。「学力」の内容は、基本的にいつの時代も変わらない。至極当然のことかのように書いたが、「変わっていない」のである。
この理由について、山口は「それ(大学入試)が非常によくできたシステムである」からだと指摘する[17]。「よさ」とは教育とスクリーニングの2点についてであり、スクリーニングに関しては偏差値付けにより厳密に序列化されていてスクリーニングには利用しやすいし、また教育面に関しても世界的な調査に照らしてアメリカなどに比べてもレベルが高いことが知られている。
一方、「近年の教育社会学では、大学の主要な社会的機能は教育(人的資本形成)よりはむしろスクリーニングだというのが定説」[18]なのだという。つまり、入学した学生のうち多くが卒業できる日本の大学の役割は、入試が終わった時点で8割方完了しているのである。これの是非についてはここで論じないことにするが、こうなると尚更入試の重要度が高まってくる。
― 3-3 生きる力を評価する ―――
3-1と3-2の内容をまとめる。近年、大学入試において求められる力が「変化」してはいない。それは試験問題を見れば明らかである。いや、もっと正確に言えば、単に「増えた」のである。大学の主要な社会的機能である、学生を就職の場に出すためのスクリーニング。これに対して重要な役割を担う入試は、とても「生きる力」を評価できるペーパーテストではない。いかに「学力」が身についているかを調べ、さらに国から求められる教科の扱いが増えた、といった程度である。
では、「生きる力」を評価するにはどうするべきなのか。山口は、前掲書で以下の通り述べている。
「生きる力」や「人間力」といった教育目標は大変結構なものだが、そうした教育は評価との相性が非常によくないのである。だからといって、政府にも財界にも、入試そのものをやめようという発想はないようである。彼らの本心が「競争に勝ち抜くエリートの選抜」だとすれば、それは当然のことである。
「人間力」なる概念を提唱した経済財政諮問会議の二〇〇二年答申では、大学改革も「人間力戦略」として位置づけられているが、そこで主張されていることは「国立大学の法人化」「能力主義の徹底」など、「人間力」と矛盾する競争主義的なことばかりである。要するに、近年の教育改革は、初等中等段階の個性重視と高等教育の競争重視という、相矛盾する方向にすすめられているのだ。その矛盾のしわ寄せは、両者を接続する大学入試に集中することになる。[19]
生きる力は、評価することとの相性が悪いのだという。こうした能力を身に着けさせることが教育現場に求められていても、実際それらは大学入試では問われることはない。というか、それ以降の教育段階で扱われることは少ない。大学入試に活かされない教育に時間を割くほど今の高校生は暇ではないのである。結果、これらの能力が国の期待通りに教育へ取り入れられることはないのである。
もし、これらが測れたとして、新しい学力、生きる力を測るため、として今行われている入試改革は無意味であるのか。
― 第4章 大学はどうあるべきか ――――
第3章では、現代において新たな「能力」が求められる社会になっていること、それに入試、ひいては大学というもの自体が現在の状況下で対応する余裕はないことを示した。このような状況下で、今の大学に対して「受験勉強」「就職予備校」以上の意味を見出すことはできるのだろうか。この論文の最後に、それを検討していくことにする。
冒頭で、私は受験勉強に意義を見出せない、という趣旨の主張をした。そして、「受験勉強」が上手、効率的に指示された勉強をこなすことができる能力が「学力」として評価される現状に違和感を抱いている。これに対する一つの答えが、以下の引用である。
学校で獲得される文化は、どんな階層文化からもかけ離れた、「中立」な、(そしてあまり価値がない)文化であるというニュアンスが含まれていた。そして、どのような階層や集団のものでもない、学校がつくりだした文化を、より早く、効率的に身に着けたものが学歴社会の勝者となった。
しかしそれだからこそ、これら勝者への称賛は、努力や勤勉、あるいは「頭のよさ」を讃えるものではあっても、「教養」や「学問」を身に着けた者への称賛とは明らかに異なる種類のものとなった。[20]
現在、世間一般に「学力」といわれるものは、「教養」や「学問」とは区別されるものだという。
おそらく、今後も入試で問われる「学力」が大きく変わることはないだろう。大学に求められる「スクリーニング」の機能のために、1900年代から指摘されている暗記型の試験は変化できない。どれだけ「新しい学力」「生きる力」が必要だと謳っても、本質が変わらない限りすべてが空回りしているように見えてしまうのだ。
しかし、大学が教えているのは「教養」や「学問」であって、入試で求められている「学力」ではない。もっと言えば、いま世間で求められている能力はあまりに多様化してきており、学校で「生きる力」を教えられるという考えに無理がある。山口はこう言う。
たしかに教育は大切だ(中略)が、「誰でも教育を受ければ何でもできるようになる」わけがないのである。そのことを忘れると、教育に対する要求過剰になる。(中略)この本では、政府の審議会や財界の提言などを何度も参照してきたが、その中に大学生や高校生の視点がほとんどまったく入っていないことにお気づきになっただろうか。[21]
― 終章 ―――――――
共通試験の導入による影響や教育評価論について論じるつもりで書き始めたこの論文だが、かなり広い範囲に手を出してしまった。今一度冒頭の問いに立ち返ることにする。「『能力』は果たして何のために必要とされているのか」「大学へは何のために進学するのか」の2点である。
まず、これからの社会に必要とされている「能力」は評価し、また比較することが難しいことは確認した通りである。社会、会社、あるいは今後の日本の発展のためには必要不可欠であるが、これが教育の場に持ち込まれることが適切なのかどうかを再検討する必要がある。私は、元々こうした能力をもっと評価した大学入試制度が必要であると考えていたが、この論文を書き終えた今、もはやその能力を中途半端に測ろうとするべきではないと思う。その代わりに、大学や高校とは別にそうした能力を育て、社会性を伸ばす場が必要であると考える。
では、大学に進学する理由は何か。受験用の「学力」や「新しい力」とは明確に区別される「教養」を学ぶためである。ここでいう教養は、第1章でふれた「異なる専門分野を総合する力」でもあり、また専門分野に関する知識でもある。こうした場は高校まででは圧倒的に不足しているし、社会に出た後にそれらを学ぶ余裕はない。
これらの教養はなぜ必要か。社会にとっての必要性はここでは論じない。物事は相互に深く関わっていることを学び、そして自分が良いと思う生き方で生きるうえで使うかもしれない学問を修める。もちろんこれ以外にも理由はあるが、主たる目的はこれでなければならないのではないか、とこの論文を書いた私は考えてしまうのである。
― 参考文献 ―――――――
苅谷剛彦(1995)『大衆教育社会のゆくえ 学歴主義と平等神話の戦後史』中央公論新社
齋藤孝(2016)『新しい学力』岩波書店
本田由紀(2005)『多元化する「能力」と日本社会 ハイパー・メリトクラシー化のなかで』NTT出版
本田由紀(2020)『教育は何を評価してきたのか』岩波書店
山口裕之(2017)『「大学改革」という病 学問の自由・財政基盤・競争主義から検証する』明石書店
吉見俊哉(2011)『大学とは何か』岩波書店
吉見俊哉(2021)『大学は何処へ 未来への設計』岩波書店
川崎医科大学 免疫腫瘍学 寄附講座 岡三喜男「現代大学の歴史と理念を振り返る」https://m.kawasaki-m.ac.jp/immuno-oncol/furikaeru.html(2023年1月9日閲覧)
腰越滋(1993)「進学適性検査の廃止と日本人の階層組織化の規範―適性か努力か―」https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds1951/52/0/52_0_178/_pdf/-char/ja(2023年1月13日閲覧)
佐々木享(発行年不明)「能研テスト――新たな共通試験」https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/16025/files/511.pdf(2023年1月13日閲覧)
統計情報リサーチ「大学進学率の推移」https://statresearch.jp/school/university/students_5.html(2023年1月11日閲覧)
e-start「学校基本調査」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tclass1=000001172319&tclass2=000001172320&tclass3=000001172415&tclass4=000001172419&tclass5=000001172420&stat_infid=000032264972(2023年1月13日閲覧)
UTokyoRepository「東京大学百年史 通史3」https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/53866(2023年1月11日閲覧)
[1] 吉見 2011、26頁。[2] 前掲書、65頁。[3] 中世ヨーロッパで教えられていた哲学。聖書などをテキストとして、神学を体系化することを目的とする。スコラはschoolの語源。(Webサイト『Wikipedia』『世界史の窓』)[4] 前掲書、75頁。[5] 前掲書、78頁。[6] 岡 2009、1頁。*吉見 前掲書、116頁。[7] 前掲書、139頁。[8] 前掲書、192頁。[9] 業績を基準に、報酬の分配や社会的な地位が決まるしくみのこと。能力主義。業績主義。[10] 苅谷 1995、24頁。[11] 腰越 1993、180頁。*統計情報リサーチ「大学進学率の推移」[12] 佐々木 発行年不明、3頁。[13] 文部科学省「学制百二十年史」より[14] 国立大学協会入試改善特別委員会「共通第1次学力試験のあり方をめぐって」より[15] 齋藤 2016、1頁。[16] 本田 2005、ⅱ頁。[17] 山口、2017 157頁。[18] 前掲書、158頁。[19] 山口 前掲書、173頁。[20] 苅谷 前掲書、142頁。[21] 山口 前掲書、278頁。
〈あとがき〉
論理構成~~~!!
どこいった~~~!
(本論文は、高1修士論文として提出し、討論部誌にも掲載することを検討していましたが後半部分がかなり雑なことになってしまいました、筆者はもう投げやりになっています)
最後までお読みいただきありがとうございました。
※本論の無断転載・複写は著作権法上認められる例外を除き、認められていません。引用は用法用量を守って正しく行いましょう。
