
ツルガキ!ロミー&アランの軌跡⑥『シュニッツラーさま、かく語りき』

もう第6回か。まだ二人の出会いの映画やっちゅうのに。

まあ、いつものことだから…

ここまでをダイジェストで紹介しよう。
全ては僕がロミー・シュナイダーとアラン・ドロンの共演作『恋ひとすじに』(原題:CHRISTINE、’58)を観たことから始まった。
はちきれんばかりの二人の瑞々しさに、僕はとっても感動した。青春アイドル映画の傑作と言っていい。
Wikiで調べてみると、なんでも1933年にロミーの母マグダが主演した映画『恋愛三昧(原題:Liebelei)』のリメイクらしいことが書かれていた。
僕は早速そっちも観てみた。
母マグダ版は、娘ロミー版よりも悲劇のヒロイン度が高目の物語だった。
幸薄そうな感じって言うのかな。
ロミーとアランはキラキラし過ぎてて、まるで「お姫様と王子様」みたいな感じだったけど、母マグダのクリスティーネは、なんだか死を予感させるムードが漂っていた。映画自体も全編にわたってそういう雰囲気だ。

ロミー版のオーディションでは、ウォルター・スコットの詩にシューベルトが曲をつけた『アヴェマリア』やったな。
「ああマリア様、あなたの慈悲深い心で男たちの戦いをやめさせてください…」っちゅう内容の歌詞や。
映画の元ネタでもあるスコットの戯曲『湖上の美人』でヒロインのエレンによって歌われるシーンと、クリスティーネのオーディションシーンは、「愛する人が戦いで死んでしまわないように、祈るような思いで歌う」という状況が共通しとる。
そやけどオカン版は違う歌で、しかもドイツ語やけど、これはなんて歌うてるんや?

母マグダ版は、ブラームスのドイツ民謡集からの『お姉さん』という曲だ。
「お姉さん、そろそろ帰ろうよ」って言う弟に対し、姉は「まだこの人と踊っていたいの」と答える。
「お姉さん、もうすぐ夜が明けてしまうよ」と弟が言うと、姉は「今帰ったら、この人はきっと違う女と踊ってしまうわ」と答える。
「お姉さん、顔が冷たいよ。どうしたの?」って弟が尋ねると、姉は「きっと朝露のせいね」と答える。
そしてついに倒れたまま動かなくなった姉がこう呟く。
「死んだら天国に行くって聞いたけど違うみたいね。でも土の下のベッドも心地よさそう…」

ふぁ!?どうゆうこっちゃ?

つまり、彼女が踊っていた相手は死神で、その踊りは「この世でのラストダンス」だったってわけだ。
中世ヨーロッパでは、死の間際に死神がやって来て「死の舞踏」を一緒に踊るという土着信仰があったんだね。
母マグダが演じるクリスティーヌにとって、初めての恋は「死の舞踏」だった…というわけなんだ。

へえ~!確かにロミー版とはちょっと様子が違うね。

死神とのラストダンスゆうたら、これを忘れちゃあかん。

だね。
ロミーの当たり役シシィことオーストリア皇后エリザベスを主人公にしたミュージカル『エリザベート』では、この死神とのラストダンスをめぐって物語が進行していくんだったね。
メルシーボークー、ナンボク。
さて、娘ロミー版と母マグダ版の違いが気になった僕は、原作とされているアルトゥール・シュニッツラーの『Liebelei』を読んでみたくなった。どっちが原作に近いのか確かめたくなったんだね。
日本語訳のものを探してみたら、もうずいぶん昔に絶版となったままだった。でも、かろうじてアマゾンのキンドル版で発見できたんだ。
大正2年に出版された森鷗外の翻訳によるものだ。
かの鷗外が翻訳するくらいの著名な作品なのに、なんでその後は絶版になったままで、他の人の翻訳版なんかも出なかったんだろう…?、なんてことをちょっと思いながら、早速僕は購入して読み始めた。
すると…

途中でページが飛んどった。
16ページ分も。

その通り。
ページ総数252の作品なんだけど、空白部分は225~240ページ…
つまり…
話が盛り上がって来てクライマックスへ突入する最も大事な場面が、ごっそりと抜け落ちていたってわけなんだ!

これは落ち込む…

しかも、僕にとってこれが電子書籍で読む初めての小説だったんだ。初体験が中折れだなんて、あんまりだよね!

そうゆうのは「中折れ」とは言わん。「落丁」や。

どうしても「空白の16ページ」が気になった僕は、原書をあたることにした。でもドイツ語が読めないんで、英語版をみながらドイツ語版と比べてみて「もともと何が書かれていたのか」を確かめようと考えたんだ。
しかし読み進めていくうちに、僕は大変な事実を知ることになった…

窓から飛び降りるのがクリスティーネじゃなくて、お父さんだったってやつだね…

そんで物語の主役がそもそもクリスティーネやのうてオトンやったっちゅうやつやな…

よく覚えてたね。その通りなんだ。
以前に「三作品における相違点」の表を作ったから、もう一度ここで上げておこう。


英語版とドイツ語版を読み進めるにつれ、鷗外の翻訳版では見過ごされていたことに僕は気付くことになる。
「あれ?この戯曲は”愛の崇高さ”や”運命のいたずら”なんかを描いたものじゃないぞ…。ほとんどサイコホラーじゃんか…」って。
しかしなぜ鷗外ともあろう人が、こんな重要な物語の基本構造を見誤ったんだろう?
だって、最初の登場人物紹介のところで「何かおかしいな」って思うはずだ。僕でさえ違和感を覚えたのに。

どないなってんねん?

冒頭の登場人物紹介はこうなっていた。
ちなみにドイツ語版も同じで、鴎外は順番も内容もそのままの形で訳している。
ハンス・ワイリング…ヨゼフスタット座のヴァイオリン弾き
クリスチイネ…その娘
ミイチイ…流行服飾女工
カタリナ…靴足袋造の妻
リナ…カタリナの娘、9歳
フリッツ…学生
テオドル…学生
紳士

アラン・ドロンが演じたフリッツの説明が、ただ「学生」だけって…
なんか脇役みたい…
どう見てもクリスチイネとフリッツが主役の恋物語には見えないよね…

ふつうこれ見たら、オトンが主役やと思うやろ…
しかも映画でフリッツがハマっとった、お色気ムンムンの男爵夫人もおらん。

そうなんだ。原作ではフリッツとテオドルの会話に出てくるだけなんだよね。
しかも随分と可哀想なこと言われる役。

かわいそうなこと?

そう。
物語の冒頭シーンで、フリッツはテオにこんな風に話す。
「最近、あの女がウザいこと言うんで困ってるんだ。誰かに尾行されてるとか、窓の外から誰かに見られてるとか。挙句の果てには、夫にバレたからもう死ぬしかない!とかわめきだす始末でね…」

性格わりーな。

それに対してテオはこんな風に忠告する。
「お前の良くないところは、そうやって相手をいちいち本気にさせることだ。8月からは軍隊生活なんだから、残された時間をもっと楽しもうぜ。この前紹介したあの町娘なんかはどうだ?遊ぶ相手ってのは、ああいう尻も頭も軽いのに限る。」

テオさんもひどい…

社会的エリート階級の「学士様」と一般庶民の町娘の関係はこんなもんだよ。ウィーンの町娘たちも、それを承知でひと時の夢にひたっていた。
学生たちは、いずれ上司やお偉いさんの娘と結婚しなければならない。箱入り無菌状態で育てられたツマラナイ女性たちだ。だからそれまでは後腐れのない町娘たちと遊んでおこうってわけだ。
日本でも似たようなものだったよね?今でもそうなのかもだけど。

ロミー&アランの映画『恋ひとすじに』でも、その名残らしきシーンがあったな。
お偉方の娘たちとの舞踏会のシーンや。
若い将校連中は、自身の出世のため、そして所属部隊のために、いつか彼女たちと結婚せなあかん。でも見るからにツマラン女ばかりやった。だから青年将校たちは嫌々舞踏会に参加しとるんやったな。もし欠席すると、彼らの上司の立場がマズくなる。

そう。そしてそのツマラナイ箱入り娘たちは、青年将校との結婚で「性に目覚める」ことになる。でも、出産して子育てが一段落した頃には、夫はあちこちに女を作っていて相手にもしてくれない。だから”元”箱入り娘の妻たちは、若い男に走るようになる。仮面舞踏会なんかに頻繁に出入りしてね。映画『恋ひとすじに』でも、男爵夫人は仮面舞踏会でアラン・ドロン演じるウブな青年将校フランツをゲットするんだよね。

せやったな。
しかも男爵がフランツに決闘を申し込んだ理由は「妻の浮気相手だから」ではなく、「周りにバレるような浮気をされて名誉を傷つけられたから」やった。

そうだったね。
男爵自身が「遊ぶなら人妻に限るぞ」ってフランツにアドバイスしてたくらいだから。
それが「世紀末ウィーン」の日常風景だったんだね。町娘たちの奔放な性、上流婦人たちの貪欲な性、そして男たちの余りにも自分勝手で呑気過ぎる性。
でもそれを社会は「無いもの」としていた。みんながやっていたことなのに、表向きはそれを「ふしだらなこと」で「あってはならないもの」としていたんだ。

オーストリア=ハンガリー二重帝国は「自由主義・文化の多様性」っちゅう理想を掲げとったんやないんか?

多民族・多文化共生国家維持のために表向きはね。でも実際は全然そうではなかった。
女性には相変わらず強い貞淑観念が求められた。処女性だね。かつての日本同様、婚前交渉をもった女性は「傷もの」とされ、婚外交渉をもった女性は「ふしだら」とされた。とうぜん中絶も「罪」とされていた。
男は何にも言われないのにね。

ひどいハナシやな。

政治的には「自由&多様性」が叫ばれ、社会的には「貞操&純潔」が重要視されていた。
世紀末ウィーンでは、この「ギャップ」に苦しむ人が急増したんだね。
だから精神分析のフロイトが現れ、美術界にはクリムトが現れた。そして、医師でもあり作家でもあるシュニッツラーが現れたんだ。

フロイトはわかるけど、クリムトやシュニッツラーは「ギャップ」とどう関係があるの?
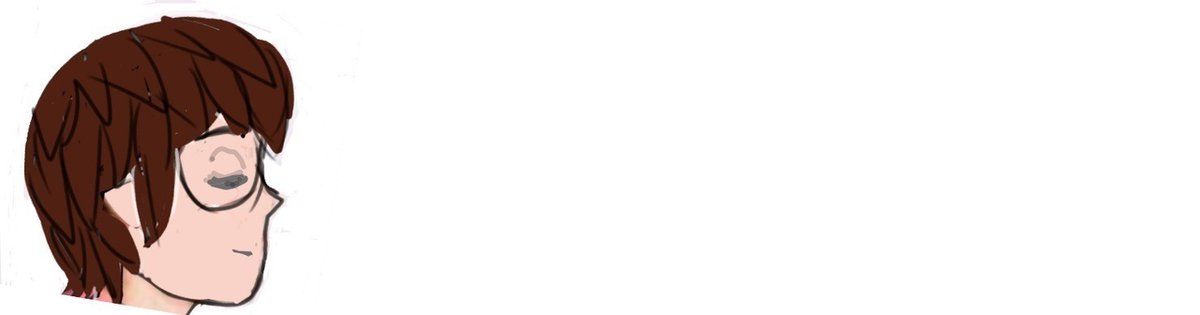
新進気鋭の美術家だった若き日のクリムトは、当時ウィーンで最も権威のあったブルグ劇場の装飾を任されることになった。

第2回で紹介した劇場やな。女帝マリア・テレジアが作って、シュニッツラーの戯曲も多く上演され、ロミー・シュナイダーの婆ちゃんが専属女優やった由緒ある劇場や。

クリムトの素晴らしい手腕に皇帝フランツ・ヨーゼフは感動し、クリムトを国民的芸術家として称えようと最高賞である皇帝賞を授与した。
このサイトにその作品群が紹介されているよ。
そして今度は国家の最高学府ウィーン大学の講堂天井壁画を依頼された。
でもその作風が問題視されてね。「人間理性の否定だ!わいせつだ!」と非難されたんだ。
クリムトはショックを受けた。そして「タテマエ的な芸術」や「重荷となる肩書」を嫌うようになった。国家が求める”お抱え絵師”になることは、表現者としての死を意味するものだったからね。
彼の芸術における最大の関心事は「性がもつダイナミズム」だ。だから彼は権威に囲われることを避け、ひたすら「リアルな性」を描くことに没頭した。
代表作である『ダナエ』とか、一連の「自慰スケッチ」はその表れでもある。

せやったんか。日本では「接吻の絵の人」やさかいな。

そしてアルトゥール・シュニッツラーも同じような立場だった。
彼はユダヤ系キリスト教徒の医師の家庭に生まれた。ウィ―ン大学医学部で学び、父と同じ咽喉科の医師となった。このお父さんが著名な医師でね、国際医学雑誌を創刊したり、当時の学会のリーダーみたいな人だったんだ。
もちろんアルトゥール・シュニッツラーも医学書を書いている。タイトルは『機能的失声症および催眠と暗示によるその治療について』だ。

催眠…?
暗示による治療?

その頃、医学界や上流階級はフロイトブームに沸いていたからね。
シュニッツラーはフロイトに強く影響され、作品の中だけでなく、治療にも催眠療法を取り入れた。

タルコフスキーの『鏡』の冒頭シーンみたいなやつか?

まさにあれだ。
国民国家の誕生は、中世以来ほぼ固定化されていた身分制度を崩壊させた。これまで一部の特権階級だけのものだったことが、一般市民にも開放されるようになったんだ。
そして「人間理性と科学の進歩で、ついに人類は幸福な社会を実現させる!」なんてことが声高に叫ばれていた。
でも実際はそうではなかった。激しい社会変動は人々の心の中に、これまでの土着文化やキリスト教をベースにした価値観と、政治・経済から導き出される新しい価値観の対立を生じさせることになった。国民国家の市民にとって「性」は個人に属する基本的権利のはずなんだけど、社会道徳はそれを許さなかったんだね。
親が子に対し性的なものを排除して厳しく育てようとすればするほど、子は実世界とのギャップで苦しむようになってきた。

なるほどな。それも今でもありそうなハナシや。

シュニッツラーは、こんなふうに世間の中で抑圧され、時に”病い”にも至る人間の葛藤や欺瞞を描き続けたんだ。
タブーとされていたことにも鋭く切り込んだため、何度も上演禁止に追い込まれたりもした。ウィーンが位置する南ドイツ語圏はカトリックの影響が強かったからね。だから一部の作品は、ベルリンなど北ドイツ語圏で上演されることが多かった。
彼は森鷗外同様に軍医でもあったんだけど、オーストリア軍の旧態依然のしきたりを批判したため、軍での階級を剥奪されてしまう。そしてウィーン大学医学部からも追放され、医師としての道も断たれてしまったんだ。

そこらへんは鷗外とは全く違うな。

そしてシュニッツラーは「婚前交渉」で子をもうけてから妻と正式に結婚したため、多数派であるキリスト教保守層から批判を受けることになる。
彼はユダヤ系でもあったんで、この時代のウィーンでは様々な差別にあっていたんだね。そこらへんの思いを『ベルンハルディ教授』という作品にぶつけている。

シュニッツラーさんは、そんな背景をもつ作家だったんだ…

そういう作家なら「若い二人の純愛悲劇」なんちゅう単純なメロドラマを書くわけないな。

その通り。
でもロミーとアランの『恋ひとすじに』は青春映画としては名作だと思うよ。
原作から「闇の部分」を排除し、見事に「ラブロマンス」へと仕立て直した。
特に、古城&湖上のWデートのあと、アラン・ドロンがロミー・シュナイダーを…じゃなくてフランツ(F)がクリスティーネ(C)を家の前まで送り届ける別れ際のシーンは、いろんな意味で名シーンだと言える。
こんなやりとりのあるシーンだ。
C「あ、雨だわ!初デートで雨にあう恋人達は、一生愛し合うんですって」
(キス)
F「約束する。僕は君のことを…」
C「だめ…。約束なんかいらない…。未来のことは自然に任せましょう…。私は何も要求したりしない…」
(C、空を見上げて)
C「ああ、雨が…雨が降って来た…」
F「じゃあ僕たちは一生愛し合うだろう」
C「口に出しちゃ駄目…。だけど…私がいない時でも私のことをずっと想っていて頂戴…」

なんか、ロミー&アランのその後のことを思うと、ちょっと感慨深いものがあるね!
(注:二人はこの映画で恋に落ち婚約するものの4年後に破局。しかし生涯にわたり互いが大切な心の支えとなった)

てか、クリスティーネは計算高い女やな!
「初デートで雨にあうカップルは一生愛し合うの」とか男に言っておきながら、男がそれに言葉できちんと応えようとすると「約束なんかいらない。自然に任せましょう」とか、わけわからんこと言いよる。
そんで空を見上げて「雨よ、雨」とか、これ見よがしにアピールや。そうやって男に(この出会いは運命レベル)って刷り込んで「君を一生愛するよ」とまで言わせといて、「そういうことは口に出しちゃダメ」とかほざきよる。
なんちゅう女や、クリスティーネは!

ははは、確かにそうだね。
実際『恋ひとすじに』のクリスティーネは結構ヤリ手なんだよ。
彼女には父親公認のフィアンセ候補がいたんだけど、フランツのことが好きになってしまったんでその関係を解消するんだ。その時の言いぐさが凄いんだよね。自分のことを大好きで結婚を熱望してる相手に「これからもお友達でいましょ。嫌いにならないでね。はい、ほっぺにキスしていいわよ。友情のキス」って笑いながら言うんだ。もちろん彼は大ショックでキスなんてできないんだけどね。
そしてWデート前には親友のミッツィと「どうやってフランツを落すか」を念入りに予行練習する。

小悪魔系!

かたやアラン・ドロン演じるフランツは、どこまで行っても優柔不断で頼りない。
初めての「大人の関係」をどうやって終わらせたらいいのかわからないんで、夫人の言いなりになってズルズルと関係を続けていたくらいだからね。
親友のテオに別れ方を教わってチャレンジしてみるんだけど、いざとなるとハッキリと言えなくて、「きっと伝わっただろう」なんてノンキに考えてしまう。

悪気はないんだけど、人を傷つけてしまうタイプだ…

でも原作では逆なんやな。

そうなんだ。
原作でのフリッツは「遊び」ができない。女をいちいち「本気」にさせてしまうという「やっかいな癖」をもつ。そんなに好きでもない相手なのに。
親友のテオが何度も「いつか身を滅ぼすぞ」って忠告して、その場では「わかった」って答えるんだけど、女性を目の前にするとケロッと忘れてしまう。
そういう「悪い癖」を持つもんだから、せっかく別れを告げにクリスティーネの家を訪れたのに、また甘い言葉を囁いて彼女をその気にさせてしまい、言葉巧みに寝室まで入りこんでしまう。

「言葉巧みに寝室まで入りこむ…」って、なんかエロいな。
でも、あんとき昼間やったし、下にオトンもおったやろ。

映画ではね。
でも原作ではそうじゃない。
フランツがクリスティーネの家を訪ねたのは夜の19時過ぎくらいで、お父さんは劇場での仕事へ出かけていた。オペラが終わるのがだいたい23時くらいで、帰宅するのは24時くらいだろう。時間はたっぷりあるね。

親が不在の夜に男を寝室に引っ張り込んだんか、あの女は!?
やるな!さすが小悪魔系や!

いや、フリッツが言葉巧みだったんだよ。
でもまあ最終的にOKしたのは彼女なんだけどね。
しかしクリスティーネの「部屋」でのやりとりなんて、もうおかしいんだ。
作者のシュニッツラーとしては、この戯曲が上演禁止にならないよう精一杯「婉曲的に」書いたんだと思うんだけど、どう読んでもコントとしか思えない。

オイラまだ子供だから、こっから先は耳栓してる…

じゃあそのシーンをシュニッツラー御本人に読んでもらっちゃおうか。

呼んだ?
Freut mich, 私がアルトゥール・シュニッツラーだ。
いつも私の作品を取り上げてくれて、どうもダンケション。
日本ではなぜか知名度が低いから、これを機にせめてカフカ並みになるといいな…

大丈夫や!
おかえもんが『海辺のカフカ』に対抗して『山辺のシュニッツラー』を書くっちゅうて息巻いとったで!

おお、それはそれは!
しかしあのシーンの一体なにが「コント」なのかわからんが、任せてくれたまえ。
Fはフリッツ、Cはクリスティーネだ。

おう!

C「なぜ急に今夜…」
F「突然だからビックリするよね?でも急に君の”部屋”を見てみたくなったんだ。どんな風なんだろう?って。そしたらもう見ないと気が済まない気分になって来たんだ。僕の中で何かが込み上げて来て、もう我慢できなくなって…。だから、いいよね?」
C「もう!そんなこと私に答えさせないで!」
F「何も心配はいらないよ。誰にも見られずに来たし、お父さんは当分帰って来ない」
C「もう…そういう意味じゃなくて…」
F「わあ!これが君の”部屋”か!なんて可愛らしいんだろう!」

おい!出だしからコントやんけ!
”部屋”って、違う意味やろ!

C「暗くてよく見えないでしょ?」
(C、ランプのシェードを外そうとする)
F「いや、いいんだ。そのままにして。ほのかな明るさで見るのがいいんだ。明るすぎちゃクラクラする…。ふうん…。なるほどね。これが君の話してた”窓”か。この”窓辺”で君はいつも”内職”してるんだね。うん、実にいい眺めだ。あそこに”黒くてもっさりしたもの”が見えるけど、あれは何だろう?」
C「カーレンベルグよ」

カーレンベルグとはウィーン郊外にある丘で「剥き出しの丘」という意味だね。

”窓”とか”内職”もオカシイやろ!
てかクリスティーネ!なに手伝っとんねん!
そこは恥じらうとこや!

ちなみにフリッツの家の窓から見えるのは「ストロー通り」だった。
ストローとは「わら」のこと。外見はちょっとくすんだ薄黄色で、中は管になっているよね。

そういうハナシやったんか!

F「通りに面していつも騒々しい”僕の部屋”とは違って、ここはさぞかし静かなんだろうね?」
C「そんなことなくてよ。昼間は案外うるさいの」
F「ここを”誰かが通ったりする”の?」
C「人は滅多に通らないけど、向かいが”錠前師”の工房だから」
F「それは最悪だ…」
C「でももう慣れてしまったわ。毎日聞いてるうちに気にもならなくなってきた…」
F「ああ、なんだか不思議な気分だ…。この”部屋”に来るのが初めてじゃないような気がするんだよ…。なんだかすべてが懐かしい…。どうしてだろう?ここに帰って来ることを僕はなぜか知っていたような気がするんだ…」

ピピー!
来たコレ、確信犯!
『ハレルヤ』の3番の歌詞と同じや!
2分55秒あたりからやで!

あの3番の歌詞はレナード・コーエンかな?それともジェフ・バックリーかな?
どちらにせよ、もしかしたらシュニッツラーの『Liebelei』を読んでいたのかもしれないね。

そうだったら嬉しいな。さて、続けるぞ。
F「もっとよく見せて…」
(F、顔を近づけて詳しく見ようとする)
C「いや…そんなとこ見ちゃダメ…」
F「おや?この”絵”は何だろう?」
C「やめてって言ってるのに…」
F「だめ、どうしても見たいんだよ」
(F、ランプを近づける)

宇能 鴻一郎か!

C「これは、”旅立ち”…そして”帰郷”…」
F「まさにそうだ」
C「見た目は決して綺麗なものではないわよね…。そうそう、隣の父さんの部屋には綺麗な絵があるのよ」
F「どんなもの?」
C「少女が窓の外を見つめてる絵。外は一面の冬景色なの。タイトルは”孤独”…」
F「ふうん…。おや?これは”本棚”だな…。シルレル…ハウフ…、へえ!百科事典まであるとは驚きだ!」
C「もう!恥ずかしいから見ないで!全巻そろってなくて、Gまでしかないのよ…」

Gräfenbergか!?

Ichi ichi surudoine…
Mosikasite bare bare nanoka?
Japaner anadoren…
Maa ii sorosoro finishda.
F「ここはホントに最高だ…。まるで世界から隔絶された場所にいるみたいで…。今この瞬間、この”部屋”だけが、宇宙の全てなのかもしれない…。あの時も確かそうだった…。僕と、僕を包むこの”部屋”だけが世界の全てだった…」
以上、『クリスティーネの”部屋”』でした。
Goseityou、Ich bin Ihnen sehr Dankbar.

Ein einfaches Dankeschön reicht nicht aus!

なんて言ったんや?アタマの「ご清聴」だけは聞き取れたんやけど…

「ご清聴感謝いたします」って言われたから「いえいえ、ありがとうって言葉じゃ足りないくらいですよ!」って答えたんだ。

シュニッツラーさん、颯爽と帰って行ったけど、もう終わったの?

耳栓しとって正解やったで。たいへんなもん聞かされた。
ええじゃろはんには10年早い。

あのあとに外で待ってたテオが部屋に乗り込んでくるんだ。「なかなか出て来ないと思ったら…何やってんだよ、お前!また俺の忠告を無視しやがって!いい加減にしろよな!」ってね。言葉には出さないけど。

なるほど。
フリッツは「依存症」なんやな、恋愛の。目の前に女がいると、そういうモードになってしまう。たいして好きでもないのに。だから自分から別れられへんのや。

その通り!

ど、ど、どうゆうこと?

今回もずいぶん長くなったんで、このへんにしておこうかな。
続きはまた次回に。

本人の朗読もあって大満足の回やったな。

ず、ずるい…
