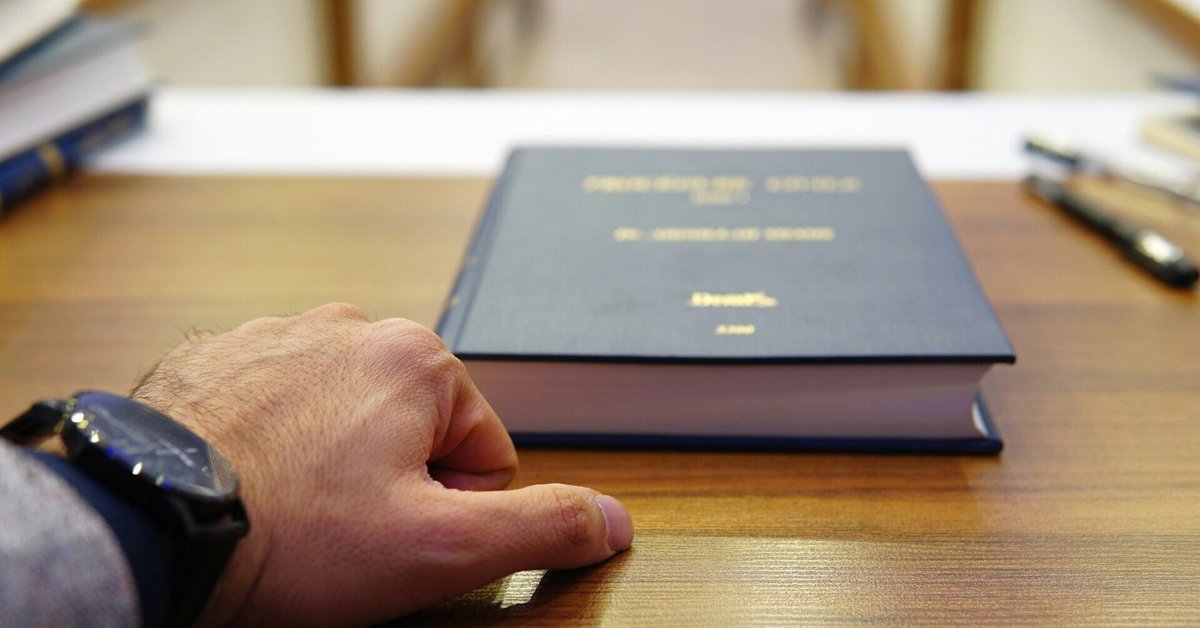
論文対策:企業
ご利用にあたり、まずは「論文対策:総論」(https://note.com/ojn/n/n9b214da5024e)
のnoteのご一読に協力をお願いします!
0.はじめに
こんにちは!おじゅんです。
最終日の午前に実施される、企業法について書いていこうと思います!
短答企業を完全なる暗記科目として割り切って、乗り越えた人もいらっしゃるかと思います。
一方、論文企業は、幸か不幸か短答よりも"楽しい"と言われることが多いように感じます。
短答から論文にかけて、最も形式が変わると言っても過言ではないため、もはや新しい科目として扱うのが適切かもしれません。
いつも通り、科目概要から入っていきましょう!
1.企業法について

論文企業は、一問一答ではなく、記述式です。
各大問は30行で構成されており、基本的には2つの中問に分割されて出題。各中問は独立していることもあれば、連続していることもあります。
中問の分量は決まっているわけではなく、大問ごとに配分が変わることがほとんど。答案用紙の分量をあらかじめ把握した上で、何を書くべきかを考えていく必要があります。

試験範囲自体は短答とほぼ変わりませんが、短答と異なり"論点"が出題される特徴があります。
短答は、論点と言っても最高裁の判例の結論のみしか問われませんでしたが、論文は地方裁の判例も出てくる上、その結論に至った理屈までを記述することになります。
したがって、どのような法的論理に基づいてその考え方に至っているのかまでを理解し、実際に出題された問題に対し今までの自分の知識を用いて的確に当て嵌めていく力が必要になります。
この時、法律科目である以上、IRACという法律思考パターンを用いて答案を作成します。
ここで、IRACについて軽く説明しておくと
I(Issue:問題提起)→R(Rules:規範定立)→A(Application:あてはめ)→C(Conclusion:結論)
という流れで記述を行うというものです。
軽く具体例を。
Q.歩行者Aが、交差点の横断歩道を横断した。この時、当該横断歩道がある交差点には信号機が設置されており、歩行者信号は赤。横断歩道が設置されている車道には車などの姿はなく、当該交差点には見通しが良い交差点だった。歩行者Aに対して信号無視に係る罪を問えるか。
実際にIRACの流れで考えてみましょう。なお、実際の法律に従った厳密な記述は行いませんが、ご了承ください。

I:信号機が設置されている交差点において、赤信号になっているにもかかわらず横断歩道を横断した歩行者Aに対して、〇条〇項に基づいて信号無視違反に係る罪を問うことはできるか。
R:この点、〇条〇項において信号無視違反に関して罰則規定を設けている趣旨は、交差点における交通事故を防止し、もって交通安全を確保することにある。確かに信号機がある交差点において信号を無視して横断することは〇条〇項に違反していると捉えることもできるが、事故を防止するという同条項の趣旨に鑑みると、事故が発生しないと認められる特段の事情が認められる場合においては信号を無視して横断するという行為を一括して罰する必要はないと解するべきである。
A:本問において、歩行者Aは信号が赤であるにもかかわらず横断歩道を横断しているが、当該横断歩道に係る交差点は見通しが良い上に周囲に車などの姿はなく、事故が発生しないと認められる特段の事情があったと認められるといえる。
C:したがって事故が発生しないと認められる特段の事情がある赤信号の交差点の横断歩道の横断は〇条〇項に基づく罰則を科す必要はなく、歩行者Aに対して信号無視に係る罪を問うことはできない。
いかがでしょうか。ここで伝えたいのは、一見条文に従うとNGにも見える事案であっても、その原則を修正してOKになる場合もあるということ。
そして、IRACの流れに沿った答案作成のイメージもつけていただけたのではないでしょうか。
もちろんこの事例について、信号無視違反に関する罪をAに対して問うこともできます。結論が分かれることがあるのが論文企業の面白さであり、難しさでもあります。
IRACに基づいた答案作成の詳しいコツについては、分量が多くなりすぎるため後日、別のnoteにて解説します。
論文企業のもう1つの大きな特徴としては、"足切り"と最も隣合わせの科目ということです。

仮に第1問で指摘条文を大幅に外し、問いと関係ない事を書いてしまう、いわゆる"論ズレ"を起こしてしまった場合、大問の素点が0点になります。
論文式試験の採点上その大問偏差点が0になり、もう1つの大問で偏差値80以上を取らない限り、科目偏差点が40を下回り足切り不合格となります。
間違えやすい条文や難しい出題がされた年は、この事故が発生し、足切りを食らう受験生が見られるようになります。過去には、他は科目合格にも関わらず、企業法が足切りで来年の論文では企業法のみ残った人もいるとか。
ここまで聞くと怖いですが、論文企業は、適切な対策を取っていればまず足切りリスクを負うことはありません。
全体観を簡単にまとめるのは難しいため、後の各チャプターで触れながら具体的な対策を書いていこうと思います。
それでは早速、内容に入っていきましょう!
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
