
〈分際〉をわきまえなかった日本 大日本帝国と史論家山路愛山の時代20
第二章 平民主義者山路愛山
今日から平民主義者としての山路愛山の姿を見ていくことにする。

「平民」としての福沢諭吉に敬意
史論家山路愛山の平民主義を考察する際、どうしても省けないのが福沢諭吉についての認識である。青年期愛山の福沢観について言及しておこう。
福沢は天保五年に生まれて明治三四年に没している(一八三五~一九〇一)。江戸時代を三三年ほど生き、明治時代を三三年生きた。おおよそ半分半分である。『学問のすゝめ』(明治五~九 一八七二~六)を著わし啓蒙につとめた近代日本最大の思想家の一人と言って良い。愛山の文にも独立や自助といった言葉がよく出現し、その思想的影響は濃厚である。明治時代に生まれた以上は避け得ないほどその存在は大きかった。愛山が生まれたのが元治元年(一八六四)であるから、年の差は二九歳で福沢が天保生まれの親とすると、愛山はその子供の世代といえよう。
「ポスト福沢世代の青年達」といった岡利郎の先行研究があるが[i]、それによれば愛山以外の思想家も、福沢という思想家を相当意識し影響も受け同時に反発を感じていたという事実である。
愛山が福沢と田口卯吉について言及した、明治二六(一八八三)年に「明治文学史」を著すころの愛山は、同年一月に、キリスト教のメソジスト三派が発刊する雑誌『護教』の、事務所を自宅に置き、キリスト教の普及伝道に努めていた。また同月に「頼襄を論ず」を『国民之友』に発表し、これを批判した北村透谷との間に、あの有名な「人生相渉論争」が展開されている。これが後から伏線として、愛山の福沢論に関係してくる。
この年二月に書かれた「明治文学史」の「福沢諭吉君及びその著述(一)」である。愛山は福沢について
「彼は実に無冠の王なりき」
と述べて、維新の三傑(西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允)が地下に眠ったあと
「而して此間に方りて白眼天下を睥睨せる布衣の学者は日本の人心を改造したり少なくとも日本人の中に福沢宗と曰ふべき一党を形造れり」
と、福沢が日本人に多大な影響を与えたことに評価を下す。このように書いた愛山こそ、まさに終生〈布衣の学者(平民の学者の意味)〉たらんとした人物であった。
福沢諭吉をこきおろした親友の徳富蘇峰は、明治三〇年(一八九七)に内務省参事官になり、明治四四年(一九一一)に貴族院議員となった。

愛山はあくまでも在野を通し、平民主義者として「日本の人心を改造」することに務めた。愛山の身の処し方は、福沢の生き方と重なるものがあり、模範としたのであろう。 〈天保の老人〉と福沢諭吉を切り捨てた蘇峰との違いでもある。
明治人と〈分際〉
「吾人の郷里に在るや、かつて君の世界国盡しを読んで始めて世界の大勢を知りたりき」
と福沢の目を通じて世界を理解したことを明らかにしている。
「吾人の彼に敬服するところは彼(福沢)が何処までも「平民」として世に立てること是也。彼れは自らその職分を知れり、自らその技能を知れり。人間の貴きは必しも冠冕に在らざることを知れり。彼れは衣貌を以て、官爵を以て人に誇る者に在らず、自己の品位は即ち自己に在ることを知れり。彼れはかくの如くにして世を渡れり、かくの如くにして自ら律し、あわせて世を教えたり、明治の時代に平民的模範を与へたる者、己の生涯をもつて平民主義を解釈したる者は彼れに非ずして何ぞや」
明治人が持っていて、現在の日本人に希薄な意識は〈職分〉の観念である。これは国家をはじめとした全体に対する〈部分〉としての意識であり、個と公の一つの結びつき方でもあった。
東京大学名誉教授で近世史研究者の尾藤正英は「役の体系の時代」と徳川時代を評価している。分際をわきまえるとか、職分とか甚だ 古臭い考え方のように思われるが、そこに個人が全体に対する義務を尽くすという点において、個人と全体との有機的な連関があったのではないかと見ているのである(『江戸時代とは何か』岩波書店)。

夏目漱石の『それから』(1909年)にも分際をわきまえることの重要性が説かれている箇所がある。
「何故働かないつて、そりや僕が悪いんぢやない。つまり世の中が悪いのだ。もつと、大袈裟に云ふと、日本対西洋の関係が駄目だから働かないのだ。第一、日本程借金を拵らへて、貧乏震ひをしてゐる国はありやしない。此借金が君、何時になつたら返せると思ふか。そりや外債位は返せるだらう。けれども、それ許りが借金ぢやありやしない。日本は西洋から借金でもしなければ、到底立ち行かない国だ。それでゐて、一等国を以て任じてゐる。さうして、無理にも一等国の仲間入をしやうとする。だから、あらゆる方面に向つて、奥行を削つて、一等国丈の間口を張つちまつた。なまじい張れるから、なほ悲惨なものだ。牛と競争をする蛙と同じ事で、もう君、腹が裂けるよ。」
実際に日本(蛙)は西洋(牛)と軍拡 を競ったことで、腹が裂けてしまった。分際をわきまえなかった罪である。身分制度を廃止した明治時代において、分際をわきまえないということは、自己認識ができていない、自己の能力に対する分析がないということである。逆に、わきまえすぎて自己を過小評価して低いところに甘んじていてもダメだということも強調された時代でもある。
平民主義者の愛山においても、日本人に染み付いているこの観念は残り続けている。そしてそれが彼の思想的な深みを形成している。愛山が福沢を一番評価する点は、平民主義の始祖が福沢であり、福沢は布衣を貫き、身を持って示した平民主義者だったからである。
しかし、こうした肯定的な福沢評価だけではすまない。愛山の人物論の特徴は、必ずその人物の生んだ時代背景と、光と陰を記述する。
「福沢君の天職は日本の人心に実際的応用的の処世術を教ふるにあり。怜悧なる商人を作り、敏捷なる官吏を作り、寛厚にして利に聡き地主を造るにあり。彼はつねに地上を歩めり、彼れはつねに尋常人の行く所を行けり。彼はつねに平直なる日本、人民の模範を作らんとなしつゝあり」
このように 肯定的に福沢を論じながらも、明治日本におけるプラグマティズム(役に立つものはすべて真理であるとする)の元祖であったと述べて、その思想の行く先に危機感を強めてもいる。
「人もし金を積んで郷里に居り、時に金を散じて人を恵み、橋を架し、道を作り、小恵小善を行ふをもつて足れりとせば、福沢君は実に天下最第一の師たらん。しかれども世は唯小善の人をもつて治むべからず、尋常平凡の人物より成立ちし共和政治は最も卑陋なる者なり、これ故に世は英雄崇拝を要す。而して福沢君はこれを教えざるなり。人は唯善く生活するを以て満足する者に非ず、人の心の深き所には温飽に満足せざるものを有す。これゆえに世は宗教を要す、これゆえに世は哲学を要す、而して福沢君はこれを教えざるなり、これみな天下の最大要求なり。而して彼れは冷眼にこれを見たり。(中略)吾人をして正直に曰はしめば、世もし福沢君の説教をのみ聞きたらんには、この世は棲息するに足らざるもの也。彼れの宗教は詮じ来れば処世の一術に過ぎず。」
と、結果的に福沢こそが、日本を物質的社会にした元凶であるとし、批判している。つまり、福沢が宗教について理解がなかったことの一番問題視しているのである。この文章の最後を
「幸いにして世は福沢君の弟子のみに非ず、この世はなお未だ全く物質的、懐疑的、冷笑的の世界に変ぜざる也」
と結ぶ。 明治第2世代が多くが宗教に目覚めたことの背景は、こうした 福沢の思想性の欠陥を埋めることでもあった。
愛山が述べているように、福沢は英雄豪傑の存在が世を動かすことに対して否定的であった。明治八(一八七五)年の『文明論之概略』に以下の文がある。
「地理書を見れば、中津(大分県中津市:福沢の出身地)の外に日本あり、日本のほかに西洋諸国あるを知るべし。なお進て、天文地質の論を聞けば、大空の茫々、日月星辰の運転に定則あるを知るべし。地皮の層々、幾千万年の天工に成りて、その物質の位置に順序の紊れざるを知るべし。歴史を読めば、中津藩もまたただ徳川時代三百藩の一のみ。徳川はただ日本一島の政権を執りし者のみ。日本の外には亜細亜諸国、西洋諸洲の歴史もほとんど無数にして、その間には古今英雄豪傑の事跡を見るべし。歴山王、ナポレオンの功業を察し、ニウトン、ワット、アダム・スミスの学識を想像すれば、海外に豊太閤なきに非ず、物徂徠も誠に東海の一小先生のみ。わずかに地理歴史の初歩を読むも、その心事はすでに旧套を脱却して高尚ならざるを得ず。」
世の中で英雄と言われていても、大きな存在から比べたら大したことはない。相対化されてしまうという。従って、彼ら 個々人の事績を過大に評価するよりも
「不特定多数の人々の間に見られる一般的傾向に着目しなければならないと」
説いたのが福沢であった[ii]。しかし、福沢は坂本多加雄によれば、決して個人の力を軽視してはいなかった。
「・・・「文明」の進歩のためには、何よりも個々人が、それぞれ従来の習慣や周囲の不特定多数の人々が抱く「世論」への「惑溺」から自らを解放して、「異端妄説」を唱道すべく努めることが必要であり、そして、その結果としてはじめて、社会全体に「多事争論」の状態が生み出されるのだという考え方であった」(前掲書)
愛山が強調した〈小英雄〉の存在が福沢においても見られないわけではない。愛山は福沢を誤読したわけではないが、注意深く読めば、福沢はすべての歴史的事象を大きな法則性に還元し世の有様をそこに当てはめたわけではない。
北村透谷に罵られた 山路愛山
この愛山の福沢論に接する際に、あの有名な近代文学史に残る北村透谷との論争を念頭に置くと違う光景が見えてくる。つまり、この時に、愛山はここで述べた福沢論で見せた唯物主義批判を、逆の立場で透谷から受けていた。愛山の
「文章即ち事業なり。(中略)人生に相渉らずんば是も亦空の空なるのみ。文章は事業なるが故に崇むべし」
との言葉に、透谷が噛みつき、
「愛山は文学を事業と捉えている」
とし、彼はそこに「ユチリチー論」[iii]を見出した。愛山こそは実用性のみを追い求める唯物的文学論者ではないか、と透谷は批判するのである。
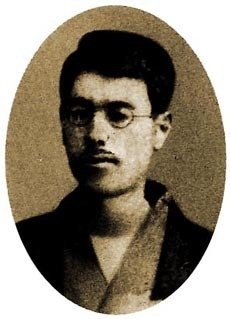
二人が議論をした際
「透谷が愛山を「足下は唯物論者なり」
と罵ると、愛山は透谷に
「卿は空想家なり」
と言い返した」[iv]という。このことが、愛山にとって見たら面白くはなかったのではあるまいか。愛山からしたら、これは透谷の一方的な誤解であって、彼はこの年に、メソジスト三派の機関紙の『護教』の編集も行っていた。宗教的な信仰も多分に持ち合わせていた彼が
「唯物論者」
と透谷から批判を受けるのは心外であった。その心理的影響がこの福沢論に現われ、福沢を愛山自身が透谷から批判された文脈をほぼそのまま適用して批判したと考えられるのである。
[i] 岡利郎 『山路愛山』 研文出版 平成一〇(一九九八)二二九頁
[ii] 坂本多加雄『近代日本精神史論』講談社 平成八(一九九六)九〇頁
[iii] 「人生に相渉るとは何の謂ぞ」『明治思想集Ⅱ』筑摩書房 松本三之介編 昭和五二(一九七七) 二〇三頁
[iv] 『山路愛山』吉川弘文館 坂本多加雄 昭和六三(一九八八) 九七頁
