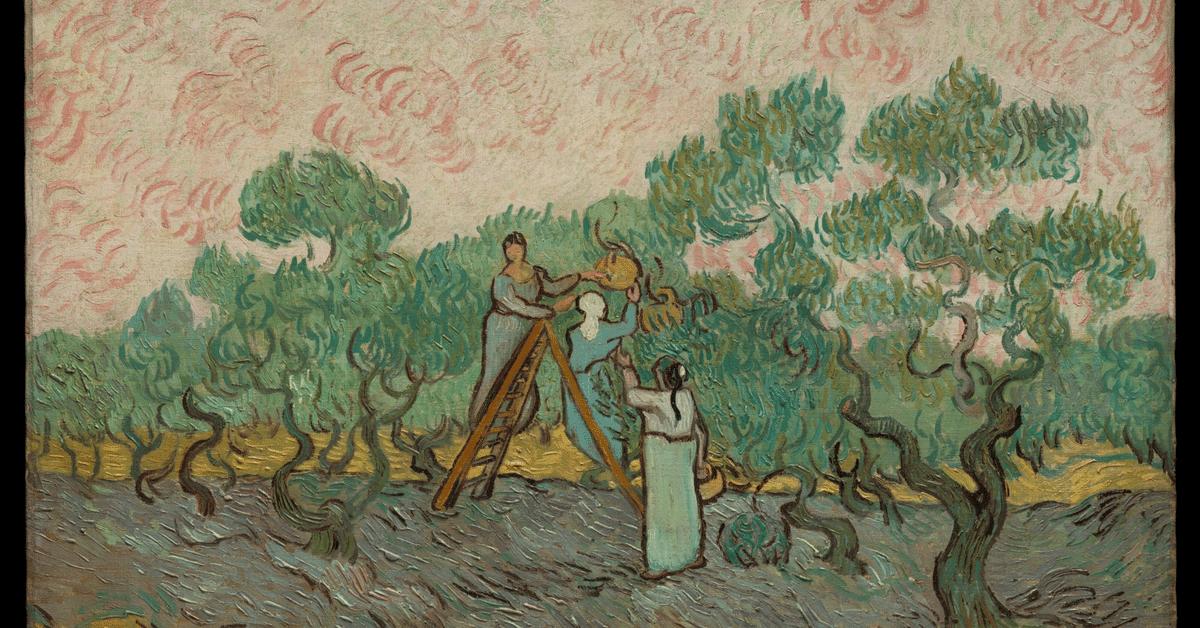
【短編小説】木曜のビヨンド ver.2
僕の自殺願望は昔からだが、より強くなったのは学生時代だ。僕が定春と出逢う頃には、僕らの両の目はぼんやりしていたし、もっと鬱蒼としていた。僕らはぼんやりすることが多かった。のんびり、とは違う。ぼんやり、は何もない。ずっと、何もない。
変わり者になるには、「それ」として注目される人間でなければならない。定春は高校時代から「それ」で、僕は決して成れていない。定春を語る時、僕を含めた人々はどうしてもその容姿を切り離すことができない。彼の大きな黒目が綺麗で、整ってしまっているのが悪いのだ。(言い訳だ。なんて醜く大衆的な己だろう)さぞモテたろうと訊いた時には、そういうのはよく分からないと返された。テンプレかよ。あの目の奥の靄は光のなかでは見えない。あの白さを知る者なら、彼がその実、女性を美しく思っていないことも――僕は定春になりたかった。何でもできて、何にもない男になりたかった。そうすれば、すれば。定春は、何を思っていただろうか。
夕方になると、僕は定春の部屋を出ていかなくちゃならない。同居の大人たちのこともあるが、何より厳しい門限のほうが大事だった。一度、家出をして一晩帰らなかった前科のために、随分厳しく縛られたものだ。実家暮らしの僕は毎朝電車で大学に通っている。通学時間はだいたい一時間くらいで、本当に大したことはない。大したことがあるのは、親が出してくれている定期代のほう。僕はいつも定春に「また、明日」を言って狭さに別れを告げる。大きな車窓つきのモスグリーンの座席に掛けるまで、僕は街の中の定春を想像する。そろそろそのシャツ、捨てろよな。文学にまみれたその手、穏やかな性格からは考えられない鋭利な文章の数々。一度だけ、僕も書いたことがある。文学を、してみたことがある。彼は、僕を乾いていると呟き慈しんだ。砂漠の如雨露の一滴で。
(ボタンひとつで何かを変えてしまえるなら、僕はもう何度世界を救っているだろう。部屋の隅に積まれたゲームたちを崩して、今日も)
定春が僕を呼ぶ。僕の気に入っている渾名で呼ぶ。おまえのその夏の涼風みたいな声も好きだよ。低すぎない青年の声だ。僕のアルトじみた声と合わさっても不快音にならないね。二人してパチンコ屋の前を通り過ぎて思案する。やってみる? もったいないかな。タバコくさいのは却下だ。
クソ親父がアル中のヘビースモーカーだから、酒もタバコも嫌いだ。大嫌いだ。定春はまた、よくわからないと言う。父親はファンタジーの中にいる、さらなるファンタジーだ。定春の顔や声は、きっと亡くなったテメーの父親に似ている。僕は、さほど似ていないけれど。幼い頃は可愛そうに父親似、なんて言われていたくらいだが、時の流れがそうさせる。母が嫌な訳じゃない。むしろ、愛している。僕は年々、母に似てきていた。皆、そうなるのだ。こういう時、定春は曖昧な顔で僕を見下ろす。普通におまえを愛せればよかったのに。僕に普通なところなどあった試しがない。
「サダくん」
あぁ、そうだ。おまえと同じ「サダ」を僕も持っているんだよ。僕はこんな名前、好きになれなかったけれどね。サダくんと定春、定春とサダくん、どっちでもいいや。
定春、本当におかしな話なんだが聞いてくれるか? 僕がおまえより背が高くて、筋肉があって、力強い指先でその肌を撫でることができたなら――なぁ、どうしてこんな馬鹿げたこと、考えてしまう。教えてくれ、定春。生きていく術を教えてくれ。これを幸福と呼ぶなら、僕は今こそ死んでしまいたいんだ。今しかないのに。早く死んでしまいたいのに。僕のこの小さく弱い腕は、おまえの背中に届かない。おまえの手はこんなにも熱く強いのに、僕は弱っちいまま、何も出来ないんだ。
定春、本当は僕がおまえを抱きたいよ。
