
『万物の黎明』読書ノート その10
"WD"はDouble David(著者である文化人類学者デビット・グレーバーと考古学者デビット・ウエングローの二人のデビット)の略です
第10章『なぜ国家は起源をもたないのか』要約
第10章でいよいよ国家の起源が論じられます。本書最大のヤマ場であり、分量も一番ある章(90ページ)です。ここまで読んできて分かるようにWDは社会進化論的人類史を徹底的に避け続けています。歴史上のあるポイントで「国家」が現れて、それが周囲に広がっていくというような見方はしません。それに代わるストーリーとしてWDが出して来るのは、「人類は色々な形態の国家を試し続けてきた」というものです。
国家の定義
そもそも「国家」とは何なのか?現代の人々はほとんどすべて国家に属していると考えられていますし、古代エジプト、古代中国の殷、インカ帝国なども「初期国家」とみなされています。しかし社会理論家たちのあいだでコンセンサスはなく、これら全ての「国家」を包括し、かつガバガバにならない定義が難しいとWDは言います。pp.410-412
イェーリング(orウェーバー)の国家の定義:「国家The state」という言葉は16世紀後半にフランスの法律家ボンタンが使い出し、19世紀後半にドイツの哲学者イェーリングが体系的な定義を試み、マックス・ウェーバーが引き継ぎました。それは以下のようなものです。
「国家とは、所与の領域内で合法的な強制力の使用を独占することを主張する機関」
つまり、ある一定の範囲の土地の領有権が主張され、その内部では「人を殺害、殴打、監禁することを許されるのは我々に限る」とある機関が宣言するとき、政府は国家になるのです。この定義は近代国家には有効ですが、人類史の中ではそのように振る舞わなかった支配者も多勢いました。あるいはタテマエはそうであっても実質はそうでなかった場合も多かったのです。イェーリング/ウェーバーの定義ではハンムラビ王のバビロニアもソクラテス時代のアテネも、征服王ウィリアムのイングランドも国家ではありません。pp.410-411
マルクス主義者の国家定義では、人民を搾取する支配階級が権力を防衛するために構築したのが国家ということになり、上述のバビロニアもアテネもイングランドも国家ということになりますが、搾取をどう定義するのかという問題が生じますし、国家を悪と断じるこの定義はリベラル派には好まれていません。p.411
20世紀の社会学者たちによる機能主義的国家観に従うと、社会が複雑になれば、その調整のためにトップダウンの指揮構造が必ずや生ずることになっています。「大規模で複雑なら国家」ということです。分かりやすくはあるのですが、これでは何も説明したことになりません。そして、第8章で取り上げた最初期の都市には、当てはまりません。初期のウルクには支配構造はありませんでした。その時代に支配構造が現れているとしたら、ウルクのような低地河川流域の大規模で複雑な社会ではなく、周辺の山麓の小規模な英雄社会においてでした。そしてその英雄社会も行政管理の原理を嫌っていましたから、これまた国家らしくありません。民族史的には北米北西海岸の社会も英雄社会的な人々ですが、国家装置と呼べるようなものは何一つ持っていない人々でした。pp.411-412
では官僚的形態と英雄的形態という二つの形態が融合したところに国家が現れるのでしょうか?ここでWDはそういう定義を下すことに意味があるのだろうか?という疑義を挟みます。国家がなくても支配体制が可能であったり、国家がなくとも複雑な灌漑システムを構築することが可能であるとしたら、それらが国家ではないと定義することに何の意味があるのでしょうか?p.412
国家をめぐる定義のやり直し:
そこでWDは次のように議論のやり直しを提案するのです。pp.413-
支配の3つの基本形態
ルソーは支配の起源を「土地の所有」に求めました。所有権への執着がヨーロッパ社会特有の問題であることは既に第4章でも述べたとおりです。では「土地を所有する」とはどういうことなのか?それはある領域内にある、土や石、草、垣根など全てのものに対する排他的アクセス権です。他の誰にもあなたの権利に異議を唱えない、あるいは許可なく侵入して立ち去らない人間を脅かしたり攻撃したりできる、あるいは武器を携帯した人間たちを動員して土地所有権に異議を唱える人間を脅かしたり攻撃したりできるなら、あなたには「土地を所有している」と言えるでしょう。ということは「不動産」とは土や石のことではなく、道徳と暴力による脅威との微妙な組み合わせの上に成り立つ法的了解だとWDは議論を展開していきます。これは前述のイェーリングによる「国家による暴力の独占」とまったく同じ構図です。pp.413-415
では、支配であるとか財産といったものは究極的には暴力から生まれると考えれば良いのでしょうか。ここで、WDは有名女優が身につけているダイヤモンドのネックレスは如何にして守られているのか?という話を展開させながら、暴力(具体的には警備員や警察によるもの)と情報の制御(いつ、どこにダイアのネックレスがあるのかを明らかにしない)と個人のカリスマ性(その女優が尊敬されていて誰も彼女の持ち物に手を出そうとしない)という3つをとりあげ、これが社会的権力の3要素だと提案するのです。すなわち、暴力の統制、情報の統制、個人のカリスマ性です。そして、この3つは近代国家の基礎をなしているとWDは主張します。pp.415-417
「暴力の統制」については、イェーリングによる国家の定義で述べた「領土内の合法的な強制力の使用を独占」する「主権」がまさに該当しています。もっとも古代の王は、実際にはこの権力はたいして行使できなかったであろうともWDは言います。王から100ヤード以上離れていれば、王の恣意的暴力は振るえないのです。この話は別の箇所でナチェズ族を例にして語られることになりますが、王の元に引きずり戻す官僚なり警察官がいなければ王の恣意的暴力も実行できないのです。p.417
それとは異なり、現代国家の主権が強大なのは官僚制(情報の統制機関)と結びついているからだからだとWDは指摘します。p.417
そして官僚制と結びついた主権は監視国家や全体主義に繋がっていきますが、民主主義によって相殺されると私たちは考えています。しかし、現在の民主主義とは大物政治家たちが繰り広げる勝敗ゲームしか意味しておらず、ほとんどの人間はたんなる野次馬です。古代ギリシャの市民集会(アセンブリー)よりは英雄社会の貴族の抗争によほど似ています。つまり限られた人間たちがカリスマ性を競っているのです。pp.417-418
暴力、情報、カリスマ性へのアクセスが社会支配の可能性を規定します。近代国家の場合はそれが主権、官僚制、競合的政治フィールドとして規定されています。そして「国家」を考える上で、この3つが揃っている必要はありません。そもそもこの3つの支配の基本形態は歴史的起源からしてまったく違うのです。p.418
(それを図示すると
社会支配の3要素:暴力 情報 カリスマ性
↕️ ↕️ ↕️ ↕️
近代国家では: 主権 官僚制 競合的政治フィールド
となります。)
古代メソポタミアでは河川流域の都市で官僚制が発生して、丘陵地帯で英雄社会的(カリスマ的)政体が現れ、両者は緊張状態にありました。そして古代メソポタミアの都市は実質的な領域的主権があった有力な証拠がありません。pp.417-418
ルイジアナのナチュズ、東アフリカのシルックの王/首長は、目の前にいる臣民に対して絶対的な権力をもっていましたが、目の届かないところで臣民は彼の命令を無視していました。p.419
近代国家は、人類史のある時点でたまたま成立した諸要素の集合体(当然そこには上述の3要素が含まれます)なのであり、現在それが解けつつあるのだとWDは言います。WTOやIMFのような地球規模の官僚組織が育ちながら、地球規模の主権が存在しないという現実を見ろというのです。そして、学者たちは近代国家でのそうした結合を過去に投影して、主権的権力(のようなもの)が行政管理システム(のようなもの)と結合した瞬間がいつだったのか、そして結合の経緯と理由を探ろうとします。たとえば、社会の規模が拡大し、行政管理システムが生じて、それを統括するための主権が生まれて、その主権を委ねるカリスマ政治家が現れる、というような説明がよくなされています。その順番にも異論はあるのですが、WDはそもそもその基底にある目的論に異議を唱えるのです。つまりそういう順番を考えるという発想の元には、さまざまなタイプの支配が遅かれ早かれ18世紀末にアメリカやフランスで成立した近代国民国家のスタイルに集約されていくという考え方があり、それ自体に異を唱えるのです。pp.419-421
WDはここから、そうした目的論を離れて初期国家の姿を描いていきます。p.421
pp.410-421まとめ:
誰もが興味を抱くであろう国家の成立という問題に対して、WDはそもそも「国家」に適切な定義を与えることが難しいことを説明した上で、議論のやり直しを提案します。社会支配の3要素として「暴力、情報、カリスマ」を挙げた上で、それらがさまざまな形態をとって国家の要素を成しているとみなすのです。たとえば近代国家ではそれらの3要素は以下のように「主権、官僚制、政治家の人気競争」という形態をとっているとみなすわけです。
社会支配の3要素:暴力 情報 カリスマ性
↕️ ↕️ ↕️ ↕️
近代国家では: 主権 官僚制 競合的政治フィールド(たとえば選挙)
近代国家では3つの要素が揃っていますが、今までの社会でこれら3つが揃うことはなかったとし、ある順番に従って出てくるということもなかったとWDは語り、その事例をみていきます。
アステカ、インカ、マヤで起こったこと
スペインがアメリカ大陸を征服しようとした時、「国家」といえるもの、あるいは「国家」と呼んで異論がなさそうな社会が二つありました。アステカとインカです。p.421
アステカでは性的暴力=男らしさが帝国拡大の原動力だったようです。規模の大きな捕獲社会(奴隷獲得戦争がかなりの割合を占める社会)であり、捕獲した奴隷は大量に殺害されていました。pp.422-423
大規模な人身御供を除けば、君主制、階層化された官僚制、高度に発達し組織化された宗教をもつ16世紀のアステカはヨーロッパ人にも分かりやすい社会でした。征服された土地では土着貴族の地位は剥奪されず、アステカ宮廷とのパトロネージュシステムによる服従が求められただけです。p.423
アステカ帝国は血まみれのスペクタクルにも関わらず、貴族の連合体であり、王も貴族の評議会の「第一発言者」にすぎず、帝国も三都市同盟でした。貴族同士は球技大会や哲学討論会で競合していました。p.425
インカ帝国はアステカを遥かに凌駕する超王国で、一般的イメージは優れた管理運営が行き届いた帝国です。しかし、王権の中心から離れた地域では多くの村落が自己統治を続けていました(アイリュ)。p.424
インカ帝国では王は太陽の化身であり、宮廷は王の血縁者で固められ、王の死後も遺体は公式行事に引き出されて宮廷は維持されました。だから、新しい王は常に帝国を拡大さして自分の領土を作る必要があったのです。王は宮廷と共に常に移動し続け、そのために道路網が整備されました。そしてインカの行政はキープと呼ばれた結縄で管理されました。そしてインカもまた性的暴力が付き纏っていました。新しい領土には神殿が建てられ、地元の処女たちを「太陽の花嫁」となるように強制し、王の意のままにされています。pp.425-427
マヤの場合
中央集権的で軍事力を基礎に置いていたインカやアステカは、スペインから来た征服者には征服しやすい国でした。中心部さえ掌握できれば、その支配機構をそのまま引き継げば良いのです。逆にそういう王国がない場合の征服は厄介で、マヤ系のユカタン半島や、グアテマラやチアパス高地の場合、征服は長期にわたる手間のかかるものであり、征服が終わっても民衆反乱が続きました。この地域は、脱集権的で反権威主義的な社会だったのです。pp.428-429
(ノート注:この箇所で言及されている「サパティスタ運動」はグレーバーにとって思い入れの深い、現在も続いているメキシコの反グローバリズム運動です。)
マヤとアステカとインカを新世界の3大文明として知っている人は、ちょっと驚くかもしれません。古典期マヤ(AD150-900)はアステカやインカによく似た王国だと思われてもいました。確かにこの時期は、エリートが統治し、文字があり碑文も多く残されていました。p.429
しかし考古学的な発見から、古典期マヤの最後の数世紀には女性の存在が強まっていたようです。そして9世紀のある時点で政治体制が崩壊し、ほとんどの大都市が放棄されています。そこで何が起こったのかは議論が続いていますが、崩壊を免れて、それどころか発展した都市チツェン・イッツァにWDは注目します。そこでは王権の性格が劇的に変化していました。より儀礼的で演劇的なものになって政治的に動けなくなり、戦士や神官の連合に日常的ガバナンスが委ねられました。p.430
6世紀ののちにスペイン人が到着した頃には、マヤの地は徹底的に脱集権化していて、小さな町や領主国に分かれ多くは王を持ちませんでした。16世紀後半に書かれた預言書には圧政者への厄災や惨劇が延々と記されていましたので、古典期マヤ以降の威圧的支配者たちが追放されてきたのだろうとWDは考えています。p.430
古典期マヤの芸術は素晴らしいのですが、それに続く「後古典期」にはみるべきものがないとされています。しかし美術品を愛好しながら生きた人間の心臓を引き裂くことが重要な儀式であると考える支配者の元で暮らすことを望む人がどれほどいるのだろうか?とWDは問いかけます。そして「古典期」に比べて「後古典期」に重要なことが起こらなかったと考える我々の思考の癖について、疑問を突きつけるのです。pp.430-431
歴史学・考古学の「原」「後」「中間」「末期」について
ここで少し脱線です。pp431-436
私たちは、文明は花の如く成長して咲いては萎んでいく、あるいは苦労して建設したものが突然崩壊するようにイメージして、そう描くことに慣れています。古典期マヤのように何百万人の人々が一斉に姿を消した例もあるのですが、エリートだけが姿を消した(そして多くの民衆は残っている)エジプト古王国の場合にも「崩壊」という表現が使われます。pp.431-432
AD900-1520のマヤを「後古典期」と表現するのも、黄金期から衰退した状態という意味を示唆しています。「原宮殿時代クレタ」「先王朝時代エジプト」「形成期ペルー」という言い方も、黄金期時代に向けて基礎を作っていたことのみを含意します。そしてこれらの「黄金時代」とは支配者がいた時代を指します。「先王朝時代のウルク」も同様で、700年に及ぶ自己統治期間を王が統治する「真の歴史」の準備期間としてのみ扱われることになります。p.432
古代エジプト史は古王国、中王国、新王国に区分され、それぞれの時代は「混沌と退廃」と形容される「中間期」で隔てられますが、中間期とはエジプトを支配する単一の人間がいなかったというに過ぎません。実際には「中間期」は合算すれば、期間にして古代エジプト史の1/3にも及びますし、政治的発展もいくつかはありました。第3中間期のテーベでは五人の未婚女性が「アメンの神妻」になり政治的経済的権力を行使しています。しかし、この政治的革新は中間期もしくは末期の一過性の出来事として片付けられています。pp.432-434
そもそも古王国、中王国、新王国という区分が19世紀後半のプロセイン学者の主導によるもので、小王国を統合して統一ドイツを作ろうとしていたビスマルク時代の国家観が反映しています。しかし、中間期を脱した中王国時代の実情は、激しい後継者争い、過酷な課税、少数民族の弾圧、強制労働の強化、隣国との抗争に彩られた時代でもあります。臣民たちにとっては、祖父たちが暮らした中間期のほうが平和に暮らせたはずなのです。pp.435-436
空間的にも同じことが言えます。都市・帝国・王国は地理的には点もしくは孤立した島々なのであって、それらの周囲には広大なテリトリーが広がっていました。そこは包括的権威を組織的に避ける社会です。それが世界で圧倒的に一般的な統治形態だったのです。pp.435
国家と3つの支配の基本形態
一般に「国家の誕生」として語られているところでは何が起きているのでしょうか?WDは支配の3つの基本形態(暴力、知、カリスマ)をそれぞれ独特に組み合わせた混成体が生じたときをもって国家が誕生したのではないかというのです。それを検証するために、膨大な数の人間を動員して組織化したのは確かだけれども、通常の国家の定義には該当しない古代の政治体を見ていこうというのです。まずはオルメカです。p.436
オルメカの事例:スポーツとしての政治
pp.436-440
紀元前1200年頃(BC1500〜BC1000)に現れたとされるオルメカ文明は、暦法や文字、球技などの発明によって、メソアメリカ文明の母ともみなされていますが、詳しいことは分かっていません。ベラクルス州の湿地帯が中心でサン・ロレンソやラ・ベンタの都市があったのですが、内部構造もよく分かっていません。pp.436-437
オルメカが平等主義ではなかったことと、エリートがいたことは分かっています。都市と後背地との関係が浅かったことも推定できます。サンロレンソが崩壊したときに地域経済にはほとんど影響がなかったようなのです。p.437

オルメカの有名な巨大頭部彫刻が球技の革製ヘルメットを被っている点にWDは注目します。マヤやアステカでも球技場はあり、それに似ているのであれば、オルメカでも細長い競技場で上位階級のチームが二手に分かれてゴム製のボールを蹴り合っていたと思われます。古典期マヤの都市では石造りの球技場が必ずありましたし、球技は神々のスポーツでした。有名な王も、球技プレイヤーとして碑文が残されています。そうした競技スポーツは戦争の延長でもありました。王室の競技大会は年中行事の一つであり、生死をかけてプレイされたのです。そして、それは大衆向けの見せ物でもありました。スペイン人の報告では、アステカの球技大会では観衆が勝負に賭け、全財産を無くして奴隷に身を落とす平民もいたそうです。pp.437-439
そこから類推してオルメカは政治的競合と見せ物を融合させ、それがメソアメリカの文化的基礎を作ったとWDは見ています。その一方でオルメカは支配のためのインフラの証拠がほとんどありません。軍事的な、あるいは行政管理的な機構が不在なのです。祭祀センターがあり、そこに(たとえば儀礼的球技のときに)季節的に人々が集まるような場所だとWDは想像します。これが「国家」なのであれば、季節的な「劇場国家」と言えるのです。p.440
チャビン・デ・ワンタルの例:秘教的知の統制
pp.440-446
インカ帝国以前にもペルーには「国家」もしくは「帝国」があったとされています。BC3000年紀にはすでにモニュメンタルなセンターがあり、BC1000〜BC200にチャビン・デ・ワンタルがセンターとして影響力を拡大しました。しかし、チャビンが国家だとしたら、それはどんなものだったのでしょうか。pp.440-441

普通の帝国は一目瞭然たる造形物を好みます。皇帝が自分自身の姿を巨大な彫像にして、万人に向けて自らの権力を誇示したりするものです。それに対してチャビンの美術は不可思議で不可解なイメージに満ちています。明らかにイメージ製作者の目的が異なるのです。「カンムリワシはみずからにからみつき、装飾の迷路の中に消失していく。人間の顔には、蛇のような牙が生えていたり、猫のように顔をしかめていたりする」p.442
WDはつい最近までの南アメリカのインディオが秘教的知識(儀礼の方法、系譜、精霊世界への旅の記録)などを、不可解なイメージに託して記録していることをもって、オルメカのこうした図象も一種の記憶術に基づくものではないかと推測します。ことにチャビンでは嗅ぎタバコ用スプーン、すり鉢、骨パイプなどが見つかっていますし、彫像の中にはサンペドロサボテンの茎を持ち上げているものもあります。このサボテンは幻覚誘発剤の原料です。また、男性像が幻覚剤のビルカの葉を囲んでいる彫像もあります。こうした幻覚剤を用いて行われるシャーマニックな遍歴(意識の変容)を記録したのが、チャビンの不可思議な彫像なのではないかとWDは推測します。pp.442-444
チャビンに残されたモニュメントには、世俗統治を思わせるものは何もありません。軍事的要塞だとか行政的区画みたいなものが無いのです。あるのは儀礼的パフォーマンスが行われたと思しき場所と秘教的知に関するものと思われる場所だけです。17世紀にやってきたスペイン人が先住民から聞き出した話では、チャビンは巡礼の地であり、神秘なる危険の潜む場所であり、国中から主要一族の長が集まりヴィジョンや神託を得ていたというのですが、これは結構当たっていたとWDは見ています。チャビンの神殿には石造りの迷路や吊り階段があり、個人の試練、イニシエーション、ヴィジョンクエストが行われたようです。迷路の果てには人間一人が通れる狭い通路がありエルランソンと呼ばれる石柱があります。p.444

支配の三つの基本原理で考えてみる
もしチャビンが帝国であったのなら、秘教的知に基づいたものでした。もしオルメカが帝国であったのなら、見世物と競技、政治指導者の個人的属性に基礎をおくものでした。これは、ローマ帝国や漢民族の帝国、インカ帝国やアステカ帝国とまるっきり違います。「国家」のようで国家では無いのです。一般には「複雑首長制」と表現されていますが、意味をなしていません。pp.444-445
支配の3つの基本原理から考えれば、チャビンにおける分散した大規模な人口に対する権力とは、ある種の知の支配によるものです。ここに武力は介在しません。オルメカにおける権力とは個人的な名声を獲得する競争の、形式化された方法を意味していました。現代の「民主主義」社会で繰り広げられる選挙だとか政治闘争にも通じる、競合的政治フィールドの典型的事例ですが、ここにも領土主権も行政機構も存在しません。pp.445-446
WDはこれらの社会を「第一次レジーム」と呼びます。3つの基本的支配形態のうち一つだけを中心に組織化しているからです。チャビンの場合は知の統制であり、オルメカの場合はカリスマ政治です。p.446
pp.421-446まとめ
ヨーロッパ人にとって、アステカとインカは分かりやすい「国家」でした。インカは皇帝が主権を握り、強固な官僚制がそれを支えていました。アステカは皇帝こそいませんでしたが捕獲した奴隷が大量に殺害されるなど暴力的な主権があり、官僚制もありました。しかし、マヤの場合はスペイン人が来た頃には徹底的に脱集権化されていて様相が異なります。WDは時代を遡って、オルメカについても語るのですが、オルメカには軍事的な痕跡も官僚支配の痕跡もなくただ球技場が残され、勝者の石像だけが残されていることからWDは定められた季節にカリスマたちが球技で競うというイベントで人々を動員していたと推測します。また、インカに先行したチャビン・デ・ワンタルでは、秘教的知を伝えるイニシエーションの儀式を執り行う施設に人々が動員されていたとみます。
つまり、オルメカは社会支配の3要素のうち、カリスマを競う球技競技だけがあって、暴力も情報も社会支配に使っていない社会であり、チャビン・デ・ワンタルは社会支配の3要素のうち、秘教的知という情報のみを用いて社会支配を行い、暴力もカリスマも使っていない社会です。WDはこうした社会を一次レジームと呼びます。
では、知の統制を行わず、競合的政治フィールドを持つこともなく、ただ暴力という主権原理だけで組織されている社会はあるのでしょうか?WDは18Cのルイジアナ南部のナチェズがそれに近いのではないかといいます。リオグランデ川以北で唯一の神聖王権の事例であり、官僚制度は最小限で、競合的政治フィールドを持たない社会です。普通、ナチェズは国家とは呼ばれませんが、主権だけがあるように見えます。つまり「国家なき主権」です。p.446
ナチェズの例:国家なき主権
ナチェズには<大村落>と呼ばれている集落があり、そこには神殿と宮殿がありました。そこに住む王は<偉大なる太陽>と呼ばれ、民に対しては恣意的な処刑、財産の没収を行い、王室の葬儀には家臣たち(王のケアをする平民たち)が人身御供に捧げられました。宮殿はナチェズの全人口4000人を収容できましたが、一年のほとんどの間<大村落>は過疎化していました。王の恣意的な権力が強すぎて、誰も寄り付かないのです。そして王はほとんど宮殿から出ないので、一般の人々は平和に日常生活を送っていました。そして王の使者が伝える王の命令を拒絶していました。pp.446-448
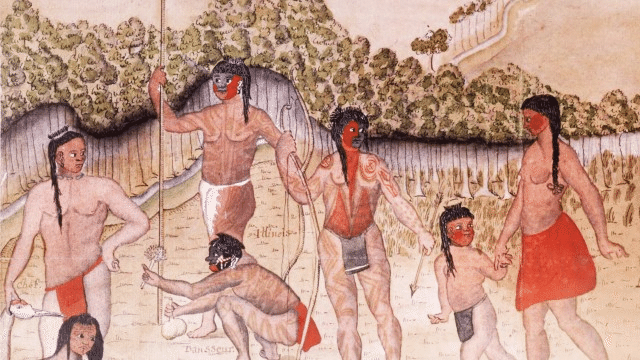
王は古典的な意味での主権者であり、法よりも上位にあるとみなされるがゆえに、どんな法も彼には適用できません。彼が暴力的に振る舞うのは、彼の超法的地位を証明するためとも考えられます。神々が道徳に拘束されていないのと同様に、その威光を纏う神聖王も道徳を超えているのです。そしてこうした神聖王は歴史的に珍しいものではありません。
王の主権は彼の周辺では絶対的ですが、行政システムが不在のために、王から距離が離れている場所では、王の命令でも従いたく無いと思えば、人々は命令を拒絶します。言ってみれば、法を超越した主権者は実質的に無害なように封じ込められるのです。pp448-450
「主権はつねに道徳秩序との決別としてあらわれる。だからこそ王はしばしば兄弟を虐殺し、姉妹と結婚し、祖先の遺骨を冒涜し、、、、、宮殿の外に立って無差別に通行人を銃殺するなど、みずからの地位を確たるものにするためになんらかの暴挙にでるのである」「しかし、まさにいそのような行為そのものによって、王はおのれを潜在的立法家や高等法院として確立するのだ」とWDは説明をし、それを無差別に稲妻を落としながら人間の道徳的行為を裁く高位の神々と同じなのだとします。そして法を無視する暴力的な人間は神聖視されることで封じ込められるのです。それが主権の内的力学だとWDは説明します。p.450
WDは国家なき主権の例として、もうひとつ、南スーダンのシルック族の例をあげています。シルックの王(レス)も、目の前にいる人間には何でもできたとされます。彼は隔離されて住んでいましたが、孤児、犯罪者、家出人などが取り巻きを形成し、王の民から略奪を繰り返していました。シルックの人々は独立心が旺盛で命令されることを嫌う人々であり、王族には少しの敬意は払うものの、服従は拒んでいます。シルックの民話には残酷な王を民たちが殺す話も出てきます。シルックはどうも、穏やかで体系的な統治方法よりも、恣意的で暴力的な主権者が散発的に現れることを好んだようだとWDは言います。pp.451-453

一次レジームまとめ
使われる支配力 例 支配の形態
暴力 ナチェズ、シルック 恣意的暴力
情報 チャビン・デ・ワンタル 秘教的知
カリスマ オルメカ 球技競技
以上のように「第一次レジューム」を見て行ったわけですが、チャビンやオルメカのエリートたちがどのように労働力を調達したのか、どういう指揮系統があったのかは不明です。古代メソポタミアのような賦役(労働奉仕)が祝祭的に行われたのかもしれませんが、それも不明です。ただ、第一次レジュームの権力が季節的要素を有していたことは確実だとWDはしています。どのように労働力が動員されたのか、WDはそれを古代エジプトの例で説明を始めます。pp.453-454
古代エジプトにおける死者祭祀の起源
ここからWDはナチェズで見られた、王の葬祭に行われる人身御供が古代エジプトから中国に至るまで、世界の様々な地域で行われていたこと、そして多くの考古学者がそれを「国家形成」が進行している証拠として見ていることに注意を向けます。人身御供/儀礼的殺戮はほとんど例外なく、新帝国や新王国建設の最初の数世代に行われているからです。往々にしてそれはライバルのエリート一族が模倣し、それからその慣行が徐々に消えていきます。では、なぜそのような殺戮がなされるのでしょうか。pp.454-455
主権者の死にあたって、主権者が保持していた最後の暴力が炸裂するように多くの人間が殺戮されます。王室の近親者、高位の軍人、政府高官までが殺されることもあります。もちろん戦争捕虜や奴隷、平民、兵士も殺されたでしょう。しかし初期王国はなぜ葬祭にあたって大量殺戮を行い、権力が安定するとそれをしなくなるのでしょうか。pp.455-456
中国の殷でも数名の重臣が殉死して丁重に葬られ、それとともに敵対氏族からの戦争捕虜も殺されて辱めを受ける形で葬られていました。p.456
5000年前のエジプトの最初期(第一王朝)の王は殷の場合とは異なり、大勢の側近と共に葬られていました。王の日常のケアに身を捧げた人々(妻、衛兵、役人、料理人、宮内官、芸人、、、)が、死後の世界でも王が王であることを支え続けるために死んでいったのです。それは愛と献身の究極的な表現ではあるのですが、同時に王の所有物として処分されたということでもあり、大きなパラドックスをなしています。王の家族のような存在であり、王の所有物のような存在でもあるということです。pp.456-457
さらにWDは、使用人と家族が入り乱れた殉死者の雑多なリストから、これらの人々をまとめて大規模に殺害する暴力によって「かれらの差異を消し去り、単一の統合体(ユニット)に融解させ、使用人を親族へ、親族を使用人へと転化させることになったに違いない」と論を進めます。つまりエジプトの王朝は、すべての臣下は、王のケアをするために働いており、王家の一員として想像されるシステムとして作られたのであり、それを動かすために、「死後もケアをする究極の家族」を作り出すのが殉死という名の大量殺掠なのではないかとWDは推測します。p.458
古代エジプトにしても古代中国にしても、権力者の華々しい大量殺戮は、マックス・ウェーバーが言うところの「家産制」の基礎を築くことを意味していたのでは無いかともWDは推測します。家父長的権力が社会全体の主権に拡大していって、つまり「父による家族の統率」が社会の一般的組織原理となるときに、通過するのが殉死という暴力である、あるいはそうした暴力によって組織原理が確立されるのではないかというのです。身内の人間を大量に殺すのも(エジプト)、敵対氏族を大量に殺すのも(殷)、王権を生産する方法と捉えることが出来ます。p.458
家産制国家
ドイツの社会学者 M.ウェーバーのいう伝統的支配の一形態。家父長制的支配構造の特殊ケースとされ,支配者が自己の家産として領有する土地を家従属民に貸与することによって家共同体を分散させ,さらに家産官僚制の整備を通じて,家産制に基づく支配権の行使が及びえない領域でのさまざまな支配関係を政治的に統合しえた国家形態をさす。古代エジプトがその典型例としてあげられるが,その他多くの国々が近世にいたるまで,かなり著しい家産制的性格をもっていた。
ナチェズの神聖王権について説明した際に、「王は法や道徳秩序を超えた存在であることを示すために、法や道徳を犯し、法や道徳を犯すことで王は法と道徳秩序を超えた存在になる」という逆理が語られましたが、古代エジプトの大量の殉死は、王は全ての臣民の父であることを示すための暴力だということです。
こうした儀礼的殺戮はエジプト第二王朝の途中で終わり、支配者の死者祭祀が盛んになり、ピラミッドの建設が始まります。つまり臣民たちが支配者のための巨大な墓を作り出すのです。「死後の世界でのケア」が「お墓の建設」に置き換わるのです。労働者の町が設立されて国中から強制的に賦役労働者が動員される古代エジプトを我々は「国家」とみなしていますが、ナチェズやシルックのような個人的主権の原理から、死者祭祀という媒介を通してエジプトの「国家形成」が行われたのでは無いかとWDは推測します。それを説明するために、エジプトの先王朝時代の話が始まります。pp.458-459
エジプト先史時代から「国家形成」まで
エジプトやスーダンのナイル川流域における新石器時代は、中近東とは異なりました。BC5000年紀は穀物栽培は重視されず、ウシが重視されていました(第7章pp.301-302)。大雑把に言って、中近東(肥沃な三日月地帯)の新石器時代は文化的焦点は「家」に置かれていましたが、アフリカでは「身体」に置かれていました。極めて早い時期から身だしなみ用品や身体の装飾品をともなった埋葬が行われています。それはエジプト王朝にも引き継がれる伝統ですが、男女大人子供問わずそうした物品は使われていましたし、身体そのものが一種のモニュメントでした。身体自体をモニュメント化するミイラ化の技術は新石器時代から試みられていました。pp.459-460
現代のナイル人であるシルックは、個人の自由を重視する移動性の高い社会を作っていますが、それと同時に気まぐれな専制君主を好みます。(前述の国家なき主権の例です。)家畜を中心に生活を組織していた多くの人々で、家父長制的組織形態が好まれる場合、似たようなことになっていますから、先史時代のナイルでも、おそらくはシルックのような王(レス)の一群によって支配されていたと想像できます。BC3500頃(第一王朝の500年前)からプチ君主の埋葬は見つかっていますが、大きなテリトリーを支配した王は現れず、小王制と小宮廷が乱立していたものと考えられます。この宮廷の中にはそれなりの規模の墓を残したものもあり、臣下の遺体とともに葬られてもいます。WDはこの状態を「主権の欠如というより、主権の過剰」と表現し、領土を行政的にも軍事的にも支配していないのに、見かけは壮大で絶対的な主権を主張していたとみています。p.461-462
こうしたナイル川流域の家畜を中心とした社会が、古代エジプトの農耕官僚社会にどのように移行したのかについて、ここからWDはアクロバティックな見解をしめします。(注釈の参照文献をみるとウェングローの論文に基づくものらしいです。) BC3500年頃、死者に対して当時の高級食品(本文では「エキゾチックな食品」)である、発酵パンと小麦のビールを供養することになり、王の墓にはそれを納める容器が備えられるようになりました。ナイル川流域やデルタ地帯で作られていたコムギが、死者の要求に応えてこの時期に洗練されて強化されたのだとWDは言うのです。p.462
もともとナイル川は定期的に氾濫するので、その流域は土地の分割が困難な地域でした。死者祭儀にはパンとビールを振る舞わなければならないという社会的要請から、持続的な分割が行われるようになり、安定した生産のため絵に鋤とウシを確保する必要が生じます。それが確保できない家族は別の手段でパンとビールを確保しなければならず、義務や債務のネットワークに絡め取られていくことになり、階級と支配ー従属の関係が生まれたというのがWDの見解です。pp.462-463
その傍証としてインカ帝国の例をWDは引きます。ペルーでの元々の日常食は凍結乾燥したジャガイモ(チューニョ)だったのですが、トウモロコシのビール(チチャ)が神々の飲み物として導入され、帝国全体の食物として広まっていきました。スペイン人が来たころには富裕層と貧困層の双方にとって儀礼に必要不可欠なものとなっていたのです。そしてトウモロコシは日常食となっていたのです。p.463
(日本において、高級加工食品であり神事に使われた餅が日常食になった過程に似ているかもしれません。)
エジプトではパン焼き釜やビールの醸造設備はBC3500頃に現れ始め、最初は共同墓地に隣接していましたが、数世紀のうちに宮殿や大墳墓に併設されるようになります。第一王朝もしくはその少し前から、死んだ王への食料供給を表向きの理由とした組織が形成されていきます。やがてパンとビールが産業規模で製造され、王室の建築プロジェクトに従事する季節労働者たちに支給されました。彼らも王へのケア供与者であり、一種の「親族」なのであり、少なくとも労働の期間中は十分な食料を供給されたのです。pp.463-464

労働者たちはパンと肉とビールを一緒に食べ、一種の「仲間」意識を育んでいたことが、残された落書きから読み取ることができます。そしてそれは船の乗組員の組織を模したものだったようです。海洋航海におけるチームワークの技術と、ピラミッドや神殿などのモニュメント建設のための技術には類似があるともされています。産業革命のときも、帆船における規律の技術が工場に移植されたとされています。ともあれ、規律技術で臣民を社会的機械に仕立て上げてモニュメント建設を行い、そのあとにお祭り騒ぎで労苦を称えたのです。pp.464-465
(p.459からをまとめ直すと、主権を過剰に振り回す遊牧民が、死者祭儀のための発酵パンと小麦ビールを必要とするようになり、そのパンとビールの製造が産業化されていったこと、また原料麦の生産のための農地や牛や鋤の確保のための債務が発生し、支配/隷属の階級分化がおこり、そして死者儀礼を中心とした王家の建築プロジェクトに人々が「王の家族/臣民」として再編されていく過程がBC.3500から第一王朝のBC.3000くらいまでに起こったことだということです。)
以上、世界で初めての「国家形成」を説明した上でWDは一般化を試みます。つまり、表向きはケアと献身に奉仕している社会的機械に例外的暴力が結合したものがエジプトの「国家」だったとみるのです。実に逆説的な話です。ケアリング労働とは、そもそも機械的労働と対立しています。ケアの対象の特質、ニーズ、特殊性を認識して理解した上で、必要なものを提供するのがケアリング労働です。その一方で私たちが「国家」と呼んでいる組織になにか共通の特徴があるとすれば、ケアリングへの対象を抽象的なものに置き換えようとする傾向なのだと、WDは指摘します。つまり「国民(ネーション)」という抽象をケアしようと欲する何かです。古代エジプトでも、人々の献身は支配者や死者のエリートという壮大なる抽象に振り向けられていました。そして組織は家族のイメージと共に機械としてのイメージで想像されるようになります。人間活動のほとんどが統治者の世話をするなり、神々を世話する統治者を手伝うなりして、上方に向かっていき、それが神の祝福と保護という形で下方にむかう流出を招き入れるのです。物理的には労働者の町での大宴会がその流出の例となります。pp.465-466
神々
奉仕(ケア)↑ ↓祝福
統治者(王)
奉仕(ケア)↑ ↓祝福と保護、宴会
臣民
この「国家形成」はモデルとして、どこまで他地域に適用できるのでしょうか?死者祭祀の供物としてのパンとビールの話のときにインカ帝国の例を傍証として引いたようにインカ帝国には適用できそうです。実際、古代エジプトとインカ帝国には類似点が多々あります。死んだ支配者のミイラ化、ミイラ化した支配者の領地が維持される仕組み、生きている王の巡回、都市生活への反感(都市は祭祀センターで定住者はいなかった)などです。しかし、この両者は他の「初期国家」とは大きく異なっているのです。p.466
メソポタミア、マヤ、中国の初期国家
初期王朝時代のメソポタミアは数十の都市国家からなり、それぞれの都市国家はカリスマ的戦士王によって統治され、支配権を争っていました。しかし、メソポタミアのこうした王たちは、道徳的な秩序の外に立って好き勝手に振る舞えるような存在だったのか、つまり「主権」を主張していたのかWDは疑っています。彼らは都市を支配していたことになっていましたが、都市は自己統治の伝統を有する商業的ハブであり、神殿行政システムに支えられた都市神がいて、王が自らを神として振る舞うことはありませんでした。(第8章pp.338-347)神の代理人もしくは神の守護者です。第6章で見てきた、三日月地帯低地の行政管理的秩序と高地の英雄社会的な政治というふたつの原理が共存していたと言えるでしょう。そして主権は神々にのみ属していました。p.467
古典期マヤの統治者アハウは一級の狩猟者であり一級の神のなりすましであり戦士であることを意味していました。いつも小競り合いをしている小さな神々のようなものです。そして行政機構はありませんでした。行政的なヒエラルキーはすべて宇宙に投影されており、天体の動きで世の全ては決定されていました。pp.467-468
こうした初期国家に共通点はあります。システムの頂点に華々しい暴力が備わっていること、家父長的世帯組織に依拠して模倣しているということ、分割された社会階級の上に統治の装置が置かれていることなどです。しかし、ここまで見てきたように、これらの要素は中央政府がなくても存在しましたし、あったとしてもその形態は多様でした。メソポタミアでは社会階級は土地保有権と商人の富に基礎をおき、マヤでは権力の基盤は土地や商業にはなくて、人の流れや忠誠心を統率する力にありました。p.468
中国の場合、殷の首都の安陽は宇宙論的蝶番であり、生者と死者の世界の狭間に位置する舞台でした。生者のためには行政機関であり、それと同時に王家の墓地と遺体を安置する神殿でもありました。そして工業区域では祖先との交流儀式に用いられる青銅器や翡翠が生産されています。この点でエジプトやインカに似ていますが、その他の点がまるで違います。殷の支配者は広域におよぶ主権を主張しませんでした。占いが重要な儀式であった点も他の初期国家とは異なります。いかなる王の決定も占いによって神々や祖霊の承認を受ける必要がありました。亀甲占いの結果は官僚が読み取って記録され、保管されました。そして、その他の用途で文字が使われていた形跡は発見されていません。そして、殷の統治者たちも生贄に使う人間を獲得するために戦争を行っていました。統一王朝の体裁は保ちながらも、競合関係にある宮廷とは争いを続けて、英雄社会的な闘技的ゲームを繰り広げていました。pp.468-470
こうしてみると、エジプトやインカのように地域での社会システムが単一の政府のもとに統合されたのは、珍しいケースに属します。殷のように統一は名目だけのことで、実際には諸宮廷が争い続けるほうが一般的だったようです。メソポタミアでも覇権が世代を超えて続くことはありませんでしたし、マヤでも勢力圏争いは決着がつかないまま続いていました。pp.470-471
「第二次」レジーム
3つの基本的支配形態、暴力の支配、知の支配、カリスマ権力はそれぞれに、主権、行政管理、英雄政治という形で結晶化するというのが、以前の議論でした。その3要素の一つだけを発展させたのが「第一次」レジームでしたが、ここで論じた「初期国家」は3つのうち二つを統合した支配の「第二次」レジームと規定することができます。その組み合わせ方は事例ごとに異なります。エジプトでは主権と行政が、メソポタミアでは行政と英雄政治が、マヤでは主権と英雄政治とが融合しました。そして、いずれも3つ目の原理は人間世界から排除されて非人間的な宇宙に転移されているとWDはいいます。pp.471-472
エジプト メソポタミア マヤ
暴力 主権(ファラオ) ❌(神話) 主権(アハウ)
情報 官僚支配 官僚支配 ❌(宇宙)
カリスマ ❌(神々) 都市支配者間の戦争 支配者間の戦争
エジプト第1中間期
古代エジプトの浮き彫りで描かれている世界では、天において神と王は同列であり、地上は農村と狩猟場の二つから成っていて王に恭順しています。それが古王国建設者が描いたエジプトのイメージであり、それをシンボライズするのが死すらも征服していると言わんばかりの巨大葬祭モニュメント(ピラミッド)でしょう。エジプトの王権は二つの顔を持ち、内なる顔は広大なる拡大家族の至高の家父長であり、外なる顔は戦争指導者であり狩猟のリーダーです。ただし、王は名誉のために命や尊厳、自由を賭ける英雄的人間としては描かれませんし、戦争も政治的な競い合いとして描かれません。王は負けるはずがないのです。国家の役人たちが競い合うフィールドもなく、役人たちはただただ王との関係(王をどのようにケアするという機能)があるだけです。主権と行政は肥大化していますが、競争というフィールドが見事に欠落しています。エジプトにはローマの戦車レースも、オルテカの球技のようなものも現れません。勝ち負けの世界は神々の世界に限られているのです。pp.472-474
君主制は記録された歴史を通じて一番人気のあった制度ですが、その魅力とはケアリングの性格を帯びた感情と、おそるべき恐怖の感情の両方を同時に動員できる能力に関係しているとWDはしています。p.474
恣意的な暴力を振るう権力(主権)と人間を機械の歯車のように使う行政機構とを統合し、英雄的競合政治が欠けていたエジプトですが、第一中間期(暗黒時代とも言われる、BC2181-2055)に反転します。古代王朝末期から州執政官(将軍)という地方指導者が統治機能を引き継いでいきました。彼らが先王時代に争いあった小王たちと異なるのは、自分たちを民衆的英雄として表現している点にあります。カリスマ的地域指導者たちであり、中央の家産制国家の崩壊と共に、公共サーヴィスの質と神々への信心を通じて、カリスマ指導者たちが民衆の支持を競い合ったのです。pp.474-476
「われは、餓えし者にはパンを与え、裸のものには衣服を与え、、、、」
古王国時代は主権原理と対立する貴族政治も人格統治もありませんが、第一中間期にこうしたカリスマ指導者の統治が行われ、世襲貴族が誕生しました。権力行使の枠組みが、主権からカリスマ政治に移行したのです。同時に民衆による王へのケアが、支配者による民衆へのケアへと変化しました。第一中間期は壮大なモニュメントが建造されなかった故に、「暗黒時代」と呼ばれ混沌の時代と見られていますが、重要な政治変化が生まれたことに注目するべきだとWDは言います。p.476
行政官僚制の起源 ーウバイド期ー
ということで古代エジプトにおける主権と行政官僚制の結びつきを見てきたわけですが、初期国家の中でこの結びつきが稀であるにも関わらず古代エジプトが国家の発祥地とみなされてきた理由は、近代人にとっての国家のイメージに合っていたからだろうとWDは言います。そして、社会が大きくなれば必然的に主権者と行政管理が生まれるというのが、これまでの一般的な歴史理解でした。これが間違っているのは、第8章で紹介した事例でも明らかです。複雑な灌漑施設は行政官が管理しなければ建設も維持もできないというのが普通の理解でしたが、バリでは農耕民が自分たちで運営・調整をしていました。記録に残っている初期国家の官僚たちも、灌漑施設に関与していたという証拠はほとんど存在していないとWDは言います。そして古代の皇帝のほとんどは臣民たちが道路を掃除したり排水溝を整備することに関心をもちませんでした。pp.476-478
(注:中国の歴代の皇帝は治水事業に関わったとされていますが、、、、夏朝の創始者である禹は黄河の治水に成功したと伝えられ、その後の実在の統治者たちも治水に手を出しています。)
また、知の独占的アクセスを支配の基盤としていたレジーム(統治)があったにしても、それは実用的な知とは限りませんでした。チャビン・デ・ワンタルでは、それは神秘主義的な知であったと思われます。名簿、台帳、会計処理、監督、監査、文書アーカイブの保管といった技術にしても、元はメソポタミアの神殿やエジプトの祖先崇拝、中国の神託の解読で生まれたものであり、実務から生じたものではありません。だから、社会が大規模になって複雑化したために、それらの情報管理技術が現れたということではないのです。p.478
それならば、専門的な行政管理技術はどこで生まれたのか?WDはシリアのテル・サビ・アブヤド遺跡(BC.6200頃)に注目して、小規模の共同体でそれが生まれたのではないかと推測するのです。テル・サビ・アブヤド遺跡は文字の発明に3,000年先立つ150人程度の後期新石器時代の村であり土製の幾何学的トークンを収めた「家政用書庫」があり、それによって資源の配分を記録していたようです。また、デザインが刻まれた印章があって、容器の栓に刻印するのに使われていました。そしてその栓の模様が照会できるように村のオフィスのような場所に集められて保管されていました。pp.478-479




テル・サビ・アブヤドの住居は均一で特に大きな家は無く、豪奢な埋葬も見られません。小規模な家族群が複雑な分業(家畜の放牧、穀物の播種・収穫・脱穀、亜麻を織る、土器作り、ビーズ作り、石彫り、冶金、、、子育て、老人のケア、家屋の建設とメンテ、冠婚葬祭)をしていたと考えられます。こうした複雑な分業を平等的にこなしていたであろう共同体は他にもありましたが、それらが記録保存技術を生み出したということは無いようです。pp.479-480
このサビ・アブヤドに見られる新技術の導入はメソポタミア周辺の村々に大きな影響を与えたようです。都市が発生する2000年前に、この技術の普及に伴って村落間の個性の差が消えていったのです。家屋も土器も標準化されていきました。この期間はウバイド期と呼ばれています。そして、都市が現れる以前までは、村落内や村落間で格差が生まれることが阻止されるようにこうした技術が使われていたようだとWDは言います。つまり、こうした管理ツールは富を徴収したり蓄積したりするためではなく、それを防ぐためのものだった可能性があるというのです。pp.480-481
アンデスの村落共同体アイリュ
アンデスのアイリュと呼ばれる平等原則を基礎に置いた村落共同体もそうした行政技術を持っていたと考えられます。メンバーは同じ服を着て、川筋ごとに布地のデザインは同じでした。家族の大小で農地は再配分され、どこかの家族が特別に豊かになることを防いでいました。各家庭が季節労働の不足に陥らないように相互に手助けをしており、そのために若い男女の人数が把握され、高齢者や病弱者のケアも保証されていました。世帯間の貸し借りは記録が残され、年末にはすべての債券と債務が帳消しになります。「村落官僚制」です。こうした貸し借りを記録していたのがキープ(結縄)で、債務が発生したり帳消しになるたびに結んだり解いたりしていました。

ツールは違いますが、メソポタミアでの行政管理システムと同じ発想があったように見えますし、背景にあるのは平等の理念だったのだとWDは推測します。p.482
行政が主権と結びつくとき
もちろん、こうしたシステムには危険性があります。こうした等価性に基づくシステムは、他の社会組織法と結びつく時に公平・公正性を装うことができます。特に征服者による暴力支配と結びつくと厄介です。今までの議論で言うところの主権が、行政管理技術を社会的支配や専制のためのツールに転化させるということです。p.482
インカ帝国では、すべてのアイリュが中央政府の下に置かれて、政府への労働債務の記録用にキープが利用されています。地域で結んだり解いたりしていたキープとは異なり、中央政府によって厳格に管理されたキープです。インカ帝国は穏健な帝国で温情的な一種の原始社会主義国家とみなす見解もありますが、社会保障を提供していたのはアイリュであって、インカ宮廷の行政機構は搾取的性格のものでした。世帯は10、50、100、500、1000、5000の単位にまとめられて、それぞれに労働義務が課せられ違反者には罰が与えられました。その結果、スペイン人が到着した頃には世襲的債務労働者階級が急速に増加しています。pp.482-484
インカがすぐれた行政管理システムをもっていたことは確かです。しかしそれは既存のアイリュというシステムの上に、一律的なシステムを押し付けたものです。それが主権が官僚制と結びついた時の典型様態なのかもしれないとWDは書きます。個々人や世帯ごとの固有の歴史を無視して、公平を装ってすべてを数字に還元し、債務奴隷が発生し続けるように仕組むということです。p.484
中東の歴史の中でも、これと同じことがおきました。旧約聖書の預言書には貢納を要求された農民たちが家畜や畑を巻き上げられて妻子を債務奴隷にせざるを得ない状況と、農民たちの怨嗟の声が満ちています。これは中国やインドでも似たようなことになっています。それが官僚制帝国の姿なのだとWDは言うのです。p.484
注:このあたりはグレーバーの『負債論』に詳しく述べられています。「ネヘミヤ記」5:1–6なども参照ください:
****
さて、ここに民がその妻と共に、その兄弟であるユダヤ人に向かって大いに叫び訴えることがあった。 すなわち、ある人々は言った、「われわれはむすこ娘と共に大ぜいです。われわれは穀物を得て、食べて生きていかなければなりません」。またある人々は言った、「われわれは飢えのために、穀物を得ようと田畑も、ぶどう畑も、家も抵当に入れています」。ある人々は言った、「われわれは王の税金のために、われわれの田畑およびぶどう畑をもって金を借りました。現にわれわれの肉はわれわれの兄弟の肉に等しく、われわれの子供も彼らの子供に等しいのに、見よ、われわれはむすこ娘を人の奴隷とするようにしいられています。われわれの娘のうちには、すでに人の奴隷になった者もありますが、われわれの田畑も、ぶどう畑も他人のものになっているので、われわれにはどうする力もありません」。
わたしは彼らの叫びと、これらの言葉を聞いて大いに怒った。
こうした暴力的な不平等も、法的平等のフィクションから始まっている点にWDは注目します。その法的平等こそが人間や物を交換可能なものにして、従属者に非人格的な要求を行うことを可能にするのです。そして元来人間同士で結ばれた「約束」であったものが非人格的で譲渡可能なものとなったとき(つまり官僚制化して、主権が絡んでくる時)「約束したり誓いを立てて人間関係を築く自由」は、正反対の債務奴隷や永久奴隷に転じるのです。たとえ「約束」が不合理な結果をもたらすときであっても、人々は長い時間を要しながらも話し合って解決策を見出してきました。しかし、主権的権力がそこに介入して地方役人が「規則は規則だからあがいても無駄である」と宣言するとき、官僚制はモンスター化するのです。pp.484-486
国家の起源を論じることは不毛である
WDは「国家(State)の起源」を論じることは幻影を追うことだ、と言います。現在、地球上の土地は国家で覆われており、国家形成は必然ともみなされています。そして、これまでに世の中で行われてきた議論は「複雑性が上昇して、ヒエラルキーが生まれて、国家が形成される」という説話に固執しており、「国家」という言葉をそのほかの意味で使用するのが困難になっています。現在の国家の姿が過去に投影されて、ある程度複雑な社会はそうした「国家」の特質を備えるようになるという思い込みから議論が始まっています。WDはそれは幻影だというのです。pp.486-487
たとえば、農耕によって余剰が生まれ、そこからフルタイムの軍事・行政・司法の専門家が現れ、国家形成が進んだという物語は根強くあります。しかし、本書で今まで見てきたレジームの中で、実際にフルタイムの専門家を配置していたものはほとんどありません。常備軍は存在せず、戦争は主に農閑期のものでした。エジプト古王国、殷王朝、メソポタミアの初期王国、古典期のアテネにおいては、農村の土地管理者、商人、建築家などの職業についている人々が交代制で統治機関で働いていたのです。さらにいえば、これらの「初期国家」が季節性のものであった可能性は強いのです。建築プロジェクト、ページェント、祝祭、国勢調査、忠誠の儀式、裁判、公開処刑などは特定の時期に集中する傾向があり、その他の時期には農作業や放牧で臣下が分散していました。何千人もの人々を動員したり、人を殺したり傷つけたりすることが出来たのですから、王国は実在していたとは言えるのでしょう。しかし、それは現れたり消えたりする王国でもあったのです。p.488
ルーズでフレクシブルな遊戯農耕から本格的な農耕への転換があったように(第6章)、特定の季節に現れていた遊戯王国が、どこかで本格的な王国に転換したと言うことなのかもしれません。その過程には家父長制の出現と世帯内での女性の地位の低下なども関わっていた可能性をWDは示唆します。p.489
季節限定の王たちには、自身が散発的な存在であることに不満があるでしょうし、臣民の側にも王を通じて宇宙と繋がるような儀礼を実質的に永続させたいという願望、あるいは全体主義的な衝動があるのでしょう。「国家」に意味があるとしたら、その願望に基づきます。ピラミッドのようなモニュメントも、数ヶ月間だけ姿を現している権力を、永遠に見せようとするための試みといえるでしょう。その(永遠に見せようとする)試みが成功したからこそ、我々はそれをそのように受け取っていますが、臣民たちがどのように権力者を見ていたのかは本当のところは分かりません。(碑文に残されているような)エリートが主張する国家の姿と、国家の実態にはギャップがあります。見せかけの国家の姿に惑わされることなく、政治の実態を把握しなければならないのです。pp.489-490
現在、我々が国家とみなしているものは、起源を異にする三つの政治形態、つまり主権、行政管理、カリスマ的競合が合流したものであるというのがWDの主張です。近代国家は、その3つがたまたま合流したものなのです。かつての王権(主権)は近代国家では民衆/人民/国民と呼ばれる存在に委ねられ、官僚制は民衆/人民/国民の利益のために存在するとみなされ、かつての貴族的競合と報奨のシステムが「民主主義」という呼ばれて国政選挙という形をとっています。そこには必然性は無かったのだとWDは言うのです。それが証拠に現在国家をまたがる官僚機構(IMF、WTO、JPモルガンのような格付け機関など)はあるのに、世界主権の原則は確立しておらず、世界的競合政治の場もないではないかとも指摘します。pp.490-491
そもそも「文明」とは何なのか
さらにWDは「文明」と「国家」がひとつのパッケージとして扱われてきたことに疑義を挟み、「国家」が起源を異にする諸要素の混成体であったように、「文明」もそのような混成体であり、いまやそれが崩れつつあると言います。そして「文明」とは何かを問い直そうとしています。pp.491-492
この章で「初期文明」として扱ってきたのは、古代エジプト、インカ、アステカ、中国、ローマ、ギリシャなど、一定の規模とモニュメントを備えた社会でした。いずれも深い階層化社会であり、権威主義的な統治が行われ、暴力と女性の徹底的な従属で支えられていました。そして「文明」という概念には影があるとWDは言います。世界秩序、神々の祝福、天命などの手の届かない理想のために人々の大切なもの(基本的な3つの自由など)を犠牲にしているのが文明であるとWDは指摘します。pp.492
「文明」とは「都市で暮らす習慣」と私たちは思い込み、都市は国家を含意するとみなしてきたとWDは指摘しますが、これは文明:civilization と都市:cityが同語源(ラテン語:civilis)であることから生じている一般解釈のようです。これに対してWDはcivilisは自発的連合による組織化や相互扶助を意味するのであって、インカや殷などよりもアンデスのアイリュやバスクの村落共同体の特性を意味していたとします。そして相互扶助、社会的協働、市民的活動、歓待、他者へのケアリングなどが真に「文明」を形成するのだとします。そして、その意味での文明史の叙述はこれからの仕事であるとします。p.492
WDはマルセル・モースがそうした文明史への一歩を踏み出し、現在の考古学者たちも都市よりもはるかに古い時代に遡る過程生活、儀礼、歓待の痕跡を見つけて文明史を書き換えつつあります。現代考古学の重要な発見は、孤立していたと思われた「部族」間に親族や商業の遠隔ネットワークが存在していたことでしょう。世界中の小さな共同体が、モラル共同体としての文明を形成していたのです。pp.492-493
世襲の王、官僚、常備軍を持たないままに、これらの小共同体は数学や暦、冶金術、農耕を行い、植物から毒物、薬物、幻覚剤を抽出する技術を開発し、織物や籠編み、轆轤と土器、石器制作、航海技術を発展させたのです。p.493
女性による文明
文明をこのように捉え直した時、その中核には女性の存在が明らかにあるとWDはいいます。彼らに言わせれば、複雑な数学的知識は織物やビーズ細工の具体的実践の中から生まれた可能性が高いというのです(6章)。これまで「文明」と呼ばれてきたものは、女性を中心とした知識体系を男性がジェンダー的に流用したものではないかとWDは言います。本章の冒頭では、野心的な政治の拡大や少数への権力集中は女性の周縁化を伴うことが多いと指摘しています。しかし、集権的な統治形態の中でも女性と女性の関心事がものごとの中心にありつづけた事例もあります。本章の最後はその事例の紹介です。pp.493-494
BC.1700-1450年にクレタ島で栄えたミノア文明は異質な社会でした。最大都市であるクノッソスは人口25000人で、東地中海の多くの都市とある意味では似ています。中心には工房施設と貯蔵施設がありますし、文字も使われていました(線文字A)。

しかし、君主制の痕跡がまるで無いのです。そしてミノア芸術でもっとも頻繁に描かれている権威ある人物は女性です。pp.494-495

こうした女性は男性よりも大きなサイズで描かれており、近隣文明の例に従えばこれは政治的優位性を示すものです。指揮のシンボルである杖を持ち、祭壇の前で儀式を行い、王座に座り、超自然な生き物や猛獣に囲まれるなど描かれています。一方の男性の描写の多くは裸のアスリートか、貢納を持参しているか、女性の高官の前で従順なポーズをしています。周囲の文化は高度に家父長制的社会であり、このような絵画はまったく見られないものです。pp.495-496
ミノアのこうした宮殿絵画に対して、女神あるいは地上の権力を持たない巫女と解釈され、ミノアの政治に絡める議論は避けられるか一切無視されていることにWDは疑義を突きつけますが、これはWDお得意の脱線です。p.496
輸入品も独特です。ミノア商人はほとんど男性であったと考えられるのですが、彼らが海外から持ち帰ったものには女性の影がちらつきます。エジプトから持ち込まれた打楽器や化粧瓶、授乳の母子像、スカラベのお守りなどは、エジプトの王族では無い女性たちの儀礼、ハトホルの儀式に関係するものなのです。クレタ島の特権者の墳墓にこれらのアイテムは集中しており、女性がこうした輸入品の需要サイドであったことが想像できるのです。また、ミノア芸術には戦争のイメージはまったく現れません。その代わりに遊戯や快適な生活にこだわった描写がみられます。pp.496-497
BC.1400年頃に近隣社会、たとえばギリシャ本土のミケーネやピュロスでは要塞が築かれるようになり、そこからの侵攻が始まり、ややあってクノッソスは占領されクレタ島が支配されます。侵攻してきたのは典型的な戦士貴族の社会でした。彼らはクレタ島に線文字Bを付け加え、読み書きのできる一握りの役人が作物や家畜を調査して、税を徴収して、職人に原材料を分配するなどの行政業務を行うようになりますが、小規模なもので、季節ごとの税以外は、王の主権は周辺の民衆にはあまり影響しなかったようです。ピュロスの宮殿は良く保存されており、巨大な炉を中心とした影の多い空間で、壁には屠殺される雄牛と竪琴を弾く吟遊詩人、王座に向かう行列などが描かれていました。pp.497-498
これに対してクレタ島クノッソスの「王座の間」はオープンスペースで、石のベンチが置かれ、近くには階段状の浴室がありました。どうも月経に関係する女性のイニシエーション儀式に関連するもののようです。クノッソス宮殿を発掘したエヴァンズは、「王座の間」を男性のためのものだと主張しましたが、WDはそこを女性評議員たちの場所であっただろうと推測しています。ミノア文明とは女性による政治的支配のシステム(女祭司の集団によって統治されるある種の神権政治)だったというのです。ミノアの美術は、ギリシャ本土の美術や中東の美術とはまったく違う感性で描かれています。ミノアの芸術に英雄は現れません。そこに描かれているのは「戯れ人(プレイヤー)」だけだとWDは言います。pp.498-500

本章を通じてWDは「国家形成」と呼ばれる過程は複雑で、多種多様であることを示してきました。とはいってもある程度の制約はあって、それが主権、行政管理、競合的政治の「三原理」と、その組み合わせです。しかし、ミノアの宮殿はそこからも外れた何かが展開していたようにも見えます。ミノアの支配のレジームとは何だったのでしょうか?断片的な知識から言えることはまだまだ限られています。p.500
しかし、考古学が新しい科学技術を使って、いままでは何も無かったかのように見えた地域からも「失われた文明」を発見していくだろうことは間違いありません。そのときに、近代的国民国家のイメージを投影することに抵抗して、今までとは違った社会的可能性を考察するべきなのだとして、WDはこの章を締め括ります。p.501
『万物の黎明』読書ノート その0
『万物の黎明』読書ノート その1
『万物の黎明』読書ノート その2
『万物の黎明』読書ノート その3
『万物の黎明』読書ノート その4
『万物の黎明』読書ノート その5
『万物の黎明』読書ノート その6
『万物の黎明』読書ノート その7
『万物の黎明』読書ノート その8
『万物の黎明』読書ノート その9
『万物の黎明』読書ノート その10
『万物の黎明』読書ノート その11
『万物の黎明』読書ノート その12
