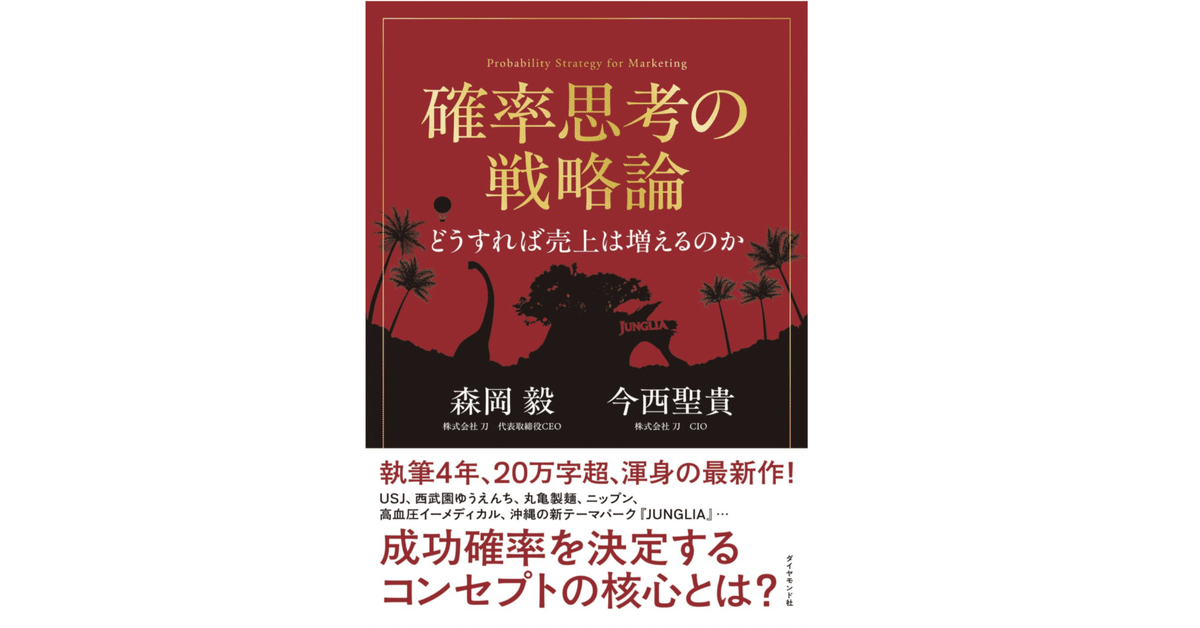
確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか?(前作を読んだ方向けのnote)
2024年10月現在で35刷13万部の大ヒット書籍「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」の続編「確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか?」が本日1月29日に発売されました。このnoteでは2作目を赤本、1作目を青本と記載し、主に赤本の内容を紹介します。
赤本(2作目)
青本(1作目)
青本を読んだことがない方は、まずは赤本を買うことをオススメします。赤本を読んだ上で実装レベルの知識を学びたくなったら青本、または後ほど紹介する関連書籍の活用をおすすめします。他にも関連するnoteや記事も紹介します(更新情報を含む)。
自己紹介(株式会社秤 小川貴史)
マーケティング・アナリストの小川と申します。2019年に森岡毅さん今西聖貴さんらの「刀」に憧れて「秤」という法人を立ち上げ、マーケティング分析の書籍を3冊出版し2024年11月には効果分析の特許を取得しました。特許は青本で紹介されていた確率モデルを用います。因果推論の分析と組み合わせることで1年間のTVCMの効果が東京ディズニーランドは147億円、マクドナルドは234億円、レッドブルは58億円の様に金額換算することができる技術です。
私は著者お二人との面識はありませんが、彼らを模範としつつ、独自の技術を研究しながら活用して複数のブランドの成長を支援しています。青本がなかったら独立も書籍出版も特許取得もありませんでした。
赤本に数式はほとんど無し。著者のノウハウや思考法を万人向けに解説。
Amazonで予約購入していた待望の赤本が届いて、真っ先に私が何を探したか?それは青本にあった多くの数式を解説した「付録」です。
そこには森岡毅さんがUSJにジョインして一発目の成功事例となったハロウィン・ホラー・ナイトを仕掛けた際に、その時期に注力する意思決定を導いた分析で、調査対象者に「最後に〇〇したのはいつですか?」(例 来園した、買った、飲んだ、食べた等)と聞いたデータからMとKを導くことで購買回数の分布などを数理的に把握する「ガンマ・ポアソン・リーセンシー・モデル」の数式などが解説されていました。前述した特許の要素技術としても日々活用しています。今回は数式の付録はありませんでしたが、青本よりも間口を広げて著者のノウハウと思考法をわかりやすく解説するものでした。
赤本の内容
赤本には数式の記載があまりなく、青本より読みやすくなっています。推計40万人と言われるマーケティング従事者に限らず、マーケティング関連業務の経験がある方やマーケティングをビジネスに取り入れたい方(かつて以下のnoteで調査結果を紹介した推計328万人)がターゲットだと思います。マーケターが本来行うべき「コンセプトの作り方」の紹介に重きが置かれています。
青本で紹介された確率モデルの数式(NBDモデル)は1959年にアンドリュー・アレンバーグ氏が発見したものです。赤本の冒頭のPart1(第1章~第3章)では氏が発見した最も重要な「ダブルジョパディの法則」を紹介しています。これは市場浸透率が低いと購買頻度も上がらない2重の苦しみとなるものです。マーケティング界の重鎮のフィリップ・コトラー氏(以下コトラー)のターゲティング理論を否定する解説もあります。コトラー信者にエビデンスを突きつけて目を冷まさせる書籍がブランディングの科学です。コトラーから学ぶ必要があるマーケティング初学者には、あまりオススメできませんが、論文として発表されている重要な法則と、それを裏付けるエビデンスとなるデータを知ることができる貴重な書籍です。赤本の冒頭ではブランディングの科学の要点を交えて、消費者行動のメカニズムを紐解いた重要な法則を解説しています。Mを増やすにはターゲットを狭めることではなく拡げることが重要なのです。
赤本のPart2以降は、青本を読んで「プレファレンス、『M』が重要ということは分かった!じゃあ、どうやってMを増やせばいいのか?」という問いに対して具体的な方法や考え方を示すものです。主に「マーケティング・コンセプト」のつくり方の解説です。終章にかけて読み進めると、あたかも著者にレクチャーしてもらっている様な感覚で、仮説を考えながら学ぶことができます。
赤本の目次
序章 “選ばれる確率”をどうやって増やすのか!?
●メロンパンの悲劇
●前作から感謝を込めて
Part1 選ばれる確率を増やすブランド戦略の本質
第1章 「プレファレンス」に集中せよ!
[1] 脳はブランドで選んでいる!〜なぜ「プロダクト」よりも「ブランド」なのか?〜
[2] 脳はランダムに選んでいる!〜個人の選択は「ポアソン分布」している〜
[3] 成功が成功を呼ぶ!〜社会全体では「ガンマ分布」している〜
[4] 市場構造の本質はプレファレンスである!〜「負の二項分布」が支配する世界〜
[5] マーケティング戦略の変数はたった3つしかない〜プレファレンス、認知、配荷〜
第2章 狭めるな! 拡げよ!
[1] マーケティング界の巨人への反論
[2] ジビエレストラン vs 牛肉レストラン
[3]「ターゲティングありき」という間違い
●「浸透率」と「購入頻度」は必ずセットになる
●“群雄割拠”市場ではどうか?
●ターゲティングの正しい理解
[4] ターゲティング理論の間違いを明示する数学的証明
[5] ターゲティングするのはどんなときか?
●WHATの定義でターゲティングが有効なとき
●HOWの定義でターゲティングが有効なとき
[6] 狭めるな! 拡げよ!
第3章 「重心」を衝け!
[1] 戦略的に集中すべき「重心」という考え方
[2]「重心」の見つけ方
[3] ブランド戦略の「重心」を定めるフレームワーク
(1)ポジショニングは相対的
(2)「消費者価値」にポジショニングする
(3)ブランド・ポジショニングの「重心」を定めるフレームワーク
●ブランド戦略の「重心」は、本当に1つだけなのか?
(4)実例:経営再建時のUSJのブランド戦略の「重心」について
Part2 プレファレンスを伸ばす「コンセプト」の本質
第4章 「コンセプト」とはなにか?
[1] その人の世界は、その人の認識のみで成立している
[2] 3つの世界を往来すると起こる“エラー”
[3]「コンセプト」はあなたの脳がつくりだす!
[4]「マーケティング・コンセプト」とはなにか?
第5章 強い「マーケティング・コンセプト」をつくる
[1]「コンセプチュアル・セル」の威力
[2] 競争に有利な「ブランド・エクイティ」をつくる
[3] 最初に「ブランド・エクイティ」を明確化せよ!
[4] ブランドの設計図「ブランド・エクイティ・ピラミッド」
(1)マーケティングの成功は、ブランド・エクイティの設計から
(2)ブランド・エクイティは、まず60点を確実に!
(3)90点を設計するために必要なもの2つ
(4)“全員野球”を可能にするブランドの設計図の恐るべき力
第6章 強いコンセプトは消費者理解がすべて
[1] モニタールームでは到達できない深淵
[2] “凡人”と“狂人”に「憑依」する
(1)「凡人」に憑依する
(2)「狂人」に憑依する
●USJ:“熱狂的IPファン”に憑依する
●スマホゲーム:“廃課金者”に憑依する
●ネスタリゾート神戸:“山遊びの狂人”に憑依する
(3)「憑依」とは要するに……
[3] 消費者の脳内想起から本能をたどる
Part3 「マーケティング・コンセプト」のつくり方
第7章 実際にブランドを設計してみよう
[1] ケース・スタディ:高血圧症のオンライン診療で3100万人を救え!
(1)「高血圧イーメディカル」設立の背景
(2) “高血圧症の放置”は大問題である
(3)「高血圧イーメディカル」の特徴
[2]「高血圧イーメディカル」のブランド設計
(1)消費者理解の概要
(2)WHO:「不安」と「大丈夫」の綱引き
(3)WHAT:プレファレンスを長期的に大きくする便益
(4)HOW:戦略便益を実感させるためのPODとPOP
(5)Brand Character:ブランドに人格を宿す!
第8章 強いマーケティング・コンセプトをつくる3つの要点
[1] 本能にぶっ刺せ!
(1)脳の情報処理の構造「システム1」と「システム2」
(2)本能を衝かれると脳は抗いがたい
[2] 文脈を操作せよ!
(1)“便益価値を高めるシーン”を文脈として設定する
(2)“消費者インサイト”を衝いて文脈を設定する
(3)消費者の“期待値を操作”して文脈を設定する
[3] 脳内記号を活用せよ!
(1)マーケティング・コンセプトの典型的なフォーマット
(2)脳内記号とはなにか?
(3)「脳内記号」を使った「ジャングリア」の事例
第9章 実際にマーケティング・コンセプトをつくってみよう
[1]「絶対に買う1人」は実在するか?
[2] 練習問題A:「自分自身」のマーケティング・コンセプト
[3] 練習問題B:「高血圧イーメディカル」のマーケティング・コンセプト
終章 コンセプトが日本の未来を創る!
●あの小さなパン屋さんの勝ち筋
●日本の未来に必要なもの
「M」を詳細に把握するなど、数式を実務に活かしたい方へ。
赤本で学んだことを実践し、有益なコンセプトのタネをみつけたら、意思決定に向かう過程で因果推論のデザインを踏まえた適切な検証が必要になりますし、性別年代ごとのMを算出し市場を構造的に把握することも重要です。
昨年に日経クロストレンドの5回連載の記事で紹介したのはFreeasy(セルフリサーチ)を使って、たった6000人に調査をするだけでブランドごとのMを性別年代ごとに算出して市場構造を把握し当該サービスや商品を選ぶきっかけとなるカテゴリーエントリーポイント(CEPs)ごとのMを算出する方法です。中小企業でも捻出できる費用の調査でも数式を活用することができます。
2020年からストアカで1000人以上の方に有料の講義を行いました。オンライン講義の「確率モデルの実装法」では日経クロストレンドの5回連載記事で紹介したエナジードリンクの調査データを教材にしています。同記事は有料記事となります。この講義は記事の閲覧をしていない方も参加可能です。
拙書のご紹介
主に青本で紹介された数式やブランディングの科学で紹介されていた法則を2021年から執筆時点までに行っていた96.6万人の調査で確認してきたデータの一部を用いて解説し、市場構造把握や顧客理解を実際に行う方法としてまとめた書籍が「確率思考でビジネスの成果を確実化するエビデンス・ベースド・マーケティング『その決定』に根拠はありますか?」です。青本や赤本を読んで、実行に移す方、消費者行動の法則やMなどの数字を使って消費者向けのビジネスで結果を出すことにこだわる方に役立てて頂けると思います。
共著者の山本寛さんは元オリエンタルランドのリサーチャーです。森岡毅さんらによるUSJの改革を、TDL側から見ていた方です。事業会社のリサーチャーとしての豊富な経験と見識があります。氏と半年間、観光とVRやMRを組み合わせた新しいアイデアの仮説を探索する擬似プロジェクトを行い、定量と定性を組み合わせて行う、仮説の作り方や顧客理解のやり方を具体的に解説しています。書籍の後半でも紹介していますが、氏がストアカで開催した「『顧客理解』を理解しよう」という講義に私が受講者として参加して目からウロコの気づきがあり感激しました。
以降、プロジェクトにご参加頂くなどお付き合いさせて頂いており「『顧客理解』を理解しよう」テーマに対応する内容の共著と書籍全体の内容のアドバイスをお願いしました。
ガンマ・ポアソン・リーセンシー・モデルの使い方や、因果推論の傾向スコア分析、無料で使えるMETA社のRobynによるMMMなど、高度なアナリティクスの実装法も紹介しました。中小企業でも使えるよう無料または安価なツールで行える方法にしています。
数式の実装を解説する動画講義も用意しました。演習データとして、エナジードリンク、外食チェーン、テーマパークの3テーマで調査した約17万人の調査ローデータを配布しています。合計7本で8時間を超える動画講義のうち、確率モデルの実装を解説する講義をYouTubeで公開しています。
赤本と同じ発売日にマーケティング意思決定に必要な分析リテラシーを学ぶ書籍も出版しました。
2025年1月29日発売「Excelで学べるデータドリブン・マーケティング」
【MMMやマーケティング分析に付帯する基礎的な統計知識から『学びたい』方向け】
「Excelで学べるデータドリブン・マーケティング」はデータの分布とは?回帰分析の決定係数とは?といった統計の基礎から学ぶことができます。判型を大きくしてB5判カラーにしました。Excelで行うデータ分析の演習の画面キャプチャーを張り付けて丁寧に解説しているからです。(2024年12月時点で)53万部を販売した大ヒットシリーズ書籍の「統計学が最強の学問である」著者の西内啓氏に「マーケターはグラフの見た目より『因果推論』に注意すべきである」と推薦コメントを頂きました。マーケティング投資を判断するMMMや調査データの分析を行う際に必要な統計や因果推論の基礎からしっかり学ぶことが出来ます。
合計8本で約9時間の付録の動画講義のうち、各章で解説する分析の内容など書籍の全体を紹介する講義をYouTubeで公開しています。書籍の内容にご興味頂ける方はまずは動画をご覧になってみてください。
以下noteでは1章まで無料公開しています。
1959年にアンドリュー・アレンバーグ氏によって発見された数式(NBDモデル)が2016年に発売された青本によって日本では周知されました。それを実務で活用すること、マーケティング戦略を決める際の土台となる確かなデータ、確かな「秤」を持つことを今後もお手伝いして参ります。
以上となります。ここまでお読みいただき誠にありがとうございました。
その他告知(※適宜更新)
消費者調査MMM(R)で確認する「購買重複の法則」noteを集めたマガジンです。現在は5つのnoteを紹介しています。
刀社と弊社の特許技術の明細書を要約したnoteです。
2月20日(木)16時からエバンジェリストをしているFreeasyのセミナーで、消費者調査MMM(R)の事例をいくつか紹介します。
3月25日にはCEPs(カテゴリーエントリーポイント)の見出し方というセミナーに登壇します。
