
穆王様と菊慈童
台風の湿った風が吹いている。
空には形をどんどん変えて流れていく雲の塊が
気分を高揚させるものの
いつ降り出すかわからない雨に
不安な気分にもなる。
慈童は、幼さが残る可愛いらしい子供で
決して美少年ではなく、むしろ不細工なほう
であろうが、華奢で脆弱そうな容姿は庇護欲をそそられた。
「慈童は可愛いな。」
兄にそう言われて、満面の笑みを浮かべる。
「甘い葡萄をやろう。」
そう言われて鳥の雛のように大きく口を開ける。
「口を開けるやつがあるか。礼儀作法を教わったばかりだろう。」
「先生が礼儀作法より甘え方 を覚えたほうが良いと言ったのです。」
先生というのは、慈童の兄が頼りにしている師匠でもあり
慈童も書や礼儀作法などを教わっている優秀な先生だ。
賢く、温厚で誠実な人柄だ。
「それは、嫌味だろう。」
先生がどのような意図で言ったかはわからないが
礼儀作法より甘え方を覚えろというのは酷い。
おそらく、礼儀作法が全く覚えられない慈童にサジを投げて
出た言葉に違いない。
ここで、今一度、食事の作法を教えるべきかもしれないが
大きく開かれた口が閉じられることがなさそうだったため
葡萄を一粒入れてやる。
嬉しそうに口をもぐもぐさせている仕草に兄はつい萌えてしまう。
「あっまい。もっとください。」
そう言うとまた、大きく口を開ける。
いやいや、甘えるのも程々にしてほしい。
「餌をねだる池の鯉のようだな。口は閉じて、手を出しなさい。」
「はーい」不満そうにしぶしぶ出された小さな手の上に葡萄の房を入れた
瑠璃の器をのせてやる。弟には重そうだ。
「葡萄は下の粒から食べ始めるのだよ。
上の粒の方がより甘いからね。」
「そうなんだ!」
美しい瑠璃ガラスの器よりも弟の目がキラと輝いて見える。
甘い葡萄のその味の法則は衝撃的であったようだ。
台風の風がよりいっそう激しくびゅうと音をたて
パラパラと雨が降り出してきたようだ。
いつのまにか、弟は、兄のそばに寄りそっている。
風の音に怯えているのかもしれない。
葡萄を頬張りながら体重を預けてくるとは
愛おしすぎる。
幸福感がヒシヒシと湧きあがってくる。
確かに甘え方は超一流かもしれない。

檜の香りが漂う扇子をハタハタと仰ぎながら
「やりたく無い仕事をやっているのは何故かな?」
呂先生が問いかけます。
「その仕事を楽しめていないせいです。」
答えるのは、慈童の兄、慈月。
「人間関係に悩むのは、どうしてかな?」
「空気を読み過ぎているからです。」
「他人に裏切られて許せないのは?」
「その人を信頼し過ぎているからです。」
「枠に押し込められていると感じるのは?」
「自分で人生の計画を立てていないせいです。」
慈月の答えを満足そうに聞き、扇子を閉じる。
「では、本日のご予定です。
穆王様が西方旅行から帰ってきたようですから
まずは、ご挨拶に出向きましょう。」
呂先生は、慈月のマネージャー的存在になっていました。
先生の言うことをきいていればたいがい間違いは無い。
先生が止めるのを聞かずに父のお供で崑崙山まで
付いて行って高山病にかかり、
死にそうになったのは記憶に新しい。
神々が住むと言われる伝説の山、崑崙山は遠かった。
父母はその後も西方へ留まっていて、慈家には
慈童と呂先生と3人きりだ。
裕福ではあるが下働きのものはいない。
「わかりました。きっと、西方の珍しいお話が聴けますね。
弟の慈童も連れて行きましょう。」

「最近はニュースなどでもパワハラの問題で
騒がれておるが、人間は基本的に対等じゃ。
王族や立派な肩書きを持った人間も
ホームレスも雇用主も労働者も対等なのじゃよ。」
「勘違いして他人を見下すのは
自分に自信がないという心理状態なのじゃ。
病気といってもよろしいでしょう。」
「おっしゃるとおりです。」
周の穆王は良く解っているというふうに
うなずいた。
秋風が気持ち良いが日差しはまだ強い。
太陽に焦がされて、汗がにじむ。
遠方から来た来客と雑談をしながら
インドのミルクティー「チャイ」を
差し出すは釈迦族の尊者
シャーキャ・ムニだ。
お釈迦様とも言う。
甘くてホットなドリンクは
美味だが、余計に汗が出そうだ。
しかしながら、汗をかくことによって
体は冷える。
「昨日は寒かったのに、
今日は暑いですなぁ」
「あああ、気がつきませんで、
クーラーをいれましょう。」
インドは50度を超える酷暑の地。
非家電式のクーラーは必需品なのだ。
円筒状のテラコッタに水を流して
この水が蒸発するときに気化熱で冷気を発生して、
暖かい空気に押し出されて冷たい風を送ることができる原理なのだ。
インドの企業が開発したものなので
2500年まえの古代インドにそんなものがあったとは
思えないが、似たようなものはあったのかもしれない。
雨季とはいえ、インドの気温は
30度越え。
ちなみにチャイの容器もテラコッタだ。
広口の円形で素朴な味わいのある素焼きの陶器
だが、飲み終わったらパリンと割る。
食器から他人の穢れが移るというのが
インド人の常識なので、穆王もそれに従う。
周の穆王はインド旅行中、
お釈迦様のところに立ち寄った。
国を平和に治めるための
お経をもらうために。
カルダモンの香りがほんのりと
かおる部屋の隅には割れたテラコッタが
散乱していた。
釈迦族の尊者は周の穆王の耳元で
こう囁きます。
「国を治めるのに大切な教えをお聞きになりますかな。」
それ!
穆王は込み上げるものを
抑えられませんでした。
わかっていらっしゃる。
「是非、拝聴いたします。」
説法ライブははじまった。
「自然はただ一つの法則によって動いておる。」
「物質的、精神的に全てのことは、幻である。
絵空事のように、確固たる存在は無い。」
「仏の言うことは、真実であって偽りではない。
医者のテクニックで間違った思い込みをしている患者に対して
治療のために真実と違うことを言ってうまく誘導しても
それを嘘偽りだと責める人がいないようなものである。」
「観音様は何時もやさしい、思いやりの眼をもって
私たち生きとし生ける衆生を見てくださ~る。
その観音様の心をもって生きれば、
海の如く無量に福が集まーる。」
「国土全体を支配する帝王の偈の全貌はこれで全てじゃ。よく覚えておくが良い。」

ゴータマ・シッダールタさん
説法ライブを拝聴した穆王は
忘れないうちに、妙文を衣に記しました。
「四海領掌の偈」
十方仏土中 唯有一乗法 (方便品)
観一切法 空如実相 (安楽行品)
仏語実不虚 如医善方便 (寿量品)
慈眼視衆生 福聚海無量 (普門品)
尊者は39歳でした。
身長は高く、痩せ型で剃髪。
穏やかな表情が好ましい。
素朴な、一枚布をドレープ状にして
巻きつけ身にまとっている。
穆王は63歳でした。
年齢を感じさせない精悍な顔立ちに
皇帝らしい威圧感があるオーラを
まとっていましたが、旅行中なので
衣服は簡素だ。
穆王は、尊者のもとを去る時に
国を治めるのに大切な教えを
拝聴したお礼に、自作の詩をプレゼントしました。
活著就該 生きているからには
活出聲音 奏でたい音があります
如鳥歌唱 鳥のようにさえずり
如花芬芳 花のように香り
如風狂嘯 風のように奔放で
如月皎潔 月のように冴え渡る
尊者は頬を桃色に染めて嬉しそうに詩を聴き入りました。
「身体に力が湧き上がるような美しい言葉じゃ。
素直で清らかな希望がございますな。」
「はい。尊者様の御言葉を聞いてこのような境地になりました。」
「さすがは一国の王ですじゃ。民が安心して暮らせるようご精進くだされ。」
イランイランの花の香りが、しっとりとまとわりつく満月の夜。
尊者との別れを惜しむ穆王様でありました。
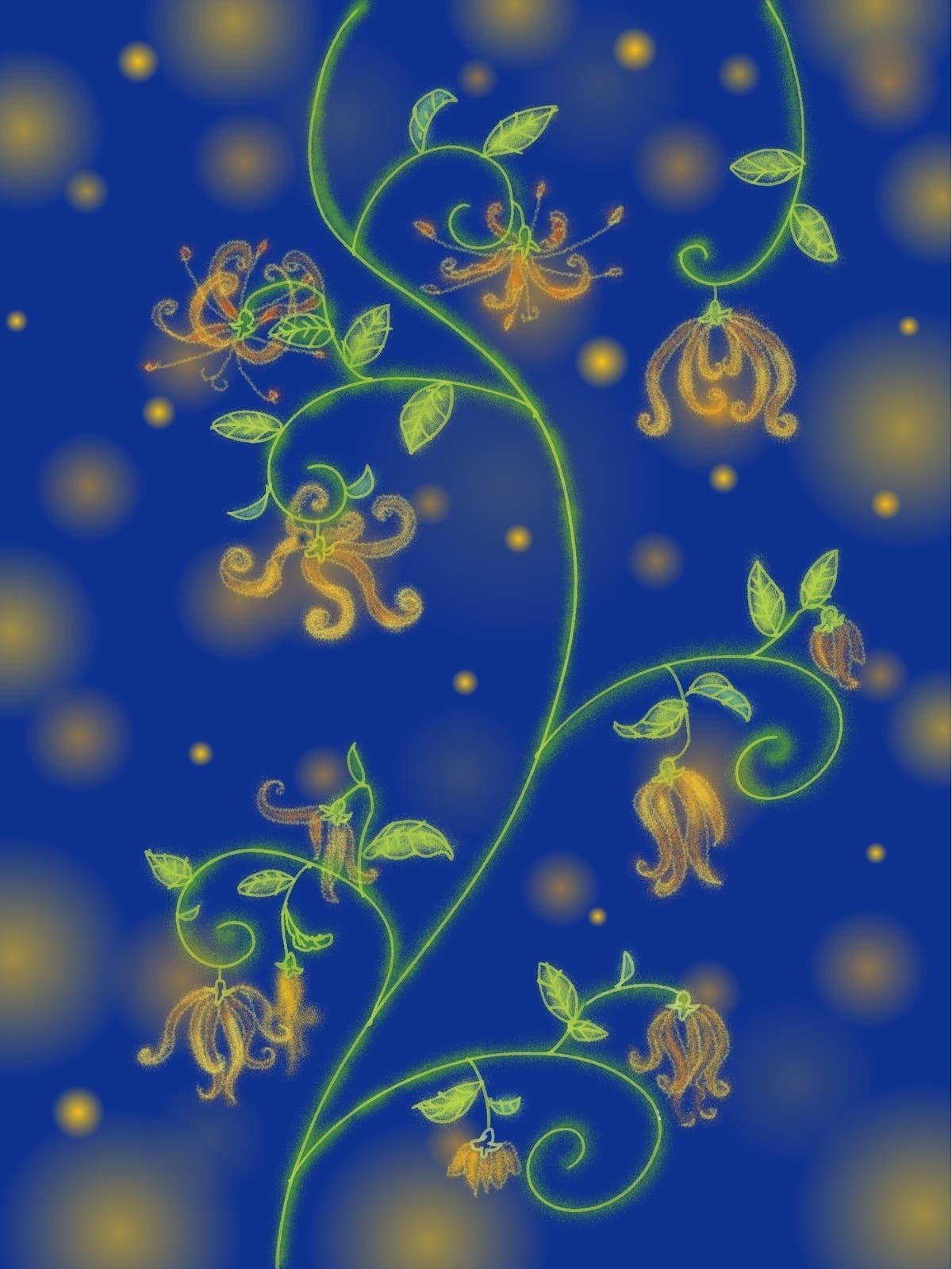
慈月は26歳。
10代の頃は王の侍者になったこともありました。
歴代の王様が可憐な男の子を侍者に置くのは
単に趣味とかではなく、世継ぎ争いの元となる
女性を遠ざけるためでもありました。
避妊具なども無かった時代なので
へたに女性の相手をするとすぐに子供が出来て
その女性を側室にせねばなりませんでした。
中には、本当に王様の子かどうか怪しいものもありました。
わざわざ、国を乱す面倒を背負い込むよりは
安全な男の子を側に置いて癒しとしました。
また、子供を預かることで、その家を、王の庇護下に
置き、遇しました。
慈月の侍者だった頃は、穆王様も王位についたばかりで
お世継ぎをつくらねばならず
侍者たちにかまうことは出来なかったので
慈月の役目は身の回りの雑用や、話し相手にとどまっていました。
20歳になったときに宮廷を去り、慈家に戻っていました。
慈童は16歳になっていました。
守らねばならない弱い存在ではなくなったものの
親しみやすい、愛らしい少年に成長しておりました。
侍者に求められた時に丁度、穆王様が西方旅行に行く
準備中だったため、お帰りになってから侍者になると
約束していました。

呂先生は、田舎に帰り、そこで
子供達を教える学び舎を作りたいと
慈月に申し出ていました。
慈童が穆王様の侍者となれば、
もう自分の役目は終わりなのだから。
普段、何があっても動じない慈月が行かないで下さいとひきとめて泣くので
いたたまれなくなってしまった。
そういうことは穆王様に言って欲しかったのに。
それにしても、5年間も国をあけて旅行する王様など前代未聞だった。
結局、王様の西方行きは誰にも止められず、国政に携わるものは泣かされたようだ。
檜は周の国には無かったので倭国から輸入していました。
最高級品だったうえ希少品でもありました。
この頃、倭国の王様は「大和国の日の皇子」とよばれていました。
檜の扇子は、職人に造らせるとさらに高価なものになりましたが
慈家のご子息に差し上げるものならと、ちゃんとしたものでなければと
良いものをつくりました。
慈月に頼まれたのは自分の使っている扇子を形見にということであったけれど、
自分で作った、しかも使い古したボロい扇子を差し上げるのはさすがに気がひけたので
慈月には風月。慈童には花鳥の文様を入れ、対になる仕立てにして
透し彫りの優美なものをこしらえました。
可愛い弟子たちに最後に贈り物ができることは
呂先生にとっても感慨深いものがありました。
場面は変わり、月明かりの無い、新月の暗闇は、いつも慈童を不安にさせる。
幼い頃から兄の布団に潜り込んで眠りにつくことはよくあることだった。 慈月のほうも、可愛い弟を抱き枕にして寝るとぐっすり眠れた。
その夜は、いきなり穆王様に触れられるのは怖いと思った慈童が 兄の布団に潜り込み、兄の手を掴み自分の逸物を握らせながら 「お兄様。どうか、私を可愛がってくださいまし。」 と、勇気を振り絞り可愛い声で懇願してみたのですが
「うわっ。じっ、じ、ど、うっ!これはいけないな。」 うええ、しかられるぅ。 当然のことながら驚いた兄は慈童の頬を 軽くつねり、お説教をはじめてくれちゃったのです。 「困った子だね。そこにお座り!」 と、布団から起き、明りを灯しました。 「いいかい。侍者というのはね、色気で王様を誘ったりはしないものなのだよ。 穢れのない清らかさが売りなんだからそんなやる気満々じゃ、 相手にされないよ。清らかなままでいた方が良いんだよ。」
兄を夜伽の練習台にしようとしたことはバレバレのようだ。
「兄様、それでは、侍者の務めが出来ぬではないですか。」
兄はミルクと砂糖を煮詰めて作った練乳がけの苺を慈童に渡した。
「自分が気持ち良くなってはダメなんだよ。王様のお手を汚すのもいけない。」 お説教するというのに甘いものをくれる兄。
食べようとするとまだ食べるなと待てをされる。 お猿の調教かよ。
と頭では思うものの、口の中は唾液で溢れかえった。
ストレスがかかると唾液の量が減るというからその対策だろうか。 薬が高価な時代だからこそ、現代人よりも健康にはずっと気を使う。 しかしながら、慈月のお説教はなおも続いたのでした。
「どうすれば穆王様が喜ぶかを常に考えて、おもてなしするのだ。 嫉妬するものや、妬むものがいたら、手なづけて自分の手駒にするのだよ。 うっかり毒を持った植物を知らずに王宮にもちこまぬよう注意しなければいけないよ。 宦官はこまめに買収するんだよ。後宮には近づかぬようにして、 うっかり死罪にならぬよう、皆の好き嫌いと王宮の規則はしっかりと把握して おくように。」
うへぇ。手なづけるとか買収とか全然、清らかとは無縁じゃんと内心は ツッコミをいれながらも、苺のほうが気になる。
「もう食べてもよろしいでしょうか?」
「いいよ。ゆっくり味わってたべるんだよ。」 甘酸っぱい味が口に広がる。 「美味しいかい?」 「はい。ものすっごく美味しいです。 私にもこの練乳の作り方を教えてくださいませ。」 「うん。ミルク200mlに砂糖50gを鍋に入れて30分煮込むんだよ。」 兄は慈童の手を優しく握り、こう言います。
「お前が何かやらかさないか心配でしょうがないよ。 お前に何かあったら、私は生きていけないよ。」 そのあとも、あれはいけない。これは、やっておいた方が良いなどと 永遠にクドクドと言われ続けたので、厠へ立つふりをして逃げた慈童でした。
2つの新しい桐箱を見たとき、慈月は微妙な気持ちになりました。 慈月が欲しかったのは新しい扇子ではなく尊敬する 先生の身につけていたものだったのですから。 しかし、せっかくの師匠の心遣いなので箱を開いてみることにしました。 「これは!なんと見事な細工でしょう。細工師は、どなたですか?」 躍動感ある優美な意匠なのに繊細で緻密な細工にはため息が出るほどでした。 「私も、まさかこれほどまでになるとはおもいませんでした。驚いています。」 先生が以前から贔屓にしていた若い細工師が精進して、技を極めたようでした。 「このような希少な才能は世に出さねばなりますまい。 この扇子を献上して穆王様にもご贔屓にしてもらいましょう。」 「えええ、嫌ですよ。」と慈童は反対したけども、目で却下した。 呂先生にお伺いをたてると、お役に立つならと快く許してくれた。 慈童が王宮に上がる日にそれは王様と王妃様に献上されました。 穆王様も王妃様も非常に喜ばれ、慈童にお礼の言葉を賜ったのでした。 細工師にも謁見が許され、慈月も、王宮の宝物を管理する仕事を任されることになりました。 穆王様は、かつてシャーキャ・ムニにプレゼントした花鳥風月の詩を思い出し、 扇子を開くたびに吟じるようになり、慈童も皆から一目置かれる存在となります。 かくして、慈童、慈月、呂先生は別々の道を歩くことになったのでした。
穆王様は常に慈童をお側に置き、離しませんでした。 夜伽こそまだしなかったけれど、 お疲れの穆王様に生姜湯などの飲み物を作り、マッサージなどをしたりするのは 慈童の役目でそのまま添い寝することもあり、心が繋がっていると感じていました。 家で兄に色々、言われたことを思い出したりもしましたが 呂先生からは、兄の言葉を鵜呑みにするのではなく自分の思う通りに やりなさいと言われていました。 思い通りにならなかったときに兄のせいにしないために。 実際、慈童は、他人を手なづけることなど出来なかったし 甘いお菓子で手なづけられるのはいつも慈童のほうでした。 議論しても相手をやりこめてはいけないよ。などと言われたが、 もともと、出来るはずもないことなので関係ありませんでした。 あれほど兄に言われたにもかかわらず、新月の夜には 不安になって、穆王様にまとわりつきました。 「怖がりだねぇ。」と優しく抱き寄せられるとつい膝の上にのったりして 穆王様のお手を汚してしまうことさえありました。 しかし、誰も慈童を叱ったり、妬んだり、いじめたりはしませんでした。
満月の夜のことでした。 穆王様はかつての寵童であった慈月に会いに行きます。
「慈月よ。元気にしておったか。」 「穆王様には慈童を可愛がっていただいているようで、ありがとうございます。」 「うん。慈童はたしかに可愛い。大切にしようと思っている。 でも、私が欲しいのはお前だよ。」 「それはわかっておりますが、私は慈家の長男ですから、血筋を残さねばなりません。 男色ばかりするわけにはいきませんが。」 「じゃあ。ちょっとだけ。ね。ね。」と慈月を抱き寄せた。 穆王様の衣服から檜の芳しい匂いがして、心が浄化されるようだ。 あの扇子を持っておられる。 「良いご縁をくださるならかまいませんよ。」 なんと、慈月は自分に結婚相手を紹介するなら愛人になっても良いと言ったのだ。 随分と興醒めなことを言う。 「しょうがないな。」 慈月はおもうようにならない。だからこそ、どうしても自分のものにしたかった。 よし、探してやろうじゃないか。慈月の結婚相手。 と思ったけど、冗談ですからと、慈月は穆王様の帯にそっと手を触れたのでした。

呂先生と同じ香りのする扇子を持つ穆王様に付き合ってあげる慈月
穆王様が、釈迦族の尊者の元を去るときも満月だった。
あの時のイランイランの香りが思い出され、情欲をそそられる。
尊者を口説いたらこう言われるだろう。
「そんなのダメにきまってるじゃろうが!」
仏教僧は女とだろうが男とだろうが獣とだろうが、性行為はダメなのだ。
情欲の処理に困った苦しげな弟子たちが、あれは良いか?これはどうか?
といちいちお伺いをたてていたけれど、
「とにかく、穴に突っ込んで気持ち良いのは全部ダメじゃ。」
とキレ気味に答えていたのには笑えた。
花鳥風月の詩を貰って頬を染めていた姿を思い出し、そのギャップに萌えた。
「生きているからには奏でたい音があります。
鳥のように歌い、花のように芳しく、風のように奔放で、月のように冴え渡る。」
恋は病気だし、快楽は麻薬だ。
しかしながら全く無いのは味気ない。ほどほどが良いというのが
仏教の真髄であろう。
しかしながら、そのほどほどでやめられないのが人間の性なのだ。
貪るのをやめなければ、いくら恵まれていても満たされることはない。
満月の夜は慈童は1人で過ごしていても全く怖くなかった。
幼いときから兄の布団にも潜り込まなかったし、 月明かりに照らされるのが好きだった。
穆王様はお出かけなので 王宮内をふらふらと出歩き、宦官たちからお菓子をもらったり 他の侍者たちとお酒を飲んで遊んだりした。
すっかり酔っ払った慈童は、どこかの部屋で ばたりと倒れて眠ってしまった。
翌朝、起きると自分の側に王の枕が置かれていました。
あれ。これって、もしかして何かやらかした?
王様の枕を元あった場所にもどさなくては。
もし、誰かにみられたら「うっかり死罪」というやつだ。 枕を衣服の中に隠しコソコソと移動する。
穆王様のお部屋の前まで行くと、 そこには侍者たちがいて、泣いている。
もうバレてる感ハンパない。逃げるか。
王の枕をその辺に置き捨て、何食わぬ顔でその場を離れることにしたのでした。
王様の留守中に枕が無くなったので侍者たちは、皆青ざめた。 枕はすぐに見つかったものの、慈童の姿がみえない。 枕に針などが仕込まれていないか入念に調べられた。 怖くなった慈童は王宮を抜け出し、慈月のもとへ行ってしまった。 慈月は優しく抱きしめ、こう言った。 「皆がお前を疑っても私だけはお前の味方だからね。」 「でも、酔っ払っていたから、私が持ち出したのです。きっと。」 「違うね。お前が寝てる間に誰かが置いたんだよ。はめられたのさ。 そういうことにしよう。」 「そんなことにはできません。」と慈童は泣いてしまった。
自分が罪を逃れようとすれば、他の誰かが疑われるのだ。
「そうしないと死罪だ。」 「仕方ありません。」
「安心おし。私がそうはならないように穆王様にお願いしてみるからね。」
「兄様にご迷惑かけられません。もう、良いのです。覚悟は決めました。」
慈童は王宮に戻り、穆王様に枕のことを正直に話したのでした。
穆王様は、慈童の話と宦官の話と照らし合わせてみました。
どうやら、お酒を飲んで王様の寝所に入り込み 寝てしまった慈童を、宦官が見つけて別室に移動した際、 王様の枕を抱いて持ち出してしまったようでした。 穆王様は慈童に言いました。
「可哀想に。お前はまだ子供だから死罪にはしないけど、流罪になる。 レッケン山は、お前のような子供がひとりで生きて行ける所では無い。
お前が死なぬよう、妙文を授けてあげよう。だから、今夜、寝所においで。」 「え、寝所にですか。」 「うん。秘文だから誰かに見られると困るからね。」
どうやら、死罪は免れたようだけど、もう、兄にも呂先生にも穆王様にも 両親にも、会えなくなってしまうらしい。
王様の寝所に行く時は、決まった作法がある。 作法は知らないよりは知っていた方が良いと言うだけで 絶対にそうしないといけないということはないのだけど、 初めて寝所に呼ばれたから緊張はする。
もしかしたら、夜伽をすることになるかもしれないからだ。
今まで、添い寝していた時は、寝所ではない別室であった。
慈童が眠ったあと、寝所に戻り、夜のお勤めをするのは 王様の大事な仕事でもあったわけです。
流罪になるのだから、夜伽はしなくても良いような気はするけど、 死なない妙文はなんとしても、もらわなくっちゃね。
西周の衣服は身分によっても色々あるのだけれど、 日本の着物と似たような形のものだった。
ロング丈カーディガンに細帯といったところです。 作法通り、脱ぎやすい衣服を着て、華やかな帯を締める。 紅を指して髪はお団子のツインテール。定番の稚児スタイル。
「そんなやる気満々じゃ相手にされないよ。」という兄の言葉を思い出す。
やっぱり、紅はやめておこう。 流罪になるっていうのに、作法とかバカらしいわ。 ツインテールのお団子もやめよう。めんどくさいからポニーテールでいいや。 でも、準備運動とお尻の穴に香油をたっぷり塗っておくのは忘れないようにしないと。
寝所に来た慈童がいきなり自分から帯を緩めたので、 驚いて帯を結びなおしてあげる穆王様。
ちなみに、いきなり帯を緩めるなんて作法はない。
「ごめんごめん。夜伽は無しだから。」 とおっしゃって妙文を出してくださいました。
慈眼視衆生 福聚海無量 じげんじしゅじょう ふくじゅかいむりょう
観音様は何時もやさしい、思いやりの眼をもって 私たち生きとし生ける衆生を見てくださる。
その観音様の心をもって生きれば、 海の如く無量に福が集まる。
「これを、朝夕に十方を一礼してこの経文を唱えるのだ。
十方っていうのは、上・下・東・南・西・北に東南・西南・西北・東北だよ。
恐ろしい獣も近づかないし、観音様がお守りくださるよ。」
「ありがとうございます。忘れないようにいたします。 最後にお願いがあるのですがよろしいでしょうか?」
「うん。いいよ。言ってみなさい。」
「家族に類が及ばぬようにお願いしたいのです。」
「大丈夫だよ。ご両親と兄上のことは任せておきなさい。」
その夜、慈童は寝所で穆王様の腕のなかで幸せそうに眠ったのでした。

流刑地レッケン山へ行く慈童の心中は悲壮なものだった。
涙を流しながら、小さくなって震える慈童を、
見送るものは皆、悲嘆にくれていました。
慈童にお酒を飲ませた侍者たちも、自分たちが悪かったのだと後悔に
くれていました。
慈童は余計なことをして、皆を心配させたり、叱られたりよくしたけれど
まあ、あいつならしょうがないか。という許されキャラでした。
ざまあみろと笑うようなものはいませんでした。
慈月は、こんなことなら、切り札は取っておくんだったと自分の甘さに吐き気がした。
せめてもの慰めに、愛する弟に菊の花を渡すのでした。
「この菊の花びらを、川の水に浸し、飲むと解毒になるからね。」
慈童は菊を受け取り、兄を見つめてこういいます。
「お元気で。兄様さえお元気なら私は幸せです。」
「お前がいないのに元気でなんていられるものか。」
「じつは、穆王様から、お釈迦様の経文をいただきました。
私はそう簡単に死んだりしませんから、どうか、ご安心ください。」
「え。本当に?随分なご寵愛だな。」
「いいえ、兄様の言う通り、ちっとも相手にされませんでした。」
「ふふ。それは、大事にされていた証拠だよ。」
「え。そんなことなのですか?」
慈童は貰った菊の葉っぱに、忘れないように経文を書いておきました。
慈眼視衆生 福聚海無量
そして、鳥も鳴かず、雲は暗く、狼や虎がいるという恐ろしい山に向かったのでした。
慈童が、レッケン山にかけられた吊り橋を渡り終わると
いま、渡って来たばかりの吊り橋が切り落とされました。
もう、後戻りは出来ません。
泣きながら、しばらく歩いていくと川があります。
透明で澄んだ川は冷たくて、慈童の渇いた喉を潤しました。
岩で囲んで水溜りをつくり、兄が解毒になるといった菊を浸します。
花びらだけでなく、経文を書き込んだ葉っぱも浸してみました。
手柄杓でその水を飲んでみたところ、
「うそ。甘い。なにこれ。」
甘いもの好きの慈童は嬉しそうです。
この川の近くに、庵を作ろう。
土を盛り上げて、寝る場所を作り、風雨を避ける
屋根と囲いを作りました。
菊は挿し芽で増やせるので、川岸の陽当たりの良い土に挿しておきました。
菊の葉に溜まったわずかな朝露が川に落ち、川の水全てが甘露の霊薬となりました。
しばらくすると、川辺一帯、菊の花が群生するようになり、
経文を唱えなくても、虎や狼は近づけなくなりました。
菊は解毒作用のほかにも、リラックス効果もあり、
菊の花の匂い成分が脳神経の機能を回復し、脳の老化を予防する効果がありました。
このように、人間には有用な菊でしたが、獣にとっては毒だったのです。
天敵に対しては、身を守る植物の性質の不思議。
これもまた、自然の原理原則のひとつなのでした。
甘い霊薬を、毎日飲んだ慈童は、病気になることもなく、
いつまでも若く、少年のままの姿でした。
霊薬は、慈童だけでなく、川の水を飲むもの全てを、不老長寿へと導きました。

菊の季節は変わり、桜吹雪が舞う頃、
不老長寿の仙人となった慈童ではありましたが、孤独に苛まれていました。
考えるのは、お優しかった穆王様のこと。
最後の夜に、抱かれた温もりをいつまでも、忘れることができません。
「お元気であろうか。」
王宮には美女が溢れ、毎日取り替えても、全員の相手をするのに何年かかるか
わからないぐらいだというのに、夜伽も無しだった自分のことなどは、
もうお忘れかもしれない。
人恋しくなった慈童は、山の中に誰か居るのを見つけます。
もしかして、穆王様が会いに来てくださったのかも。
「このような山奥にどなたでしょう?」
「魏の文王、曹丕だ。お前こそ何者だ?」
「私は、西周の穆王様の侍者、慈童の成れの果てです。」
「西周の穆王は700年前の人物だ。さてはもののけか?」
「こんな可愛いもののけがありますか?仙人ですよ。あれから700年の月日が経ったとは
信じられません。穆王様と過ごした日々はあんなに短かったのに。」
「不老長寿の霊薬で仙人になったのだな。余にも飲ませて欲しいのだが。」
「どうぞ。どうぞ。川の水が全て、霊薬でございます。」
「このようなところで、寂しいであろう。余が慈童殿を召抱えよう。」
「私は、穆王様の侍者でございますから、ご遠慮いたします。」
慈童は誘いを断り、穆王様がもうこの世にいらっしゃらないことを知ると、
これ以上、生きる意味はないと、静かに目を閉じたのでした。
慈童をレッケン山へ見送った数日後、 穆王様は慈月を訪ね、
慈童を助けられなかったことを、申し訳なかったと詫びました。
「可愛いそうなことをした。余を恨んでくれてもよいぞ。」
「とんでもございません。お釈迦様の経文をいただいたことに感謝しております。」
「知っておったのか。非公開文だから、慈童には内緒だと言っておいたのに。」
「破格のお心遣い。この御恩は一生忘れません。」
「いやいや、本日は余が詫びに来たのだからね。
せめてもの慰みに慈月のお慕いするお方を王宮に招いておいたよ。」
「良いご縁のお話なら、本当に冗談ですから。
それに、今はそんな気分ではございません。」
「あああ。そっちは、まだなんだが、お招きしたのは、呂師匠だよ。」
「え。呂先生をどうして?」
「だって、今まで、いくら口説いても、お腹が痛いとか、
日が悪いとか言って、逃げていたお前が、呂先生がいなくなったとたんに、
あっさりおちたんだから、わかるよ。」
「あ。それ、誤解でございます。私と先生はそんな仲ではありませんぞ。」
「うん。もちろん冗談だよ。水入らずで心おきなく、尊師と語らいなさい。」
紅葉が赤く色づく頃、落ち葉を踏みわける音だけが響く昼下がり、
慈月は、呂先生と昔のように、問答をすることができるとおもうと
悲しみがほんの少しだけやわらいだのでした。
「昔、慈童がまだ幼い頃に、礼儀作法より甘え方を覚えるよう
呂先生に言われたそうですが、あれは何だったのですか?」
「慈童様がお小さい頃は、誰かを頼ることをしないで、
何事も一人で解決しようとしていたから、
みんな、慈童様の味方だから、もっと周りを頼りにするようにと言っただけですよ。」
「慈愛と信頼を持って他人と建設的に関わることが福を招き寄せるのです。」
「それで、あのお気楽な性格になったのですね。」
「いやあれは、慈月様が甘やかし過ぎたせいでしょう。」
完
