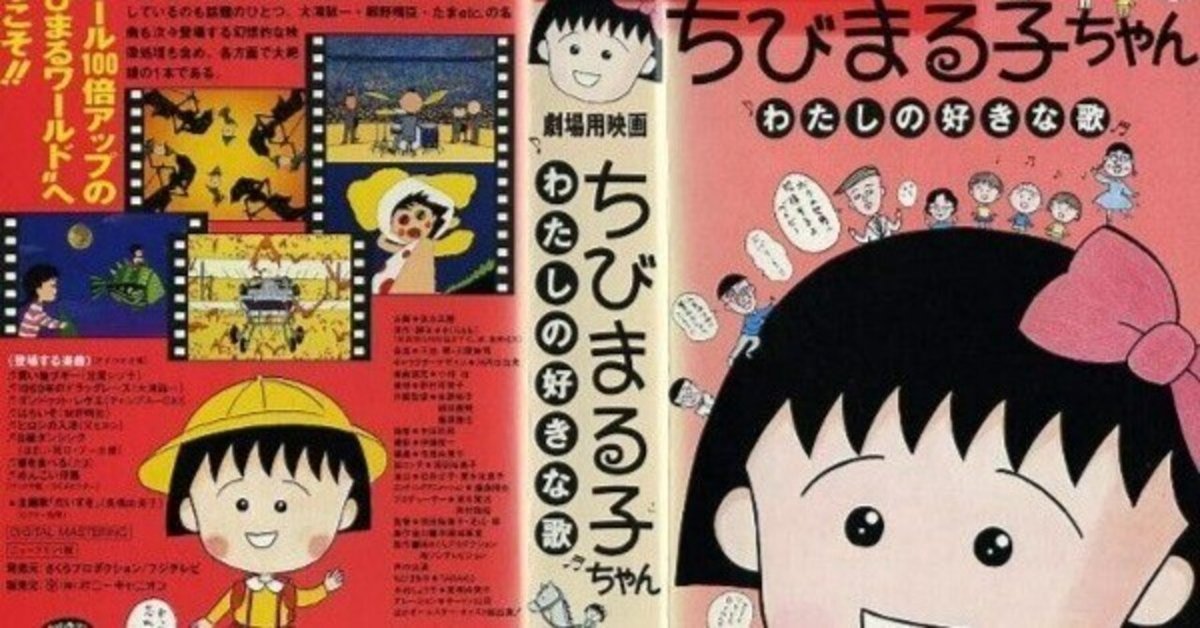
[VHS発掘③]原色眩くMVのドギツさよりも突き刺さるのは"女の幸せ"という圧力、そして彼女に夢を諦めさせた張本人は他でもない・・・ 映画『ちびまる子ちゃん わたしの好きな歌』
結論から言おう・・・・・・こんにちは。(´・ω・`)
はじめて自分で買ったCDはWANDSの『時の扉』のO次郎です。

個人的にはその後の『スラムダンク』『ぬ~べ~』等のアニメ主題歌担当の
being系アーティストさんとしてのイメージが強くなりました。
ぜひとも錆びついたマシンガンでこの不穏な現代を撃ち抜いていただきたいものです…。
今回は、VHSでだけ観られる傑作映画の発掘企画「VHSだけ見つめてる」の第三弾、『ちびまる子ちゃん わたしの好きな歌』をご紹介しましょう。
というのも、このGW中にTwitterにて、”本作が名画座の神保町シアターで上映中で、連日盛況になっている”という投稿を目にして俄然興味が湧き、自分も観てみた次第なのです。
今現在もちょっとずつアレンジが加えられつつも『サザエさん』と併せて日曜夕方のアンニュイなムードに抗するごとくの明るい笑いを振りまいている『ちびまる子ちゃん』のアニメですが、本作は見方によってはそうした誰も傷つけない万人受けするイメージを覆すような一本です。
ですので、普段の平和なテイストのイメージのまま『ちびまる子ちゃん』を卒業してしまった方々にこそ読んでいただきたいと思っております。
文末に視聴方法も書いてますので、自分で観たいからネタバレ許しませんよな方はそちらのリンクまで。
それでは・・・・・・リンリンランランソーセージ!!!
Ⅰ. どんな作品?
まるちゃんが学校の授業で「わたしの好きな歌」というテーマで絵を描くことになった、ということで、要所要所にフルコーラスの音楽パートが挿入されています。主としてそれらが実在のアーティストの曲やそのオマージュと思しき曲なのでそれが現行ソフト化の障壁になっているのかとも思いましたがはてさて。
ちなみに、劇場公開当時に発売されたサントラCDも廃盤・プレミア化している一方、コミックはkindle版で今でも容易に手に入るようです。
そうした音楽パートももちろん出色の出来なのですが、私がどうにも本作で惹き込まれたのがストーリーで、特に本作のキーパーソンである絵描きのお姉さんが”夢を諦める(”夢破れる”ではない)”後半の展開の自己閉塞感がどうにもいたたまれず、それがそのまま、原作者であり本作の脚本も担当されているさくらももこさんの内奥の苦悩だったのかと思うとなおさら圧倒されてしまいます。
肉親に自分の選択を否定されるのと、信頼している他人に別の選択を勧められるのと、当人にとってどちらがより辛いものなのでしょうか。
Ⅱ. 劇伴とゲストキャストと
・音楽 - 千住明
物語終盤、まるちゃんが絵描きのお姉さんとの別れを意識するようになっていくくだりで、普段の『ちびまる子ちゃん』からは到底想起されないような悲壮感溢れる特徴的でヒロイックな劇伴が流れたので「オヤッ?」と思ったらやはり・・・。

リアルタイムに観た初めてのガンダム作品で、幼少期の自分には宗教とエゴの生み出す陰鬱な物語はサッパリ響きませんでしたが、胸を掻き毟るような悲しい音楽は間違いなく刺さりました。
・"絵描きのお姉さん"木村しょう子役 - 高橋由美子

コレに近い感じの献血か何かの、彼女がモデルの啓発ポスターが貼ってありました。
誰かがイタズラの定番で目の部分に画びょうを差し込んでて、先生にめっちゃ怒られてたなぁ…。
当時、ソロのアイドルは絶対数が減っていたからかテレビで観ることが珍しかったので彼女は印象に残っています。大ヒットしたTVドラマの『南くんの恋人』とその主題歌『友達でいいから』はこの翌94年の1月クールなので、まさに売り出し中の頃でしょうか。

それがゆえに当時の日本全国でこの物語のような女性の選択が夥しい数で行われていたかと思うと
なおのこと重たいんです。

『めぞん一刻』のドラマ版の朱美さんがけっこう好きでした。
出演シーンそんな多くなかったけどなかなか体当たりだったな~。
すったもんだが有ったうえに、夏目さんと有吉さんの結婚とタイミングが被ってほとんどニュースになりませんでしたが、想い人と何卒お幸せに、ということで。
Ⅲ. あの時代の若い女性が生きていくには、ということ
問題の絵描きのお姉さんの行く末の前に、それに絡む形でシーンを振り返ります。
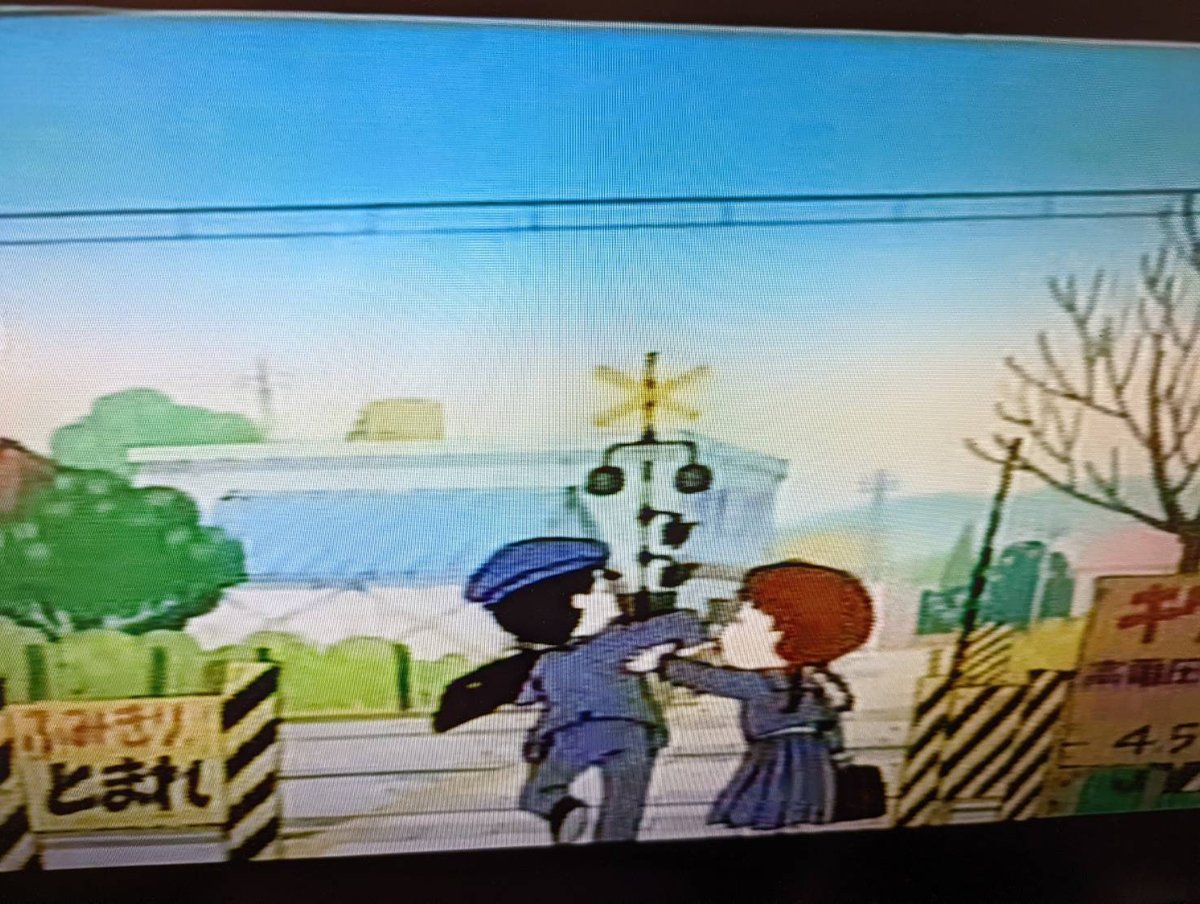
意を決して男の子の腕に自分の腕を絡めようとした女の子が男の子に慌てて振り払われ、
また何事も無かったかのように二人並んで歩きます。



絵を描くことになったまるちゃんは音楽の授業で習った『めんこい仔馬』を
題材にすることにしたが・・・

という戦意高揚歌だったことを聞いて大泣きするまるちゃん。
「まるちゃん、この子はいつか仔馬とお別れする日が来るけど、仔馬のことが大好きな今の気持ちは永遠に変わらない、っていうイメージの絵にしたらどうかな?」という
お姉さんのフォローのセリフが既に死亡フラグ感バリバリである。


お姉さんの付き添いで来た恋人の大学生のお兄さんは、二人になった隙に唐突にプロポーズ。
微妙な空気になりつつもその場では結論出るわけなし。

・・・っていうか、”ずうとるび”の方じゃないのかよ。

ほんでもって、いよいよ。
冬休み中に故郷の北海道に帰省して、年老いた父と慣れ親しんだ馬たちをを見るにつけ、卒業後に早々に家業を継ぐ決意を新たにしたお兄さんとの正念場のシーンです。
「わたし・・・わたし、どうしても一度は東京で暮らしてみたいの。いろんな出版社が有って・・・自分のチャンスを試してみたいの。」
『絵は東京じゃなくても描けるじゃないか』
「わたしは、たくさんの人に自分の描いた絵を見てもらいたいの。結婚なんて・・・・・・まだ考えられない。」
『キミは僕と一緒に人生を歩いていくことより、自分の夢を選ぶんだね。』
去っていくお兄さんを黙って見送るお姉さんに、たまらずまるちゃんが諭します。

『ダメだよ、お姉さんはあの人じゃなきゃダメだよ。絵は・・・絵は北海道でも描けるじゃん。でもお兄さんは、お兄さんはひとりしかいないもん。お兄さんはいつもお姉さんを見てたよ。』
「ほんとね・・・。」
この作品の時代である70年代半ば、まだまだ”女性の幸せ=結婚”の図式で以てして、自分のやりたいことにある程度で見切りをつけての結婚、それもその後の自分を食わせてくれる経済的に将来性のある男性との"良縁"が親類だったり社会通念だったりからの有形無形の圧力として強かったはずです。
しかしながら小学生のまるちゃんは未だそうした社会性が希薄なはずで、そのうえでお姉さんの絵の才能の理解者であったその主人公が、”純愛>絵への情熱”という諭しを行うのです。
これは言い換えれば、”お姉さんには絵の才能が有るけど、誰もが理解してくれるであろう純愛とそれに連なる幸せを捨ててまで追求するほどの孤高の才では無いよ”と断罪しているかのようです。
これがもし、お姉さんの両親や恋人であるお兄さんが結婚へと諭そうとしたのであれば、お姉さんも拒絶の余地が有ります。”親の世間体だったり自分の都合でお姉さんのアイデンティティーの発露としての絵を奪おうとしている”という図式が出来上がるからです。
しかしながら上述のように、本作ではいわば偏見の無い部外者の立場であるまるちゃんがお姉さんの絵への情熱と恋人との結婚との価値判断を下したことで、お姉さんはもはや東京で挑戦するまでも無く、その結果を突きつけられてしまったのではないでしょうか。
おそらくですが、まるちゃんが逆の方向にお姉さんを諭そうとする展開であれば、多くの人に分かりやすく響きやすい展開になっていたと思います。つまり、
まるちゃんが自分が描いた絵で学校で賞を貰ったことを報告しようとお姉さんの元を訪れ、そこでお兄さんのプロポーズを受けるお姉さんを目撃する。
↓
ショックを受けるまるちゃん。「『東京に出てたくさんの人に自分の絵を見てもらいたい』って言ってたじゃん!お姉さんのウソツキ!いくじなし!」
と叫んでその場を逃げ出す。
↓
泣きながら帰ってきたまるちゃんを見た家族がワケを聞き、社会の厳しさや大人の世間体をやんわりとまるちゃんに教えて、お姉さんの気持ちをわかってあげるよう諭す。お姉さんに謝りに行きたいが気まずいまるちゃんの元にお姉さんから”〇月△日に北海道に引っ越すので、最後に会ってお話ししたいです”との手紙が届く。
↓
意を決して当日お姉さんに会いに駅に向かうまるちゃん。「お姉さん、ごめんね。・・・今までありがとう、元気でね。」と新幹線のホームで再会したお姉さんと涙ながらに抱き合ってさよならして終幕。
というストーリー運びであればスッキリ胸に落ちて感動的です。
しかしながらその大団円に持っていかず、”まるちゃん”という無垢の主人公を使ってお姉さんに夢を諦めさせた展開はどこまでも残酷であり、原作者のさくらももこさんのあの時代に対する断罪のように感じられました。
物語を追うのが途中だったので再開しますと、

どうしても花嫁姿を一目見たいまるちゃんは大胆にも学校を仮病で抜け出します。
そして招待客以外は会場に入れないので、付近のジャングルジムのてっぺんからのコレ。
お姉さんから貰ったペンダントを持参してるのは良いとして、
「バンザ~~イ!!バンザ~~イ!!!」はさすがにちょっと…。
戦前の話が随所に出てくるのでもはや確信犯でしょう。

傍にいるお母様が「まだ泣くのは早いでしょ」と苦笑するが、
嬉し涙だけではないのは明らかなわけで。

めでたし、めでたし…?
おそらく、もうそれ以後にお姉さんが絵を描くことはなかったでしょう。もし描いたとしてもそれまでの彼女の絵と同列には置けません。仔馬が軍馬にはなれるかもしれませんが、軍馬が元の仔馬に戻れないのと同じです。
この世界線のまるちゃんが成長した後、このエピソードを深い後悔とともに思い出すとしたら、二重三重に残酷な物語なのではないでしょうか。
Ⅳ. まとめ
というわけで、ちょっと己の解釈が過ぎるとは思うのですが、一方で作中の描写に一貫したリードが有るのは間違い無いと思います。

仔馬が軍馬として連れていかれる展開は敢えて生徒たちに教えなかったそうで、
戦争で想い人と生き別れてしまった過去があるようです。
冒頭のシーンで腕を組むことを男の子から拒まれる女学生の姿が有りましたが、”自分の望む形での愛を全うできない女性の姿”というテーマは一本通っているのではないでしょうか。
また、おそらくジョージ秋山さんの短編だったかと思いますが、本作を観ていて思い出した作品が有ります。タイトルは忘れましたが、話の筋は以下のような感じです。
ヒット作を何作も生み出している人気作家が己の作家性に悩み、遂に”自分の本当に描きたい作品だけを描く”と決心する。
↓
新しい仕事を次々に断り、自分のための作品を描き進めるが、貯蓄はどんどん減っていき、ついには食べるにも困るようになる。
↓
野宿生活になって数十年、極寒の雪模様の中で息絶えてしまうが、彼の手の中には長年をかけて描き上げた彼自身のための作品と大満足の死に顔が。
↓
その遺稿は出版社の手に渡り、誰のものともわからない作品として脚光を浴びる。
この物語の主人公の作家は男性でしたが、果たしてあの時代にその主人公を女性にすることにリアリティーが有り得たでしょうか。
そしてこの『ちびまる子ちゃん わたしの好きな歌』は、愛にしろ夢にしろそれに女性が自分の信じる形で殉ずることを許さない社会と時代への抗議とも怨嗟ともとれる作者の意思表示のように、私には映りました。
コンプライアンスの観点からいろいろと表現規制の厳しくなっている昨今ですが、今現在のアニメの『ちびまる子ちゃん』には、万人が楽しめる娯楽成分だけでなく、その奥にある今は亡き原作者のマグマ溜まりのような想いの片鱗だけでも画に載せて届けてほしいものです。

コミックス未掲載の伝説の封印回、
98話「まる子、夢について考える」が
雑誌りぼんに掲載されるのは本作からおよそ2年後…。
Ⅴ. 視聴方法
現在、名画座での上映やCSでの再放送以外はVHSビデオでしか観られない本作ですが、渋谷のTSUTAYAに在庫があり、首都圏の方はレンタルで観られます。
〇場所: 渋谷TSUTAYA
〇料金: 下画像ご参照下さい。
※準新作がセールの時はVHSレンタルも対象になるようです。
※VHSデッキレンタルも可
〇その他: VHSデッキの出力は3色ケーブルなので、再生時に3色ケーブル→HDMIの変換器が必要

今回は長々と自説を展開してしまいましたので、次は作品選びにしても内容にしてもなるべくサラッとライトにしようと思います。
それでは・・・どうぞよしなに。
いいなと思ったら応援しよう!

