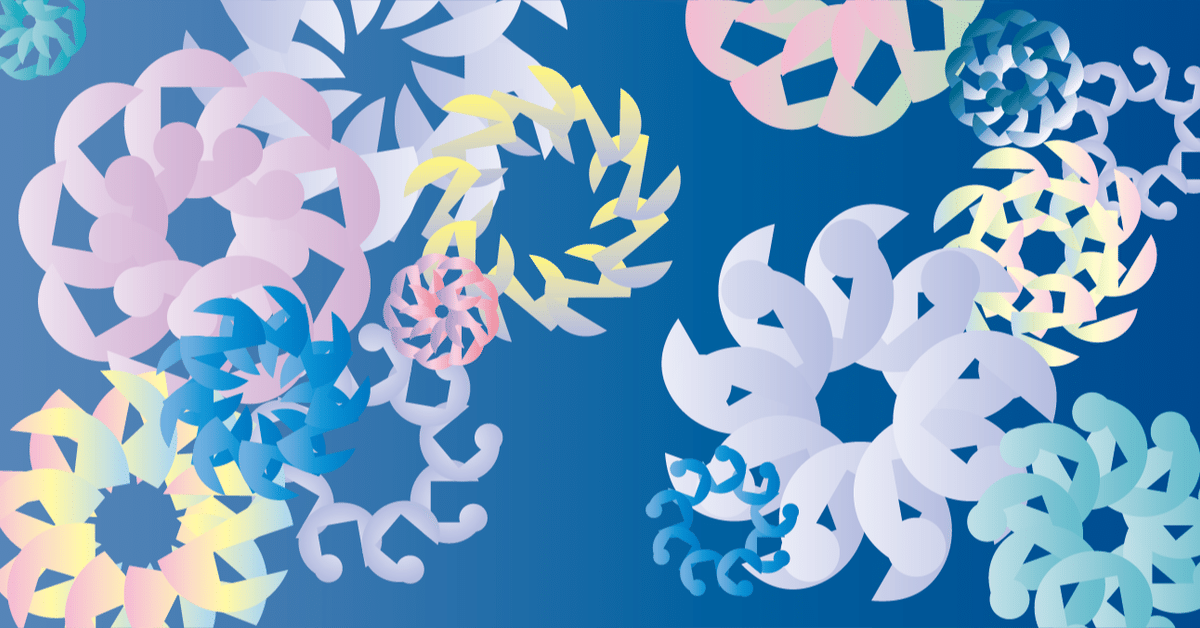
【短編ー後】花火
オーダーを受けた料理を「作る」とき、副産物として出るイルミネーションは、人によって様々だ。大抵はいくつかのパターンに当てはまる。
例えば先程のナポリタンを食べていた男性は、ライブ会場でたかれるスモークのような、緩やかに発光するタイプのものだ。色味は日により違うのだが、今回は赤紫色だった。
他にも、レーザー光線型、ホタル型、仏の後光の型などがある。しかし、少女のような花火型は大変珍しかった。私はこの仕事を長くやっているが、今までにお目に掛かったことは二回しかない。つまり、三度目の花火だ。
少女から細く伸びた光の先端が、まさしく開花するように弾ける。見事な打ち上げ花火である。しかも連弾で、白い部屋の隅々を鮮やかに彩る、極彩色だった。ショックピンク、マリンブルー、メイズイエロー、アップルグリーン。
カドミウムオレンジの花火が打たれ、イルミネーションショーは終焉を迎えた。圧巻の時間だった。気づけば私は、心臓のある辺りに手を添えて、必死に息を整えようとしていた。鼓動を、全身で感じている。余韻に浸りたい気もしたが、客に動揺している姿を見せるのは避けたかったのだ。
「……お客様、お疲れ様でした。目をお開けください」
声を慎重に抑えて掛けると、少女はゆっくりと瞼を開いた。顔を上げ、座り姿勢を正すと、目尻を擦りながらとろんと囁いた。
「なんか、体がぽかぽかして……疲れていたのかな」
「どうかお気になさらず。皆様、そう仰るので」
実際、途中で眠ってしまう客は多い。料理により「言葉にならない気持ち」が心の外へ抽出されるので、空いてしまったところを埋めるように、心が動くのだそうだ。その結果、麻酔を打たれた感覚になるらしい。
テーブルにカトラリーを静かに並べ、服を汚さないためのナフキンを少女に差し出す。そして料理を取り出した。オーダーされた赤身のステーキだ。鉄板皿の上で、ジュージューと肉が唸っている。
「うわぁ、すごい。冷えてそうなのに……」
少女が驚くのも無理はなかった。私が料理が取り出したのは、テーブル横に設置されている冷蔵庫のような機械からだからだ。ちなみに、熱かろうが冷たかろうが、料理はすべてここから出てくる。
「面白いキッチンでございましょう? どうぞ、温かいうちにお召し上がりくださいませ」
ほかほかの半ライス、氷の入ったお冷も用意した私は、後方に下がった。少女はごくりと、かしこまった姿勢で料理を眺めていた。しかし、それは束の間のこと。やがてナイフとフォークを手に取ると、そっと肉の端に切れ込みを入れた。口に運ぶ。
「……美味しい」
零れた言葉が、私の耳に転がり込んだ。私は何も言わなかった。彼女も、わざわざ振り返って感想を言うわけではない。しばらくは、控えめな食事の音が淡々と続いた。
「……一緒に、これ食べたかったなぁ」
ふと、少女は誰かに話し掛けるように、呟いた。ステーキを切り分ける手は止めない。彼女のどこか透明感のある本音は、まるで子供が手放した風船のように、空間に漂っているように私には思えた。
「それなのに、どうして?」
少女は、途切れ途切れに風船を飛ばした。
「親友じゃなかったの?」「違うのに」「私は先輩のことなんて」「なんか優しくはされたけど」「応援してたのに」「違うってば!」「なんでお母さんも知ってるの?」「近所の幼馴染だから?」「嘘つき」「避けてないで、話を聞いてよ」「……バカみたい」
ああ、これは風船ではなかった。
私は急に気づいてしまった。これもまた、花火なのだ。パチパチ弾けるブーケのような花火を、彼女は打ち上げようとしている。ふわふわとした、丸みのある言葉に換えようと努力しているだけで。
音をたてないように私は踵を返した。スタッフルームにある物を取りに行くために。背後で、鼻をすする音が微かにした。
「……うぅっ」
「ごちそうさまでした。とても美味しかったです」
料理を食べ終わった少女は、しっかりとした口調で喋るものの、どこかアンニュイな表情をしていた。もしかしたら疲れたのかもしれない。ここに来る客は、食後は大抵、2パターンの反応を示すからだ。自分の気持ちが理解できてスッキリするか、心の在り方の変化について行けず戸惑うか。両方、の場合もあるかもしれないが。
「それは何よりでございました。……お客様、こちらを差し上げたいと存じます。よろしければどうぞ、お受け取りくださいませ。ほんの気持ちです」
「えっ……?」
お冷以外の食器を下げた後、そのままコイントレーを介して会計を行う。財布を鞄にしまう少女が席を立つ前に、わたしは小さな紙袋をテーブルの上に置いた。彼女は躊躇いがちに中身を開ける。中身は、蒼い押花をラミネート加工した栞だ。
「綺麗な花……なんて言うんですか?」
「アイリスです。実は以前、お客様から頂いた物でして」
「えっ? そんな、その人に悪いですよ……」
慌てて栞を返そうとする少女に、私は微笑んだ。予想通りの行動だが、実際に見ると、予想以上に可愛らしく感じられた。
「問題ありません。なぜならば、その方も別の人物から頂いて、その人物も誰かから貰ったらしいのです」
「……どういうことですか?」
「このアイリスは、ずっと旅をしているのです。そして、今度は私が送り出す番だと、直感致しました」
少女はどう捉えているのか、私の話に聞き入る。
「もちろん、お客様がどうしても受け取りかねるのならば、強要は致しません。いかがなさいますか?」
しばらく少女は考え込んでいたが、ゆっくりと顔を上げて言った。その瞳は、あの花火のように、キラリと瞬いていた。
「……貰います。大切にします! ありがとう」
「こちらこそ、有難うございます」
本日の最後のお客様が、貴女で良かった気がする。
礼を言われた意味が分からないらしい少女はきょとんとしていたが、ふわふわと口元は緩んでいた。
お客様を見送り、自らも帰り支度を済ませて店を出る。一歩外を出ると、繁華街らしい喧騒が私を包んだ。カラフルな看板、数多の会話が混ざった音楽。そうだ、そういえば世界はこうだったと、いつも考えてしまう。
「……私は、どんなイルミネーションなのかな」
無意識に店を振り返って、花火に思いを馳せていた。私は「料理」をもてなす側なので、自分のイルミネーションを見たことはない。いずれにせよ、自分のものは見れないシステムだが、気になってはいる。
いつか私にも、言葉にならない感情を抱えて生きる日が訪れるのだろうか。そして、食べる側になるのだろうか。
「ふっ」
ぼうっとしている自分を急激に自覚し、小さく吹き出してしまう。周囲の人間に見られていたかはわからない。しかし気まずさはあるので、口元に手を添え、取り繕うように歩き出した。
夜食はどうしようか。人知れず悩みながら、私はネオンの輝く街の人波に溶け込んだ。
トップ絵は、前編と同じくTajifusenさんから。前編を確認しながら絵を眺めるていると、本当にこの話にピッタリだと思えてきました♪
そして、皆様。お読みいただき有難うございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
