
[特別寄稿」 老いと死と家族 -百歳老人の心理学ノート- 名誉顧問 杉溪一言

コロナ第7波の跳梁(ちょうりょう)。先の見えないウクライナ戦争。連日の猛暑。次々に起こる日本列島の災害…。厳しい現実が続いているこの頃ですが、協会員の皆様はお元気で日々ご活躍のことと思います。
このたび、「そよかぜ」誌から寄稿を依頼されましたので、久しぶりに近況やら思うことを書き連ねて責(せめ)を塞(ふさ)ぎたいと思います。一老人の呟(つぶや)きをサラリと読んでいただければ幸いです。
さて、年月はどんどん経って当協会も創立以来37年を数えます。そして私も年を重ね、去る3月百歳になりました。折しも桜が満開となり、雰囲気満点の中で3桁の人生を踏み出しました。
人生100年時代と言われる今日、百寿の人は全国で8萬数千人も居るそうですから、特に珍しい話ではないのでしょうが、私のところにも思いがけず、総理大臣や東京都知事、武蔵野市長などから祝いが届き、百という節目の重さを感じさせられました。当協会からも大きな花束をいただきとても嬉しく思いました。決して短くはない協会での年月が、録画の早送りのように頭の中を駆け巡りました。
桜が散って緑が次第に深まってくる頃、祝いの騒ぎも一段落し、百寿の気分も薄らいできて、私はまた静かな日常を取り戻しました。そして――静寂の中に言い知れぬ寂寥(せきりょう)感が漂いはじめました。
私は昨年の暮れに、長く病床にあった妻を看送りました。ライフストレスの研究では、配偶者との死別が人生上で体験するライフイベントの中で、ストレス度が最も高い出来事とされています。生活の上でも精神的にも大切な存在であった伴侶を喪って数ヶ月。空虚感、孤独感が襲ってくるのはごく自然の理とも言えましょう。
私は、祝い事の高揚した気持ちとの落差も重なって、一刻(いっとき)「老人性うつ(●●)」のような状態だったと思います。

私は高齢になり研究の第一線を退いて久しいのですが、今でも幾つかの学会からジャーナル(研究誌)が送られてきます。現代の当面する課題が反映されていて、興味深く読んでいます。
折しも、タイミングよく出版された心理学の研究論文集が私の目に留まりました。「心理老年学と臨床死生学――心理学の視点から考える老いと死」と題する部厚な本です (佐藤眞一編著、ミネルヴァ書房2022)。300ページの中に16編の論文が載っていて、老いのわが身にはどれもが興味をそそります。各章のタイトルは、編者が、著者たちに投げかけた問いの形になっています。ここにその中の数編を抜き出すと―――、
・ 老年期の孤立、孤独はどのような問題につながるのか?
・ 老いの先にある幸福とは?
・ 老いにより培われるものはあるか?
・ 百歳長寿者は他の高齢者と何が違うのか?
・ 認知症ケアに欠けていること、必要な事は何か?
・ 死と死別に関する心理学の成果とは?
・ 大切な人の死といかに向きあい、そして生きるのか?
編著者で、著者たちの指導者でもあった佐藤氏は、まとめの中で「死と生の研究は人類にとって課題のフロンティアであり続ける。そしてまた、死を見つめるということは、生を見つめることでもある」といっています。
自らも老い、大切な人の死を身近に体験した私は、改めて老いるということの意味、死と向き合って生きるということへの根源的な問いに出会ったような気がしました。そして、与えられた静寂のなかで思索を重ねることに、内心の愉悦を味わいながら、いつの間にかうつ(●●)から脱け出していました。

「老いと死と家族」と題するこのエッセーで、私は何を語ろうとしているのでしょうか。わが家にも訪れた家族ライフサイクルのうねりの中で、家族システムの再構築が秘かに進行しています。私は一家の家父長から「要介護」の老人となり、被支援者の座に着いています。親子の関係が逆転した今、受け身の人生を体験しつつあります。
入力、出力の逓減(ていげん)と言う厳しい現実の中で生きる道は「最適化」の論理でしょう。これは小さな目標で最大の幸せを得ると言う方略で、心理学的に言えば要求水準を下げて達成感を味わうということです。中国の古典にある「富在知足」(富は足ることを知るにあり)と言う箴言(しんげん)も同じ意味を含んでいますから、いまに始った話ではありませんが。
伴侶の死は遅かれ早かれ訪れる摂理ですが、その対応はそれぞれで、十把一絡げに論ずることは出来ません。私の親戚に私と同年輩の大正11年生まれの女性がいましたが、今年に入ってまもなく転んで急逝しました。百歳の誕生日を目前にしてのことでした。介護に尽くしてきた家族の嘆きは大きく、ケアの限界を超えていましたが、先日私の所へ来て家族で語り合い(ナラティブ)、いくらかの癒しになったようでした。今後、悲嘆の超克のプロセスがさらに語られるなら、グリーフワークもさらに深まることでしょう。
家族の物語は日々に綴られていきますが、それを心に紡ぎ、その絆を胸の奥に刻みつける営みは、生死を超えて家族の関係性を確かなものとしていくのではないでしょうか。
私は家族支援に携わる一人として、支援者が“当事者”意識を失わず、自ら
の体験の意味を考えていくことが支援力の向上につながるのではないかと思っています。
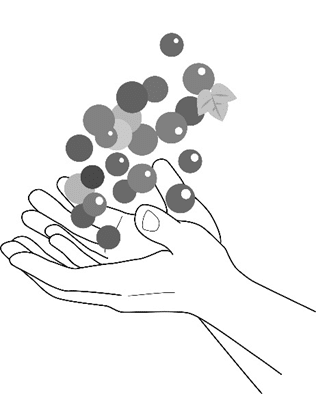
言い知れぬ寂寥感を味わった私は、そのネガティブなプロセスを経て、いま、百歳からの人生を新しく踏み出そうとしています。勢い余って転ばないように気を付けながら…。(会報誌:そよかぜNo52より)
