
論文を読めるようになろう!:研究が始まる前の準備
こんにちは。元農大生です。皆さん研究室は決まりましたか?
研究室に入ったらやること、それは研究です。そのためには論文を読むことが必須となります。ただ、論文というものは独特な形式で書かれているので、初見で見た時は何が何だかわかりません。
僕も最初気合い入れて、「研究室も決まったし、勉強するぞ!」と思っていましたが、意味がわからなさすぎて白目剥いて横転しました。先輩に聞いても読んでたら慣れるしか言われないし。
論文見てみたけど何もわからないって人もいると思います。でもそれは当たり前なので安心してください。いきなり法律の本を読んでも何書いてるかさっぱりわからないですよね?それは僕たちは専門用語や言い回しを知らないからです。それと同じ。
常日頃から読むことのトレーニングをしていないのに、突然専門分野の論文を英語ですらすらと読めるようになる訳ないじゃないですか。そもそも論文の読み方なんか、ちゃんと教わっていないですし。
そんな課題を解決するために今回は、研究室配属が決まってからまず覚えるべき「論文の読み方」について解説します!(僕は自然科学系の研究をしていたので、自然科学系論文の読み方になります。)
なぜ論文を読まないといけないのか
まずなんで論文を読まないといけないと思いますか?
卒業研究のため?先輩に言われたから?英語の勉強のため?間違ってはないですが、論文を読む1番の目的は「最新の情報を手に入れること」です。
科学的知見は毎日更新されます。なので情報を常に追っていくことが必要になります。論文を読まないと、アップデートが出来ずにいつまでも古い情報にとらわれたり、間違っている仮説を信じ続けたりしてしまいます。研究においては「前提や仮説がそもそも間違えていた」ということもよくあるので、論文を読み情報を更新していくことがとても重要です。
それに自分の研究は自分にしかわかりません。もちろん先生や先輩に研究の背景や実験方法などある程度のことは教わりますが、基本的に全員「新しいこと」をやることになります。
先生も先輩も研究の進め方は教えてくれますが、情報は誰も教えてくれないです。だからこそ自分で情報を取りに行く能力が必要なわけですね。
研究室によってはみんなの前で論文紹介みたいな形で、論文を読む練習がありますがそれだけでは圧倒的に量が足りないです。理想は1日1本読むこと。最初は時間がかかりますが、慣れれば30分〜1時間くらいで読めるようになるので安心してください。
ただ、がむしゃらに読んでも読めるようにはならないので、読めるようになるための一つの方法として紹介します。これが絶対に正しいとは限らないので、参考程度に自分に合ったやり方を探してください。
論文の種類
まずは論文の種類について解説します。とりあえず英語で書いてたら論文っていう訳ではなく、大きく分けると2種類あります。
①原著論文
論文といえば普通この原著論文のことを指します。著者が独自に行った研究に基づき、取り扱う問題が原則的に一つです。同じ条件の下で別の人が実験を行った場合にその論文の内容を再現でき(再現性がある)、目的と結果が明確に示されており、第三者の専門家により厳格に査読されていることなどが特徴です。
②レビュー論文
総説論文や調査論文とも呼ばれます。レビュー論文は、特定の分野の重要な先行研究を集めて、立ててまとめた論文です。レビュー論文自体に新たな発見等はありませんが、その分野に関して俯瞰的に捉えることができます。レビュー論文で扱われているテーマについて、何が解決されており、何が解決されていないのかが浮き彫りになるため、その分野に関する研究を始める前に読んでおくべき論文ともいえます。
補足
査読とは
査読とは、他の研究者が論文をチェックして、内容が正しいか、役に立つか、そして新しい発見があるかどうかを確認する仕組みです。論文を公開する前に、その分野の専門家が詳しく読んで、問題があれば修正を求めます。権威ある一流の雑誌ほど、審査は厳格かつ詳細になされる傾向にあります。(例えばCellとかNature)研究によっては、査読開始から掲載までに何年もかかるようなものもあります。
インパクトファクター(IF)とは
インパクトファクターとは、自然科学や社会科学の学術雑誌が各分野内でもつ相対的な影響力の大きさを計測するための指標の1つです。研究者は学術雑誌に自分の研究の成果を示した論文を掲載します。学術雑誌に論文が掲載されるためにはその研究に詳しい専門家からの査読を受ける必要があります。査読が行われることによって、その研究の質の高さ、結果や研究手続きの信頼性などを担保します。
まずはIFが高い雑誌に載ってる論文から読んでみるといいと思います。注意が必要なのはIFの目安は分野によって異なるということ、IFで論文の価値が測れるか?ということではありません。IFが低くてもとても重要な仕事も多く、自分の仕事に関わるような論文であればIF関係なく必見です。
例えば、統計学に関する手法を扱った論文などはほとんどの場合IFがあまり高くありません。最初はいい論文、悪い論文の区別がつかないと思うので各分野の一流誌の論文をなるべく読みましょう。これは調べたらすぐ出てきます。
レター、速報
学術雑誌は査読があるため投稿から掲載まで時間がかかります。新規性と独創性をできるかぎり早く確保したい場合や、その分野の研究者に成果を早く伝えたいために用意されているのが Letter です。そのため査読期間は短い。Letter 専門の雑誌もあります。原著論文に比べると小さい問題、現在進行形の研究成果が記載されています。(問題、解決方法と結果の概略、あるいは新しい問題など)
原著論文を読む前に
いきなり英語の原著論文を読んでもいいですが、ハードルが高いです。気合が入ってる人はここを読み飛ばしても大丈夫です。僕はいきなり原著論文は心が折れました。
①まずは日本語で情報収集
興味のある研究テーマや、研究室の研究について知りたい人はまず情報のインプットのために日本語の文献を読みましょう。先輩の卒論・修論・博論も知識整理に役立ちます。(先輩の論文→日本語文献がいいかも)
日本語文献のイメージはこんな感じです。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/yakushi/129/11/129_11_1327/_pdf
研究背景や、専門用語が頭に入っていないと原著を読んでもその研究の意義がわからないですし、いちいち単語調べることになり頭に入ってきません。レビューを読めばそこも解決できますが、なるべく最初はハードル下げていきましょう。日本語で読めるものがあるなら、そっちの方が何倍も理解しやすいです。
ただし、これはもう口酸っぱく言われてると思いますが、Wikipediaや誰が書いてるかよくわからない記事はやめてください。正しい情報ではない可能性が高いです。
探し方としては、J-STAGE(科学技術情報発信・流通総合システム)やCiNii(NII学術情報ナビゲータ)を使いましょう。どちらも論文や雑誌などの学術資料を検索できるデーターベースサイトです。
その分野で有名な先生を知っていれば名前でも検索できます。先輩の卒論の引用文献・参考文献にもあると思うので、そこから探すのも有効です。
テーマに関するものを5本くらい読めば研究背景や、専門用語は理解できるようになっています。(専門用語は無限に出てきますが、ある程度テーマによって出てくるものは決まっています。)
②英語のレビューで情報収集
テーマの概要が大体理解できたら、英語のレビューに移りましょう。ここでの目的は英語の専門用語を覚えることと、論文の表現に慣れることです。
・英語の専門用語を覚えるとは
当たり前ですが日本語と英語の単語では全然違います。例えば塩基性は英語で「basic」ですよね。これくらい簡単なものだったら間違えることは少ないですが、中にはそれがその意味だったんだっていうものもあります。あとはテーマ頻出の単語もあるので、覚えておくと読むスピードが上がります。
・論文の表現に慣れるとは
論文はある程度書き方が決まっています。なので、慣れてくると「あ、ここから先を読めば結果がわかるな」ということがわかってきます。例えば結果の部分でよくみられる表現はこんな感じです。高校英語がわかっていれば苦労することはないので安心してください。
【実験の目的・方法を述べるときの表現例】
In order to … / ~するために
To elucidate ... / 〜を明らかにするために
To this end ... / この目的のため、~
【実験の結果を述べるときの表現例】
As a result, … / 結果として~だ
【結論を述べるときの表現例】
Our results provide the evidence for … / 我々の結果は〜の証拠を提供する
It should be noted that … / ~は強調されるべきである
This result suggests that … / この結果は~ということを提案している
We concluded that … / ~と結論づけた
このように表現がわかっていれば、ここは何について書いているということわかるので、読む速さがどんどん上がっていきます。
原著論文の読み方
ここまできたら原著を読む準備はもうできています。あとは原著に慣れるだけ。原著論文は構成が決まっているので、まずは構成を解説し、おすすめの読み方を紹介します。後ほど改めて説明しますが、1回目で全て理解しようとしなくていいです。
欲しいのは情報なので、「何が明らかになったか」が知れたらOKです。細かいところは2回目以降に理解していきましょう。ここでの論文の選び方の注意は、「短い論文(速報など)を選ばないこと」です。確かに文量が短いものは読みやすいですが、研究背景や実験方法が省略されてることが多いので、内容の理解が逆に難しいです。
妥協せず、気合い入れていきましょう。原著論文の構成基本的な構成は以下の通りです。この下で図を含めて解説します。
Title (タイトル)
Authors (著者名)
Abstract (概要)
Introduction (イントロ)
Results (結果)
Discussion (考察)
Conclusion (結論)
Methods (方法)(Methodsは最初の方に来ることもあります。)
Reference (引用文献)




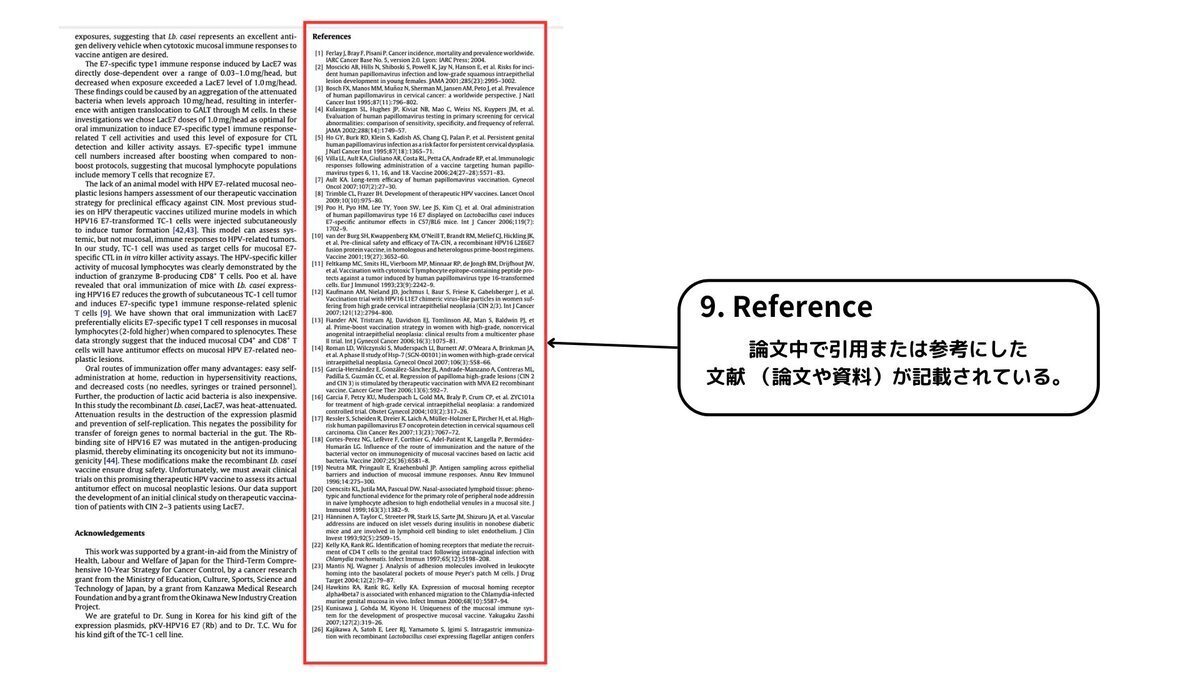
おすすめの読み方
論文のイメージは湧きましたか?難しそうと思っても心折れないでください。実際にどう読み進めていけばいいか解説します。
まず前提として、一度に全て理解できなくてもいいです!
馴染みのない論文を最初からスラスラ読むことは難しいです。ていうか無理です。なので2周以上読むことを前提に考えておきましょう。また、書き込めるよう印刷しておくといいです。僕も気になった部分やポイントを書き込めるように最初は印刷していました。
【1周目】

まずは大枠をつかむために、頭から一回読み切りましょう。わからない英文を読んでいると、ついつい目が滑りがちで頭がぼーっとしてくるかもしれませんがそこは気合いです。パワー。
頻繁に出てくる専門用語はその都度立ち止まって辞書で調べて紙にメモでもしておいてください。受験で習ったように構文解釈をしてもいいですが、ひとつの文にあまりとらわれて時間をかけないようにしてください。
また、本文に図表との対応を示す図や表( Fig X とか、Table X とか)に、蛍光ペンなどでマークを入れておくと、図表と本文との対応がとりやすいです。またこの時点で実験方法は読む必要ないです!そもそも配属直後は実験手法なんか全然知らないですしね。
各章ごとにわからないところは横にメモを入れておけば、後で何がわからなかったかを思い出しやすいです。2周目以降に役立ちますこれを踏まえた上で、大まかにはこの流れで読むのがおすすめです↓
①Abstractで論文のストーリーを把握
②Introductionでその研究背景、意義、を把握
③Conclusion,Discussionで著者が主張したかったこと、今後の展望を把握
④Resultsで著者の主張をどのように裏付けているのかを把握
もう一度言いますが、これで完全に理解できなくて大丈夫です。むしろ1回読んだだけで理解できるわけがない!と開き直ってください。
【2周目以降】
2周目はイントロは飛ばしてResultsが正しく解釈できるようにしていきましょう。(忘れているところなどはさらっと読み返す。)
Resultsでは基本的に情報は、実験結果を示した図表データの読み解きという形で記載されています。例えば著者がグラフを示して、「薬物 A よりも B の方が、細胞をよく殺した」と書いていれば、本当にそういっていいのかを、グラフをよく見て確認してください。
棒グラフであれば、文章に記述された棒の一本一本を確認しつつ、また折れ線であれば、その変化を左から右に追っていくというふうに、自分が実験者として得たデータのつもりで、詳細に見ていきましょう。
じゃあ図を見ても、それと対応する文章を読んでも、なぜ結果としてそういえるのかがわからない場合にはどうしたらいいか。ここで実験方法を読みましょう。どのような実験操作によって、どのような図が作成されたかの詳細が書かれているかを確認してください。
それでも何をやっているのかがわからない人は、そもそも書かれてある実験手法自体がわっていないことになります。その場合は、教科書やネットで実験の、やり方、得られる情報について調べる必要があります。先輩に聞いてみるのもいいですね。
大切なことは、実験を、その結果(データ)をみて客観的に判断することです。文章だけ読んで、著者の「解釈」に引きずられてはいけません。
著者は論文を採択にこぎつけるために、都合の良い無理な解釈をしている場合があります。僕たち読者はあくまでも、書かれた結果について、エビデンス重視で正確にデータを読み取ることが大切です。
おまけ:1つ上のレベルに行くために
どうだったでしょうか?ここまでくれば論文の読み方についてはある程度わかったと思います。ここからはもう1つ上のレベルに行くために必要なことを紹介します!
①数をこなす
1回これを実践しただけでは、読むスピードは速くなりません。最初は読み切るだけで半日以上かかるかも知れません。早く読めるようになるコツは、1本を徹底的に読むより、1日1本って決めて読むことです。
たとえ読みが粗くてよくわからなくても、1時間でざっくり一報を読んでしまうトレーニングを日々続けていきましょう。
②批判的に読む
批判的に論文を読め、とよく言われます。「科学はまず疑うことから始まる」これも有名な言葉ですね。
研究をする際には疑り深い、性格の悪い人にならないといけません。常に心に関西人を飼って「なんでやねん」と突っ込みをいれる精神が必要です。
例えば図ひとつを見るにしても、原理と方法を知らなければ「何を」「どこまで」議論できるかわかりません。単なる模式図のみに頼った論文の解釈はせずに、本当に根拠があるかどうかを確認しましょう。
こうすることで自分の研究が始まった時も自分のデータを客観的な視点から厳しく評価することができるようになります。
また、読むスキルが向上するにつれて、よい論文と悪い論文がわかるようになります。どのような論文がよい論文で、どのような論文が悪い論文なのか。この判断にはさまざまな評価基準がありますが、例えば必要な情報をすべてエビデンスとともに提示し、第三者が再現できるように記述されている論文はよい論文です。
逆に、最小限の情報を不完全な形で出している論文は悪い論文といっていいでしょう。(ST◯P細胞)
まとめ
長くなってしまいましたが、解説は以上になります。ぜひ論文が読めるようになっていい研究のスタートダッシュを切れるようにしてください!
周りでどうしたらいいかわからない子がいたら是非このやり方を紹介してみてください。ドヤ顔でこの内容を語ってくれて構いません。
わからないことや、疑問に思うことがあればマシュマロで質問してください!!
▼マシュマロ
https://t.co/Y3110YMSFM
<参考資料>
http://www.chem.waseda.ac.jp/koide/20160108.pdf
https://www.library.osaka-u.ac.jp/doc/LS_20201203_english_articles.pdf
