
まずは、つぎはぎでもいい|「エシカルフード基準」づくりの裏側 vol.2
こんにちは。「Tカードみんなのエシカルフードラボ」公式note担当の東樹です。
エシカルフードの有識者12名と対話を重ね、2022年3月30日にラボが発表した「エシカルフード基準」。約1年かけて、「エシカルフード」を定義し、「どの食品がエシカルなのか」を示すための基準を策定しました。

国内において先進的な取り組みと言える基準の策定にあたって、運営面ではどのような課題や工夫があったのでしょうか。ラボの運営事務局の皆さんに「基準づくりの裏側」をお聞きしていきます。
今回は、ラボリーダーであるCCCMK ホールディングス株式会社の瀧田さんと湯浅さんへのインタビューをお届けします。大企業版と中小企業版が公開されているエシカルフード基準ですが、内容を継続的にブラッシュアップしていくための取り組みと、その難しさについて語っていただきました。
・・・
網羅的な基準をつくることの難しさ
ー 2022年3月にエシカルフード基準の大手企業版が公開され、その半年後に第2版の公開となりましたが、半年の間にどのような対話がなされたのでしょうか?
(瀧田)
第1版を2022年の3月30日に公開した後、4〜5社から内容についてフィードバックをいただきました。「かなり厳しい基準になっている」というご意見でした。
元々、基準をつくる段階から、メーカーのみなさん、流通企業のみなさんとは対話を行ってきました。日本の食品業界の現状に即した基準をつくり、実効力を持たせるためです。
主に、基準のしきい値を決める際にご意見をいただいていました。しきい値というのは、「どのレベルまで項目を達成していれば、エシカルフードとして推薦できるのか」を示すものです。
3月、基準を文書として可視化したことで、今まで以上に細かい対話に移れるようになりました。その中で、企業のみなさんから新たな意見をいただき、第2版公開に向けて内容をブラッシュアップすることになりました。
(湯浅)
第1版は、イギリスの「Ethical Consumer」と対話しながらも、日本の企業に即した基準にするということを意識しながら作ってきました。それでも、公開するとフィードバックを通じて様々な課題が見えてきたので、第2版はより現実的な内容になっています。
(瀧田)
加えて、基準の中で考慮しないといけない原材料についてのフィードバックもありました。
たとえば、エシカルフード基準のフード評価は、大きく農産物、水産物、畜産物、フェアトレード、オーガニック、と項目がわかれていますが、その中でパーム油だけ切り出して基準を設けています。パーム油を取り巻く社会的な問題が大きすぎるからです。
ですが、パーム油と同じように考慮しないといけない原材料は他にもたくさんある、というご意見をいただきました。

ー 企業のみなさんからのフィードバックを反映するにあたって、難しかった部分はありますか?
(瀧田)
一番難しかったのは、原材料についてですね。エシカルフードは食品なので、原材料が無数にあるじゃないですか。
私たちは「Ethical Consumer」の基準をベースにしているので、パーム油だけを切り出していたのですが、フィードバックを受けてカカオ豆も切り出すことにしました。それとともに、ほぼ同じポジションにあるコーヒー豆も切り出すことに決めました。
ただ、本当にそれだけでいいのか、という部分に悩みました。切り出さなければいけない、社会的な問題を抱える原材料が他にもあるのではないか、それを網羅しないといけないのではないか、と。ですが、原材料とエシカルの両方に詳しいプロフェッショナルって、なかなか存在しないんですよね。
(湯浅)
膨大な数の食品がある中で、網羅的に見られる人はいないですね。なので、どこに抜け漏れがあるか、まだわからないんです。
(瀧田)
とにかく社会に出してみて、社会からのフィードバックを元にブラッシュアップすることで社会実効性を高めていけばいい、網羅性を最初から担保しなくてもいい、と吹っ切って、まずはカカオ豆とコーヒー豆を追加することにしました。
エシカルフード基準って、ある意味つぎはぎで作られていくんだろうな、と思うんです。「Ethical Consumer」の基準も、30年間かけてつぎはぎで作られたものですし。そのようにしなければ、基準は作れないんじゃないかと思います。

知識の補完に力を入れた「中小企業版」
ー 2022年9月12日、大手企業版の第2版と同時に中小企業版も公開されていますね。
(瀧田)
元々、エシカルフード基準の大企業版と中小企業版をそれぞれつくる必要があると考えていました。まずフレームとして大企業版を作成し、おって中小企業版を出す、というステップで進めてきました。
(湯浅)
中小企業版は、大手企業版の第2版をベースにしながらも、文章をより平易にし、用語集など解説も盛り込んでいます。
中小企業とコミュニケーションを取る際には、エシカルに関する言葉が共通言語になりにくい場合があり、そこが難しいポイントです。たとえば、「二酸化炭素排出」と言った時に、具体的に何をすると排出されて、何をすると抑えられるのか、ということがわからなかったりします。
なので、採点するにあたっても、大手企業の場合は容易に進められるのですが、中小企業にとっては「丸をつけていいのか、いけないのか」という判断が難しいんです。
(瀧田)
エシカルフード基準は自己採点制なので、余計に難しいのだと思います。同じ取り組みをしている2社があったとして、1社が丸をつけた項目に、もう1社はバツをつけるということも起こり得ます。
できるだけそういった状況が生まれないよう、回答がブレにくい項目を考えるのが難しかった部分です。
(湯浅)
また、生活者が採点結果を見た時に、採点の根拠がわかりやすいよう、具体的にどのような取り組みをしているのかを中小企業版では詳しく書いていただくようにしています。大手企業は元々情報を開示しているので根拠がわかりやすいのですが、中小企業は情報開示がないことも多いので。
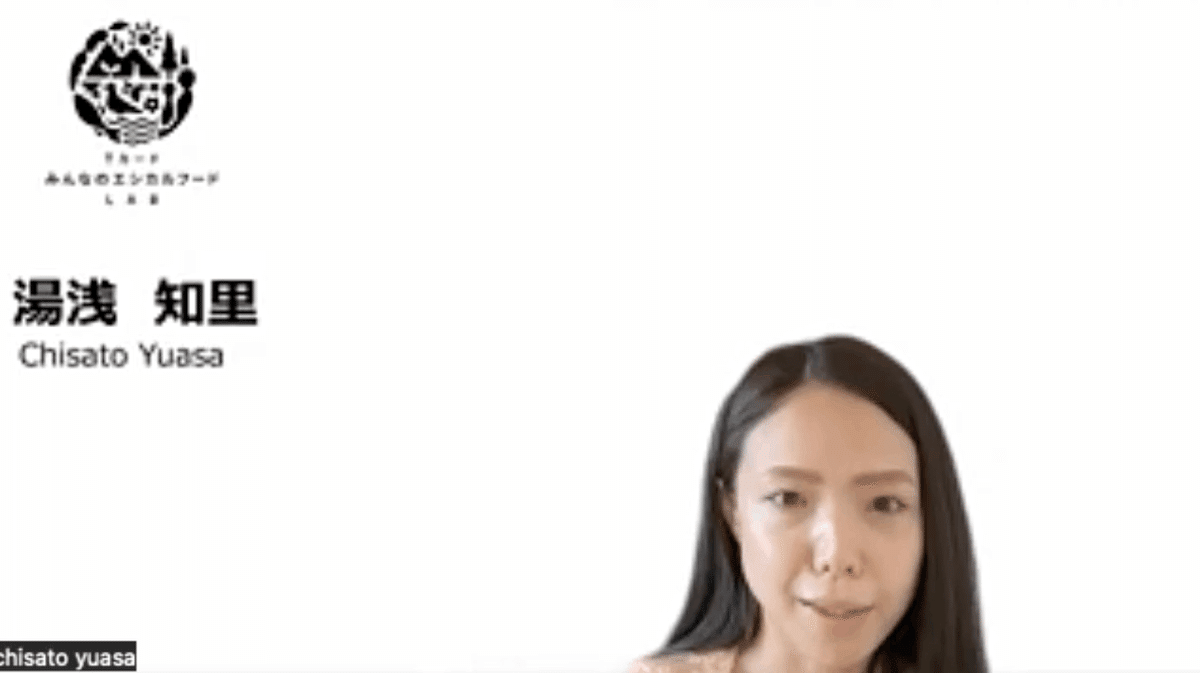
世界の動きがエシカルイシューにつながる
ー 基準をブラッシュアップしていくにあたり、社会の動きも注視されているのでしょうか?
(瀧田)
やはり、エシカルに関する動きは欧州が先行しているので、欧州で最も問題になっているエシカルイシューはウォッチしないといけないと思っています。
先日、「Ethical Consumer」のロブ・ハリソンさんが来日されたので、欧州でホットなエシカルトピックスを尋ねたところ、「気候変動は食と強くつながっている。食に生活者が向き合うことで、気候変動の問題に大きく貢献できる、という話が今はホットだ」とおっしゃっていました。
元々、世の中的にそのような認識はあると思いますが、これだけ地球の問題が逼迫しているので、よりクローズアップされているのかな、と思います。
それ以外にも、戦争の問題など、社会情勢がエシカルイシューに関わってくるので、注視する必要があります。
最低でも1年に1回は基準を見直すことになっていますが、それに加えて、社会的に大きなトピックスが生まれた場合は臨時で協議することになっています。社会の変化に合わせて、項目を追加したり、しきい値を見直したりしていく予定です。

多様な観点を基準に取り入れたい
ー 今後、基準をブラッシュアップしていく上で、新たに対話したいステークホルダーはいますか?
(瀧田)
環境NGOや、国際的な第三者認証機関と対話したいと思っています。俯瞰的かつ網羅的な情報収集をして、客観的に分析・判断を行っている団体ならではの意見がもらえることを期待しています。
また、ラボと同じような取り組みを行っている一般社団法人や、農水省、環境省といった関係省庁とも対話をしたいですね。
(湯浅)
個別の食品に特化した協会とも対話をしたいという話が出ています。たとえば、カカオの協会など。原材料に関する基準を考える際に、食品に関する専門知識を持つ団体と対話することは意義があると思います。
(瀧田)
「エシカル」って幅がとてつもなく広くて、ほとんど世界のすべてじゃないですか。エシカルフード基準をつくる上では、そこに「食品」という、原材料や製造方法が無数にあるものをかけ合わせていかないといけません。なので、やはりすべてを網羅的に知っている人はいなくて、そこに基準づくりの難しさを感じています。
今述べたような方々との対話を通じて、できるだけ多様な観点を取り入れることが、何よりも重要だと思っています。
・・・
■ Tカードみんなのエシカルフードラボ
■ 公式Twitterでは、「エシカルフード」に関する情報を発信中!
