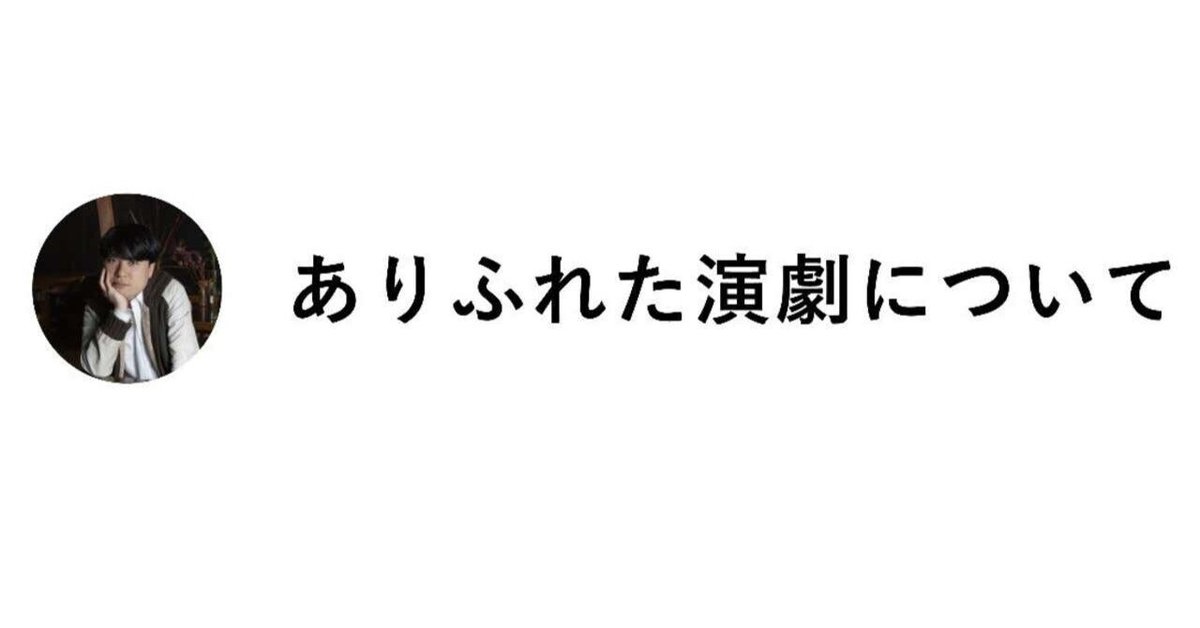
「ありふれた演劇について」26
2020年代も3年目を迎えて、いよいよ「21世紀的なもの」が本格的に議論され始めたのを感じる。「21世紀の○○とは?」というような問いかけを耳にすることは多くなった。いや、もちろんそういうトピック自体は以前からあったのだけど、その「21世紀的なもの」がまさに現在到来しているのだというリアリティはずいぶん強くなった。これまでの時代とは明らかに違うということが、様々な具体的な名詞(デジタル革命、GAFA、ポスト・ヒューマン、気候変動、等々……)と一緒に共有されて、議論の前提となった。共通の基盤を持ち、あらゆる領域を横断するような「21世紀的なもの」が立ち現れているという感じだ。
ことカルチャーの領域においては、デジタル化を前提とした消費行動がまさに「21世紀的な」カルチャーを生み出しているという話をよく聞く。音楽はサブスクで聴かれることを前提に制作され、映画は配信サービスで閲覧されやすいように、あるいはYouTubeを日常的に見ている人々に響くように作られるらしい。スピーカーからイヤホンへ、スクリーンからデバイスへといったハード面の変化も相まって、それらの要素は作品の長さや構成、(音質やCGの肌理といった)質感にも影響し、「20世紀的な」作品とは明らかに違うスタイルが誕生している。作り手と鑑賞者、あるいは鑑賞者同士のコミュニケーションの変化も含めれば、単に作品だけでなくカルチャー全体が「21世紀的な」ものに変貌しているとも言える。
私は演劇を制作しているので、どうしても「21世紀的な」演劇について考えざるを得ない。それはどういう演劇だろうか? 演劇は、古典的なフォームを守るのであれば、デジタルデバイスで鑑賞することはできない。あくまで実際の劇場で/眼の前にあるものを/肉眼で観る表現形態だ。もちろん、デジタルデバイスを用いて鑑賞する作品も存在する(し、自分でもそういうものを制作したことがある)が、そうでなければ「21世紀的な」演劇は不可能だ、と言ってしまうのはあまりに早計だろう。
もちろん、演劇はポップミュージックやメジャー映画のようには、「消費」との密接な関係を持ってはいない。演劇を観に行くのには、音楽を聴いたり映画を観たりするのに比べてはるかに高いモチベーションが要る。期間は短く、場所は限定され、チケット代も高い。「消費」させるとしても、かなりモチベーションの高い、世間一般から見ればごく一部のファン層をターゲットにすることになる。元々がそういうコンテンツだから、例えば「もっと手っ取り早くデジタルで済ませたい」という欲望を持つ者など、ほとんどいないだろう(もちろん、過去の演劇はアクセスできないので、デジタルアーカイブとして残ることには価値はある)。
デジタル化に相当するような試み自体には、大きく分けて2つの方向性がある。ひとつはデバイスに依存した、(かの、懐かしい)ZOOM演劇やVR演劇※などの、デジタル技術で劇場そのものを作る方法。もうひとつはプロジェクション・マッピングのように、劇場における視覚表現の中にデジタル技術を用いる方法だ。いずれも21世紀に発達した技術を用いており、SNSや偏在するカメラ、リアリティの拡張やオブジェクト指向論といった「21世紀的な」トピックとも関連する。しかしこれらの手法が演劇を決定的に「21世紀的な」ものに変貌させたのだとは、どうしても思えない。むしろ、これまで演劇の文脈で語られてきたことを、より目に見えやすい形で表現したもののように見える。
※VR演劇といったときに、例えば小泉明郎『縛られたプロメテウス』のような、用意された空間でVRゴーグルを装着して鑑賞する作品を想起される方もいるかもしれないが、こちらは実際の劇場での表現をVR技術を用いて拡張しているという意味では後者に近い。ここではclusterやVRChatなど、どこからでもアクセスできるサービスを用いて行う演劇をイメージしている。メタバース演劇と言ってもいいかもしれない。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
