
ジャズを軽く聴き始めたい人への軽い名盤紹介 28 山あり谷あり アート・ペッパー
こんにちは。
今回は、正に山あり谷ありの人生を送り、わずか57歳でこの世から去ってしまったアート・ペッパーの名盤をご紹介したいと思います。
山あり谷ありというのは、彼はヘロイン中毒者だったわけです。
そのため、何度も演奏することをやめたり、再開したりを続けた演奏家人生でもありました。
演奏家である時間よりも、ジャンキーとして矯正施設にお世話になっている時間の方が長いのではないかとさえ、思われていたようです。
また、演奏家として絶好調と思われる50年代にも施設への入退所はしばしばあり、彼自身、告白の中で「麻薬代欲しさに演奏していた」と言っているほどです。
60年代に入ってからは、完全に長期入院を余儀なくされ、演奏活動は一切出来なくなりました。
普通のミュージシャンなら、そこでジ・エンドとなるんですが、彼の凄いところは、70年代に完全復活したところにあります。
そして初めての日本公演を行い、その時の日本人の熱烈歓迎ぶりにいたく感動し、すっかり日本のファンになってしまいました。
それだけ彼のプレイには、日本人の心の琴線に触れる何物かがあったのだと、容易に想像がつきます。
よく言われるのは、アートのプレイは、復帰前と復帰後とのどちらの方が良いか?という問題です。
確かに鋭い切れ味や、ゾクリとするフレーズが多く聴けるのは復帰前です。
復帰後のプレイはどちらかといえばリラックスした、そして優しく、達観したようなメロディが多く聴かれます。
悪く言えば牙を抜かれた狼のよう。
しかし、どちらもアート・ペッパーの音楽です。そんな比較をする方がおかしいですよね。
私はどちらも好きですよ。後期の方が癒される感じはします。
さて、そろそろアルバムの紹介に移ります。
『Modern Art』 (1957年)

2 魅惑されて
3 君微笑めば
4 クール・バニー
5 ダイアンのジレンマ
6 サヴォイでストンプ
7 恋とは何でしょう
8 ブルース・アウト
パーソネル
アート・ペッパー(as)
ラス・フリーマン(p)
ベン・タッカー(b)
チャック・フローレス(ds)
これは最高傑作と呼べる作品だと思います。
CDによっては、ステレオミックスされた別テイクが入っていたり、(『Modern Art Complete Edition』)、曲順が入れ替わっていたり、色々あって混乱しますが、ここにある8曲が基本だと思います。
一曲目「Bulues in」から、いきなりやられます。バッキングはベースのみ。緩急を付けた抉り取るようなプレイ。ゾクリとします。
ラストの「Blues out」もそうです。同様にベースのみのバッキングで自由に掘り下げて深いメロディ。この二曲だけでもこのアルバムを聴く価値があります。
その他の有名スタンダード曲なども、スイスイと波乗りしながら、自然とメロディーが出てくるような感じ。そして鋭い切れ味。
まさにアート・ペッパーの真骨頂です。
「波乗りしながら」と書きましたが、ペッパーの傑作の一つに『サーフライド』という作品があります。ジャケットは最悪ですけど内容は素晴らしいものです。やはり、彼のプレイはサーフィンしているように感じます。
『The Return of Art Pepper』 (1956年)

2 Broadway
3 You Go to My Head
4 Angel Wings
5 Funny Blues
6 Five More
7 Minority
8 Patricia
9 Mambo de la Pinta
10 Walkin' Out Blues
11 Pepper Steak
12 You're Driving Me Crazy
13 Tenor Blooz
14 Yardbird Suite
15 Straight Life
パーソネル
Art Pepper - alto saxophone
Jack Sheldon - trumpet (tracks 1, 2, 4-7, 9 & 10)
Russ Freeman - piano
Leroy Vinnegar - bass
Shelly Manne - drums
2管クインテットによる作品です。この盤は、特別にペッパーの大傑作というわけではないのですが、私が好きな作品ですので挙げてしまいまいました。
どこが好きかというと、ウェストコーストの気心の触れたメンバーなのでしょうか、とてもリラックスした感じと、いつもの鋭い切れ味が同居しているような部分が好きだからです。
return of〜というからには、直前まで療養していたのでしょう。しかし、この人にはブランクのための不調というものがないのでしょうか? いつもの切れ味鋭い、波乗りペッパーがここにいます。
各メンバーも最上の演奏をしており、特にトランペットのジャック・シェルダンは、随所で良いプレイを聴かせてくれます。
『ART PEPPER + ELEVEN』(1960)
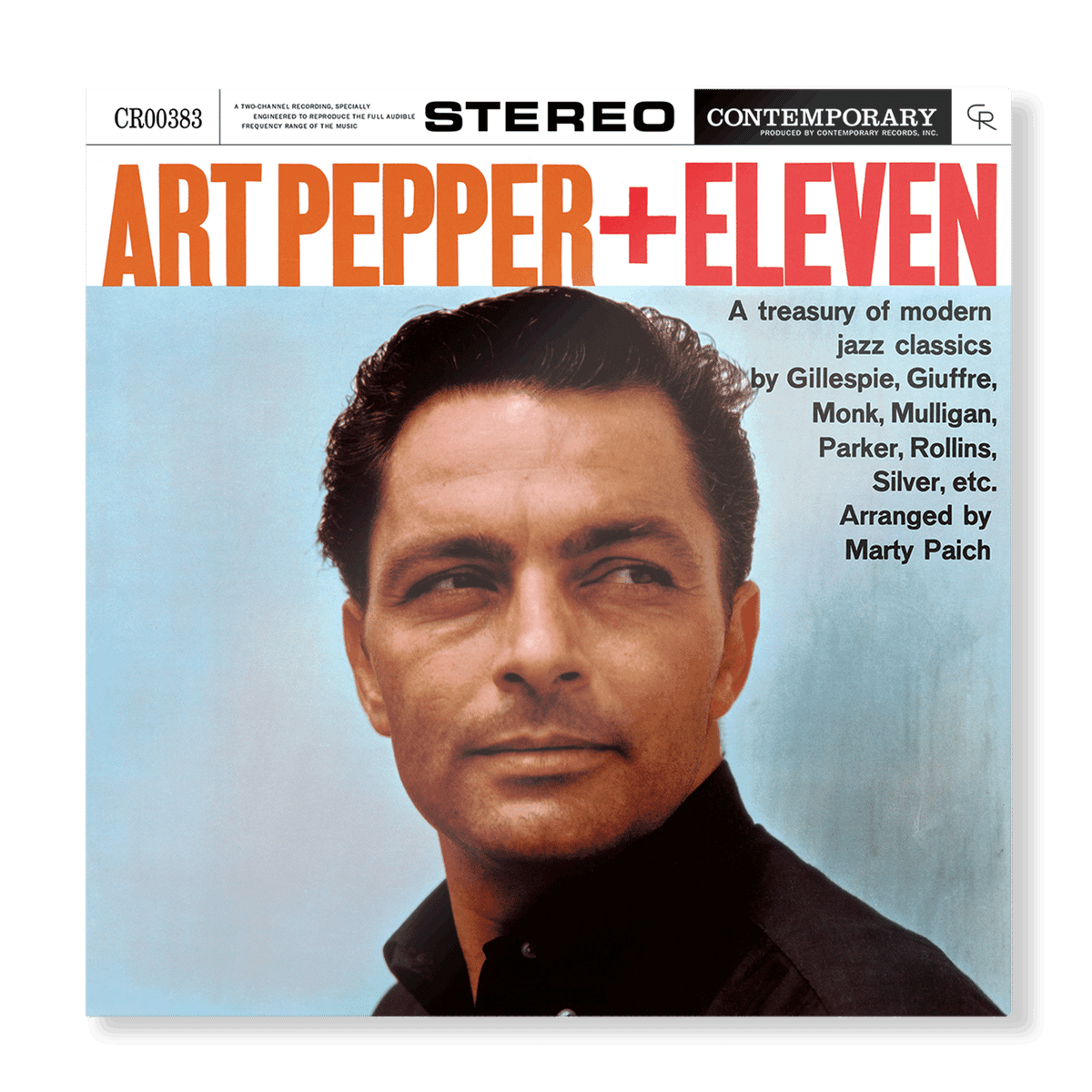
2 Groovin' High
3 Opus De Funk
4 Round Midnight
5 Four Brothers
6 Shaw Nuff
7 Bernie's Tune
8 Walkin' Shoes
9 Anthropology
10 Airegin
11 Walkin' (Original Take)
12 Walkin' (Alternate Take 1)
13 Walkin' (Alternate Take 2)
14 Donna Lee (Original Take)
15 Donna Lee (Alternate Take)
このアルバムは、ビッグバンドを従えたペッパーのリーダー作になります。
ジャケットの顔。イケメンですよね。当時で言うところの男前です。
しかし、目をよく見るとクスリでいっちゃっているような目をしています。
この後、数枚のレコードを吹きこんで長期療養に入るわけです。
このアルバムについては、マーティ・ペイチというピアニスト兼アレンジャーがいます。今で言うクインシー・ジョーンズみたいな人ですね。
そのマーティ・ペイチのアレンジによるアルバムになります。
ですので、このアルバムに魅力があるのはペイチの貢献も大きく関わってきます。しかし、ソリストに力がないことにはここまでの魅力あふれる名盤にはなりません。
このアルバムでもペッパーはスラリすらりとサーフィンをしているかのように、次々と、突き刺さってくるかのようなメロディーを紡ぎ出します。
このアルバムでは、いつものアルトサックスに加えて、クラリネットやテナーサックスによるよるプレイも聴くことが出来ます。
以上、アート・ペッパーの絶頂期を代表する三枚を挙げてみました。
実は、もう一枚、彼のキャリアを語る上では欠かせないアルバムがあります。
『Art Pepper Meets the Rhythm Section』というもので、当時のマイルス・デイビスのリズム隊とのセッションによる作品です。
彼の代表作のような扱われ方をしていますので、一聴の価値はあるでしょう。しかし私は、どうもこの盤は苦手なんです。
なぜかどの曲も、アドリブが全部同じに聴こえることと、ペッパーとリズムセクションを左右のトラックに完全に分離した録音の仕方がいまいち好きになれません。しかし代表作なので、一応は挙げておきます。

2 Red Pepper Blues
3 Imagination
4 Waltz Me Blues
5 Straight Life
6 Jazz Me Blues
7 Tin Tin Deo
8 Star Eyes
9 Birks Works
以上、アート・ペッパーの魅力を述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
少しでも興味を持っていただけると嬉しいです。
彼の復帰後の70年代の作品についても、機会があれば触れてみたいと思います。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
