
41【日本2024 Day 13:11月24日(日)縄文時代に触れた「歴史民俗資料館」@壬生町】
九州や関西と違って、そんなに古くから
人が住んでいたと言うイメージは関東に
なかったのですが、実は、栃木には多くの
土器や古墳などが存在し、その一部は
美術館などでも見ることができます。
なにしろ横浜出身で、20代からアメリカ移住
している私は、同じ関東でも栃木のことは
疎く、今回、「初めて!」のことがいっぱい!
.
.
お腹がいっぱいになって幸せ気分絶頂の
時に、落合さんが連れていてくださったのが
そんな有史以前の壬生を知ることのできる
壬生町町立歴史民族資料館!











こちらも学芸員の方
学芸係長の深津栄美さんと
学芸員の藤栄友里絵さん
が付いてくださって
詳しくご説明いただきました!
さっと何も知らずにみて歩くのとなんと
言う違いでしょう!
面白いエピソードや謂れなども紹介して
くださるので、一人で見て回るのとは全く
違う面白さがあります。


.
.
落合さんと一緒でさらに面白いのは、
資料館で働いている方達のことも詳しいので
「この展示は、◯◯さんのものです。」
と、学芸員さんたちの研究や好みの
対象の強さが展示に反映されているのを
ご存じで、その辺のエピソードも入ること。
.
.
縄文や弥生の後に、お武家さんの時代に
急に展示が飛ぶのはご愛嬌・・みたいな
感じでおっしゃいましたが、実は、
延々と1万年は続いた縄文時代!
弥生時代(紀元前300年〜紀元300年)の
600年や有史の歴史なんて「瞬間」な訳です。
なぜか小学校低〜中学年の頃に考古学者に
憧れて本を読み込んでいた自分をすっかり
忘れていましたが、目の前の
世界で2番目の規模の巨大な縄文土器
などを解説付きで見ているうちに40年以上
前の自分が蘇ってくるようでした。









.
.
栃木に有名な武将もいて、それぞれの
歴史がありと言うのも、今まではあまり
知らないでいました。












そもそも義務教育中に学校で習ったこと
以外、歴女ではないので、大して
知らなかったと言うのもあります。
古い歴史の中、多くのドラマがこの地で
あったんだと思うような展示物に接することで
自分の栃木への理解も進み、県外からの
観光客がこぞってくることのない場所
ならではの土地に根付くものに触れることが
できたことに感謝!
.
.



複数のアーティストの展示がされていた特別展
「壬生のサムライと日光ブランド
「聖地日光」をアートプロデュースした男」
では、色合いやタッチが好きなものがあり、
旅の後半に、訪れることが決まっている日光を
自分の目で見たら全く違う印象になるんだろうと
思いながら鑑賞。
(撮影禁止区域)
.
.
それぞれの目で見た「栃木」が、一つの
アートになって、他の人の目に触れることの
大事さも感じました。
先細りが心配される伝統工芸の世界のものは
もちろんです。
職人芸は絶えてしまえばそれまでなので
美術展だけではない形で後世に残って
いってもらいたいなぁと思いました。
.
.
学芸係長の深津栄美さん、
学芸員の藤栄友里絵さんから
ご案内の最後に写真を豊富に盛り込んだ本
「壬生のサムライと日光ブランド
「聖地日光」をアートプロデュースした男」
や、人気が出て手に入りにくいカード
「壬生城記念カード」
をプレゼントしていただきました。

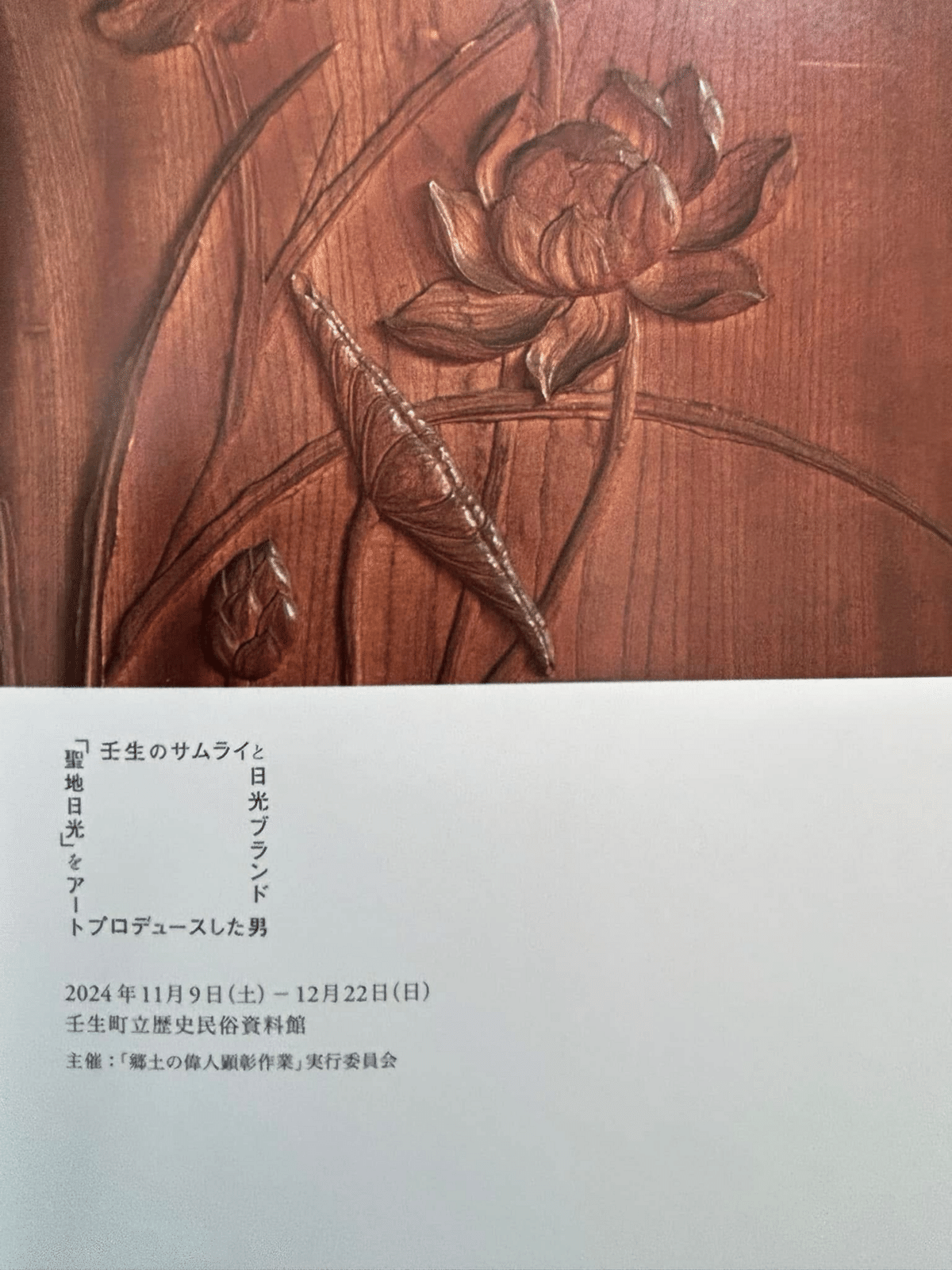



貴重なご案内の機会もどうもありがとうございました。


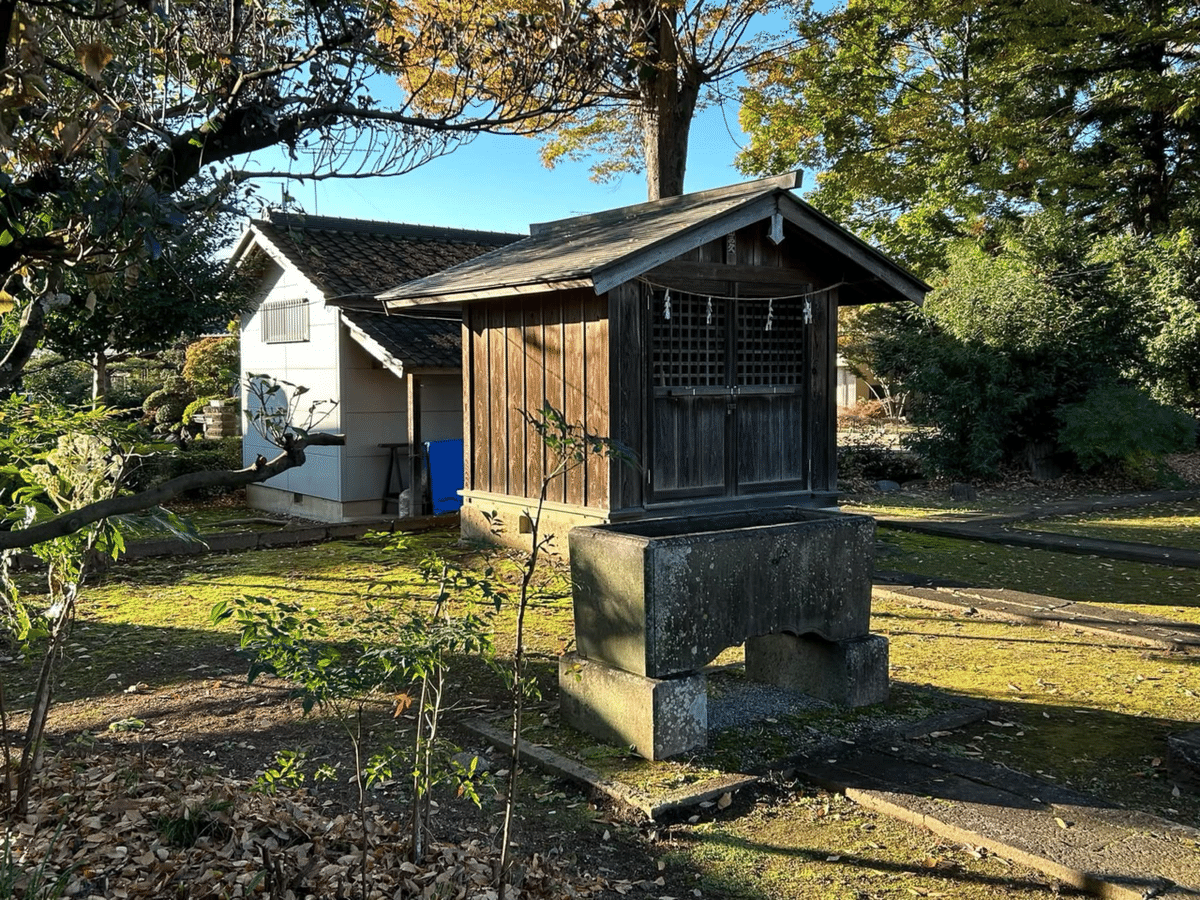


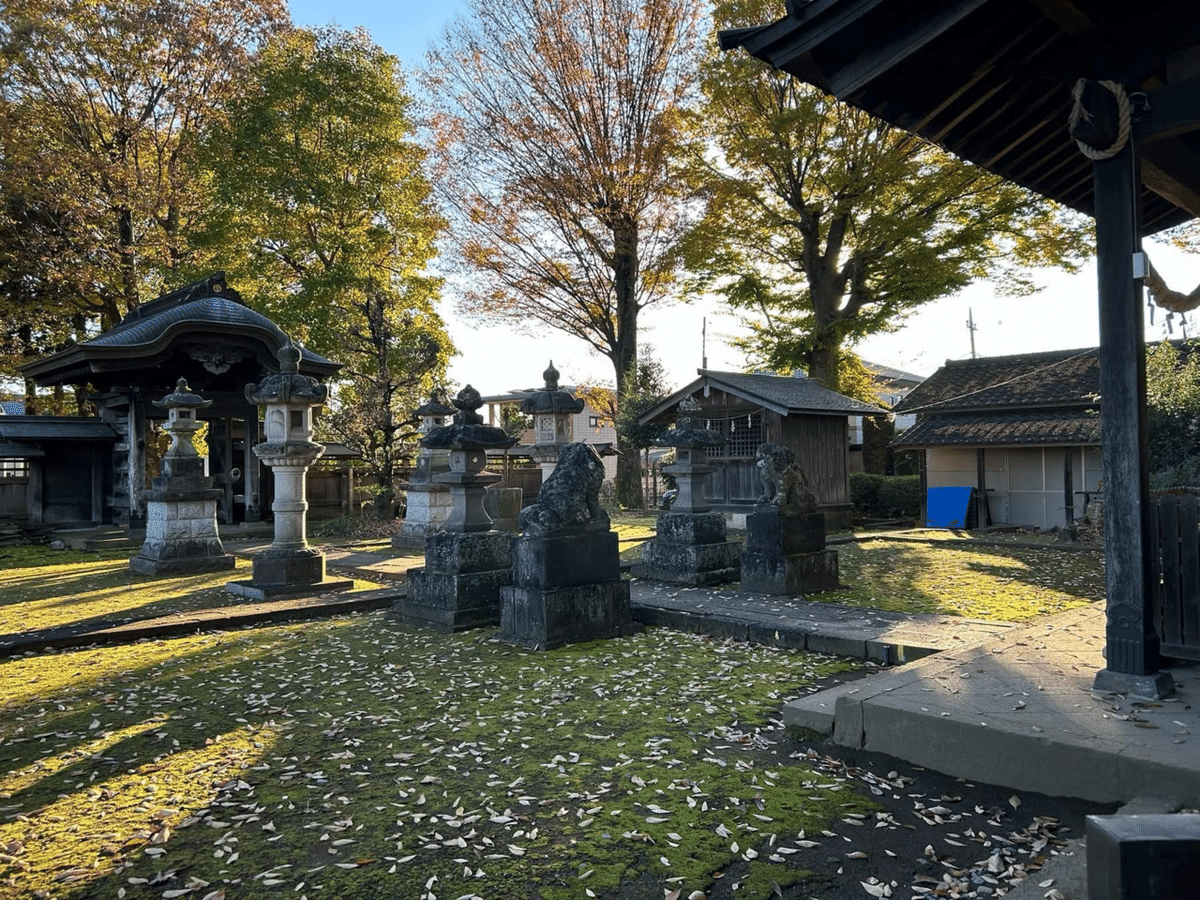






.
.
石室
落合さんのご案内で向かった先が
有史以前からの「石室」。
古墳の一部から発見された石室。






現代の技術や機械がない時代にどうやって
組んだのかと大きな岩や板で造られていて
いるものを見ると、いつも不思議に思います。
栃木県民以外はほとんど訪れたことが
ないかもしれないと思うこの場所に
実際入ってみて、何か、古代の力が
私に作用したかどうかはわかりませんが
そもそも力のある人のために作られた
古墳の一隅に21世紀になってアメリカ
から来て立っているのだと感慨深かったです!
紅葉樹の色付いた葉と穏やかな晩秋の
夕暮れの柔らかな日差しの中、
前を歩く3人の背中を見遣りながら、
幾重にも重なり始めた落ち葉を踏み
締めながら、滑って転ばないように
歩を進めながら車に戻りました。
✨ ✨ ✨ ✨ ✨
壬生町立歴史民俗資料館
〒321-0225 栃木県下都賀郡壬生町本丸1-8-33
【TEL/FAX】0282(82)8544
【開館時間】9:00〜17:00
【休館日】月曜日、祝日、年末年始(12/28~1/4)
※企画展期間中は祝日も開館
✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨
