
とっておきの「エモい」をあげる 【呼応する星たち】短編 一万字強
「呼応する星たち」あらすじ
「言わないでいたら、俺にメリットってなんかある?」
片思いしている佐野のシャーペンを盗んでしまった小春。
それを知った明希から、黙っているかわりに「カップルっぽいこと」をするように言われ――。
・ 小説内の文章、画像などの無断引用・転載禁止
・ 他の投稿サイトにも掲載しています
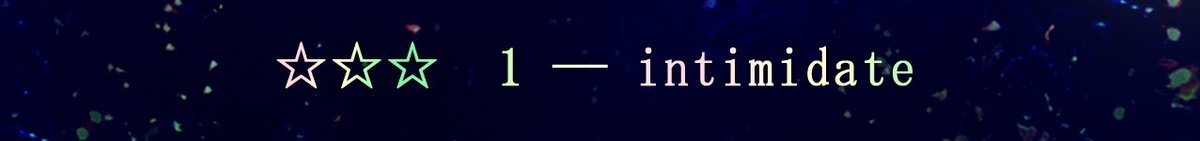
十七歳にして人生が終わった、と思った。
教室の扉が開いた瞬間、わたしの心臓は鷲掴みされた。
「だめじゃん、小春ちゃん。いくら好きだからって、人のもの盗んじゃ」
そう咎められ、咄嗟にポケットに隠した佐野のシャープペンシルは、汗でぬるぬると滑った。
教室のなかは凍えるほど寒いというのに、身体じゅうの汗が止まらない。グラウンドから聞こえていたはずの野球部のけたたましい掛け声が、途端に聞こえなくなった。
「それって窃盗だよ? 立派な犯罪」
「ま、待って。誤解しないで。これはさっき床に落ちてるのを見つけて、佐野に渡すつもりで」
「いまさ、小春ちゃんのリュックから出してたよね。
シャーペンなくしたけど見てない? って佐野が訊いたときは、見てないってはっきり言ってたのに」
嘘つきだなあ、と明希は楽しそうに笑った。
そのとおりだった。
わたしは佐野のシャーペンを盗んだ。
正確には、教室に落ちていた佐野のシャーペンを見つけて拾って、本人に返さなかった。盗んだというのは少し違う気もするけれど、それでも盗んだうちに入る。
どうしてリュックから出して、うっとりと眺めてしまったのだろう。
誰もいない放課後の教室で、完全に油断していた。
そもそも盗んだりなんてしなければ――。
わたしを白い目で見る佐野が瞼に浮かび、血の気がさあっと引いた。
音を増す鼓動が、胸を突き破る。
「おっ、お願い。言わないで。お願いだから、誰にも言わないで!」
懇願しながら、わたしは明希に詰め寄っていた。
一歩、二歩。
わたしと明希の間には、もう距離がない。
「どうしようかな」
教室でいつもヘラヘラとお茶らけている明希の目が、鋭くわたしを見下ろした。盗人に向けるには正しい眼差し。
正し過ぎて、痛い。
「お願い……。秘密にして」
声も膝も、すべてが震えていた。
それでも必死に絞り出した願いを、明希は容赦なくばっさりと切り捨てた。
「言わないでいたら、俺にメリットってなんかある?」
メリット。確かに明希にメリットは、なにもない。
だけど、わたしと明希は友達じゃなかっただろうか。
一年生から同じクラスで、安藤と石井で席が近いこともあって、軽くしゃべったり、授業ではいっしょにグループワークしたことも何度かあった。クラスでカラオケに行けば、同じバンドが好きで少し盛り上がったりもした。
少なくとも、名前で呼び合うくらいには親しいつもりだった。
メリットがないから、なんて理由で願いを聞き入れてもらえないとは思っていなかった。
「ここはさ、俺のお願いもきいてよ。そしたらフェアじゃん」
「お願いって……。どんな……」
「俺さ、まだあっちの経験ないんだよね」
ぎょっとして後ずさった。踵のぶつかった机がガタガタと音を立て、恐怖を揺さぶる。
「あ、もしかして小春ちゃんも経験なかった? そうだよね、シャーペン盗むくらいだもんね」
経験どころか、彼氏がいたこともなければ、告白したことも、されたこともなかった。
教科書の端から、ちらちらと佐野の横顔を盗み見る――それが私の日常だった。
佐野から「おはよう」と言われたら頬が染まり、一言二言、言葉を交わせば、一日中ふわふわとしていられた。
それで満足していたはずなのに、クリスマスが近いせいか、親友の由奈に彼氏が出来たせいか、わたしのなかでもう一人のわたしが囁いた。
どうせ告白もなにも出来ないで、ただのクラスメイトで終わるんだから、ほんの思い出にシャーペンくらい――。
センチメンタルに酔った結果がこれだ。
最低な思い出が出来上がってしまった。
「経験ない同士って、どうなんだろうな。やっぱり難しいのかな。小春ちゃんはどう思う?」
まさか明希は、わたしにそういうことを望む気なのか。
ごくりと唾を飲み、絶望を飲み下したかったけれど胸に詰まった。
ミルクティー色の前髪から覗く明希の目が、すっと細くなる。
「なんで顔、真っ赤にしてんの。経験って、彼氏がいた経験って意味なんだけど。違うこと想像してたでしょ。小春ちゃん、泥棒なうえにむっつりか。すごいな。佐野に教えてあげよ」
「や、やめてっ」
「なんで? うけると思うけど」
ふるふると首を横に振ると、明希の目がますます細くなった。
恐怖を煽る、三日月の目。
仄暗い湿った教室で、明希は無邪気な子どものように言った。
「ちょっとつき合ってよ。黙っててあげるからさ」
☆☆☆
罪を犯した罪人は、罰を受けなければならない。
つまりシャーペンを盗んだわたしは罰を受けなければならない――けれど、これはいったいどういう罰だろう。
「小春ちゃん、ほんとうにコーヒーだけでいいの?」
たっぷりの油と砂糖の香り。きゃあきゃあ騒ぐ学生たち。
わたしのテンションとはひどく対照的に、ドーナツショップは賑わっていた。
教室で見せた表情をすっかり消して、何事もなかったように明希がドーナツを頬張るので、わたしもコーヒーに口をつけてみる。コーヒーはいつもよりやけに苦々しく、舌に残った。
「俺のドーナツ、半分食いなよ」
「ううん。いい」
「いつも教室で菓子いっぱい食ってるじゃん。ほら、遠慮すんなよ」
明希はチョコレートのかかったシンプルなドーナツを半分に割った。チョコレートのたっぷりかかった方をわたしにくれたのは、やさしさだろうか。
ちびちびとドーナツをかじると、舌に残っていた苦味が薄れ、口のなかの水分をぜんぶ持っていかれた。ふたたびコーヒーに口をつける。
「……ノート」
ふいに、明希が呟いた。
「ノート?」
「俺の英語のノート渡すから、宿題の答え書いてきてよ。で、明日の授業までにノート返して」
「宿題って……。よくわからないんだけど、わたしより明希の方が英語出来るよね?
いや、英語だけじゃなくて全般的に、だけど」
明希はいつだってクラスで上位の成績だった。
誰よりも明るく染めた髪に、ゆるく着崩した制服。
そうは見えないけれど、じつはけっこう真面目な奴、というのが明希の印象だった。
「そうだけどさ。あ、小春ちゃんも俺になんか宿題やらせていいよ。数学でも化学でも、なんでも」
どうしてわたしに英語の宿題をやらせて、自分も宿題を引き受けるのだろう。
それこそ明希にメリットはない。むしろデメリットだ。
「やっぱりよくわからないんだけど、宿題やってくれば黙っててくれるってこと?」
「うん。あと明日の放課後、どっか行こ」
「えっと、それは……なんで?」
訊ねると、明希は大きくため息をついた。
わかってないなあ、と言うように大袈裟に肩を竦める。
「言ったじゃん。経験ないって。俺さ、そういう高校生カップルっぽいことをしてみたいんだよね。放課後にどっか遊びに行ったり、いまみたいにお茶したり。だけどほら、彼女いないし」
それなら彼女をつくればいいじゃないか。
明希は見た目は悪くないし、女の子と話すのだって慣れているように見える。どこまで本気かわからないけれど、明希のことを「けっこういいよね」と言う子は何人かいる。
明希なら彼女をつくることは、きっと難しくない。
「春ちゃんだってそういうの憧れてるんじゃない? 漫画とかドラマの話して、尊いとかエモいとか、女子たちみんなできゃーきゃー騒いでるじゃん」
「えっ……」
「いいよな、ああいうの。嫌みで言ってるんじゃなくてさ、なんかすげえ楽しそうで、いいなって思うよ」
そこまで大音量で騒いでるつもりはなかったけれど、明希に聞こえているということは、佐野にも聞こえているかもしれない。
どうしよう。ミーハーな女だと思われていたら。
明希は楽しそうでいいなんて言うけれど、佐野がどう思うかはわからない。
落ち込んでいると、明希はとつぜん噴き出した。わたしの憂鬱を蹴飛ばすように、大きな口で笑う。
「ちょっと、なんで急に笑ってるの?」
「だって小春ちゃん、顔に出過ぎ。大丈夫、佐野はいつもぼーっとしてるから。そういうの気にしてないって」
「そうかな……」
「平気だって。楽しいことがあるのは、いいことじゃん」
それなら明希は、いいことだらけだ。
明希はいつだって楽しそうに笑ってる。箸が転がっても、体育祭でリレーのアンカーを押しつけられても、購買でパンが売り切れてなにも買えなくても、とにかく楽しそうに笑ってる。
もはや明希のデフォルトは、笑顔なんじゃないかと思う。
「相手が佐野じゃなくて悪いけど、予行練習ってことでさ。させてよ、カップルっぽいこと。それに、ぶっつけ本番が好きな奴ってこわくない? 緊張で失敗しそうじゃん。大丈夫大丈夫。さすがにチュウとかしないから。ちょっと彼氏っぽいこと、してみたいだけだから」
チュウと言われ、反射的に目の前の唇に目がいった。
ぽってりとして、冬だというのに血色がいい。それに、やわらかそう――なんて考えていると、ピンク色の唇はにっこり微笑んだ。
急いで視線を逸らし、熱くなる耳朶を感じながら、わたしは必死に考える。
いま一番大事なのは、黙っていてもらうこと。
すごく親しい男友達と放課後を一緒に過ごしたりするだけ、と考えてみれば、問題はない気がする。それに明希に宿題をやってもらえるという、メリットだってある。
「それって、いつまでやるの?」
「さあて、そろそろ帰るか」
明希はわたしの言葉を遮るように言い、「小春ちゃんちまで送るね」と続けた。遠回りさせるからいいと断っても、「これも彼氏っぽいことだから」と返された。
ずっと車道側を歩き、満員電車で潰されそうなわたしをガードする明希は確かに彼氏っぽくて、不覚にもわたしの胸はほのかに甘く締めつけられてしまった。

いつもより早く登校して、明希の机にノートを押し込んだ。
まだ眠い目を擦り、自分の机に突っ伏す。誰もいない教室はなんの乱れもなくて、ひんやりしている。
女子高生も二年目となると新鮮味はない。
一年生のころは漫画やドラマのような恋愛が、ある日とつぜん自分にもやってくるんじゃないか、と期待した。
だけど現実は、イケてる同級生となんらかのハプニングで同居する羽目にはならないし、不良な先輩に「おもしれえ女」と顎をクイッと持ち上げられることもなかった。
現実には起きないことだから。だから、そういう物語に需要があるのだろう。
尊いもエモいも、現実世界では厳しい。それを得られるのは一部のカースト上位者だけ。
昨日の帰り道はちょっとエモかったけど、あれは予行練習だからカウント出来ない。
「安藤って、来るの早いんだな」
声のする方を見ると、佐野が爽やかに微笑んでいた。急いで身体を起こして、おはよう、と返す。
「今日も寒いな。早く冬休みになってほしい」
佐野はそう言いながらポケットに手を入れ、缶コーヒーを出した。わたしの方へ、すっと近づく。
「微糖のコーヒー、飲める?」
「えっ、なんで。どうしてっ」
とつぜんの問いに、声が裏返った。
佐野のきりりとした眉が、おどけるように下がる。
「これ、間違えて買っちゃったんだ。俺、コーヒーって苦手で。よかったら、もらってくれないかな」
「あ、そしたらお金……」
「いいよ。いらない」
缶コーヒーを差し出し、佐野がふたたび微笑む。わたしは火照った顔を隠すように、うつむいてお礼を言った。
「おはよ。佐野、小春ちゃん」
ぱっと顔を上げると、日差しに髪を透かせた明希がいた。
なんというバッドタイミング。
シャーペンのことは秘密にすると約束してくれたけれど、それでもひやひやしてしまう。
そんなわたしを知ってか知らずか、明希はニッと微笑み、佐野へ近づく。
「なあ、佐野。昨日なくしたって言ってたシャーペン、見つかった?」
「いや、見つからない。あちこち見たんだけどさ」
「へえ。どこにいったんだろうな」
ちらりとわたしの方を見て、明希は目を細めた。電車のなかでほのかにときめいてしまった昨日の自分をぶん殴りたい。
「まあ、安物だったからいいんだけど。俺、ちょっと自販機行ってくるわ」
そう言って佐野が教室を出ると、明希はぺたんこのリュックを開いた。
「ほい。数学のノート。小春ちゃんの字、相変わらずまん丸いのな。ダンゴ虫みたい」
「……ありがとう」
差し出されたノートに手をのばす。わずかに触れる指先。
自分のノートが明希のリュックから出てくるのはなんだか奇妙で、むずむずした。
「明希の英語のノート、机に入れておいた。たぶん間違ってない、と思う」
「サンキュ。お礼にこれあげる」
わたしよりひと回りは大きい手が差し出したのは、無糖の缶コーヒーだった。ずいぶんと温かい。
「小春ちゃんは無糖だろ」
机に置いてあった微糖コーヒーのプルタブを引き、明希は一気に飲み干した。
一瞬のことで、わたしは止めることも、文句も言うことも出来ず、ただ目を見開いていた。
「放課後、昨日のドーナツ屋のとこで待ってるから」
☆☆★
放課後。買い物に行こうと誘う由奈にごめんと断り、わたしは約束どおりドーナツ屋に向かった。
相手は明希で、これは予行練習。
それでも放課後に男の子と待ち合わせるのははじめてのことで、心臓はそわそわと騒がしくなった。
ドーナツ屋の前で明希の背中を見つける。
近づきながら呼びかけても、音楽でも聴いているのか、明希は反応しなかった。
キャメルのダッフルコートが髪に合ってるな、と思いながら、軽く肩を叩いた。
「ごめん、明希。待たせたかな」
振り向いた明希は少し驚いた顔をしてから、ゆるい笑顔を浮かべた。
「すごい。彼女っぽい」
呼びかけただけなのにオーバーな反応。
カップルみたいなことがしたい、という明希の想いは、わたしが思っていたより強いのかもしれない。
「ほい。俺の英語のノート。小春ちゃんのノートもちょうだい」
明希はノートを差し出した。
「え、今日も交換するの?」
「うん」
ノートを受け取り、数学のノートを差し出した。ふと、思い出す。
「あのさ。数学の宿題、答えが完璧なのは感謝してるけど、あの落書きはなに? あの変な、くまみたいな犬みたいな猫みたいなのは」
明希はわたしのノートにイラストを描いていた。頼りない、へろへろした動物らしきイラスト。
「あれは、くまぬちゃん」
「くまぬちゃん? そんなキャラいるんだ。知らなかった。流行ってるの?」
「ううん。世間の人は知らない。俺のオリジナルキャラだから。かわいいでしょ」
ウケを狙うわけでもなく、さらっと言われ、思わず噴き出てしまった。
数学の回答よりも大きなスペースを使って描かれたそれは、どう見たってかわいくはなかった。
「ところで小春ちゃんって、映画は好き?」
「好きだよ」
「じゃあ、映画行こ。観たいやつある?」
ごく自然に。さも当然のように。
歩き出した明希の手が、わたしの手を握る。
「ちょっと、これは……」
「この辺ならうちの学校の奴いないよ。ほら、寒いしさ」
寒いと言うわりに、明希の手は熱っぽかった。さほど小さくもないわたしの手が、すっぽりと熱で包まれる。
やっぱり、男の子なんだな。
明希の顔はわりと中性的だけど、身体はこんなにも違う。靴だって大きくて重たそうで、中で小動物が暮らせそう。
「小春ちゃんはポップコーンはしょっぱい派? 甘い派?」
「ハーフアンドハーフ派」
「欲張りだなあ」
へらへら笑う明希の横顔をよく見ると、耳が赤かった。
気のせいかな、と考えていると、今度は大きな手のひらが汗ばみはじめたことに気づいた。
困った。こっちまでつられて汗ばんでしまう。
「なんかさ、最近すごく暗くなるよね。星がきれいに見えるからいいんだけどさっ」
つい、早口に告げてしまった。
緊張がありありと表に出てしまう自分は、確かに明希の言うとおり予行練習が必要かもしれない。
「今日も帰り、送ってくから。小春ちゃんちまで」
「いいよ。そういう意味で言ったんじゃないよ」
「この時期って酔っ払いも多いじゃん。だからさ」
そんくらい、させてよ。
陽気なクリスマスソングが流れるなか、かさついた声でちいさく呟いた明希の耳は、やっぱり赤かった。

映画の翌日も早く登校して、ノートを交換した。
ノートには、またもやくまぬちゃんがでかでかと描かれていた。やっぱりかわいくない。
『映画おもしろかった! 次は水族館 or 動物園(行きたい方に丸つけて)』
くまぬちゃんの口から奇妙にのびる吹き出しに、子どものような字で書かれたメッセージ。
ふふっと笑い、わたしは水族館に丸をつけた。
放課後はまたドーナツ屋の前で待ち合わせ、近くの公園のベンチに並んで座った。錆びたブランコがキィキィと乾いた音を立てる。
明希いわく、「公園のベンチってカップルぽい」のだそうだ。
「昨日さ、親になんか言われなかった? 帰り遅い、とか」
「ぜんぜん。うち、けっこうゆるいから」
「そっか」
「明希こそどうだったの? 自分ちに着いたの、けっこう遅い時間だったでしょ」
「平気平気。ぜんぜん平気」
「そう? 映画、つき合わせちゃってごめんね。あの映画、明希の好みじゃなかったよね」
映画は少女漫画が原作の胸きゅん必至ラブストーリーだった。
冴えない主人公がひょんなことから学校一かっこいい先輩と親しくなり、恋のライバルが登場したり、ふたりの気持ちがすれ違ったりを乗り越え、めでたくカップルになる――という王道物語。
「なんで謝るの? 俺、おもしろかったってノートに書いたじゃん」
「でも、明希は少女漫画とか興味ないでしょ」
「確かに読んだことはないけど。あ、今度貸してよ。小春ちゃんのおすすめ少女漫画」
「それ、本気で言ってる?」
「本気。だめ? 絶対に汚したり、折り目つけたりしないから」
だめではないけれど、「こういう恋愛に憧れてる」と明希に明かすようで恥ずかしい。
しどろもどろしていると、明希が口を開いた。
「とりあえずさ。つき合わせたとか、ごめんとか言うの、もうなし。俺、そういうの好きくない」
「え……」
「もう言わないでよ。そういうの」
わずかに風が吹き、明希からやわらかな柔軟剤の香りがした。
ね? と後押しする明希に、わたしは頷く。
「まあ、そもそも俺が小春ちゃんを脅してつき合わせてるんだよな」
明希は視線を落とし、ごめん、と低い声で謝った。
その姿にこちらの調子が狂う。
「で、でもっ。映画、楽しかったよ? ポップコーンは売り切れだったけど、チュロスおいしかったし。いまだって、なんか新鮮だなって思ってるよ? すごくいい予行練習じゃないかな」
焦って口走ると、明希は顔を上げた。
「そうだな。いい予行練習だな。次はポップコーン、ぜったい食べような」
「……つぎ」
「うん。次」
明希はへらっと笑い、口からは真っ白な八重歯が覗いた。
今日も家まで送ってくれたので、そのまま外で待ってもらい、わたしは急いでエコバッグに漫画を詰め込んで明希に渡した。
おすすめを絞るのは難しくて、エコバッグははち切れそうだった。
「ちょっと減らす?」と訊くと、「まさか。ぜんぶ読む」と明希はうれしそうに笑った。
テディベア柄のエコバッグをしっかりと抱き抱えて帰っていく明希は、きっと彼女が出来たら大事にするだろうな、とわたしは思った。
次の日のノートには、くまぬちゃんの吹き出しに『少女漫画おもしろいな! これがエモいってやつか。水族館、明後日はどう?』と書かれていた。
その下には箇条書きで漫画ごとの感想がびっしり書かれていたので、授業そっちのけでわたしは見入った。
わたしの不動のナンバーワン少女漫画は『エモエモのエモ』と賞賛されていた。
今日も家まで送ってくれたので、そのまま外で待ってもらい、わたしは急いでエコバッグに漫画を詰め込んで明希に渡した。
おすすめを絞るのは難しくて、エコバッグははち切れそうだった。
「ちょっと減らす?」と訊くと、「まさか。ぜんぶ読む」と明希は笑った。
テディベア柄のエコバッグをしっかりと抱えて帰っていく明希は、きっと彼女が出来たら大事にするだろうな、とわたしは思った。
次の日のノートには、くまぬちゃんの吹き出しに『少女漫画おもしろいな! これがエモいってやつか。水族館、明後日はどう?』と書かれていた。
その下には箇条書きで漫画ごとの感想がびっしり書かれていたので、授業そっちのけでわたしは見入った。
わたしの不動のナンバーワン少女漫画は『エモエモのエモ』と賞賛されていた。

――クリスマスイブ、会ってくれない?
水族館の帰り道、明希はかしこまった口調で言った。
微細に震える睫毛に、こわばった表情。
不自然な明希に、わたしもまた不自然な口ぶりで「い、いいよ」と返した。
経験ない同士のわたしたちには、まだまだ予行練習は必要のようだ。
慣れたことといえば、くまぬちゃんだ。
毎日見ているうちに、少しかわいく見えてきた。奇妙だけど、ちょっと愛らしい。
慣れとはおそろしいものだ。
ノートも時間も、いまやすっかりわたしは明希と共有している。
★★★
待ち合わせの十五分前に駅につくと、明希はもうそこにいた。
日曜日ということもあってか、駅前はけっこうな混雑だった。それでもすぐに明希を見つけられたのは、寒空の下でひかる髪色のせいか、それとも――。
「明希、お待たせ」
「メリクリ、小春ちゃん」
はじめて見た明希の私服は、意外にもモノトーンでまとめられていた。
ダッフルコート姿を見慣れていたせいか、レザージャケットを着た明希はいつもよりずっと大人びて見える。
シャープな顎のラインだとか、なめらかに動く喉ぼとけだとか、今日はやたらと細部が目につく。
「小春ちゃんの服、かわいいね。お星さまみたい」
「あ、ありがとう……」
真冬の空に星を散りばめたようなワンピースはお気に入りで、着るのがもったいなくてずっとクローゼットで眠っていた。
わたしにはかわい過ぎる気がしたのも、着れない理由だった。
だけど明希が「プレゼントはまじでいらないから、めいっぱいかわいくしてきて」と言ったので、勇気を出して袖を通した。
勇気、出してよかったな。
コーディネートに合わせて買ったリップから、さくらんぼがほのかに香る。
「じゃあ、行きましょか」
そう言って差し出された手を、わたしはきゅっと握った。
明希の目がまん丸くなる。
「すごいじゃん。小春ちゃんがこうやって握ってくれたの、はじめて」
「これは……。なんていうか、条件反射っていうか、その」
ごにょごにょ言っていると、まん丸だった明希の目がそっと微笑んだ。
「これならもう大丈夫だね」
「大丈夫って?」
「いつ本番のデートがあっても、大丈夫ってこと」
大丈夫。
安心するはずの言葉に、なぜか痛みが走る。
紙で切れた指先のように、見えない傷口からじわっと赤が滲む。
「動物園なんて、俺いつぶりだろう」
「ね。わたしもすごいひさしぶり。カワウソいるかな」
「いるいる。ユーラシアカワウソとコツメカワウソが」
「よく知ってるね。明希って、そんなに動物好きだったんだ?」
「あ、うん。まあね」
もしかして、調べてきたのだろうか。
考えていると、目の前はもう動物園のゲートだった。
★★★
閉園時間いっぱいまで歩き回って空を仰ぐと、星たちが瞬いていた。
いつもより早い時間から輝く星たちは、今日がクリスマスイブだと知っているのかもしれない。
ゲートを出て駅へ向かう人たちは皆、うれしそうに「疲れた」と口にしている。
「似てたな、プレーリードッグ」
「似てたって、なにに?」
「小春ちゃん、プレーリードッグに似てるって言われない?」
「えー? はじめて言われた」
笑って答えたものの、内心は穏やかではなかった。
プレーリードッグの柵の前で、明希はかわいいかわいいと呆れるくらいに連呼して、なかなか離れなかった。
ぐるりと動物園を一周したあとに、「もう一度見たい」とまで言った。
深い意味はないとわかっていても、春の海のように胸が鳴る。
「ほい」
駅前で信号待ちをしていると、明希はとつぜん真っ白な封筒を差し出した。
「え、なに?」
「小春ちゃんにクリスマスプレゼント」
「プレゼントは、なしって……。わたし、本当に用意してなかったよ。ごめん、どうしよう」
「ストップ」
「あ、ごめんじゃなくて……。ありがとう」
でも、と言いかけると同時に、信号が青に変わった。
「それ、すぐに開けて」
そう言って、星よりも明るい笑顔を一瞬だけ向けて、明希は駆け出した。
人波をすり抜け、そのまま一直線に駅の改札のなかまで通り抜けていく。
缶コーヒーを飲まれてしまったときのように、わたしはまたなにも出来ずに固まっていた。
「……どういうこと?」
思わず声に出していた。隣にいたカップルが、不審そうにわたしを見る。
その視線に耐えられず、振り切るように封筒を開いた。
封筒のなかには、手のひらに収まるほどの紙片。
『ロッカーご利用証明書』と印字されている。
もしかして。
わたしは急いで証明書に印字されたロッカーに向かった。
明希がエモエモのエモ、と評した漫画。
それは主人公とその幼なじみとの、友達以上、恋人未満の関係を描いた物語だった。
ある日、主人公の下駄箱には差出人のわからない、一通の封筒が入っていた。
封筒のなかには『掃除用具入れ』と書かれた、メモ帳の切れ端。
その手書き文字から、主人公は幼なじみから贈られたものだとすぐに気がつく。
わけがわからないまま掃除用具入れを開けた主人公は、その隅に封筒を見つける。なかには『机のなか』と書かれたメモが入っていた。
主人公が机のなかに手を入れれば、やはりまたメモの入った封筒があった。今度は『図書館のAの棚』と書かれていた。
そんなことを繰り返し、巡り巡って体育館の裏へ行くと、そこには幼なじみの男の子がいた。
ずっとずっと、好きだった。
飾りのない、まっすぐな告白。
主人公は封筒を握りしめ、驚きとよろこびの涙を流した。
由奈は「普通に告白したらいいのに、なんでたくさん封筒を開けなきゃいけないの? 資源の無駄じゃない?」と言ったけれど、わたしにはむしろそれがよかった。
主人公は封筒は開けるたび、胸を高鳴らせたに違いない。
いまのわたしのように。
息を切らしてロッカーを開けると、なかにはぽつんと封筒があった。
封を開ければ、また同じようにロッカーご利用証明書の紙片が入っていた。
わたしは次のロッカーへと急ぐ。
明希は。
明希は、待ち合わせよりずっと早く来て、準備してくれたのだろうか。
鼻先が、つんと痺れる。
二つ目のロッカーは、駅から歩いてすぐの路地にあった。
封筒を取り出し、逸る指で利用証明書の紙片を出すと、くまぬちゃんの描かれた付箋がついていた。
ぐにゃぐにゃした吹き出しのなかの文字に、視線を走らせる。
『金がないから次でラスト。ごめん。でも、ちょっとエモいだろ?』
じゅうぶんだよ。
胸のうちで呟き、わたしは最後のロッカーへと向かう。
駅の通路脇にあるロッカー。明希はそこで待っているのだろうか。
それともロッカーを開けると同時に、どこからか出てくるのだろうか。
想像をふくらませ、駅へ向かう。
口元がゆるみ、足早になる。
だけど、ロッカーの前にいたのは
「佐野?」
戸惑いのまざった笑みを浮かべた佐野は、メリクリと言った。
わたしも同じようにメリクリと返し、二人で首を傾げる。
「なんで佐野がここに?」
「明希から呼び出されて。安藤は?」
「わたしはここのロッカーを開けるように、明希から指示をもらって」
「なんだそれ? 意味わからないな」
佐野が笑うので、わたしも同じように笑った。
なぜだか胸には不安が押し寄せてきた。
「それにしても、寒いな。安藤、平気?」
「うん。平気」
「とりあえず、ロッカー開けてみるか」
「え……」
「こうしてここにいたって、寒いしさ。その紙にロッカーの暗証番号が書いてあるの? 貸して」
わたしの手から紙片を取った佐野が、暗証番号を押していく。
やめて。開けないで。
胸騒ぎを覚え、声を絞り出す。
「や、やめよう。開けないでいいよっ」
わたしの言葉を覆うようにガチャンを音を立て、鍵は解除された。
佐野の手がロッカーの扉を引く。
赤と白。きらきら瞬くちいさなひかりが、魔法のように宙を舞った。
ロッカーからあふれ出したのは、無数の真っ赤な風船と白い薔薇の花びらだった。
ひらりと地面に落ちた紙を、佐野が拾う。
『小春ちゃん、佐野。両思いおめでとう!』
ラメいっぱいのクリスマスカードに、ばかみたいに大きく書かれたメッセージ。
なんで。
どうして。
ゆっくりと、佐野がわたしの方を振り返る。
「ごめん。俺が明希に、安藤のこと相談してて……。それでこんなことしたんだと思う。あいつ、悪ふざけが過ぎるな。巻き込んじゃって、ごめん。だけど俺、本当に安藤のことが好きなんだ」
真っ赤な顔で佐野は言った。
誠意に満ちた眼差しを、まっすぐわたしに向けて。
それなのにわたしは、なんで、どうして、でいっぱいで、なにも言えなかった。
「返事、いつでもいいから。考えてくれたらうれしい」
それからわたしは、何度も明希に連絡した。
だけどメッセージはずっと未読のままで、電話にも出てくれなかった。
★★★
長い長い冬休みが、やっと明けた。
明希にどんな顔をするべきか考えながら、学校へ向かう。
怒った顔をするのも、なんだか子どもっぽい。
ここは何事もなかったように、クールに澄ました顔をしようと思ったけれど、廊下の窓ガラスに映ったわたしの顔は、登園拒否する幼稚園児のようだった。
いったいわたしは、なにに怒っているのだろう。
「おはよう、安藤」
その声にぎくりとして振り向くと、佐野は少しだけ居心地悪そうにして微笑んだ。
「お、おはよう、佐野」
「宿題、終わった?」
「うん。なんとか……」
「俺、終わらなかったよ。安藤が返事くれないから」
「えっ」
「冗談だよ。返事はいつでもいいって言っただろ」
佐野はくすくす笑いながら教室へ入り、仲間たちの輪へと吸い込まれていった。
ひさしぶりの教室は、なんだかやけに騒がしかった。
それは休み明けのクラスメイトとの再会による妙なハイテンションとは違い、どこかねっとりとした嫌な空気だった。
いったいなんだろう。
不思議に思っていると、「あめおめ、小春!」と由奈が駆け寄ってきた。
「あけおめ。ねえ、なんかあったの? 変な空気だけど」
「それがさあ、ビッグニュース」
「ビッグニュース?」
なんとね、と由奈が切り出すと、ちょうどチャイムが鳴り、担任の柴ちゃんがやってきた。
みんなバタバタと席につき、ねっとりとした空気は散り散りになった。
柴ちゃんは白髪のまざった前髪を軽くかきあげ、新年の挨拶をはじめた。
明希の席だけが、ぽっかりと空いている。
「えー……。知ってる者もいると思うが、ご家庭の事情で、石井が学校を辞めることになった」
教室中がざわめき、わたしは止まった。
言葉も、呼吸も、思考も。
すべてが止まった。
みんなに静かにするよう促す柴ちゃん。
親父がヤバい仕事やってただの、夜逃げだの反社だの、どれが真実かわからない情報を無責任に口にするクラスメイト。
わたしは縋りつくように、机のなかのノートの角をぎゅっと握った。
「せんせーい。安藤さんが体調悪そうなんで、保健室つれていきまーす」
由奈がわたしの腕を掴み、教室の外へとずるずる引っ張り出した。
人気のない廊下で、足元からすうっと冷えていく。
「ちょっと小春、どうしたの? 顔色やばいよ。保健室まで歩ける? それにしてもびっくりだよね、明希のこと。わたしさ、昨日ぐうぜんコンビニで明希のこと見かけたんだよね。小春にごめんって謝っといて、なんて言うから、明日学校で会うんだから、ちゃんと自分で謝りなよって言ったんだけど……。あんたたち、喧嘩でもしてたの?」
なしだって言ってたのに。
ごめんは好きくないって言ってたのに。
どうして最後にくれたものが、それなの?
指先から滑り落ちたノートが、はらりと開いた。
くまぬちゃんが頼りなく、わたしに微笑みかける。
毎日のように眺めたくまぬちゃんには、もう愛おしさしかこみ上げてこなかった。
―― 了 ――
【補足】
2022年の冬に下記の企画にてピックアップしていただいた短編に加筆修正しました。受賞ではないので本コンテストへの応募には影響ないと思いますが、念のため記載いたします。
https://maho.jp/info/entry/advent-campaign
