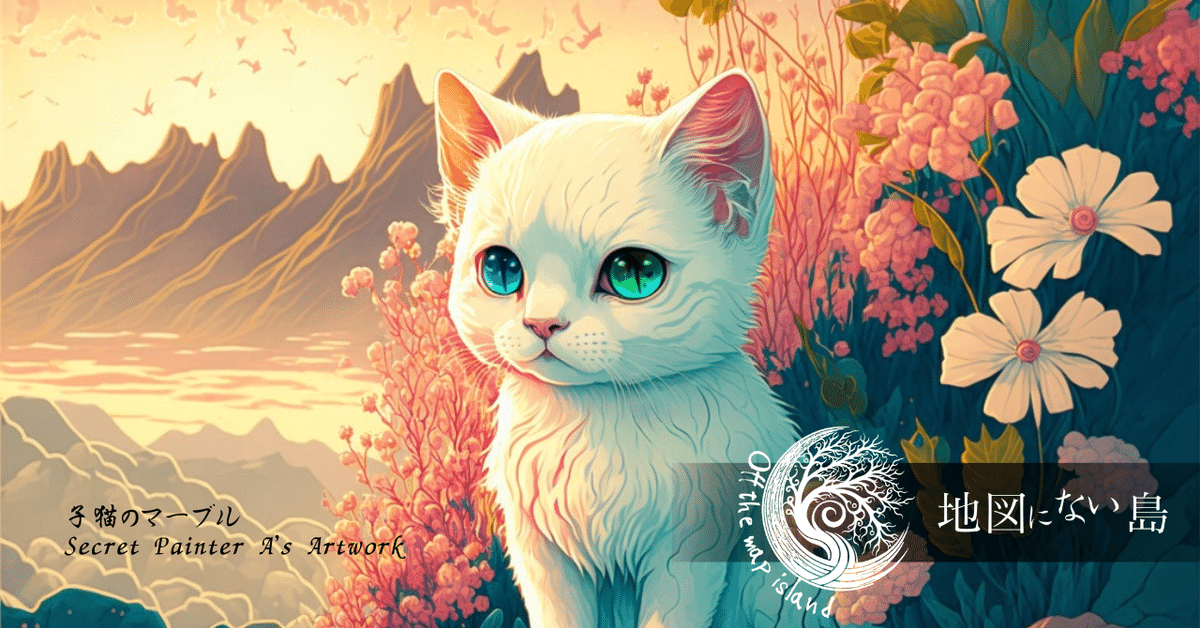
地図にない島 #4 島、ふたたび
うれしさと、期待。
不安と、恐れ。
そして、思いがけず強く沸き上がったのは、孤独感。
島側から開かれる<道>を通れるように、ネプラが案内係として、再びぼくの前に現れた。
島には、どこからでも、行ける。
ぼくの、アパートの部屋からでも。
今夜は、満月だ。
明るい。
この辺りは市街地からは離れていて、まだ開発もそんなに進んでいない。
アパートの前は空き地で、その向こうは田畑。
便利ではないが、家賃は安くて見晴らしが良くて、もう10年以上住んでいる。
開けた窓からは5月の風が入ってきて、過ごしやすい。
孤独感なんて。
一度も...というのは嘘だけれど。
おじいちゃんがいなくなってから1年も経った頃には、そんなもの感じることはなくなっていた。
それからは、もうずっと、感じないで過ごしてきた。
ぼくは、誰かと長時間過ごすというのが、得意ではない。
一人でいるほうが気が楽だ。
ただ。
確かに、ぼくは、知っている。
「一人でいること」と「孤独であること」は、同じではない。
ネプラの身の回りに漂う、光を曲げる霧の影。
それを見た時、ぼくの中にはたくさんの相反する思いがわき出てきて。
こんなのは夢だ...と、口から出そうになった。
ああ、だめだ。
そんな、無駄の極みのような泣き言を、口に出すわけにはいかない。
いくら、考えること全部、筒抜けだといっても。
「コージローの紋章を」
ネプラはぼくの内心など淡々と無視して、うながした。
おじいちゃんの木箱の板を、紋を上にして、彼の前に示す。
「ふむ。よくぞ、これほど綺麗なままで残しておいた」
「ずっとしまい込んであっただけだよ」
「これがなくとも渡ることはできるが、あればスムーズにすむ。よいことだ」
おじいちゃんの道具入れには、雲をデザインした紋章が描かれていた。
薄くなったら描き直し、箱を交換する時は、新しいものに同じ紋を描いて。
それが何なのかは、ぼくも、よく知っている。
それは、ある種の魔方陣のようなもので。
<島>へ、外部の...特に人間を招き入れる時、その個を識別するためのマークだ。
IDカードのようなものか。
おじいちゃんは、島へ行くときいつも、この紋を描いた箱を持っていた。
スケッチ道具や、島のみんなへのお土産を入れて。
ああ…お土産…考えてなかった。
「では行こうか。やり方は覚えていような」
ぼくは沈黙のまま、手のひらを紋の上に重ねた。
これを、ぼくだけの手で開くのは、初めてだ。
そもそも、これはおじいちゃん用のシンボルであって、ぼく用ではない。
ぼくが一緒に行くようになって、おじいちゃんが紋を少し調整してくれたのだ。
ちゃんと機能してくれるんだろうか?
…あれ?
待てよ…
おじいちゃんがいなくなってからも、島に行ったことがなかったか?
確か…
意識があらぬところへ向かいかけた時。
ぼくの背を、ネプラの翼が荒っぽく押した。
「何をしている。気を逸らすな。早く入れ」
扉が開いているのは、ほんの数秒しかないのだ。
そうだった。
扉を通り抜ける時の、この感覚。
懐かしい。
空気のカーテンのようなものを突っ切る感じ。
<向こう側>へ出るまでは、ほんの数秒/一、二歩にすぎない。
体感的にも、実時間でも。
空気カーテンを抜ける、その一回目で、こちらの扉を通り。
二回目で、向こう側の扉を通る。
一回目と二回目の<間>は、ぼくの知覚ではキャッチできない。
紋に仕込まれたコード+道案内のネプラの力。
二つの効力の掛け合わせで、この瞬きする間の移動が、なされる。
ネプラが一緒なら、迷わずに向こう側へ行ける。
が、そうでなければ通過はもちろん、元の世界に戻ることも極めて難しいとか。
ぼくは<道>の中で迷ったことはないので、定かではないけれど。
祖父は、何度か迷ったことがあるらしい。
行くも戻るも極めて困難...というところを、何度か迷うって。
どんなだ。
<向こう>に抜けたとたん、ふわっと甘くて濃い大気の香りの中に出た。
島だ。
この香り。
この空気。
<地図にない島>に、また、来ることができた。
呼吸が、しやすい。
濃くて綺麗な空気だ。
緑と水の香り。
また涙が出そう。
今日のぼくは、30年分泣いてる気がする。
目の前には、いかにも「魔法使いの住処」然とした家の入り口があった。
巨大な古木の根元に作られた、アーチ型のドア。
玄関ポーチ代わりのウッドデッキと、揺り椅子。
椅子の上で丸くなって寝ていた白い子猫が、ぼくらに気付いた。
ビー玉のような目は、左右の色が違う。
子猫はふわっと椅子から降り、とことこ近づいてきた。
島と人の世界では、時間の流れは全く異なる。
23年という年月だったはずだけれど。
この子は、今もまだ、あの頃と同じ子猫のまま。
時差問題については、昔おじいちゃんと来ていた時にも、慣れるのに時間がかかったように思う。
「時差という問題ではないと、前に教えなかったか?」
その声は、背後から飛んできた。
子猫はサッとぼくの足元をすり抜け、駆け寄っていく。
「なんだ、おまえ、もっと渋くなってるかと思ったが…まるでガキのままじゃないか」
声の主は、スタスタとぼくの横を素通りして、玄関へ向かった。
細身の身体に似つかわしくない大きな壺を、肩の上に載せている。
子猫が足元にじゃれつくのをつま先で押しのけながら、ウッドデッキを上がっていく。
家とネプラの主。
年齢不詳。
見た目は小柄な女性だが、その姿は単に、収まりがいい感じだからそうしているだけ(と、以前聞いた)
通り名は、エクウ。
本名も、素性も、本来の姿も、誰も知らない。
ぼくは、その姿を、ただ突っ立って眺めるだけだ。
23年とか。
いや、それどころか、記憶に埋没させて思い出しもしなかったのは、ぼくで。
さすがに、夏休み明けの登校日感覚には、すぐには戻れない。
ネプラの姿は、消えていた。
案内を終えたので、他の仕事に戻っていったのだろう。
ウッドデッキでは、平和で愛らしい光景が繰り広げられている。
エクウが壺を下ろそうとすると、子猫が邪魔するように回り込む。
小さな白い毛のかたまりを、エクウがつま先で押しのける。
子猫は負けじと、またもや壺の邪魔をしに戻ってくる。
何度目かの応酬の末、子猫はつま先に掬い上げられて、ポンと宙に放り上げられ、エクウの片腕に抱えられる。
この一連の動作は、子猫のお気に入りの遊びだ。
子猫の名は、マーブル。
マーブルは、おじいちゃんの膝の上もお気に入りだった。
ぼくは、彼がよほど上機嫌の時でないと、触れさせてもらえない。
マーブルを片腕に、壺を揺り椅子の横へと下ろして。
エクウは、開けたドアに半身入りながら、ぼくを振り返った。
「おまえ、ずっとそこに突っ立ってるつもりか?」
顎先のしぐさで、中へと促す。
彼女の目の奥には、果ての無い深淵が宿っている。
謎だらけの島。
謎だらけの島民。
ここには、「神様」も、やってくる。
ぼくは、目線を少しあげて。
前へ、足を進めた。
つづく
文章/川口緋呂@神龍画家
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
