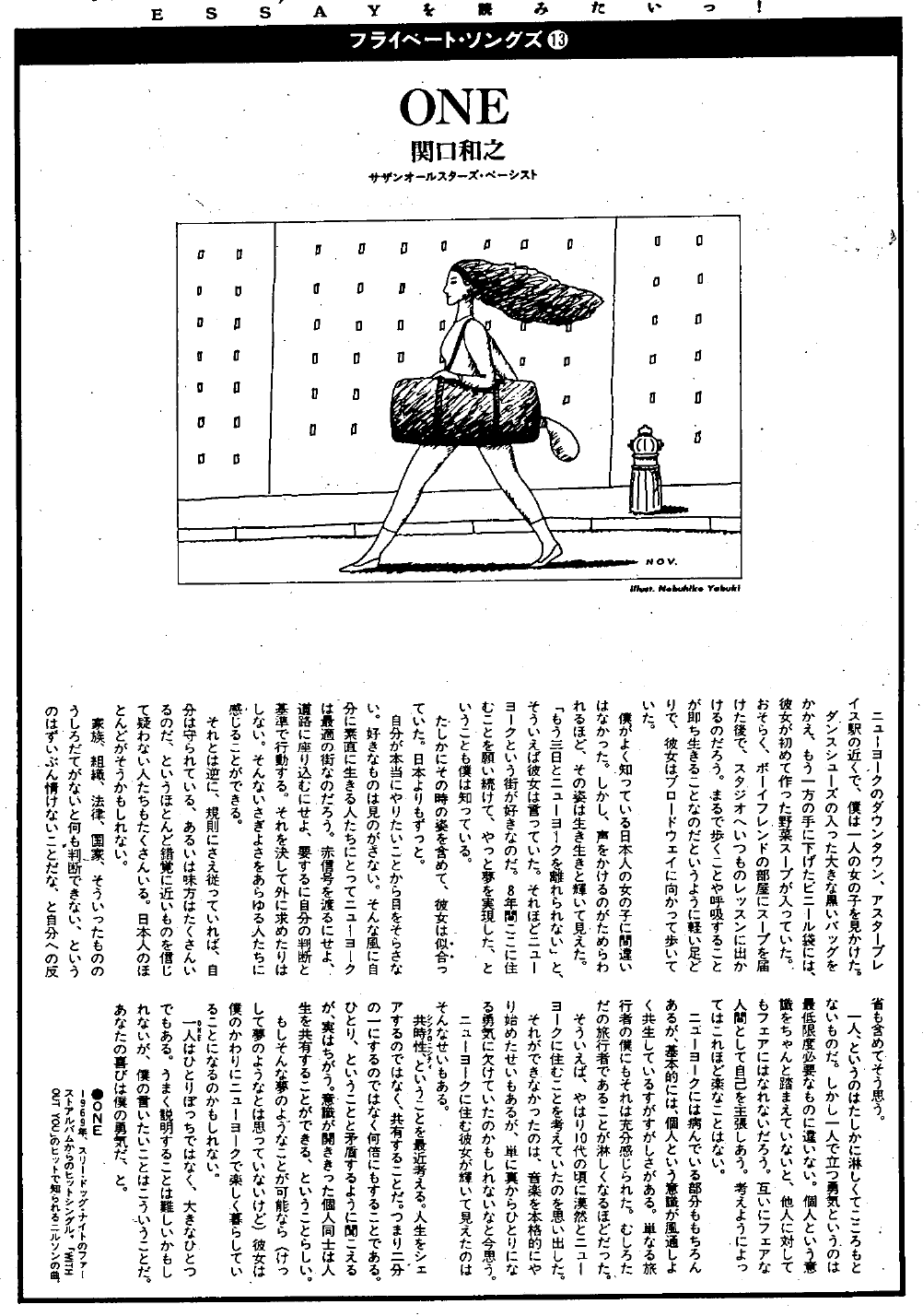ONE
【雑誌「CAZ」にて1989年に連載スタートした「プライベートソングズ」を原文のまま掲載します】
ニューヨークのダウンタウン、アスタープレイス駅の近くで、僕は一人の女の子を見かけた。
ダンスシューズの入った大きな黒いバッグをかかえ、もう一方の手に下げたビニール袋には、彼女が初めて作った野菜スープが入っていた。おそらく、ボーイフレンドの部屋にスープを届けた後で、スタジオへいつものレッスンに出かけるのだろう。まるで歩くことや呼吸することが即ち生きることなのだというように軽い足どりで、彼女はブロードウェイに向かって歩いていた。
僕がよく知っている日本人の女の子に間違いはなかった。しかし、声をかけるのがためらわれるほど、その姿は生き生きと輝いて見えた。「もう三日とニューヨークを離れられない」と、そういえば彼女は行っていた。それほどニューヨークという街が好きなのだ。8年間ここに住むことを願い続けて、やっと夢を実現した、ということも僕は知っている。
たしかにその時の姿を含めて、彼女は似合っていた。日本よりもずっと。
自分が本当にやりたいことから目をそらさない。好きなものは見のがさない。そんな風に自分に素直に生きる人たちにとってニューヨークは最適の街なのだろう。赤信号を渡るにせよ、道路に座り込むにせよ、要するに自分の判断と基準で行動する。それを決して外に求めたりはしない。そんないさぎよさをあらゆる人たちに感じることができる。
それとは逆に、規則にさえ従っていれば、自分は守られている、あるいは味方はたくさんいるのだ、というほとんど錯覚に近いものを信じて疑わない人たちもたくさんいる。日本人のほとんどがそうかもしれない。
家族、組織、法律、国家、そういったもののうしろだてがないと何も判断できない、というのはずいぶん情けないことだな、と自分への反省も含めてそう思う。
一人、というのはたしかに淋しくてこころもとないものだ。しかし一人で立つ勇気というのは最低限度必要なものに違いない。個人という意識をちゃんと踏まえていないと、他人に対してもフェアにはなれないだろう。互いにフェアな人間として自己を主張しあう。考えようによってはこれほど楽なことはない。
ニューヨークには病んでいる部分ももちろんあるが、基本的には、個人という意識が風通しよく共生しているすがすがしさがある。単なる旅行者の僕にもそれは充分感じられた。むしろただの旅行者であることが淋しくなるほどだった。
そういえば、やはり10代の頃に漠然とニューヨークに住むことを考えていたのを思い出した。それができなかったのは、音楽を本格的にやり始めたせいもあるが、単に真からひとりになる勇気に欠けていたのかもしれないなと今思う。
ニューヨークに住む彼女が輝いてみえたのはそんなせいもある。
共時性(シンクロニシティ)ということを最近考える。人生をシェアするのではなく、共有することだ。つまり二分の一にするのではなく何倍にもすることである。ひとり、ということと矛盾するように聞こえるが、実はちがう。 意識が開ききった個人同士は人生を共有することができる、ということらしい。
もしそんな夢のようなことが可能なら(けっして夢のようなとはおもっていないけど)彼女は僕のかわりにニューヨークで楽しく暮らしていることになるのかもしれない。
一人(ONE)はひとりぼっちではなく、大きなひとつでもある。うまく説明することは難しいかもしれないが、僕の言いたいことはこういうことだ。あなたの喜びは僕の勇気だ、と。
ONE
1969年、スリー・ドッグ・ナイトのファーストアルバムからのヒットシングル。「WITH OUT YOU」のヒットで知られる二ルソンの曲。
関口コメント:
ハワイに通うようになる前はニューヨークに夢中だった。できることなら住みたいと思っていた。それがハワイになったのはもちろんウクレレと出会ったからである。それにしてもアメリカはどこへ行こうとしてるのだろうと余計な心配をしてしまうこの頃。