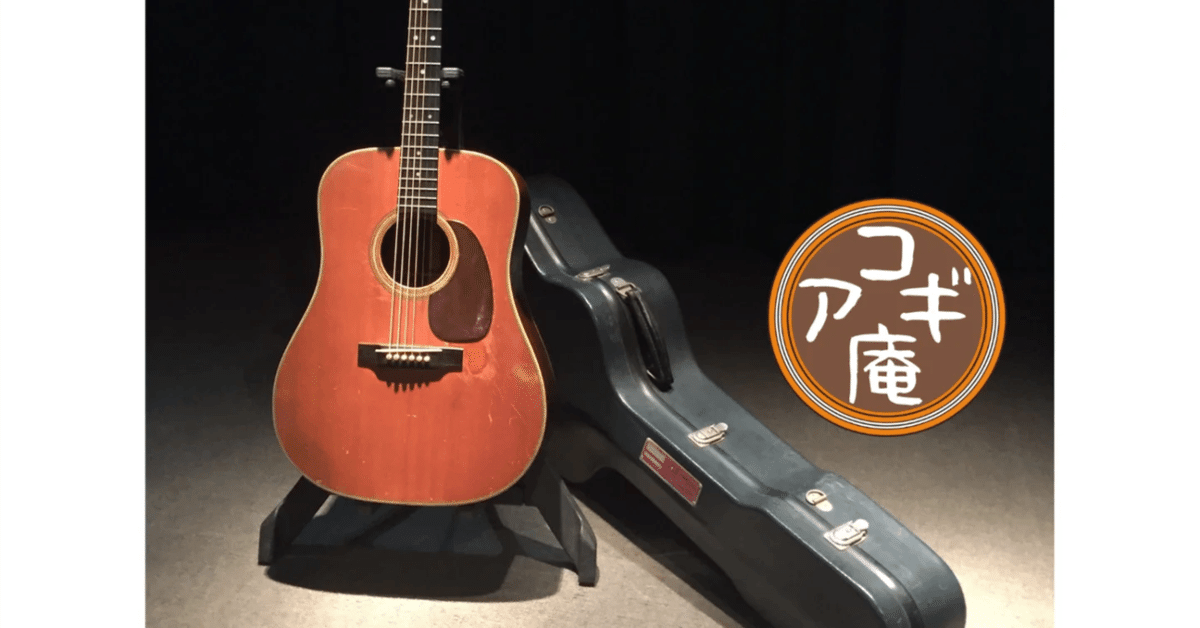
「あらためて、コンバージョンの話」 「何故、エム・シオザキなのか?」
「終活ギター アコギ庵」「アコギ弾き比べサロン アコギ庵」です。
アコギ一筋54年。アコギの終活をやろうというオッサンが、《何かアコギ好きのためにできることはないか?》というところからスタートしました。アコギ好きのための”Support and Assist”を目標に、何かしらお役にたてることがあればいいなと思っています。
そうそう簡単に弾くことができないと思われるギターも、何本か用意しています。初心者の方用、中級者用のギターもあります。とにかく来て弾いていただいて、そこから何かが始まることを期待しております。アコギ好きの皆様とお話しすることを楽しみに、お待ちしております。
「あらためて、コンバージョンの話」
コンバージョンという言葉をググってみたら、ウェブマーケティングで使われる言葉というのが出てきました。「全然違うやん!」ということで、あらためて‴コンバージョン ギター‴でググってみました最初に出できたのは「エレキの世界ではよくあります。最も多いのはギブソンのレスポール。」という説明でした。こんな感じです。
"コンバージョンはエレクトリック・ギターの世界ではよくあります。一番多いのはたぶん、ギブソンのレスポールで、1952年から57年の間に作られたゴールド・トップのレスポール・モデルを、テール・ピースを取り替え、ピック・アップを付け替え、トップのフィニッシュをはがして、58~60年製のレスポールみたいに仕上げるわけですね。"(ネットで見つけた情報から引用させていただきました。)
アコギの世界でも数はそれほど多くありませんが、コンバージョンはかなり以前からありました。最も多いのは1969年以前のMartin D-28を、プリウォーのD-45にコンバートするパターンです。相当な手間と経費はかかりますが、これが最も付加価値を高めることができるからでしょう。やはりD-45の存在はデカいですね。
まだハカランダものの価格がそれほど高くなかった時代なら、ジャンク品を探せば十分採算を採ることができたでしょう。が、最近はヴィンテージギターの価格高騰でそういうことも難しくなってきました。マーチン社が行ったコンバージョンでもない限り、採算をとるのは容易ではないと思います。マーチンというメーカーのブランド力、ネームバリューは、やはり凄いと言わざるを得ません。

さすがはマーチン社のコンバージョン、お値段が違います!!



しかしながら、自分の中には「今のマーチンは、昔のマーチンではない!」というイメージがあります。小さなファクトリーで少人数でありながら、良質の木材がふんだんにあり手作業で製作されていた時代。その頃と今を、同じマーチンだと捉えるのは非常に難しいです。というか、まったくの別モノといった方が良いもかもしれません。
このギターも当時のスタイルを忠実に再現した仕様(スティールTバーロッド仕様や、塗り込みピックガード、フォワードシフテッドによるスキャロップドXブレーシング、及び接着剤にニカワが使用されているなど)とのことですが、トップ・サイド・バックのボーダーに使用されているアバロンはラミネートだと思います。(確認していないので、断定はできませんが。)
「何故、エム・シオザキなのか?」
これも、コンバージョンに関連する話です。
奇しくも前述のD-45と同様のコンバージョン(1950年製のD-28をプリウォーのD-45にコンバート)の製作を昨年の9月に塩﨑 雅亮さん(エム・シオザキ弦楽器工房)にお願いしました。そのコンバージョンが、あと少しで完成!というところまで来ました。今月中(2024年10月)には受け取ることができそうです。



マーチン社で初めて14フレットのD-28が製作されたのが1934年。その年の総製作本数は、3,595本でした。ギター製作用の木材がふんだんにあり、良い部分だけを切り取って使用していた時代です。(材料となる木材の4分の1しか使わず、残りの部分は捨てられていたそうです。クウォーターソーンと言われていました。)ハカランダを例にとっても、この頃のマーチンギターの写真を見れば、最近のものとは全く違うことがよくわかります。ほとんどが無茶苦茶きれいな柾目のハカランダです。最近の木目を見慣れていると(基準にすると)、「これ、ハカランダなのでしょうか?」と思ってしまう人もいるのでは?それぐらい材の質が違います。
ちなみに把握できるマーチン社のシリアルナンバーから、直近の製作本数を調べたら117,643本(2023年)でした。すげぇー!
コンバージョンの魅力の一つは、今ではあり得ないと言ってもよいほどの(古き良き時代の)材を使っているということです。そして何10年も前に製作されたギターを、まったく別のギターに生まれ変わらせるということです。ある意味最近よく言われているサステナブル(Sustainable)という考え方にも通じるかもしれません。
ここで問題になるのはそういった古き良き時代の材を使って、本当に価値のあるギターを創り出せるのか?ということです。要は、誰がその作業をするのか?ということです。これはアメリカの市場でもよく言われていることで、コンバージョンの価値を決める一番大きな要素といってもよさそうです。日本では間違いなく塩﨑さんがその第一人者で、同じレベルでできる職人さんはいないだろうと思っています。今までこなしてきたリペアの数も、他のリペアマンの比ではないでしょう。プリウォーのD-45やOOO-45をはじめ、とんでもない数のヴィンテージマーチンのリペアをされています。
リペアするということは、その時代の木材の質やギターの構造、サウンドを知ることができます。これはギターを製作するビルダーにとっては、ものすごく大きな経験(財産といってもよいでしょう)になるはずです。塩﨑さんは、1982年にシーガル弦楽器工房を設立。(現、エム・シオザキ弦楽器工房)それ以来ずっとマーチン一筋に歩んで来られました。ひょっとしたら今のマーチン社にいる職人の誰よりも多くの経験を積んでおられるかもしれません。個人的には、マジでそうではないかと勝手に推測しています。違った角度から見れば、塩﨑さんがリタイヤしてしまったら後がないやん!と思わざるを得ない状況です。
そんなこんなで「この人しかいない!」、そういう気持ちで塩﨑さんにコンバージョンの製作お願いしました。もうすぐ完成です。近いうちに報告させていただきます。楽しみや~!!
拙い文章をお読みいただき、誠に有難うございます。
皆様の感想、ご意見をお聞かせください。 またアコギに関する相談等がございましたら、どんなことでもOKです。遠慮なくお尋ねください。
アコギ庵は「ギターを弾いてもらって、ゆっくりアコギの話をする。」そんな場所です。勝手ながら、完全予約制で運営させていただいております。
お手数ですが、まずはメール、もしくはメッセージでご連絡をお願いいたします。
宛先 e-mail:mail@acogian.com または twitter(@acogibucho)にお願いします。
FACEBOOKのページもあります。こちらにメッセージを送っていただいてもかまいません。よろしくお願いいたします。
